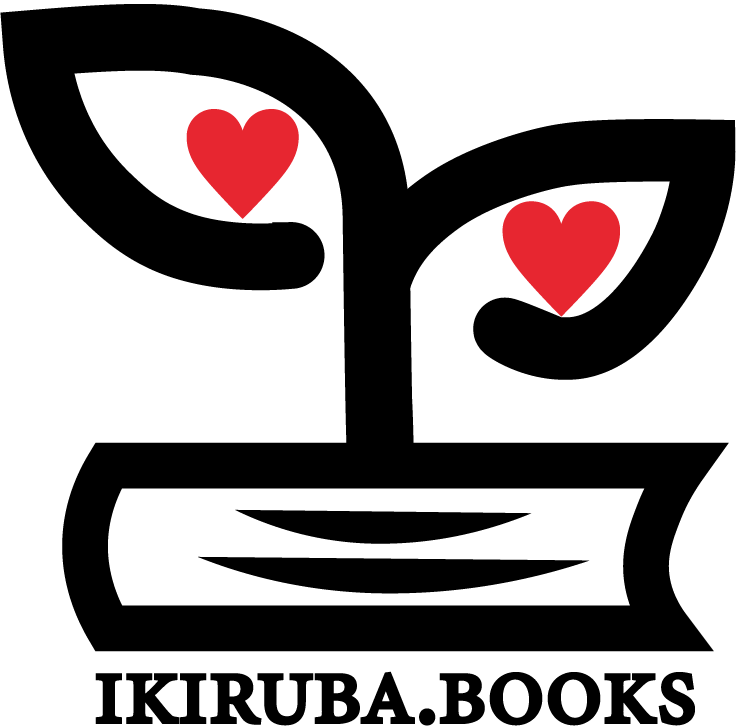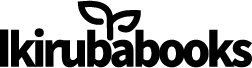-

検証 ナチスは「良いこと」もしたのか?
¥902
☆店長のひと言 「読んだあとに自分の見識がどう変わるか(変われる)どうか。」 内容紹介 「ナチスは良いこともした」という言説は、国内外で定期的に議論の的になり続けている。アウトバーンを建設した、失業率を低下させた、福祉政策を行った――功績とされがちな事象をとりあげ、ナチズム研究の蓄積をもとに事実性や文脈を検証。歴史修正主義が影響力を持つなか、多角的な視点で歴史を考察することの大切さを訴える。 目次 はじめに 第一章 ナチズムとは? 第二章 ヒトラーはいかにして権力を握ったのか? 第三章 ドイツ人は熱狂的にナチ体制を支持していたのか? 第四章 経済回復はナチスのおかげ? 第五章 ナチスは労働者の味方だったのか? 第六章 手厚い家族支援? 第七章 先進的な環境保護政策? 第八章 健康帝国ナチス? おわりに ブックガイド 著者プロフィール 小野寺拓也(オノデラ タクヤ) 1975年生まれ.東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了. 博士(文学).昭和女子大学人間文化学部専任講師を経て,現在,東京外国語大学大学院総合国際学研究院准教授.専門はドイツ現代史. 著書に『野戦郵便から読み解く「ふつうのドイツ兵」――第二次世界大戦末期におけるイデオロギーと「主体性」』(山川出版社),訳書にウルリヒ・ヘルベルト『第三帝国――ある独裁の歴史』(KADOKAWA)などがある. 田野大輔(タノ ダイスケ) 1970年生まれ.京都大学大学院文学研究科博士後期課程研究指導認定退学.博士(文学).大阪経済大学人間科学部准教授等を経て,現在,甲南大学文学部教授.専門は歴史社会学,ドイツ現代史. 著書に『ファシズムの教室――なぜ集団は暴走するのか』(大月書店),『愛と欲望のナチズム』(講談社),『魅惑する帝国――政治の美学化とナチズム』(名古屋大学出版会)などがある. (岩波書店ホームページより引用) ISBN:978-4-00-271080-8 Cコード:0336 A5判120ページ 発行:岩波書店 発売日: 2023年07月07日

-

空と花とメランコリー 榎本マリコ作品集
¥1,900
【中古 帯に傷みあり(画像参照)】 (参考:定価2,700円+税) ☆店長のひと言 「こういうの好きな人は大体友だち少ないですよね。(私です)」 内容紹介 顔を隠された異形の人物像が、『82年生まれ、キム・ジヨン』など話題書の装幀に採用され、 一躍脚光を浴びる画家・榎本マリコの初作品集。 初期作から最新作、クライアントワークまでを厳選し、相反するイメージの組み合わせが想像を掻き立てる榎本作品の全貌に迫る! 斎藤環氏(精神科医)、沓名美和氏(現代美術史家)、小松隆宏氏(ギャラリスト)による跋文も収録 (芸術新聞社HPより) 著者プロフィール 榎本マリコ (エノモトマリコ) (著/文) 画家。1982 年生まれ、東京都在住。ファッションを学んだのち独学で絵を描き始め る。都内で個展やグループ展多数。チョ・ナムジュ著『82 年生まれ、キム・ジヨン』 ( 筑摩書房 )、川上未映子の連載小説「黄色い家」( 読売新聞 ) の挿絵などを手がけた。 ISBN:978-4-87586-682-4 Cコード:0071 B5判139ページ 発行: 芸術新聞社 発売日: 2023年11月28日
-

「空気」を読んでも従わない
¥500
【中古 状態きれい】 (参考:定価820円+税) ☆店長のひと言 「そもそも空気を読めるだけですごい能力なわけで、それ以上求めるのは無茶な話なんですよ。」 内容紹介 「個性」が大事というけれど、集団の中であまり目立つと浮いてしまう、他人の視線を気にしながら、本当の自分は抑えつけていかないと……。この社会はどうしてこんなに息苦しいのだろう。もっと自分らしく、伸び伸びと生きていきたい! そんな悩みをかかえるアナタにとっておきのアドバイス。「空気」を読んでも従わない生き方のすすめ。 目次 はじめに 1 なぜ先輩に従わなければいけないの? 2 どうして,人の頼みを断れないのだろう? 3 「世間」と「社会」 4 「世間」の始まり 5 「世間」を壊そうとする人達 6 根強く残る「世間」 7 「世間」は中途半端に壊れている 8 外国には「世間」はない 9 人の頼みを断るのがつらいヒミツ 10 もし人から頼まれたら 11 敵を知るということ 12 「空気」ということ 13 「世間」のルール1 年上がえらい 14 「世間」のルール2 「同じ時間を生きる」ことが大切 15 「世間」のルール3 贈り物が大切 16「世間」のルール4 仲間外れを作る 17 「世間」のルール5 ミステリアス 18 「世間」はなかなか変わらない 19 5つのルールと戦い方 20 強力な「世間」との戦い方 21 同調圧力 22 自分を大切に思うこと 23 仲間外れを恐れない 24 たったひとつの「世間」ではなく 25 私を支えるもの 26 スマホの時代に おわりに 著者プロフィール 鴻上 尚史 (コウカミ ショウジ) (著/文) 鴻上尚史(こうかみ・しょうじ) 作家・演出家・映画監督。1958年愛媛県生まれ。早稲田大学法学部卒業。大学在学中の1981年、劇団「第三舞台」を旗揚げする。87年「朝日のような夕日をつれて87」で紀伊國屋演劇賞団体賞、95年「スナフキンの手紙」で岸田國士戯曲賞、2007年に旗揚げした「虚構の劇団」の旗揚げ三部作戯曲集『グローブ・ジャングル』で10年、読売文学賞戯曲・シナリオ賞を受賞。著書に『「空気」と「世間」』『不死身の特攻兵』(以上、講談社現代新書)、『ベター・ハーフ』(講談社)、『人間ってなんだ』『人生ってなんだ』『世間ってなんだ』(以上、講談社+α新書)、『鴻上尚史のほがらか人生相談』(朝日新聞出版)、『同調圧力のトリセツ』(中野信子との共著、小学館新書)など多数。 ISBN:978-4-00-500893-3 Cコード:0236 新書判 224ページ 発行:岩波書店 発売日: 2019年04月20日

-

見えないスポーツ図鑑
¥1,500
【中古 表紙に汚れあり(画像参照)】 (参考:定価2,000円+税) ☆店長のひと言 「見た目をコピーしてもうまくいかないのって、こういうことなんでしょうね。」 紹介 研究者たちが考えていることって――実はめちゃくちゃ面白い。 抱腹絶倒&試行錯誤の「本邦初」、研究ドキュメンタリー 視覚障害者の方々にスポーツの臨場感をどう伝えるか、から始まった研究は「スポーツ」を翻訳することに向かった。 研究をスタートさせるも、相次ぐ失敗が壁となって立ちはだかる。 しかし、そんなことでは研究者は諦めない! 思わぬアイディアから方向を転換し、十種目の競技のエキスパートとタッグを組んで「人力VR」の開発に挑むことに!? 【各氏、推薦!】 相馬千秋氏(アートプロデューサー) ゲーム性、緊張感、駆け引き、速度、バランス……スポーツを「翻訳」すると、それはもはやアート!誰かのからだに創造的に憑依するための、身体感覚翻訳マニュアル、決定版。 太田雄貴氏(公益社団法人日本フェンシング協会会長) フェンシングの翻訳なんて……できるんだ! 競技者の間でも話題沸騰。さっそくアルファベットを揃えました。 稲見昌彦氏(東京大学総長補佐・教授/超人スポーツ協会代表理事) 「見ることは信じること(Seeing is Believing)」という諺、実は「感じることこそ真実(but Feeling is the Truth)」と続く。 本書は、スポーツを見ることの背後にある、本質(バーチャリティ)に迫ります。 目次 はじめに――伊藤亜紗 第1章:ラグビーを翻訳する――古川拓生 第2章:アーチェリーを翻訳する――高井秀明 第3章:体操を翻訳する――水島宏一 第4章:卓球を翻訳する――吉田和人 第5章:テニスを翻訳する――遠藤 愛 第6章:セーリングを翻訳する――久保田秀明 第7章:フェンシングを翻訳する――千田健太 第8章:柔道を翻訳する――石井孝法 第9章:サッカーを翻訳する――堀野博幸 第10章:野球を翻訳する――福田岳洋 おうちで翻訳 おわりに――渡邊淳司 あとがき――林阿希子 https://www.parasapo.tokyo/topics/101110 著者プロフィール 伊藤亜紗 (イトウアサ) (著/文) 美学者。東京工業大学科学技術創成研究院未来の人類研究センター/リベラルアーツ研究教育院准教授。MIT客員研究員(2019)。2010年に東京大学大学院人文社会系研究科博士課程を単位取得のうえ退学。同年、博士号を取得(文学)。主な著作に『目の見えない人は世界をどう見ているのか』(2015、光文社)、『どもる体』(2018、医学書院)、『記憶する体』(2019、春秋社)、『手の倫理』(講談社、近日刊行)など。 渡邊淳司 (ワタナベジュンジ) (著/文) NTTコミュニケーション科学基礎研究所 上席特別研究員(NTTサービスエボリューション研究所2020エポックメイキングプロジェクト 兼任)。主著に『情報を生み出す触覚の知性』(2014、化学同人、毎日出版文化賞(自然科学部門)受賞)、『情報環世界』(2019、NTT出版、共著)、『表現する認知科学』(2020、新曜社)など。文化庁メディア芸術祭での受賞、Ars Electronica Prixでの受賞や審査員等、表現・体験領域での活動にも関わる。 林阿希子 (ハヤシアキコ) (著/文) NTTサービスエボリューション研究所 2020エポックメイキングプロジェクト 主任研究員。大阪大学大学院生命機能研究科修了。 人間中心設計の研究者として、高齢者向けウェブデザインの研究や、空港での人流誘導サインの実証実験、物体認識技術を用いた展示会アプリの開発等に携わる。ユーザの心理・行動モデルの研究を行う一方で、実サービス化に向けた体験創造を行う 。 共著に『ウェブユニバーサルデザイン』(2014、近代科学社)。 ISBN:978-4-7949-7192-0 Cコード:0095 四六判312ページ 発行: 晶文社 初版年月日: 2020年10月10日

-

80歳、まだ走れる
¥2,860
☆店長のひと言 「マスターズには夢がある。誰ですか、自分はマヨネーズでいいなんて言ってるのは。」 内容紹介 老いを甘んじて受け入れる必要はない ランニングに打ち込んできた著者は、人生の半ばで絶望に打ちひしがれていた。怪我に悩まされ、体力とスピードの衰えに意気消沈し、走ることを諦めようと思ったとき、高齢者スポーツの驚くべき世界に出会う。そして、マスターズ世界陸上で人生を変える体験をすることになる。本書は絶望から希望へと向かう一人の男性の非常に個人的な記録であると同時に、ライフスタイルとトレーニングを調整することで生理学的な衰えの進行を遅らせることができること、そして人間の精神力によって高齢になっても楽しく健康的に走り続けられることを証明した画期的なガイドブックでもある。 スポーツの楽しさが年齢によって失われていると感じているすべての人への希望のメッセージ。 著者プロフィール リチャード・アスクウィズ (著/文) 英国の著名なランニング作家・ジャーナリストの一人。受賞歴多数。 栗木 さつき (クリキ サツキ) (翻訳) 翻訳家。慶應義塾大学経済学部卒。50歳で初めてフルマラソンを完走、マイペースでマラソンを続けている。訳書にブラッチュリー『運を味方にする「偶然」の科学』(東洋経済新報社)、キャロル『パレットジャーナル』(ダイヤモンド社)、シネック『WHYから始めよ!インスパイア型リーダーはここが違う』(日本経済新聞出版)、シュミル『Numbers Don’t Lie』(共訳)、フォックス『SWITCHCRAFT 切り替える力』(以上、NHK出版)など。 ISBN:978-4-7917-7677-1 Cコード:0075 四六判406ページ 発行: 青土社 発売日: 2024年9月27日

-

恋と誤解された夕焼け
¥1,430
☆店長のロマンスなひと言 「恋に捕捉された流れ星」 紹介 コトバの最尖端を疾走し続けてきた詩人が新たな沃野に向かう第12詩集! 《だから空がとても赤く燃えている。ぼくは愛されたい。》――今、ここにいる私たちの魂の秘密は、詩のコトバによってしか解き明かすことができない。《どこからなら、きみを連れ去る神様の手のひらがやってきても平気か、教えて。水平線か、地平線?》生命と世界の光と影をあますところなく照らし出す決定的な43篇。 著者プロフィール 最果タヒ (サイハテタヒ) (著/文) 詩人。1986年生まれ。2006年、現代詩手帖賞受賞。07年、第一詩集『グッドモーニング』で中原中也賞受賞。14年『死んでしまう系のぼくらに』で現代詩花椿賞受賞。主な詩集に『空が分裂する』『夜空はいつでも最高密度の青色だ』『夜景座生まれ』『不死身のつもりの流れ星』『落雷はすべてキス』など。小説に『星か獣になる季節』『パパララレレルル』など。エッセイ集に『きみの言い訳は最高の芸術』『「好き」の因数分解』『恋できみが死なない理由』『無人島には水と漫画とアイスクリーム』など、そのほかの著作に『千年後の百人一首』(共著・清川あさみ)、対談集『ことばの恐竜』、翻訳『わたしの全てのわたしたち』(サラ・クロッサン/共訳・金原瑞人)、絵本『うつくしいってなに?』(絵・荒井良二)などがある。 ISBN:978-4-10-353813-4 Cコード:0092 四六変型判96ページ 発行: 新潮社 初版年月日: 2024年5月30日
-

幻肢痛日記
¥2,090
☆店長のひと言 「大切なものほど失ってから気付くのと似ていると言えないでしょうか。」 内容紹介 切断した筈なのに、足のあった場所が痛む。「ない」のに「痛い」とはどういうことだろう? 右足を失った「僕」が経験した不思議な現象、幻肢痛から考えた、わからないものについての記録。 (河出書房新社ホームページより引用) https://bookandbeer.com/event/bb241118a/ 著者プロフィール 青木 彬 (アオキ アキラ) (著/文) 1989年生。キュレーター。首都大学東京インダストリアルアートコース卒。アートを「よりよく生きるための術」と捉えアーティストや企業等と協同しアートプロジェクトを企画。著書に『素が出るワークショップ』。 ISBN:978-4-309-23162-4 Cコード:0036 四六判200ページ 発行: 河出書房新社 初版年月日: 2024年10月25日
-

体はゆく できるを科学する〈テクノロジー×身体〉
¥1,400
【中古 状態きれい】 (参考:定価1,600円+税) ☆店長のひと言 「器用な人って頭で体を縛っていないということなのかも。」 紹介 「できなかったことができる」って何だろう? 技能習得のメカニズムからリハビリへの応用まで―― ・「あ、こういうことか」意識の外で演奏ができてしまう領域とは ・なぜ桑田真澄選手は投球フォームが違っても結果は同じなのか ・環境に介入して体を「だます」“農業的”テクノロジーの面白さ ・脳波でしっぽを動かす――未知の学習に必要な体性感覚 ・「セルフとアザーのグレーゾーン」で生まれるもの ……etc. 古屋晋一(ソニーコンピュータサイエンス研究所)、柏野牧夫(NTTコミュニケーション科学基礎研究所)、小池英樹(東京工業大学)、牛場潤一(慶應義塾大学)、暦本純一(東京大学大学院)ら、5人の科学者/エンジニアの先端研究を通して、「できる」をめぐる体の“奔放な”可能性を追う。 日々、未知へとジャンプする“体の冒険”がここに 著者プロフィール 伊藤 亜紗 (イトウ アサ) (著/文) 東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授、東京工業大学科学技術創成研究院未来の人類研究センター長。東京大学大学院人文社会系研究科美学芸術学専門分野博士課程修了(文学博士)。専門は美学、現代アート。著書に『ヴァレリーの芸術哲学、あるいは身体の解剖』(水声社)、『目の見えない人は世界をどう見ているのか』(光文社新書)、『目の見えないアスリートの身体論』(潮新書)、『どもる体』(医学書院)、『記憶する体』(春秋社)、『手の倫理』(講談社メチエ)、『体はゆく できるを科学する〈テクノロジー×身体〉』(文藝春秋)など多数。 ISBN:978-4-16-391631-6 Cコード:0095 四六判248ページ 発行: 文藝春秋 発売日: 2022年11月28日

-

世界を、こんなふうに見てごらん
¥350
【中古 状態きれい】 (参考:定価550円+税) ☆店長のひと言 「子どもの頃から観察好きだし得意なんですけど、結果をすぐに忘れるのなんとかしたい。」 紹介 日高先生の人間、どうぶつ、いきものがたり 動物行動学者が、生きものと自然のユニークで新鮮な見方を、子どもでもわかる言葉でシンプルに伝える。21世紀に生きるすべての人々に贈る、やさしい自然の魅力発見の書。(解説/篠田節子) 著者プロフィール 日高 敏隆 (ヒダカ トシタカ) (著/文) (1930-2009) 東京生まれ。動物行動学者。東京大学理学部動物学科卒業。学生時代は岩波書店でアルバイトをしながら,夜は大学で研究をつづけた。東京農工大学教授,京都大学教授,滋賀県立大学初代学長,総合地球環境学研究所所長,京都市青少年科学センター所長などを歴任。1982年に日本動物行動学会を創設し,動物の行動から生きかたを探る学問を日本に広めた。生きもののふしぎをユーモラスに伝えるエッセイに定評がある。『チョウはなぜ飛ぶか』で毎日出版文化賞受賞。エッセイに『春の数えかた』など。翻訳書も多数。根っからの昆虫,ネコ好き。 ISBN:978-4-08-745027-9 Cコード:0195 文庫判208ページ 発行: 集英社 発売日: 2013年1月18日
-

あらゆることは今起こる (シリーズケアをひらく)
¥2,200
☆店長のひと言 「事実は小説よりも木なり。」 紹介 眠い、疲れる、固まる、話が飛ぶ、カビを培養する。それは脳が励ましの歌を歌ってくれないから?――ADHDと診断された小説家は、薬を飲むと「36年ぶりに目が覚めた」。私は私の身体しか体験できない。にしても自分の内側でいったい何が起こっているのか。「ある場所の過去と今。誰かの記憶と経験。出来事をめぐる複数からの視点。それは私の小説そのもの」と語る著者の日常生活やいかに。SFじゃない並行世界報告! 著者プロフィール 柴崎友香(しばさき・ともか) 1973年、大阪府生まれ、東京都在住。大阪府立大学卒業。1999年「レッド、イエロー、オレンジ、オレンジ、ブルー」が文藝別冊に掲載されデビュー。2007年『その街の今は』で芸術選奨文部科学大臣新人賞、織田作之助賞、咲くやこの花賞を受賞。2010年『寝ても覚めても』で野間文芸新人賞、2014年『春の庭』で芥川賞を受賞。その他に『パノララ』『千の扉』『百年と一日』ほか、エッセイに『よう知らんけど日記』など、著書多数。 ISBN:978-4-260-05694-6 Cコード:3347 A5判304ページ 発行:医学書院 書店発売日: 2024年5月13日

-

「能力」の生きづらさをほぐす
¥1,980
【中古 カバー、帯にスレあり(画像参照)】 (参考:定価2,000円+税) ☆店長のひと言 「女子力、人間力、免疫力、長州力…、いろいろ言われても疲れちゃうよね。」 紹介 【発売たちまち重版!】 生きる力、リーダーシップ力、コミュ力… ◯◯力が、私たちを苦しめる。 組織の専門家が命をかけて探究した、他者と生きる知恵。 前職では「使えない」私が、現職では「優秀」に。 それって、本当に私の「能力」なの? 移ろいがちな他人の評価が、生きづらさを生み出す能力社会。 ガン闘病中の著者が、そのカラクリを教育社会学と組織開発の視点でときほぐし、 他者とより良く生きるあり方を模索する。 目次 はじめに プロローグ 母さん、僕は仕事のできない、能力のないやつですか? 第1話 能力の乱高下 第2話 能力の化けの皮剝がし―教育社会学ことはじめ 第3話 不穏な「求める能力」―尖るのを止めた大学 第4話 能力の泥沼―誰も知らない本当の私 第5話 求ム、能力屋さん―人材開発業界の価値 第6話 爆売れ・リーダーシップ―「能力」が売れるカラクリ① 第7話 止まらぬ進化と深化―「能力」が売れるカラクリ② 第8話 問題はあなたのメンタル―能力開発の行き着く先 第9話 葛藤をなくさない―母から子へ エピローグ 母さん、ふつうでない私は幸せになれますか? 伴走者からの言葉 磯野真穂 おわりに 著者プロフィール 勅使川原 真衣 (テシガワラ マイ) (著) てしがわら・まい:1982年横浜生まれ。東京大学大学院教育学研究科修士課程修了。BCG、ヘイ グループなど外資コンサルティングファーム勤務を経て独立。2017年に組織開発を専門とする、おのみず株式会社を設立し、企業はもちろん、病院、学校などの組織開発を支援する。二児の母。2020年から乳ガン闘病中。 磯野 真穂 (イソノ マホ) (執筆伴走) いその・まほ:人類学者。専門は文化人類学、医療人類学。2010年早稲田大学文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。早稲田大学文化構想学部助教、国際医療福祉大学大学院准教授を経て2020年より独立。 著書に『なぜふつうに食べられないのか-―拒食と過食の文化人類学』(春秋社)、『医療者が語る答えなき世界――「いのちの守り人」の人類学』(ちくま新書)、『ダイエット幻想――やせること、愛されること』(ちくまプリマ―新書)、『他者と生きる』(集英社新書)、共著に『急に具合が悪くなる』(晶文社)がある。本作では、著者の執筆に伴走し、言葉を寄せる。 訂正のお知らせ: 初版第1刷p105の5行目に訂正がございました。以下を修正いたします。 ×社会教育学者 → ○教育社会学者 ISBN:978-4-910534-02-2 Cコード:0095 四六判264ページ 発行: どく社 初版年月日: 2022年12月25日
-

治りませんように : べてるの家のいま
¥800
SOLD OUT
【中古 状態きれい】 (参考:定価2,400円+税) ☆店長のひと言 「売れますように」 紹介 精神障害やアルコール依存などを抱える人びとが、北海道浦河の地に共同住居と作業所"べてるの家"を営んで30年。 べてるの家のベースにあるのは「苦労を取りもどす」こと-保護され代弁される存在としてしか生きることを許されなかった患者としての生を抜けだして、一人ひとりの悩みを、自らの抱える生きづらさを、苦労を語ることばを取りもどしていくこと。 べてるの家を世に知らしめるきっかけとなった『悩む力』から8年、浦河の仲間のなかに身をおき、数かぎりなく重ねられてきた問いかけと答えの中から生まれたドキュメント。 目次 記憶 死神さん べてるの家 浦河弁 なつひさお 救急通い 遭難者 あきらめる 立ち往生 新しい薬 幻聴とダンス 生きる糧 青年の死 ぺてるの葬儀 その人を語る 爆発系 ピア・サポート 撤退 当事者研究 アイメッセージ 収穫の秋 病気への依存 人間アレルギー 治さない 日だまり 苦労の哲学 しあわせにならない 著者プロフィール 斉藤道雄 (サイトウミチオ) (著/文) 1947年生まれ。ジャーナリスト。TBSテレビ報道局の記者、ディレクター、プロデューサー、解説者として報道番組の取材、ドキュメンタリー番組の制作に従事。先端医療、生命倫理、マイノリティ、精神障害、ろう教育などをテーマとしてきた。2008年から5年間、明晴学園の校長、その後4年間、理事長を務めた。著書に『原爆神話の五〇年』(中公新書、1995)『もうひとつの手話』(晶文社、1999)『悩む力――べてるの家の人びと』(みすず書房、2002)『希望のがん治療』(集英社新書、2004)『治りませんように――べてるの家のいま』(みすず書房、2010)『手話を生きる――少数言語が多数派日本語と出会うところで』(みすず書房、2016)『治したくない――ひがし町診療所の日々』(みすず書房、2020)がある。 ISBN:978-4-622-07526-4 四六判 251ページ 発行: みすず書房 初版年月日: 2010年2月17日
-

長い読書
¥2,530
☆店長のひと言 「私は長い積読。」 紹介 「本を読みなさい。 ぼくのまわりに、そんなことをいう人はいなかった。」 小説を読みはじめた子ども時代、音楽に夢中でうまく本が読めなかった青年期から、本を作り、仕事と子育てのあいまに毎日の読書を続ける現在まで。 吉祥寺のひとり出版社「夏葉社」を創業し、文学をこよなく愛する著者が、これまで本と過ごした生活と、いくつかの忘れがたい瞬間について考え、描いた37篇のエッセイ。 本に対する憧れと、こころの疲れ。ようやく薄い文庫本が読めた喜び。小説家から学んだ、長篇を読むコツ。やるせない感情を励ました文体の力。仕事仲間の愛読書に感じた、こころの震え。子育て中に幾度も開いた、大切な本…。 本について語る、あるいは論じるだけではなく、読むひとの時間に寄り添い、振り返ってともに考える、無二の散文集。 「ぼくは学校の帰りや仕事の帰り、本屋や図書館で本を眺め、実際に本を買い、本を読んだあとの自分を想像することで、未来にたいするぼんやりとした広がりを得た。」 目次 本を読むまで 本を読むまで 大きな書棚から 家に帰れば 『追憶のハイウェイ61』 バーンズ・コレクション 江古田の思い出 遠藤書店と大河堂書店 大学生 『風の歌を聴け』 本を読むコツ 文芸研究会 Iさん すべての些細な事柄 「アリー、僕の身体を消さないでくれよ」 大学の教室で 本と仕事 『言葉と物』 『なしくずしの死』 『ユリシーズ』がもたらすもの 沖縄の詩人 リフィ川、サハラ砂漠 遠くの友人たち 『魔の山』 H君 団地と雑誌 本づくりを商売にするということ 「ちいさこべえ」と「ちいさこべ」 アルバイトの秋くん 本と家族 リーダブルということ 『アンネの日記』 『彼女は頭が悪いから』 子どもたちの世界 宿題 ピカピカの息子 声 そば屋さん 山の上の家のまわり 長い読書 著者プロフィール 島田潤一郎 (シマダジュンイチロウ) (著/文) (しまだ・じゅんいちろう) 1976年高知県生まれ、東京育ち。日本大学商学部会計学科卒業。アルバイトや派遣社員をしながら小説家を目指す。2009年、出版社「夏葉社」をひとりで設立。「何度も、読み返される本を。」という理念のもと、文学を中心とした出版活動を行う。著書に『あしたから出版社』(ちくま文庫 2022)、『古くてあたらしい仕事』(新潮文庫 2024、近刊)、『90年代の若者たち』(岬書店 2019)、『本屋さんしか行きたいとこがない』(同 2020)、『父と子の絆』(アルテスパブリッシング 2020)、『電車のなかで本を読む』(青春出版社 2023)がある。 *ここに掲載する略歴は本書刊行時のものです。 ISBN:978-4-622-09698-6 Cコード:0095 四六判256ページ 発行:みすず書房 初版年月日: 2024年4月16日
-

目の見えない人は世界をどう見ているのか
¥550
【中古 状態きれい】 (参考:定価760円+税) ☆店長のひと言 「私がもし視覚を失ったら…、今のところ不安しかないのですが。さて。」 紹介 私たちは日々、五感―視覚・聴覚・嗅覚・触覚・味覚―からたくさんの情報を得て生きている。なかでも視覚は特権的な位置を占め、人間が外界から得る情報の八〜九割は視覚に由来すると言われている。では、私たちが最も頼っている視覚という感覚を取り除いてみると、身体は、そして世界の捉え方はどうなるのか??? 美学と現代アートを専門とする著者が、視覚障害者の空間認識、感覚の使い方、体の使い方、コミュニケーションの仕方、生きるための戦略としてのユーモアなどを分析。目の見えない人の「見方」に迫りながら、「見る」ことそのものを問い直す。 目次 【序 章】見えない世界を見る方法 【第1章】空 間 ― 見える人は二次元、見えない人は三次元? 【第2章】感 覚 ― 読む手、眺める耳 【第3章】運 動 ― 見えない人の体の使い方 【第4章】言 葉 ― 他人の目で見る 【第5章】ユーモア ― 生き抜くための武器 著者紹介 伊藤亜紗(いとうあさ) 1979年東京都生まれ。東京工業大学リベラルアーツセンター准教授。専門は美学、現代アート。もともと生物学者を目指していたが、大学三年次より文系に転向。2010年に東京大学大学院人文社会系研究科基礎文化研究専攻美学芸術学専門分野博士課程を単位取得のうえ退学。同年、博士号を取得(文学)。日本学術振興会特別研究員などを経て2013年より現職。研究のかたわら、アート作品の制作にもたずさわる。主な著作に『ヴァレリーの芸術哲学、あるいは身体の解剖』(水声社)、参加作品に小林耕平《タ?イ?ム?マ?シ?ン》(国立近代美術館)などがある。 ISBN 978-4-334-03854-0 新書判 発行 光文社 書店発売日 2015年4月16日

-

ほの暗い永久から出でて
¥550
【中古 帯に破れあり】 (参考:定価: 650円+税) ☆店長のひと言 「ホラー映画みたいなタイトルですが、中身は逆です。」 紹介 世界的な物語作家と聖路加の気鋭の漢方医が打ち合う、生命を巡る白熱のラリー! 『精霊の守り人』から医学の未来まで、知的好奇心を刺戟する圧倒的な面白さ! なんのために生まれ、なんのために生き、なんのために死ぬのか。 人は、答えが出ないとわかっている問いを、果てしなく問い続けるような脳を与えられて、生まれてきたのでしょうか。--上橋菜穂子 なんのための生なのか、という問いは、いささか弱音のようにも聞こえるのですが、この弱音こそが、優れた物語の書き手である上橋さんの「創作の源泉」であるように私には見えてくるのです。--津田篤太郎 最愛の母の肺がん判明をきっかけに出会った作家と医者。 二人の話は、身体のシステム、性(セックス)、科学・非科学、自然災害、宗教、音楽、絵画、AI、直感……、漫画から古典、最新の論文にいたるまで縦横無尽に広がっていき、物語の創作の源泉もひもとかれていく。かつてないほど刺激的な思考体験ができる究極の一冊。 コロナ禍にみまわれた2020年、文庫化にあたって、新章「未曽有の難局にどう向き合うか」(津田篤太郎)、「地球に宿る」(上橋菜穂子)を追加。 【著者略歴】 上橋菜穂子 1962年東京生まれ。立教大学文学部卒業。文学博士。川村学園女子大学特任教授。89年『精霊の木』で作家デビュー。著書に『精霊の守り人』をはじめとする「守り人」シリーズ、『狐笛のかなた』『獣の奏者』『鹿の王』など。野間児童文芸賞、路傍の石文学賞、本屋大賞、日本医療小説大賞など数多くの賞に輝き、2014年には児童文学のノーベル賞といわれる国際アンデルセン賞作家賞を受賞する。 津田篤太郎 1976年京都生まれ。京都大学医学部卒業。医学博士。聖路加国際病院リウマチ膠原病センター副医長、日本医科大学付属病院東洋医学科非常勤講師、北里大学東洋医学総合研究所客員研究員。西洋医学と東洋医学の両方を取り入れた診療を実践している。著書に『未来の漢方』(共著)、『病名がつかない「からだの不調」とどうつき合うか』『漢方水先案内』がある。 ISBN:978-4-16-791566-7 Cコード:0195 文庫判224ページ 発行:文藝春秋 書店発売日: 2020年9月2日
-

子どもたちの階級闘争
¥1,980
【中古 状態きれい】 (参考:定価: 2,400円+税) ☆店長のひと言 「無償化で解決する問題なんてむしろ問題ではないわけでして。」 紹介 「わたしの政治への関心は、ぜんぶ託児所からはじまった。」英国の地べたを肌感覚で知り、貧困問題や欧州の政治情勢へのユニークな鑑識眼をもつ書き手として注目を集めた著者が、保育の現場から格差と分断の情景をミクロスコピックに描き出す。 2008年に著者が保育士として飛び込んだのは、英国で「平均収入、失業率、疾病率が全国最悪の水準」と言われる地区にある無料の託児所。「底辺託児所」とあだ名されたそこは、貧しいけれど混沌としたエネルギーに溢れ、社会のアナキーな底力を体現していた。この託児所に集まる子どもたちや大人たちの生が輝く瞬間、そして彼らの生活が陰鬱に軋む瞬間を、著者の目は鋭敏に捉える。ときにそれをカラリとしたユーモアで包み、ときに深く問いかける筆に心を揺さぶられる。 著者が二度目に同じ託児所に勤めた2015-2016年のスケッチは、経済主義一色の政策が子どもの暮らしを侵蝕している光景であり、グローバルに進む「上と下」「自己と他者」の分断の様相の顕微描写である。移民問題をはじめ、英国とEU圏が抱える重層的な課題が背景に浮かぶ。 地べたのポリティクスとは生きることであり、暮らすことだ──在英20年余の保育士ライターが放つ、渾身の一冊。 目次 はじめに──保育士とポリティクス I 緊縮託児所時代 2015-2016 リッチとプアの分離保育 パラレルワールド・ブルース コラム 子どもたちを取り巻く世界 1 貧困ポルノ オリバー・ツイストと市松人形 緊縮に唾をかけろ 貧者分断のエレジー コラム 子どもたちを取り巻く世界 2 RISE──出世・アンガー・蜂起 リトル・モンスターと地上の星々 ふぞろいのカボチャたち クールでドープな社会変革 ギャングスタラップ児とムスリム・プリンセス 天使を憐れむ歌 コスプレと戦争と平和 託児所から見たブレグジット コラム 子どもたちを取り巻く世界 3 フットボールとソリダリティ ターキッシュ・ホリデイ(トルコの休日) フードバンクの勃興とわれわれの衰退 ザ・フィナーレ 笑い勝つその日のために 中書き II 底辺託児所時代 2008-2010 あのブランコを押すのはあなた フューリーより赤く その先にあるもの。 ゴム手袋のヨハネ 小説家と底辺託児所 神の御使い 母獣。そして消えて行く子供たち 故国への提言──UK里親制度って、結構ボロックスだよ。 白髪のアリス 炊事場のスーザン・ボイル ロザリオ たどり着いたらいつもどしゃ降り 愛のモチーフ マイ・リトル・レイシスト ブライトン・ロック──ミテキシーとベッキーと、時々、ミッキー もう一人のデビー 人種と平等のもやもや──インクルージョン ある追悼 おわりに──地べたとポリティクス 初出一覧 著者プロフィール ブレイディみかこ (ブレイディミカコ) (著/文) 保育士・ライター・コラムニスト。著書に、『花の命はノー・フューチャー』(2005年、碧天舎。ちくま文庫より2017年改題復刊予定)、『アナキズム・イン・ザ・UK──壊れた英国とパンク保育士奮闘記』(2013年)、『ザ・レフト──UK左翼セレブ列伝』(2014年)(以上、Pヴァイン)、『ヨーロッパ・コーリング──地べたからのポリティカル・レポート』(2016年、岩波書店)、『THIS IS JAPAN──英国保育士が見た日本』(2016年、太田出版)、『いまモリッシーを聴くということ』(2017年4月刊予定、Pヴァイン)、『子どもたちの階級闘争――ブロークン・ブリテンの無料託児所から』(2017年4月、みすず書房)。雑誌『図書』に「女たちのテロル」を連載中。1996年から英国・ブライトン在住。 ISBN:978-4-622-08603-1 Cコード:0036 四六判296ページ 発行:みすず書房 書店発売日: 2017年4月19日

-

言葉の風景、哲学のレンズ
¥1,430
☆店長のひと言 「“店長のひと言”も、みなさんにどう伝わっているのやら。」 内容紹介 言葉のコミュニケーションは、希望と切実さと複雑さに満ちている。「紀伊國屋じんぶん大賞2023」第2位『言葉の展望台』著者が贈る、最新哲学エッセイ!「痛み」を伝える言葉、webの中の私の「言葉だけの場所」、「どういたしまして」の可愛さ、当事者視点からの語りかた、「からかい」が起きる場面、メタファーが見せてくれるもの、定義することへの懐疑、カミングアウトの意味とその先……。さまざまな哲学の概念や理論はそれぞれが一個のレンズで、このレンズを使って見た風景と、別のレンズを使って見た風景と、その両方を通した風景はすべて違っているかもしれないし、そのどれかが正しいわけではないかもしれない。でもいろいろなレンズを通してみることで、裸眼で見たのとは違う風景の可能性に気づき、新しい仕方で物事を理解したり語ったりしていくきっかけになるかもしれない。(本書「はじめに」より) 【目次】 痛みを伝える 言葉だけの場所 「どういたしまして!」の正体 該当せず からかいの輪のなかで たった一言でこんなにもずるい 給料日だね! 言葉のフィールド カミングアウト ぐねぐねと進む 安全な場所ーー『作りたい女と食べたい女』 命題を背負う 一緒に生きていくために 著者プロフィール 三木 那由他 (ミキ ナユタ) (著/文) 1985年、神奈川県生まれ。2013年、京都大学大学院文学研究科博士課程指導認定退学。2015年、博士(文学)。現在、大阪大学大学院人文学研究科講師。著書に『話し手の意味の心理性と公共性』『グライス 理性の哲学』、共著に『シリーズ新・心の哲学1 認知篇』、共訳書にブランダム『プラグマティズムはどこから来て、どこへ行くのか』がある。 ISBN:978-4-06-533680-9 Cコード:0095 四六判 160ページ 発行:講談社 発売日: 2023年11月09日
-

障害があり女性であること : 生活史からみる生きづらさ
¥2,750
☆店長のひと言 「“弱者”のステレオタイプ化や専門と言う名の縦割りから脱するには。」 紹介 障害のある女性48名の生活史から、「障害があり女性である人たち」を生きづらくさせている社会構造や差別について、深く考察した一冊。障害者について論じられるときには、性差別のせいで女性の声がかき消され、女性について論じられるときには障害者差別のせいで障害女性の声はかき消されるという状況がある。しかし、障害のある女性が受ける差別の実態を明らかにする試みはいまだ途上にあり、複雑に絡み合う問題を把握するためのデータは圧倒的に不足している。本書は、この不足を埋めることを試みるものである。 目次 第Ⅰ部 障害とジェンダーをめぐる困難 第Ⅱ部 ライフコースと性役割 第Ⅲ部 これまでとこれから 課題・論点 著者プロフィール 土屋 葉 (ツチヤヨウ) (著/文 | 編集) 1973年生まれ。専攻は家族社会学。お茶の水女子大学大学院人間文化研究科修了。博士(社会科学)。現在、愛知大学文学部教授。著書『障害者家族を生きる』(勁草書房)、共著『被災経験の聴きとりから考える――東日本大震災後の日常生活と公的支援』(生活書院)。障害学研究会中部部会の一員として編んだものに、『愛知の障害者運動――実践者たちが語る』(現代書館)がある。 ISBN:978-4-7684-3598-4 Cコード:0036 四六判320ページ 発行:現代書館 書店発売日: 2023年10月4日

-

かざらないひと 「私のものさし」で 私らしく生きるヒント
¥2,420
☆店長のひと言 「かざらないようにみえるまでの道のりな。」 紹介 「自分をどう魅せる?」から自由に見える、あのひとが考えていること フリーアナウンサー・赤江珠緒、家政婦&料理人・タサン志麻、産婦人科医・高尾美穂、フリーアナウンサー・堀井美香、「北欧、暮らしの道具店」店長・佐藤友子。 絶大な支持を集める「かざらない」たたずまいを持つ彼女たちの人生の軌跡を振り返り、その時々の「思い」に焦点を当てながら、何を大事にして生きてきたのかを紐解く濃厚インタビュー集。 他人のものさしに左右されず、でも世の中とうまく折り合いをつけながら、自分のものさしを持って生きている。そんなふうに見える彼女たちには、どんな思考と行動の蓄積があったのか。 その等身大の言葉の数々のなかに、あなた自身が大切にしていること、大切にしたいと思っていることと共鳴する何かがきっと見つかるはずです。 <本文より> たぶん私、カツオっぽいんですよね。――赤江珠緒 馬鹿にされても別にいいや、私は楽しいことやってるんだもん、みたいにずっと思っていますね。――タサン志麻 そこに同年代の女子がいれば当たり前に楽しく過ごすでしょ、という感覚で看護師さんたちに接してきました。――高尾美穂 自分そのものをそんなに大した人間じゃないと思っているのがベースにあるんでしょうね。そうすると、他の人の行動とか言葉も受け入れられる。――堀井美香 「かざらないひと」っていうタイトルの本に出ちゃっていいのかな、私、かざってるんで…。――佐藤友子 目次 「面白さ」を大事にするひと…赤江珠緒 モヤモヤを行ったり来たりする/山をぐるっと回って考えたい/「物語」から人間心理を学ぶ/「心がタフ」で続いてきた/女性という意識はなかったけれど/100%をめぐる葛藤/まだまだ自分に飽きてない 「納得」を大事にするひと…タサン志麻 自分の思いをうまく言葉にできなかった/不器用だからこそ誰よりも努力した/心が動く就職先を探し続けた/「なんか違う」をごまかしきれなかった/「家政婦」がいつでも戻れる場所に/私を変えた夫のロマンと田舎の暮らし/思いがあればレシピ以上のものができる 「意志」を大事にするひと…高尾美穂 自分は「凡人」だと感じたから/嫌がらせする人を達観して見ていた/好きなものは高校時代から変わらない/気づけば「人たらし」と言われていた/「あなたのいいところを私は知ってるよ」/すべてのことは自分で選べる/私たちは助け合って生きていく 「普通」を大事にするひと…堀井美香 人に見つからないように全力疾走/「東京の普通」に負い目を感じて/嫉妬しない、口出ししない夫婦関係/人をあまり敵と思わない/メインではない場所が落ち着く/普通の人の本物の言葉を届けたい/自分を身軽にしていくのが心地いい 「気持ち」を大事にするひと…佐藤友子 10代で自分をリセットした/「本当の自分」はノートのなかに/自分を広げていくことが心地いい/私のなかの、うるさい友子/「働く主婦」である私/「ひとりの星」を持っている人が好き/停滞している自分とも向き合いたい 版元から一言 「かざらない」人柄によって多くの人を惹きつけている5人の女性たちの濃厚なインタビューの言葉には、彼女たちが今の状態に至るまでに悩んだこと、頑張ってきたこと、大切にしてきたことがたくさん詰まっています。読んでくださった方が、気持ちがふっとラクになったり、背中を押されたりしながら、「自分のものさし」を育むヒントを得ていただければ嬉しいです。 ISBN:978-4-911191-01-9 Cコード:0095 A5判256ページ 発行:月と文社 初版年月日: 2024年2月15日
-

体育がきらい
¥750
【中古 状態きれい】 (参考:定価880円+税) ☆店長のひと言 「体育や給食が嫌いなことは知っていた。ただ誰も肯定しなかった。」 紹介 ボールが怖い、失敗すると怒られるなどの理由で嫌われがちな体育だが、強さや速さよりも重要なことがある。「嫌い」を哲学で解きほぐせば、体育の本質が見える。 先生はエラそうだし、ボールは怖い! 体育なんか嫌いだ!という児童生徒が増えています。なぜ、体育嫌いは生まれてしまうのでしょうか。授業、教員、部活動。問題は色々なところに潜んでいます。そんな「嫌い」を哲学で解きほぐせば、体育の本質が見えてきます。強さや速さよりも重要なこととは? 著者プロフィール 坂本拓弥(さかもと・たくや):1987年東京都生まれ。千葉大学教育学部を卒業。東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科を単位取得退学。博士(教育学)。明星大学教育学部助教を経て、現在は筑波大学体育系助教。専門は体育・スポーツ哲学。特に身体論と欲望論。共編著に『探究 保健体育教師の今と未来 20講』(大修館書店)、共著に『スポーツと遺伝子ドーピングを問う:技術の現在から倫理的問題まで』(晃洋書房)、『はじめて学ぶ体育・スポーツ哲学』(みらい)などがある。 ISBN:978-4-480-68461-5 Cコード:0237 新書判224ページ 発行:筑摩書房 発売日: 2023年10月6日
-

もうやってらんない
¥480
【中古 状態きれい】 (参考:定価2,500円+税) ☆店長のひと言 「“あのとき、実は傷ついたのよね。”とあとで言われたときの気持ちを思い出しました。」 紹介 ある日、アフリカ系アメリカ人のベビーシッター、エミラは、誘拐犯に間違えられてしまう。黒人差別だと怒る白人の雇い主アリックスは、抗議するようエミラを焚きつけるが、そのいっぽうで名誉黒人気取りの恋人がアリックスの元カレだと知ったエミラは――。 著者プロフィール カイリー・リード(Kiley Reid) 1987年、ロサンゼルス生まれ。アリゾナ大学とメアリーマウント・マンハッタン・カレッジで学ぶ。トルーマン・カポーティ財団のフェローシップを受けながら、数多くのピュリッツァー賞受賞者を輩出してきたアイオワ・ライターズ・ワークショップを修了した。2019年刊行の本書『もうやってらんない』は、デビュー作にしてブッカー賞にノミネートされ、全米での書籍の売れ行きに最も影響力があるとされる女優リース・ウィザースプーンのブッククラブの選定図書になった。現在ペンシルヴェニア州フィラデルフィア在住。 (Hayakawa Books & Magazinesより引用) ISBN:978-4-15-210098-6 Cコード:0097 四六判448ページ 発行:早川書房 発売日: 2022年4月5日
-

自閉症は津軽弁を話さない リターンズ 「ひとの気持ちがわかる」のメカニズム
¥1,100
☆店長のひと言 「話さないではなく話せないと思ってしまっていました。」 紹介 「自閉症の子って津軽弁話さないよね」妻の一言から調査は始まった。10年間の研究のすえ妻の正しさは証明され、この変わった研究は全国紙にも載る結果に。それから数年後、方言を話すようになった自閉症児が現れた――。多数者である私たちはどう方言を話すか、相手の意図をどう読み取っているか。そもそも「普通」の発達とは何かを問うことで、ことばの不思議から自閉スペクトラム症を捉えなおそうと試みる画期的ノンフィクション。 第I部 自閉スペクトラム症の振る舞いと認知の謎 第1章 音声の絶対音感者 第2章 自閉症は熊本弁がわからない 第3章 人はどうやってことば遣いを選ぶのか――社会的関係性と心理的関係性 第4章 なぜ、ごっこ遊びでは共通語を使うのか 第5章 印象としての方言 第6章 意図とミラーニューロン――行為を見ることの意味 第7章 意図とコミュニケーション――目標とプランの読み取り 第8章 意図と協同作業――なぜ、意図を読むことが大切なのか 第9章 ルール間の葛藤――社会的ルールとオリジナルルール 第10章 社会的手がかりへの選好のパラドクス ――わからないから注意を向けないのか、注意を向けていないからわからないのか 第11章 伝わる情報、広がる情報――ミームの概念 第12章 共同注意と情報の共有 第13章 もしも自閉スペクトラム症の子が25人、定型発達の子が5人のクラスがあったら 第14章 おさらい 第II部 新たなる謎 第15章 方言を話すようになった自閉スペクトラム症 第16章 再び調査開始 第17章 ケースの実態 第18章 なぜ、自閉スペクトラム症も方言を話すようになるのか ――社会的スキルの獲得と関係性の変化 第19章 自閉症は日本語を話さない 目次 第I部 自閉スペクトラム症の振る舞いと認知の謎 第1章 音声の絶対音感者 第2章 自閉症は熊本弁がわからない 第3章 人はどうやってことば遣いを選ぶのか――社会的関係性と心理的関係性 第4章 なぜ、ごっこ遊びでは共通語を使うのか 第5章 印象としての方言 第6章 意図とミラーニューロン――行為を見ることの意味 第7章 意図とコミュニケーション――目標とプランの読み取り 第8章 意図と協同作業――なぜ、意図を読むことが大切なのか 第9章 ルール間の葛藤――社会的ルールとオリジナルルール 第10章 社会的手がかりへの選好のパラドクス ――わからないから注意を向けないのか、注意を向けていないからわからないのか 第11章 伝わる情報、広がる情報――ミームの概念 第12章 共同注意と情報の共有 第13章 もしも自閉スペクトラム症の子が25人、定型発達の子が5人のクラスがあったら 第14章 おさらい 第II部 新たなる謎 第15章 方言を話すようになった自閉スペクトラム症 第16章 再び調査開始 第17章 ケースの実態 第18章 なぜ、自閉スペクトラム症も方言を話すようになるのか ――社会的スキルの獲得と関係性の変化 第19章 自閉症は日本語を話さない 著者プロフィール 松本 敏治 (マツモトトシハル) (著/文) 1957年生まれ。博士(教育学)。公認心理師、特別支援教育士スーパーバイザー、臨床発達心理士。1987年、北海道大学大学院教育学研究科博士後期課程単位取得退学。1987~89年、稚内北星学園短期大学講師。89~91年、同助教授。91~2000年、室蘭工業大学助教授。00~03年、弘前大学助教授。03~16年9月、弘前大学教授。11~14年、弘前大学教育学部附属特別支援学校長。14~16年9月、弘前大学教育学部附属特別支援教育センター長。16年10月より、教育心理支援教室・研究所『ガジュマルつがる』代表。 ISBN:978-4-04-400781-2 Cコード:0147 文庫判272ページ 発行:KADOKAWA 初版年月日: 2023年8月25日
-

正しいパンツのたたみ方
¥350
【中古 状態きれい】 (参考:定価840円+税) ☆店長のひと言 「パンツのたたみ方から人生論が広がります。」 内容紹介 家庭科は,自分の暮らしを自分で整える力だけでなく,この社会の中で他者とともに生きていく力を育ててくれる教科だと実感した著者は,自ら専任教員となる.ご飯の作り方,お金とのつきあい方,時間の使い方など自立にあたってどんな知識や技術が必要か,10代の暮らしに沿って具体的にアドバイスする. 目次 はじめに 序章 家庭科を学ぶ意味 パンツのたたみ方に悩む男性に温かいアドバイスを/お互いの違いを知る教科/あなたは家庭科が好きですか? 1章 いま,生きているワタシ 目指せ! 弁当高校生/さわやかな朝の目覚めのために/朝ご飯が一日を変える/自立ってなんだろう?/勉強ってなんだろう?/副教科は強い味方! 2章 家族の中で生きる 家族って誰のこと?/家族のかたち/わたし的家族のボーダーライン/自分にとっての家族/家族の食卓/食事作りの宿題/家族の条件/「理想の結婚相手」で考える人間関係 3章 社会の中で生きている 働くということ/何のために働きますか/支え合って生きる/いろいろあるぞ,お金の問題/悪徳商法と消費者の問題/「なぜ,騙されたんだろう」/かしこい消費者になろう/働くっていうことは/アルバイトを始めてみると/お金はこわい!/経済的な自立/労働者としての権利/ワークライフバランス/老後のことはまだ早い?/100歳になった自分/もうひとつの感想/老後に備える/実習大好き!!/プロフェッショナルとパーソナル/パーソナルな技術がなぜ必要か 終章 ゆたかに生きるためのスキル あなたの遊びはどのレベル?/DVフリーの恋愛関係/メッセージを送り続ける/「依存でもなく「支配」でもなく/一人でいるのも楽しいけれど,二人でいるともっと楽しい おわりに 著者プロフィール 南野忠晴(みなみの ただはる) 1958年大阪府堺市生まれ.大阪府立高校英語科教員として13年間勤めながら,家庭科で教員採用試験を再受験.大阪府立高校で初の男性家庭科教員のひとりとなる.NHK教育テレビ高校講座「家庭総合」講師,「家庭科教員をめざす男の会」世話人.市民を対象とした「ジェンダー入門講座」や「生き方講座」など,講演会の講師としても活躍している.著書に『はじめて語るメンズリブ批評』(共著,東京書籍),『教育とはなんだ』(共著,筑摩書房)など. (岩波書店ホームページより引用) ISBN:978-4-00-500674-8 Cコード:0237 新書判224ページ 発行:岩波書店 発売日: 2011年2月18日
-

病と障害と、傍らにあった本。
¥2,200
☆店長のひと言 「本のいいところは、自分のペースで向き合えるところ。」 紹介 病名や障害の名前ではひとくくりにできない、その実情。それゆえにその只中にいる人は、心身のつらさのみならず、誰とも分かち合えない想いに孤独に陥りがちになる。そんな時、外の世界と自分の内とを繋ぐ「窓」となる本は、あったのか。12人12様の病や障害の体験と本との関わりについて綴る本書は、固有な体験としての病や障害の実情と、生きることの「意志」の現れでもある「読む」ことの力を伝える一冊です。 目次 【本を知る】 齋藤陽道 母の絵日記 頭木弘樹 本嫌いが病気をして本好きになるまで 岩崎航 病をふくめた姿で 【本が導く】 三角みづ紀 物語に導かれて 田代一倫 写真と生活 和島香太郎 てんかんと、ありきたりな日常 【本が読めない】 坂口恭平 ごめん、ベケット 鈴木大介 本が読めない。 【本と病と暮らしと】 與那覇潤 リワークと私―ブックトークがあった日々 森まゆみ 体の中で内戦が起こった。―原田病と足るを知る暮らし― 【本と、傍らに】 丸山正樹 常にそこにあるもの 川口有美子 それは、ただ生きて在ること 前書きなど 病名や障害の名でひと括りにできない 固有の症状や想い。 誰かと分かち合うこともできなくて、ひとり。 そんなとき、傍らには どんな本があったのか。 版元から一言 病や障害といった、重いテーマを扱いながら、本書に収録したエッセイにはどれも不思議と、一筋の光が指しているように思える。それは「読む」という行為に生きるという意志が含まれているからなのか。読後感は希望を見出す一冊です。 著者プロフィール 齋藤 陽道 (サイトウ ハルミチ) (著/文) 一九八三年東京都生まれ。写真家。生まれつき聞こえに障害がある感音性難聴と診断を受ける。中学生まで「聴文化」で育ったのち、都立石神井ろう学校入学を機に「日本手話」と出会う。またその頃から写真を始める。二〇一〇年に写真新世紀優秀賞受賞。二〇一一年、写真集『感動』、二〇一九年『感動、』(いずれも赤々舎)刊行。二〇一三年、ワタリウム美術館にて個展「宝物」開催。私生活では同じく感音性難聴である写真家、盛山麻奈美と結婚。二人の間に生まれた子供は二人とも聴者だった。二〇二〇年、息子へ歌う子守唄をきっかけに「うた」を探る日々を追ったドキュメンタリー映画『うたのはじまり』(河合宏樹監督)が公開。エッセイ集に二〇一八年刊行『声めぐり』(晶文社)、『異なり記念日』(医学書院)他多数。 頭木 弘樹 (カシラギ ヒロキ) (著/文) 文学紹介者。大学三年の二十歳のときに潰瘍性大腸炎を患い、十三年間の闘病生活を送る。そのときにカフカの言葉が救いとなった経験から二〇一一年、『絶望名人カフカの人生論』(飛鳥新社、のちに新潮文庫)、二〇一六年『絶望読書―苦悩の時期、私を救った本』(飛鳥新社、のちに河出文庫)、二〇一九年などの著書を刊行。また、ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』をミステリーとして再構成した『ミステリー・カット版 カラマーゾフの兄弟』(春秋社)、落語にも造詣が深く、『落語を聴いてみたけど面白くなかった人へ』(ちくま文庫)他著書多数。同年、潰瘍性大腸炎の闘病の日々を詳細に綴った『食べること出すこと』(医学書院)を刊行。NHK「ラジオ深夜便」の『絶望名言』コーナーに出演中。 岩崎 航 (イワサキ ワタル) (著/文) 一九七六年宮城県生まれ。詩人。本名は、岩崎稔。三歳の頃に筋ジストロフィーを発症。十七歳の頃、未来に絶望し死を考えたが、「病をふくめたありのままの姿」で自分の人生を生きようと思いを定める。現在は胃ろうからの経管栄養と人工呼吸器を使い、在宅医療や介護のサポートを得て自宅で暮らす。二十五歳から詩作、二〇〇四年から五行歌を詠む。二〇一三年、詩集『点滴ポール 生き抜くという旗印』(写真・齋藤陽道、ナナロク社)が大きな話題を呼ぶ。二〇一五年、エッセイ集『日付の大きいカレンダー』、二〇一八年、兄の岩崎健一が絵を、航が詩を綴った共著の画詩集『いのちの花、希望のうた』(以上、いずれもナナロク社)刊行。二〇二〇年、第二詩集『震えたのは』刊行予定。 三角 みづ紀 (ミスミ ミヅキ) (著/文) 一九八一年鹿児島県生まれ。東京造形大学に進学。一年生の冬に膠原病の全身性エリテマトーデスとの診断を受ける。その頃から詩の投稿をはじめ、二〇〇四年、第四十二回現代詩手帖賞受賞。同年、第一詩集『オウバアキル』にて第十回中原中也賞受賞。第二詩集『カナシヤル』で南日本文学賞と歴程新鋭賞を受賞。二〇一四年、第五詩集『隣人のいない部屋』で第二十二回萩原朔太郎賞を史上最年少で受賞。書評やエッセイの執筆も多く、二〇一七年、エッセイ集『とりとめなく庭が』(ナナロク社)刊行。ワークショップや詩のコピーライティングなど活動は多岐に渡り、中でも朗読活動を精力的に行う。スロヴェニア、リトアニア、イタリア、ベルギーなど多くの国際詩祭に招聘される。二〇二〇年、詩集『どこにでもあるケーキ』(ナナロク社)刊行。 田代 一倫 (タシロ カズトモ) (著/文) 一九八〇年福岡県生まれ。写真家。二〇〇〇年、大学在学中にうつ病と診断を受ける。九州産業大学大学院在学中の二〇〇六年、福岡市でアジア フォトグラファーズ ギャラリーの設立、運営に参加。同年、三木淳賞奨励賞受賞。韓国、九州で肖像写真を中心に撮影、発表。二〇一〇年に東京、新宿の photographers ‘galleryに拠点を移す。二〇一三年、東日本大震災の被災地の人々を撮影した『はまゆりの頃に 三陸、福島 2011~2013年』(里山社)刊行。同年さがみはら写真新人奨励賞を受賞。二〇一四年より東京の人々の撮影を開始、東京都写真美術館他で発表。二〇一七年に韓国・鬱陵島の人々を撮影した『ウルルンド』(KULA)刊行。二〇一七年秋より双極性障害を発症。二〇二〇年九月に新潟、砂丘館にて個展開催。 和島 香太郎 (ワジマ コウタロウ) (著/文) 一九八三年山形県生まれ。中学三年生の時に、てんかんと診断される。映像の世界を志して進学した京都造形芸術大学で、ドキュメンタリー映画監督、佐藤真に師事。二〇〇八年、文化庁若手映画作家育成プロジェクトに選出され、『第三の肌』を監督。二〇一二年、監督作品『小さなユリと 第一章・夕方の三十分』が、SKIPシティ国際Dシネマ映画祭短編部門にて奨励賞受賞。二〇一七年より、これまで知られることの少なかったてんかん患者の日々を素朴に語り合うポッドキャストラジオ「ぽつラジオ」を開始。二〇一九年、坪田義史監督のドキュメンタリー映画『だってしょうがないじゃない』で編集を担当。 坂口 恭平 (サカグチ キョウヘイ) (著/文) 一九七八年熊本県生まれ。二〇〇四年、路上生活者の住居を撮影した写真集『0円ハウス』(リトルモア)刊行。以降、ルポルタージュ、小説、思想書、画集、料理書など多岐にわたるジャンルの書籍、音楽、絵などを発表している。二〇一一年五月、福島第一原発事故後の政府の対応に疑問を抱き、自ら新政府初代内閣総理大臣を名乗り、新政府を樹立。希死念慮に苦しむ人々との対話を「いのっちの電話」として、自らの携帯電話(〇九〇-八一〇六-四六六六)の番号を公開。近年は投薬なしの生活を送るようになり、二〇二〇年、その経験と「いのっちの電話」をもとに行ったワークショップを誌上で再現した『自分の薬をつくる』(晶文社)、また「いのっちの電話」を十年続けてわかったことを記した『苦しい時は電話して』(講談社新書)を刊行。また、自らの「薬」として描いた風景画集『Pastel』(左右社)刊行。 鈴木 大介 (スズキ ダイスケ) (著/文) 一九七三年千葉県生まれ。文筆業。貧困からセックスワークに就く女性や子ども、詐欺集団など、社会の斥力の外にある人々をおもな取材対象とするルポライターとして執筆活動を行い、主な著書に『最貧困女子』(幻冬舎新書)など。しかし二〇一五年、四十一歳の時に突然、脳梗塞を発症。身体の麻痺は軽度だったが、その後遺症として記憶障害、認知障害などの高次機能障害が残る。その体験を綴ることを自らのリハビリとし、二〇一六年『脳が壊れた』、二〇一八年『脳は回復する 高次脳機能障害からの脱出』(いずれも新潮新書)を刊行。また、二〇一八年、高次機能障害と発達障害などの類次点を探った『されど愛しきお妻様 -「大人の発達障害」の妻と「脳が壊れた」僕の18年間』(講談社)、二〇二〇年『「脳コワさん」支援ガイド』(医学書院)、『不自由な脳』(金剛出版)など。小説に『里奈の物語』(文藝春秋)がある。 與那覇 潤 (ヨナハ ジュン) (著/文) 一九七九年神奈川県生まれ。歴史学者。地方公立大学に勤務していた二〇一四年に双極性障害を発症し、休職を経て離職。二〇一八年、自身の体験を踏まえた『知性は死なない』(文藝春秋)、二〇二〇年、『心を病んだらいけないの?』(斎藤環と共著、新潮選書)などの著作で、精神病理を切り口に現代社会の諸問題を考察している。本書では挙げきれなかったリハビリ中に影響された書物についても、後者のブックガイドで紹介した。その他、二〇〇九年、博士論文をまとめた『翻訳の政治学』(岩波書店)、二〇一一年、大学在職時の講義録をまとめた『中国化する日本』(文藝春秋、後に文庫化)、二〇一三年、『日本人はなぜ存在するか』(集英社、後に文庫化)などを刊行、著書その他多数。 森 まゆみ (モリ マユミ) (著/文) 一九五四年東京都生まれ。作家。一九八四年、季刊の地域雑誌「谷中・根津・千駄木」を創刊し、地元の人々の聞き書きをベースにした雑誌づくりで地域コミュニティの活性化に貢献。一九九二年、サントリー地域文化賞受賞。一九九八年『鷗外の坂』(新潮社)で芸術選奨文部大臣新人賞、二〇一四年『『青踏』の冒険:女が集まって雑誌をつくるということ』(平凡社)で紫式部文学賞受賞。他著書多数。二〇〇七年、自己免疫疾患である原田病に罹患。二〇一〇年、病後の日々を綴った『明るい原田病日記―私の体の中で内戦が起こった』(亜紀書房)を刊行。みずからの病の体験と東日本大震災を経て、「足る事を知る」ことの重要性を今一度再確認すべく、二〇一七年、縮小社会研究会の松久寛氏との共著『楽しい縮小社会』(筑摩書房)を刊行。近著に『本とあるく旅』(産業編集センター)など。 丸山 正樹 (マルヤマ マサキ) (著/文) 一九六一年東京都生まれ。シナリオライターとして活動。頸椎損傷という重い障害を持つ妻と生活をともにするうち、さまざまな障害を持つ人たちと交流するようになる。次第に、何らかの障害を持った人の物語を書くことを模索するようになり、二〇一一年、ろう者の両親のもと育った聴者の主人公が手話通訳士となって事件解決に一役買うミステリー小説『デフ・ヴォイス』(文藝春秋)でデビュー。同作が『デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳士』として文庫化(文春文庫)されたのに続き、『龍の耳を君に』(創元推理文庫)、『慟哭は聴こえない』(東京創元社)として人気シリーズとなり、二〇二〇年、スピンオフとして『刑事何森 孤高の相貌』(東京創元社)も刊行。他、居所不明児童をテーマにした『漂う子』(文春文庫)など。 川口 有美子 (カワグチ ユミコ) (著/文) 一九六二年東京都生まれ。都立西高卒(三三期生)。夫の海外赴任のためロンドンで暮らしていた最中の一九九五年、母がALSに罹患。その介護体験を記した『逝かない身体――ALS的日常を生きる』(医学書院)で二〇一〇年、第四十一回大宅壮一ノンフィクション賞受賞。他に『末期を越えて』(青土社)、共編著に『在宅人工呼吸器ケア実践ガイド―ALS生活支援のための技術・制度・倫理』(医歯薬出版)など。副理事長を務めるNPO法人さくら会ではヘルパー養成研修会を毎月開催。当面の目標は日本の難病呼吸器ユーザーの豊かな生を世界に知らしめること。都内マンションで猫3匹と理学療法士を目指す息子と同居中。