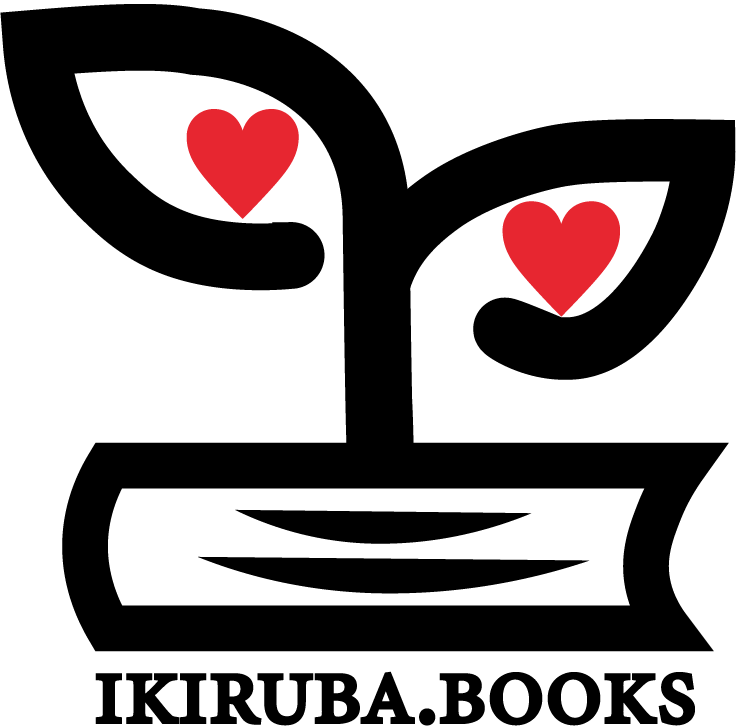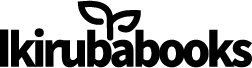-

ビッグイシュー518号
¥500
☆店長のひと言 「鳥には鳥以外の声は何に聞こえてるんですかね?雑音?」 【内容紹介】 特集 シジュウカラは言葉を話す 鈴木俊貴さん(動物言語学者/東京大学准教授)は街の中を歩いていて、鳥の声が聞こえてくると言葉として理解できるといいます。まるでドリトル先生のようではないですか。そんな稀有な能力を、大学3年生の冬から長野県の軽井沢にある「野鳥の森」で研究を始め、これまで20年にもおよぶ研究生活によって手に入れました。 特に、シジュウカラを対象に、森の中に巣箱をかけて鳥たちの繁殖や子育ての様子を観察し、多様な実験を繰り返した結果、仲間を集める鳴き声、ヘビやハシブトガラス、猛禽類などに対し、警戒を促す鳴き声を特定。ヒナたちも親鳥の鳴き声を聞き分けるなど、シジュウカラにも言葉があることを証明しました。さらに、2つの言葉を組み合わせて文をつくること、文法があることなど、感動的な事実を明らかにしてきました。 今や国際的に認められ、国内外で大きな反響を呼ぶ鈴木さんの研究と、新たに創設した学問「動物言語学」について聞きました。 TOP INTERVIEW スペシャルインタビュー 森洋子 緻密な鉛筆画で、子どもたちが想像と現実を行き来する世界を描いた絵本『かえりみち』『おるすばん』などで知られる森洋子さん。そんな森さんの新作『ある星の汽車』は、ある星の生き物の未来を問いかける、美しく胸を打つ絵本。昨年10月に発売、すでに4刷を重ねるほど注目を集めています。 森さんに作家としての道のりと、『ある星の汽車』の誕生などについて聞きました リレーインタビュー・私の分岐点「ALOHA7」代表。元アナウンサー 大木優紀さん 唯一の趣味だった「旅行」を仕事に。家族でハワイに移住した今が分岐点 国際記事 イタリア。シチリアの「アンドロメダ劇場」 イタリア西南部の地中海に浮かぶシチリア島。ロレンツォ・レイナは牧羊を本業としながら独学で建築を学び、約40年かけて野外の劇場やオブジェを創り上げました。天文学にインスピレーションを得たその独特な創造性は、どこから生まれ、どのように実現したのでしょうか?そんな彼が、できあがるまでの軌跡や想いを語ります。 WORLD STREET NEWS 世界短信 連載記事 原発ウォッチ! 「原発停止で国富流出」は“印象論” 浜矩子の新ストリート・エコノミクス 岩と硬い平面の挟間で 雨宮処凛の活動日誌 「この国で未来を描く」ことが「違法」とされる子どもたち ホームレス人生相談 体力維持のために心がけていることは? ジェンダー平等を目指す地方議会議員候補者を支援 ――わたしたちのバトン基金 女性議員比率が先進国でいまだ最低水準の日本。地方議会議員に立候補を考える人たちの壁になっているのが、選挙に出るための「金銭面での不安」です。そうした経済的なリスクをサポートする「わたしたちのバトン基金」が設立されました。代表の能條桃子さんに話を聞きました。 読者のページ My Opinion 販売者に会いにゆく カナダ『リティネレール』ラボワ 夜パン模様 「捨てない」を目指す思いをともに 監督インタビュー 『愛がきこえる』沙漠 監督 FROM EDITORIAL 編集後記 (ビッグイシュー日本HPより抜粋)
-

見えないスポーツ図鑑
¥1,500
【中古 表紙に汚れあり(画像参照)】 (参考:定価2,000円+税) ☆店長のひと言 「見た目をコピーしてもうまくいかないのって、こういうことなんでしょうね。」 紹介 研究者たちが考えていることって――実はめちゃくちゃ面白い。 抱腹絶倒&試行錯誤の「本邦初」、研究ドキュメンタリー 視覚障害者の方々にスポーツの臨場感をどう伝えるか、から始まった研究は「スポーツ」を翻訳することに向かった。 研究をスタートさせるも、相次ぐ失敗が壁となって立ちはだかる。 しかし、そんなことでは研究者は諦めない! 思わぬアイディアから方向を転換し、十種目の競技のエキスパートとタッグを組んで「人力VR」の開発に挑むことに!? 【各氏、推薦!】 相馬千秋氏(アートプロデューサー) ゲーム性、緊張感、駆け引き、速度、バランス……スポーツを「翻訳」すると、それはもはやアート!誰かのからだに創造的に憑依するための、身体感覚翻訳マニュアル、決定版。 太田雄貴氏(公益社団法人日本フェンシング協会会長) フェンシングの翻訳なんて……できるんだ! 競技者の間でも話題沸騰。さっそくアルファベットを揃えました。 稲見昌彦氏(東京大学総長補佐・教授/超人スポーツ協会代表理事) 「見ることは信じること(Seeing is Believing)」という諺、実は「感じることこそ真実(but Feeling is the Truth)」と続く。 本書は、スポーツを見ることの背後にある、本質(バーチャリティ)に迫ります。 目次 はじめに――伊藤亜紗 第1章:ラグビーを翻訳する――古川拓生 第2章:アーチェリーを翻訳する――高井秀明 第3章:体操を翻訳する――水島宏一 第4章:卓球を翻訳する――吉田和人 第5章:テニスを翻訳する――遠藤 愛 第6章:セーリングを翻訳する――久保田秀明 第7章:フェンシングを翻訳する――千田健太 第8章:柔道を翻訳する――石井孝法 第9章:サッカーを翻訳する――堀野博幸 第10章:野球を翻訳する――福田岳洋 おうちで翻訳 おわりに――渡邊淳司 あとがき――林阿希子 https://www.parasapo.tokyo/topics/101110 著者プロフィール 伊藤亜紗 (イトウアサ) (著/文) 美学者。東京工業大学科学技術創成研究院未来の人類研究センター/リベラルアーツ研究教育院准教授。MIT客員研究員(2019)。2010年に東京大学大学院人文社会系研究科博士課程を単位取得のうえ退学。同年、博士号を取得(文学)。主な著作に『目の見えない人は世界をどう見ているのか』(2015、光文社)、『どもる体』(2018、医学書院)、『記憶する体』(2019、春秋社)、『手の倫理』(講談社、近日刊行)など。 渡邊淳司 (ワタナベジュンジ) (著/文) NTTコミュニケーション科学基礎研究所 上席特別研究員(NTTサービスエボリューション研究所2020エポックメイキングプロジェクト 兼任)。主著に『情報を生み出す触覚の知性』(2014、化学同人、毎日出版文化賞(自然科学部門)受賞)、『情報環世界』(2019、NTT出版、共著)、『表現する認知科学』(2020、新曜社)など。文化庁メディア芸術祭での受賞、Ars Electronica Prixでの受賞や審査員等、表現・体験領域での活動にも関わる。 林阿希子 (ハヤシアキコ) (著/文) NTTサービスエボリューション研究所 2020エポックメイキングプロジェクト 主任研究員。大阪大学大学院生命機能研究科修了。 人間中心設計の研究者として、高齢者向けウェブデザインの研究や、空港での人流誘導サインの実証実験、物体認識技術を用いた展示会アプリの開発等に携わる。ユーザの心理・行動モデルの研究を行う一方で、実サービス化に向けた体験創造を行う 。 共著に『ウェブユニバーサルデザイン』(2014、近代科学社)。 ISBN:978-4-7949-7192-0 Cコード:0095 四六判312ページ 発行: 晶文社 初版年月日: 2020年10月10日

-

80歳、まだ走れる
¥2,860
☆店長のひと言 「マスターズには夢がある。誰ですか、自分はマヨネーズでいいなんて言ってるのは。」 内容紹介 老いを甘んじて受け入れる必要はない ランニングに打ち込んできた著者は、人生の半ばで絶望に打ちひしがれていた。怪我に悩まされ、体力とスピードの衰えに意気消沈し、走ることを諦めようと思ったとき、高齢者スポーツの驚くべき世界に出会う。そして、マスターズ世界陸上で人生を変える体験をすることになる。本書は絶望から希望へと向かう一人の男性の非常に個人的な記録であると同時に、ライフスタイルとトレーニングを調整することで生理学的な衰えの進行を遅らせることができること、そして人間の精神力によって高齢になっても楽しく健康的に走り続けられることを証明した画期的なガイドブックでもある。 スポーツの楽しさが年齢によって失われていると感じているすべての人への希望のメッセージ。 著者プロフィール リチャード・アスクウィズ (著/文) 英国の著名なランニング作家・ジャーナリストの一人。受賞歴多数。 栗木 さつき (クリキ サツキ) (翻訳) 翻訳家。慶應義塾大学経済学部卒。50歳で初めてフルマラソンを完走、マイペースでマラソンを続けている。訳書にブラッチュリー『運を味方にする「偶然」の科学』(東洋経済新報社)、キャロル『パレットジャーナル』(ダイヤモンド社)、シネック『WHYから始めよ!インスパイア型リーダーはここが違う』(日本経済新聞出版)、シュミル『Numbers Don’t Lie』(共訳)、フォックス『SWITCHCRAFT 切り替える力』(以上、NHK出版)など。 ISBN:978-4-7917-7677-1 Cコード:0075 四六判406ページ 発行: 青土社 発売日: 2024年9月27日

-

幻肢痛日記
¥2,090
☆店長のひと言 「大切なものほど失ってから気付くのと似ていると言えないでしょうか。」 内容紹介 切断した筈なのに、足のあった場所が痛む。「ない」のに「痛い」とはどういうことだろう? 右足を失った「僕」が経験した不思議な現象、幻肢痛から考えた、わからないものについての記録。 (河出書房新社ホームページより引用) https://bookandbeer.com/event/bb241118a/ 著者プロフィール 青木 彬 (アオキ アキラ) (著/文) 1989年生。キュレーター。首都大学東京インダストリアルアートコース卒。アートを「よりよく生きるための術」と捉えアーティストや企業等と協同しアートプロジェクトを企画。著書に『素が出るワークショップ』。 ISBN:978-4-309-23162-4 Cコード:0036 四六判200ページ 発行: 河出書房新社 初版年月日: 2024年10月25日
-

夜明けを待つ
¥1,980
紹介 生と死を見つめ続けてきたノンフィクション作家の原点がここに! 私たちは10年という長い年月を、とことん「死」に向き合って生きてきた。 しかし、その果てにつかみとったのは、「死」の実相ではない。 そこに見えたのは、ただ「生きていくこと」の意味だ。 親は死してまで、子に大切なことを教えてくれる。 (第1章「『死』が教えてくれること」より) 家族、病、看取り、移民、宗教……。 小さき声に寄り添うことで、大きなものが見えてくる。 『エンジェルフライト』『紙つなげ!』『エンド・オブ・ライフ』『ボーダー』……。 読む者の心を揺さぶる数々のノンフィクションの原点は、 佐々涼子の人生そのものにあった。 ここ10年に書き溜めてきたエッセイとルポルタージュから厳選! 著者初の作品集。 (目次より抜粋) 第1章 エッセイ 「死」が教えてくれること 夜明けのタクシー 体はぜんぶ知っている 今宵は空の旅を 命は形を変えて この世の通路 幸福への意思 もう待たなくていい ダイエット ハノイの女たち 未来は未定 夜明けを待つ 痛みの戒め 柿の色 ひろちゃん 和製フォレスト・ガンプ 誰にもわからない トンネルの中 スーツケース 梅酒 ばあばの手作り餃子 縁は異なもの 第2章 ルポルタージュ ダブルリミテッド1 サバイバル・ジャパニーズ ダブルリミテッド2 看取りのことば ダブルリミテッド3 移動する子どもたち ダブルリミテッド4 言葉は単なる道具ではない 会えない旅 禅はひとつ先の未来を予言するか 悟らない オウム以外の人々 遅効性のくすり 佐々涼子(ささ りょうこ) ノンフィクション作家。1968年生まれ。神奈川県出身。早稲田大学法学部卒。日本語教師を経てフリーライターに。2012年、『エンジェルフライト 国際霊柩送還士』(集英社)で第10回開高健ノンフィクション賞を受賞。2014年に上梓した『紙つなげ! 彼らが本の紙を造っている 再生・日本製紙石巻工場』(早川書房)は、紀伊國屋書店キノベス!第1位、ダ・ヴィンチBOOK OF THE YEAR第1位、新風賞特別賞などに、2020年の『エンド・オブ・ライフ』(集英社インターナショナル)は、Yahoo!ニュース|本屋大賞2020年 ノンフィクション本大賞に輝いた。他の著書に『ボーダー 移民と難民』(集英社インターナショナル)など。 2024年9月、悪性脳腫瘍のため横浜市戸塚区の自宅で死去。56歳没 ISBN:978-4-7976-7438-5 Cコード:0095 四六判 272ページ 発行: 集英社インターナショナル 発売日: 2023年11月24日

-

体はゆく できるを科学する〈テクノロジー×身体〉
¥1,400
【中古 状態きれい】 (参考:定価1,600円+税) ☆店長のひと言 「器用な人って頭で体を縛っていないということなのかも。」 紹介 「できなかったことができる」って何だろう? 技能習得のメカニズムからリハビリへの応用まで―― ・「あ、こういうことか」意識の外で演奏ができてしまう領域とは ・なぜ桑田真澄選手は投球フォームが違っても結果は同じなのか ・環境に介入して体を「だます」“農業的”テクノロジーの面白さ ・脳波でしっぽを動かす――未知の学習に必要な体性感覚 ・「セルフとアザーのグレーゾーン」で生まれるもの ……etc. 古屋晋一(ソニーコンピュータサイエンス研究所)、柏野牧夫(NTTコミュニケーション科学基礎研究所)、小池英樹(東京工業大学)、牛場潤一(慶應義塾大学)、暦本純一(東京大学大学院)ら、5人の科学者/エンジニアの先端研究を通して、「できる」をめぐる体の“奔放な”可能性を追う。 日々、未知へとジャンプする“体の冒険”がここに 著者プロフィール 伊藤 亜紗 (イトウ アサ) (著/文) 東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授、東京工業大学科学技術創成研究院未来の人類研究センター長。東京大学大学院人文社会系研究科美学芸術学専門分野博士課程修了(文学博士)。専門は美学、現代アート。著書に『ヴァレリーの芸術哲学、あるいは身体の解剖』(水声社)、『目の見えない人は世界をどう見ているのか』(光文社新書)、『目の見えないアスリートの身体論』(潮新書)、『どもる体』(医学書院)、『記憶する体』(春秋社)、『手の倫理』(講談社メチエ)、『体はゆく できるを科学する〈テクノロジー×身体〉』(文藝春秋)など多数。 ISBN:978-4-16-391631-6 Cコード:0095 四六判248ページ 発行: 文藝春秋 発売日: 2022年11月28日

-

「能力」の生きづらさをほぐす
¥1,980
【中古 カバー、帯にスレあり(画像参照)】 (参考:定価2,000円+税) ☆店長のひと言 「女子力、人間力、免疫力、長州力…、いろいろ言われても疲れちゃうよね。」 紹介 【発売たちまち重版!】 生きる力、リーダーシップ力、コミュ力… ◯◯力が、私たちを苦しめる。 組織の専門家が命をかけて探究した、他者と生きる知恵。 前職では「使えない」私が、現職では「優秀」に。 それって、本当に私の「能力」なの? 移ろいがちな他人の評価が、生きづらさを生み出す能力社会。 ガン闘病中の著者が、そのカラクリを教育社会学と組織開発の視点でときほぐし、 他者とより良く生きるあり方を模索する。 目次 はじめに プロローグ 母さん、僕は仕事のできない、能力のないやつですか? 第1話 能力の乱高下 第2話 能力の化けの皮剝がし―教育社会学ことはじめ 第3話 不穏な「求める能力」―尖るのを止めた大学 第4話 能力の泥沼―誰も知らない本当の私 第5話 求ム、能力屋さん―人材開発業界の価値 第6話 爆売れ・リーダーシップ―「能力」が売れるカラクリ① 第7話 止まらぬ進化と深化―「能力」が売れるカラクリ② 第8話 問題はあなたのメンタル―能力開発の行き着く先 第9話 葛藤をなくさない―母から子へ エピローグ 母さん、ふつうでない私は幸せになれますか? 伴走者からの言葉 磯野真穂 おわりに 著者プロフィール 勅使川原 真衣 (テシガワラ マイ) (著) てしがわら・まい:1982年横浜生まれ。東京大学大学院教育学研究科修士課程修了。BCG、ヘイ グループなど外資コンサルティングファーム勤務を経て独立。2017年に組織開発を専門とする、おのみず株式会社を設立し、企業はもちろん、病院、学校などの組織開発を支援する。二児の母。2020年から乳ガン闘病中。 磯野 真穂 (イソノ マホ) (執筆伴走) いその・まほ:人類学者。専門は文化人類学、医療人類学。2010年早稲田大学文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。早稲田大学文化構想学部助教、国際医療福祉大学大学院准教授を経て2020年より独立。 著書に『なぜふつうに食べられないのか-―拒食と過食の文化人類学』(春秋社)、『医療者が語る答えなき世界――「いのちの守り人」の人類学』(ちくま新書)、『ダイエット幻想――やせること、愛されること』(ちくまプリマ―新書)、『他者と生きる』(集英社新書)、共著に『急に具合が悪くなる』(晶文社)がある。本作では、著者の執筆に伴走し、言葉を寄せる。 訂正のお知らせ: 初版第1刷p105の5行目に訂正がございました。以下を修正いたします。 ×社会教育学者 → ○教育社会学者 ISBN:978-4-910534-02-2 Cコード:0095 四六判264ページ 発行: どく社 初版年月日: 2022年12月25日
-

治りませんように : べてるの家のいま
¥800
SOLD OUT
【中古 状態きれい】 (参考:定価2,400円+税) ☆店長のひと言 「売れますように」 紹介 精神障害やアルコール依存などを抱える人びとが、北海道浦河の地に共同住居と作業所"べてるの家"を営んで30年。 べてるの家のベースにあるのは「苦労を取りもどす」こと-保護され代弁される存在としてしか生きることを許されなかった患者としての生を抜けだして、一人ひとりの悩みを、自らの抱える生きづらさを、苦労を語ることばを取りもどしていくこと。 べてるの家を世に知らしめるきっかけとなった『悩む力』から8年、浦河の仲間のなかに身をおき、数かぎりなく重ねられてきた問いかけと答えの中から生まれたドキュメント。 目次 記憶 死神さん べてるの家 浦河弁 なつひさお 救急通い 遭難者 あきらめる 立ち往生 新しい薬 幻聴とダンス 生きる糧 青年の死 ぺてるの葬儀 その人を語る 爆発系 ピア・サポート 撤退 当事者研究 アイメッセージ 収穫の秋 病気への依存 人間アレルギー 治さない 日だまり 苦労の哲学 しあわせにならない 著者プロフィール 斉藤道雄 (サイトウミチオ) (著/文) 1947年生まれ。ジャーナリスト。TBSテレビ報道局の記者、ディレクター、プロデューサー、解説者として報道番組の取材、ドキュメンタリー番組の制作に従事。先端医療、生命倫理、マイノリティ、精神障害、ろう教育などをテーマとしてきた。2008年から5年間、明晴学園の校長、その後4年間、理事長を務めた。著書に『原爆神話の五〇年』(中公新書、1995)『もうひとつの手話』(晶文社、1999)『悩む力――べてるの家の人びと』(みすず書房、2002)『希望のがん治療』(集英社新書、2004)『治りませんように――べてるの家のいま』(みすず書房、2010)『手話を生きる――少数言語が多数派日本語と出会うところで』(みすず書房、2016)『治したくない――ひがし町診療所の日々』(みすず書房、2020)がある。 ISBN:978-4-622-07526-4 四六判 251ページ 発行: みすず書房 初版年月日: 2010年2月17日
-

しにたい気持ちが消えるまで
¥1,570
【中古 状態きれい】 (参考:定価1,600円+税) ☆店長のひと言 「死にたいも生きたいも自然なこと。でもそれだけでは終わらない。」 紹介 16歳のとき、死のうと思った。すごく天気の良い日で、こんな日に死ねるなんて幸せだと思った。自宅のベランダから飛び降り、頸髄を損傷するが一命をとりとめる。 「死ななくて良かった」、「何もできなくても生きていていい」 現在を生きる筆者による、自死を止めたい、やさしくなりたい、お守りのような言葉。書き下ろし自伝エッセイ。 著者プロフィール 豆塚エリ (マメツカエリ) (著/文) 1993年、愛媛県生まれ。16歳のとき、飛び降り自殺を図り頸髄を損傷、現在は車椅子で生活する。大分県別府市で、こんぺき出版を拠点に、詩や短歌、短編小説などを発表。NHK Eテレ『ハートネットTV』に出演するなど、幅広く活動中。 ISBN:978-4-7796-4671-3 Cコード:0095 四六判304ページ 発行:三栄 発売日: 2022年9月16日
-

おりがみ大全集 完全版
¥800
【バーゲンブック※】 (参考:定価1,900円+税) ☆店長のひと言 「一枚の紙に命を吹き込むのはあなた!」 紹介 おりがみ本の決定版が、開きやすい大型上製本で登場! 日本国内では子どもから大人、お年寄りまで変わらない人気の「おりがみ」。国内だけでなく、アジア、欧米など海外からも熱い視線を集めています。 たった1枚の紙をおるだけで見事な立体に仕上がるおりがみは、日本が誇るアート。 お金も時間も広い場所も必要なく、幼稚園・保育園から大学まで、教育の現場でも格好の教材として古くから親しまれてきました。 幾何学的な思考力を育て、指先のトレーニングにもなり、紙を大切にする心も育てます。 この本は、鶴、かぶと、風船、だましぶねなどをはじめ、だれでもおったことがある人気の定番作品を中心に、おりたい作品、あこがれの作品をすべて集めた超保存版の1冊。 箸袋や小箱、季節の飾りなど、暮らしに役立つかわいい紙小物も手数紹介しています。 大きなイラスト、文字で開きやすい製本だから、テーブルや床に開いたまま置けて便利。オールカラー224ページという充実の決定版。 わかりやすい写真と正確なプロセスイラストを見ながらおれば、子ども、大人、お年寄りまで、難しくなく完成。 この1冊で一生役立つ、まさにおりがみの大百科全集。 1家に1冊常備して、家族みんなで楽しんでください ISBN:978-4-07-291693-3 Cコード:2077 AB判224ページ 発行:主婦の友社 発売日: 2013年12月13日 ※バーゲンブック(自由価格本)とは、出版社の意思で定価販売ではなく、割引販売できる未使用の本・雑誌のことです。通常本と区別するため裏表紙にシールが貼ってあります。

-

頭のうえを何かが Ones Passed Over Head
¥2,530
☆店長のひと言 「病床から描かれたものはリハビリというか成長の過程のようでした。」 紹介 「ストローク(脳梗塞)は僕にとって恩寵でした。そして深い教えでした。」 『抽象の力』(第69回芸術選奨文部科学大臣賞)の岡﨑乾二郎さんは、2021年10月に脳梗塞で倒れました。 倒れてから1ヵ月後に麻痺した右手で描いた40作以上の絵と「リハビリ記」(2万7千字)が収録されています。 本書は、カラー部分だけでも約100頁ある画集であり、病をも創造の糧とする示唆に溢れた手記でもあります。 前書きなど 【本書より】 2021年10月30日土曜日の23時でした。知り合いにPCでメッセージを送りはじめたときに指がもつれはじめ、腕から力が抜け、右手も右足も瞬く間に動かなくなりました。椅子からずり落ちるように、なんとか床に横たわりました。脳梗塞だと思いました。(リハビリ記 冒頭) 絵を再び描くなんてことはありえないと思い込んでいた一人の脳梗塞片麻痺患者にとって、目の前で出来上がっていく絵は、自分で描いたものであるにもかかわらず、人ごとのように驚きをもって見えたものである。だからスマホで家族やスタッフにそれを送った。ネコが自分が獲ったエモノ、見つけた事物を家人の手元に持っていって自慢するようなものである。(あとがきより抜粋) 著者プロフィール 岡﨑乾二郎 (オカザキケンジロウ) (著/文) https://kenjirookazaki.com/jpn/ 1955年東京生まれ。造形作家。批評家。セゾン現代美術館、豊田市美術館で大規模な個展を開催するとともに、美術批評を中心として執筆を続ける。主著に『ルネサンス 経験の条件』(文春学藝ライブラリー)、『抽象の力 近代芸術の解析』(亜紀書房/第69回芸術選奨文部科学大臣賞)、『感覚のエデン』(亜紀書房/第76回毎日出版文化賞〈文学・芸術部門〉)、『絵画の素 TOPICA PICTUS』(岩波書店)など。 ISBN:978-4-86732-023-5 Cコード:0071 A5横判144ページ 発行:ナナロク社 発売日: 2023年12月14日
-

自閉症は津軽弁を話さない リターンズ 「ひとの気持ちがわかる」のメカニズム
¥1,100
☆店長のひと言 「話さないではなく話せないと思ってしまっていました。」 紹介 「自閉症の子って津軽弁話さないよね」妻の一言から調査は始まった。10年間の研究のすえ妻の正しさは証明され、この変わった研究は全国紙にも載る結果に。それから数年後、方言を話すようになった自閉症児が現れた――。多数者である私たちはどう方言を話すか、相手の意図をどう読み取っているか。そもそも「普通」の発達とは何かを問うことで、ことばの不思議から自閉スペクトラム症を捉えなおそうと試みる画期的ノンフィクション。 第I部 自閉スペクトラム症の振る舞いと認知の謎 第1章 音声の絶対音感者 第2章 自閉症は熊本弁がわからない 第3章 人はどうやってことば遣いを選ぶのか――社会的関係性と心理的関係性 第4章 なぜ、ごっこ遊びでは共通語を使うのか 第5章 印象としての方言 第6章 意図とミラーニューロン――行為を見ることの意味 第7章 意図とコミュニケーション――目標とプランの読み取り 第8章 意図と協同作業――なぜ、意図を読むことが大切なのか 第9章 ルール間の葛藤――社会的ルールとオリジナルルール 第10章 社会的手がかりへの選好のパラドクス ――わからないから注意を向けないのか、注意を向けていないからわからないのか 第11章 伝わる情報、広がる情報――ミームの概念 第12章 共同注意と情報の共有 第13章 もしも自閉スペクトラム症の子が25人、定型発達の子が5人のクラスがあったら 第14章 おさらい 第II部 新たなる謎 第15章 方言を話すようになった自閉スペクトラム症 第16章 再び調査開始 第17章 ケースの実態 第18章 なぜ、自閉スペクトラム症も方言を話すようになるのか ――社会的スキルの獲得と関係性の変化 第19章 自閉症は日本語を話さない 目次 第I部 自閉スペクトラム症の振る舞いと認知の謎 第1章 音声の絶対音感者 第2章 自閉症は熊本弁がわからない 第3章 人はどうやってことば遣いを選ぶのか――社会的関係性と心理的関係性 第4章 なぜ、ごっこ遊びでは共通語を使うのか 第5章 印象としての方言 第6章 意図とミラーニューロン――行為を見ることの意味 第7章 意図とコミュニケーション――目標とプランの読み取り 第8章 意図と協同作業――なぜ、意図を読むことが大切なのか 第9章 ルール間の葛藤――社会的ルールとオリジナルルール 第10章 社会的手がかりへの選好のパラドクス ――わからないから注意を向けないのか、注意を向けていないからわからないのか 第11章 伝わる情報、広がる情報――ミームの概念 第12章 共同注意と情報の共有 第13章 もしも自閉スペクトラム症の子が25人、定型発達の子が5人のクラスがあったら 第14章 おさらい 第II部 新たなる謎 第15章 方言を話すようになった自閉スペクトラム症 第16章 再び調査開始 第17章 ケースの実態 第18章 なぜ、自閉スペクトラム症も方言を話すようになるのか ――社会的スキルの獲得と関係性の変化 第19章 自閉症は日本語を話さない 著者プロフィール 松本 敏治 (マツモトトシハル) (著/文) 1957年生まれ。博士(教育学)。公認心理師、特別支援教育士スーパーバイザー、臨床発達心理士。1987年、北海道大学大学院教育学研究科博士後期課程単位取得退学。1987~89年、稚内北星学園短期大学講師。89~91年、同助教授。91~2000年、室蘭工業大学助教授。00~03年、弘前大学助教授。03~16年9月、弘前大学教授。11~14年、弘前大学教育学部附属特別支援学校長。14~16年9月、弘前大学教育学部附属特別支援教育センター長。16年10月より、教育心理支援教室・研究所『ガジュマルつがる』代表。 ISBN:978-4-04-400781-2 Cコード:0147 文庫判272ページ 発行:KADOKAWA 初版年月日: 2023年8月25日
-

病と障害と、傍らにあった本。
¥2,200
☆店長のひと言 「本のいいところは、自分のペースで向き合えるところ。」 紹介 病名や障害の名前ではひとくくりにできない、その実情。それゆえにその只中にいる人は、心身のつらさのみならず、誰とも分かち合えない想いに孤独に陥りがちになる。そんな時、外の世界と自分の内とを繋ぐ「窓」となる本は、あったのか。12人12様の病や障害の体験と本との関わりについて綴る本書は、固有な体験としての病や障害の実情と、生きることの「意志」の現れでもある「読む」ことの力を伝える一冊です。 目次 【本を知る】 齋藤陽道 母の絵日記 頭木弘樹 本嫌いが病気をして本好きになるまで 岩崎航 病をふくめた姿で 【本が導く】 三角みづ紀 物語に導かれて 田代一倫 写真と生活 和島香太郎 てんかんと、ありきたりな日常 【本が読めない】 坂口恭平 ごめん、ベケット 鈴木大介 本が読めない。 【本と病と暮らしと】 與那覇潤 リワークと私―ブックトークがあった日々 森まゆみ 体の中で内戦が起こった。―原田病と足るを知る暮らし― 【本と、傍らに】 丸山正樹 常にそこにあるもの 川口有美子 それは、ただ生きて在ること 前書きなど 病名や障害の名でひと括りにできない 固有の症状や想い。 誰かと分かち合うこともできなくて、ひとり。 そんなとき、傍らには どんな本があったのか。 版元から一言 病や障害といった、重いテーマを扱いながら、本書に収録したエッセイにはどれも不思議と、一筋の光が指しているように思える。それは「読む」という行為に生きるという意志が含まれているからなのか。読後感は希望を見出す一冊です。 著者プロフィール 齋藤 陽道 (サイトウ ハルミチ) (著/文) 一九八三年東京都生まれ。写真家。生まれつき聞こえに障害がある感音性難聴と診断を受ける。中学生まで「聴文化」で育ったのち、都立石神井ろう学校入学を機に「日本手話」と出会う。またその頃から写真を始める。二〇一〇年に写真新世紀優秀賞受賞。二〇一一年、写真集『感動』、二〇一九年『感動、』(いずれも赤々舎)刊行。二〇一三年、ワタリウム美術館にて個展「宝物」開催。私生活では同じく感音性難聴である写真家、盛山麻奈美と結婚。二人の間に生まれた子供は二人とも聴者だった。二〇二〇年、息子へ歌う子守唄をきっかけに「うた」を探る日々を追ったドキュメンタリー映画『うたのはじまり』(河合宏樹監督)が公開。エッセイ集に二〇一八年刊行『声めぐり』(晶文社)、『異なり記念日』(医学書院)他多数。 頭木 弘樹 (カシラギ ヒロキ) (著/文) 文学紹介者。大学三年の二十歳のときに潰瘍性大腸炎を患い、十三年間の闘病生活を送る。そのときにカフカの言葉が救いとなった経験から二〇一一年、『絶望名人カフカの人生論』(飛鳥新社、のちに新潮文庫)、二〇一六年『絶望読書―苦悩の時期、私を救った本』(飛鳥新社、のちに河出文庫)、二〇一九年などの著書を刊行。また、ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』をミステリーとして再構成した『ミステリー・カット版 カラマーゾフの兄弟』(春秋社)、落語にも造詣が深く、『落語を聴いてみたけど面白くなかった人へ』(ちくま文庫)他著書多数。同年、潰瘍性大腸炎の闘病の日々を詳細に綴った『食べること出すこと』(医学書院)を刊行。NHK「ラジオ深夜便」の『絶望名言』コーナーに出演中。 岩崎 航 (イワサキ ワタル) (著/文) 一九七六年宮城県生まれ。詩人。本名は、岩崎稔。三歳の頃に筋ジストロフィーを発症。十七歳の頃、未来に絶望し死を考えたが、「病をふくめたありのままの姿」で自分の人生を生きようと思いを定める。現在は胃ろうからの経管栄養と人工呼吸器を使い、在宅医療や介護のサポートを得て自宅で暮らす。二十五歳から詩作、二〇〇四年から五行歌を詠む。二〇一三年、詩集『点滴ポール 生き抜くという旗印』(写真・齋藤陽道、ナナロク社)が大きな話題を呼ぶ。二〇一五年、エッセイ集『日付の大きいカレンダー』、二〇一八年、兄の岩崎健一が絵を、航が詩を綴った共著の画詩集『いのちの花、希望のうた』(以上、いずれもナナロク社)刊行。二〇二〇年、第二詩集『震えたのは』刊行予定。 三角 みづ紀 (ミスミ ミヅキ) (著/文) 一九八一年鹿児島県生まれ。東京造形大学に進学。一年生の冬に膠原病の全身性エリテマトーデスとの診断を受ける。その頃から詩の投稿をはじめ、二〇〇四年、第四十二回現代詩手帖賞受賞。同年、第一詩集『オウバアキル』にて第十回中原中也賞受賞。第二詩集『カナシヤル』で南日本文学賞と歴程新鋭賞を受賞。二〇一四年、第五詩集『隣人のいない部屋』で第二十二回萩原朔太郎賞を史上最年少で受賞。書評やエッセイの執筆も多く、二〇一七年、エッセイ集『とりとめなく庭が』(ナナロク社)刊行。ワークショップや詩のコピーライティングなど活動は多岐に渡り、中でも朗読活動を精力的に行う。スロヴェニア、リトアニア、イタリア、ベルギーなど多くの国際詩祭に招聘される。二〇二〇年、詩集『どこにでもあるケーキ』(ナナロク社)刊行。 田代 一倫 (タシロ カズトモ) (著/文) 一九八〇年福岡県生まれ。写真家。二〇〇〇年、大学在学中にうつ病と診断を受ける。九州産業大学大学院在学中の二〇〇六年、福岡市でアジア フォトグラファーズ ギャラリーの設立、運営に参加。同年、三木淳賞奨励賞受賞。韓国、九州で肖像写真を中心に撮影、発表。二〇一〇年に東京、新宿の photographers ‘galleryに拠点を移す。二〇一三年、東日本大震災の被災地の人々を撮影した『はまゆりの頃に 三陸、福島 2011~2013年』(里山社)刊行。同年さがみはら写真新人奨励賞を受賞。二〇一四年より東京の人々の撮影を開始、東京都写真美術館他で発表。二〇一七年に韓国・鬱陵島の人々を撮影した『ウルルンド』(KULA)刊行。二〇一七年秋より双極性障害を発症。二〇二〇年九月に新潟、砂丘館にて個展開催。 和島 香太郎 (ワジマ コウタロウ) (著/文) 一九八三年山形県生まれ。中学三年生の時に、てんかんと診断される。映像の世界を志して進学した京都造形芸術大学で、ドキュメンタリー映画監督、佐藤真に師事。二〇〇八年、文化庁若手映画作家育成プロジェクトに選出され、『第三の肌』を監督。二〇一二年、監督作品『小さなユリと 第一章・夕方の三十分』が、SKIPシティ国際Dシネマ映画祭短編部門にて奨励賞受賞。二〇一七年より、これまで知られることの少なかったてんかん患者の日々を素朴に語り合うポッドキャストラジオ「ぽつラジオ」を開始。二〇一九年、坪田義史監督のドキュメンタリー映画『だってしょうがないじゃない』で編集を担当。 坂口 恭平 (サカグチ キョウヘイ) (著/文) 一九七八年熊本県生まれ。二〇〇四年、路上生活者の住居を撮影した写真集『0円ハウス』(リトルモア)刊行。以降、ルポルタージュ、小説、思想書、画集、料理書など多岐にわたるジャンルの書籍、音楽、絵などを発表している。二〇一一年五月、福島第一原発事故後の政府の対応に疑問を抱き、自ら新政府初代内閣総理大臣を名乗り、新政府を樹立。希死念慮に苦しむ人々との対話を「いのっちの電話」として、自らの携帯電話(〇九〇-八一〇六-四六六六)の番号を公開。近年は投薬なしの生活を送るようになり、二〇二〇年、その経験と「いのっちの電話」をもとに行ったワークショップを誌上で再現した『自分の薬をつくる』(晶文社)、また「いのっちの電話」を十年続けてわかったことを記した『苦しい時は電話して』(講談社新書)を刊行。また、自らの「薬」として描いた風景画集『Pastel』(左右社)刊行。 鈴木 大介 (スズキ ダイスケ) (著/文) 一九七三年千葉県生まれ。文筆業。貧困からセックスワークに就く女性や子ども、詐欺集団など、社会の斥力の外にある人々をおもな取材対象とするルポライターとして執筆活動を行い、主な著書に『最貧困女子』(幻冬舎新書)など。しかし二〇一五年、四十一歳の時に突然、脳梗塞を発症。身体の麻痺は軽度だったが、その後遺症として記憶障害、認知障害などの高次機能障害が残る。その体験を綴ることを自らのリハビリとし、二〇一六年『脳が壊れた』、二〇一八年『脳は回復する 高次脳機能障害からの脱出』(いずれも新潮新書)を刊行。また、二〇一八年、高次機能障害と発達障害などの類次点を探った『されど愛しきお妻様 -「大人の発達障害」の妻と「脳が壊れた」僕の18年間』(講談社)、二〇二〇年『「脳コワさん」支援ガイド』(医学書院)、『不自由な脳』(金剛出版)など。小説に『里奈の物語』(文藝春秋)がある。 與那覇 潤 (ヨナハ ジュン) (著/文) 一九七九年神奈川県生まれ。歴史学者。地方公立大学に勤務していた二〇一四年に双極性障害を発症し、休職を経て離職。二〇一八年、自身の体験を踏まえた『知性は死なない』(文藝春秋)、二〇二〇年、『心を病んだらいけないの?』(斎藤環と共著、新潮選書)などの著作で、精神病理を切り口に現代社会の諸問題を考察している。本書では挙げきれなかったリハビリ中に影響された書物についても、後者のブックガイドで紹介した。その他、二〇〇九年、博士論文をまとめた『翻訳の政治学』(岩波書店)、二〇一一年、大学在職時の講義録をまとめた『中国化する日本』(文藝春秋、後に文庫化)、二〇一三年、『日本人はなぜ存在するか』(集英社、後に文庫化)などを刊行、著書その他多数。 森 まゆみ (モリ マユミ) (著/文) 一九五四年東京都生まれ。作家。一九八四年、季刊の地域雑誌「谷中・根津・千駄木」を創刊し、地元の人々の聞き書きをベースにした雑誌づくりで地域コミュニティの活性化に貢献。一九九二年、サントリー地域文化賞受賞。一九九八年『鷗外の坂』(新潮社)で芸術選奨文部大臣新人賞、二〇一四年『『青踏』の冒険:女が集まって雑誌をつくるということ』(平凡社)で紫式部文学賞受賞。他著書多数。二〇〇七年、自己免疫疾患である原田病に罹患。二〇一〇年、病後の日々を綴った『明るい原田病日記―私の体の中で内戦が起こった』(亜紀書房)を刊行。みずからの病の体験と東日本大震災を経て、「足る事を知る」ことの重要性を今一度再確認すべく、二〇一七年、縮小社会研究会の松久寛氏との共著『楽しい縮小社会』(筑摩書房)を刊行。近著に『本とあるく旅』(産業編集センター)など。 丸山 正樹 (マルヤマ マサキ) (著/文) 一九六一年東京都生まれ。シナリオライターとして活動。頸椎損傷という重い障害を持つ妻と生活をともにするうち、さまざまな障害を持つ人たちと交流するようになる。次第に、何らかの障害を持った人の物語を書くことを模索するようになり、二〇一一年、ろう者の両親のもと育った聴者の主人公が手話通訳士となって事件解決に一役買うミステリー小説『デフ・ヴォイス』(文藝春秋)でデビュー。同作が『デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳士』として文庫化(文春文庫)されたのに続き、『龍の耳を君に』(創元推理文庫)、『慟哭は聴こえない』(東京創元社)として人気シリーズとなり、二〇二〇年、スピンオフとして『刑事何森 孤高の相貌』(東京創元社)も刊行。他、居所不明児童をテーマにした『漂う子』(文春文庫)など。 川口 有美子 (カワグチ ユミコ) (著/文) 一九六二年東京都生まれ。都立西高卒(三三期生)。夫の海外赴任のためロンドンで暮らしていた最中の一九九五年、母がALSに罹患。その介護体験を記した『逝かない身体――ALS的日常を生きる』(医学書院)で二〇一〇年、第四十一回大宅壮一ノンフィクション賞受賞。他に『末期を越えて』(青土社)、共編著に『在宅人工呼吸器ケア実践ガイド―ALS生活支援のための技術・制度・倫理』(医歯薬出版)など。副理事長を務めるNPO法人さくら会ではヘルパー養成研修会を毎月開催。当面の目標は日本の難病呼吸器ユーザーの豊かな生を世界に知らしめること。都内マンションで猫3匹と理学療法士を目指す息子と同居中。
-

言葉を失ったあとで
¥1,800
SOLD OUT
【中古 帯の破損※以外は状態きれい(画像参照)】 (参考:定価1,800円+税) ☆店長のひと言 「被害者を減らすためにも加害者への理解と支援は必要なんだけれど、それを声高に主張すると世間様に叩かれるという…。」 紹介 アディクション・DVの第一人者と、沖縄で若い女性の調査を続ける教育学者。現場に居続ける二人が真剣に、柔らかく、具体的に語る、「聞く」ことの現実。 「聞くの実際」。アディクション・DVの第一人者と、沖縄で社会調査を続ける教育学者。それぞれの来歴から被害/加害をめぐる理解の仕方まで、とことん具体的に語りあった対談集。 【目次】 まえがき 信田さよ子 第一章 言葉を失ったあとで 二〇二〇年一一月二七日 中立の立場とはなにか/加害者の話をどう聞くか/加害を書けるか/加害者が被害を知る/性被害の特殊性/仏壇継承者/暴力の構造を知る/スタイルの違い/学校が話を聞けない場所に/援助が料金に見合うか/質疑応答へ/加害者の普通さ/厳罰化は何も解決しない/言葉をいっしょに探す/ゼロ・トレランスの弊害/まずはいい時間をつくる/三つの責任 読書案内① 第二章 カウンセリングという仕事、社会調査という仕事 二〇二一年二月六日 精神科医にできないこと/教室の実践記録のおもしろさ/原点は児童臨床のグループ/沖縄から離れて/「性の自己決定」の実際/社会調査が示すこと/医者になるか、女性のアルコールやるか/女性の依存症の特異さ/八〇年代の精神病院の経験が一生を決めた/生身の人間の話がおもしろい/ネクタイを褒める/沈黙に強くなる 読書案内② 第三章 話を聞いて書く 二〇二〇年二月二三日 精神疾患の鋳型/解離は手ごわい/医療との関係/加害はパターン化している/精神科の役割/値踏みされている/お金をもらうか払うか/許諾のとりかた/書く責任/モスバーガーの文脈/身体は触らない/身体は自分のもの/聞きとりのあと/トランスクリプトの確認の仕方 読書案内③ 第四章 加害と被害の関係 二〇二一年三月一二日 被害者元年/起源は七〇年代/仲間は当事者/学校現場の変化/公認心理師の国家資格/被害者の両義性/暴力をなくす練習/加害者プログラムの順番/加害者の書きづらさ/映画で描かれる暴力/打越正行さんの調査 読書案内④ 第五章 言葉を禁じて残るもの 二〇二一年三月二七日 性被害をどのように語りはじめるのか/臓器がぶらさがっている感覚/フラッシュバックの意味/被害経験の読み替え/選択肢のすくなさ/家族の性虐待/語りのフォーマット/言葉を禁じる/性加害者の能動性/ユタを買う/一二月の教室/オープンダイアローグの実践 読書案内⑤ 第六章 ケアと言葉 二〇二一年五月一一日 カウンセリングに来るひとたち/男性の語りのパターン/加害者の語り/加害者プログラムの肝/DV被害者支援と警察/家族はもうだめなのか?/使えるものはぜんぶ使う/親との関係を聞く/被害者共感の効果/権力と言葉/「加害者」という言葉の危うさ/ブルーオーシャンへ/被害者は日々生まれている/当事者の納得する言葉 読書案内⑥ あとがき――「聞く」の現場の言葉を聞く 上間陽子 著者プロフィール 信田 さよ子 (ノブタ サヨコ) (著/文) 1946年、岐阜県生まれ。公認心理師・臨床心理士。原宿カウンセリングセンター顧問、NPO法人RRP研究会の代表理事。著作に『家族と国家は共謀する』(角川新書)、『増補新版 ザ・ママの研究』(新曜社)、『カウンセラーは何を見ているか』(医学書院)など多数。 上間 陽子 (ウエマ ヨウコ) (著/文) 1972年、沖縄県生まれ。琉球大学教育学研究科教授。生活指導の観点から主に非行少年少女の問題を研究。著作に『海をあげる』(筑摩書房)、『裸足で逃げる』(太田出版)、共著に『地元を生きる』(ナカニシヤ出版)など。 ISBN:978-4-480-84322-7 Cコード:0095 四六判352ページ 発行:筑摩書房 発売日: 2021年12月2日
-

91歳セツの新聞ちぎり絵 ポストカードブック
¥1,650
☆店長のひと言 「スーパーでパスコの食パンを見る度にセツさんの作品を思い出します。」 紹介 89歳で夫を亡くし、2019年1月、90歳から始めた新聞ちぎり絵作品と人生の聞き書きを収録した『90 歳セツの新聞ちぎり絵』は5刷に! 旺盛な食欲を感じさせるハンバーガーやお盆のお供物の剣先イカなど、バラエティに富んだモチーフとユーモラスな言葉、精緻な表現力で注目を集める。世界中が閉塞感に包まれた2020年も、変わらず毎日創作を続け、表現力も観察眼も深化。 主に、91歳になった2020年の1年間で作った新作を中心に、32点を収録したコメント付ポストカードブックが出来ました。セツさんの創作の源を探る読み物(ちぎり絵くふう解説/ 1 日のすごし方/セツさんの「昔のしごと」他)も充実。 なかなか会えない遠くのあの人へ、セツさんの明るいパワーをポストカードで送るも良し、作品集として純粋に楽しむも良し、な一冊です。 目次 ひとことコメントつきポストカード32点/【読み物】「セツさんのちぎり絵くふう解説」「セツさんの1日」「孫から見た ばあちゃんというヒト・木村いこ」 前書きなど 誰かを喜ばせることを何よりの喜びとして働き続けてきた。おいしいものができたら、おすそわけ。趣味といえば、食べることくらいだった。 2018 年11 月、89 歳のとき夫を亡くし、気力を落とした。2019 年のお正月、娘に勧められ、90 歳で新聞ちぎり絵を始めた。孫が作品をツイッターに投稿すると、またたく間に話題になった。見知らぬ誰かの喜ぶ声が力になり、腕を上げた。ツイッターのフォロワーはいつしか4万人を越えていた。 2020 年、91 歳。変わらずに生き生きと作品を作り続けた。世界中が呆然と立ち止まったこの年も進化し続けた。91 歳の1年間に生み出された作品を中心に、ポストカードブックを作りました。 なかなか会えない遠くのあの人へ、セツさんの明るいパワーをおすそわけしていただけましたら幸いです。 版元から一言 第1弾『90歳セツの新聞ちぎり絵』は、コロナ以後、なかなか簡単に会うことのできない遠くの家族や知り合いを元気づけるために、プレゼント用としても喜ばれてきました。そこで、91歳になり、ますます旺盛な創作意欲で、表現力もより一層深みを増す木村セツの新聞ちぎり絵を、今回はポストカードブックにしてみました。遠くにいる大事なあの人へ、セツさんの明るいパワーをおすそわけしていただけましたら幸いです。 著者プロフィール 木村 セツ (キムラ セツ) (画) 1929 年(昭和4年)1月7日奈良県桜井市生まれ。戦争中は学徒動員により、紡績工場で働く。戦後、銀行に勤めるが、家庭の事情で退職。3人の子供を育てながら、養鶏、喫茶店、農業などの仕事に励む。2018年末に夫が他界。2019 年元旦から長女の勧めで新聞ちぎり絵を始め、才能が開花。ツイッターアカウントはフォロワー数4 万人以上(2021年1月現在)。90 歳の1 年間につくった作品を集めた作品集『90歳セツの新聞ちぎり絵』(里山社)が好評発売中。 関連リンク http://satoyamasha.com/books/2512 ISBN:978-4-907497-13-2 Cコード:0071 A6変80ページ 発行:里山社 初版年月日: 2021年2月28日

-

英語で「日本」を話すための音読レッスン〈CD付き〉
¥980
【中古 状態きれい】 (参考:定価1,600円+税) ☆店長のひと言 「Do you know Japan?」 内容紹介 「日本」を紹介するストーリーを読むことで、雑談や会話にそのまま使える音読の本。usefull expressionも加え、実戦的な1冊。寺と神社の違いや、英語公用語化等35のストーリーで、楽しみながら読める。 著者プロフィール 浦島久(うらしま・ひさし) 1952年北海道豊頃町生まれ。小樽商科大学(経営学)、帯広畜産大学修士課程(農業経済)を修了。大学卒業後に松下電器産業株式会社(現社名:パナソニック株式会社)へ入社するが、1977年に北海道へUターンし、帯広市にて英会話学校「イングリッシュハウス・ジョイ」を設立。現在は、ジョイ・イングリッシュ・アカデミー学院長、小樽商科大学特認教授、写真家。 著書に『話せる! 英語音読【初級編】』(共著、日本実業出版)、『自分を語る英語』(ジャパンタイムズ)、『1分間英語で自分のことを話してみる』(共著、中経出版)、『自分のこと100言う英会話』(共著、ダイヤモンド社)他多数。これまで韓国で5冊、台湾で1冊が翻訳出版されている。趣味は、音楽(ジャズ、ヒーリング系の音楽が好き)、旅行(これまで旅した国は19か国)、カーリング(世界シニアカーリング選手権2009、2010、2013に出場)。 マイケル ・ノア アメリカ・オハイオ州生まれ。オハイオ大学卒。日本にて私立高校、英会話学校などで英語教師として勤務。日本での滞在はトータル20年間。現在はハワイにて英語教材・出版物の執筆、校閲に携わる。著書に『話せる! 英語音読【初級編】』(共著、日本実業出版)がある。 (日本実業出版社ホームページより引用) ISBN:978-4-534-05119-6 Cコード:0082 A5判 発行:日本実業出版社 書店発売日: 2013年09月27日
-

「毎日音読」で人生を変える ~活力が出る・若くなる・美しくなる~
¥1,050
【中古 状態きれい】 (参考:定価1,500円+税) ☆店長のひと言 「試しに読んで見たら、自信が崩壊しました。」 紹介 生島ヒロシさん、推薦!寺田式音読の凄い力! 「オレたちひょうきん族」などで人気を博した元フジテレビアナウンサーが還暦を迎えたとYahoo!ニュースなどで紹介された。その寺田理恵子が50代で見事に復活!それを支えたのが「音読」だった! 2000年からは仕事を離れ専業主婦として生活していたが、父の死、母の認知症に夫の急逝が重なり、心身がボロボロに。そんなどん底時代に、生島ヒロシさんに声をかけてもらう。14年もブランクがあるのに……「大丈夫、できるよ」と生島さんに背中を押され、ラジオ番組に出演が決まる。その日から「音読」トレーニングをはじめ、成果は歴然。そうした体験をもとに、いまでは朗読教室を主宰。 本書は、音読にあたってのセルフカウンセリングから、声をよくするレッスン、滑舌がよくなるレッスンもカバー、「風立ちぬ」「夢十夜」「心の飛沫」「だしの取り方」などなど、著者厳選の音読テキストを掲載。 目次 はじめに なぜ「音読」をはじめたか 第1章 音読はいいことだらけ! 第2章 簡単! 寺田式音読レッスン 第3章 たのしく「毎日音読」! 著者プロフィール 寺田理恵子 (テラダリエコ) (著/文) 元フジテレビアナウンサー。「心とからだ磨きの朗読」主宰。 東京都に生まれる。聖心女子大学文学部を卒業。武蔵野大学人間関係学部を卒業。フジテレビ時代は「オレたちひょうきん族」などバラエティ番組に出演し、人気を博す。その後、フリーになり、2000年からは専業主婦として生活していたが、50代に入ると父の死、母の認知症、夫の急逝が重なり、心身がボロボロに。そのときから「音読トレーニング」をはじめ、見事に復活。。現在、朗読教室・アナウンススクールの講師を務めるかたわら、認知症サポーターとして朗読ボランティアや認知症の理解を深める講演活動をおこなっている。 ISBN:978-4-86581-309-8 Cコード:0095 四六判 184ページ 発行:さくら舎 書店発売日: 2021年09月09日
-

老化で遊ぼう
¥300
【中古 状態きれい】 (参考:定価476円+税) ☆店長のひと言 「本当の老いは75歳からだったでしょう、ご先輩。」 内容紹介 オムツは当てていてもオツムは元気。すっかり老人力のついた、昭和12年生れの漫画家と画家兼作家が、これからの輝かしい人世を語る。 男性女性、どちらがボケ上手?初めてチーズを食べたのは何歳?性に関する一番古い記憶は?穴あきパンツや一度だけ使った爪楊枝をいつ捨てる? お二人の芸術観をまじえた爆笑対談10連発!人生は70歳を超えてからですぞ、ご先輩。 ISBN:9784101364032 出版社:新潮社 文庫:320ページ 発売日:2008年02月28日
-

敏感すぎるあなたへ 緊張、不安、パニックは自分で断ち切れる
¥1,540
【中古 状態きれい】 (参考:定価1,600円+税) ☆店長のひと言 「性格や病気ではなく、一時的な脳の誤作動と考えるだけで、少しラクになれる気がします。」 紹介 あがり症、不安などはあなたのせいではなく、脳の誤動作かも。仕事などで極度の緊張、息苦しさ、腹痛が続き、何かおかしいと思っている人、また、心療内科に行っても「単なるストレス」と言われるだけの人など、病的とは言えないまでも、緊張や不安で日常生活に支障が出ている人向けの、自分でできる行動療法。 食生活、運動、思考法などを変えるだけで、心がすっとラクになる。ドイツで大ベストセラー! ベルリン有名クリニック臨床心理士が脳科学に基づく画期的な方法を伝授。 食事、運動、「テンセンテンス法」、「5つのチャンネルテクニック」……etc 脳に「良い手本」を見せて、すばやく、持続的に不安を断ち切る。 もう不安にはならない! 著者プロフィール クラウス・ベルンハルト (クラウスベルンハルト) (著/文) 臨床心理士。科学・医療ジャーナリストとして活躍後、心理学、精神医学を学ぶ。 現在、不安症やパニック発作の専門家として、ベルリンでカウンセリングルームを開設。 最新の脳科学に基づいた画期的療法「ベルンハルト・メソッド」はドイツで注目を集めている。 脳神経科学教育マネジメント協会(AFNB)会員。 ISBN:9784484181035 出版社:CCCメディアハウス 判型:4-6 ページ数:208ページ 定価:1600円(本体) 発行年月:2018年03月
-

ウイルスも認知症も生きづらいのも、すべて歯のせい?
¥1,210
☆店長のひと言 「お口は健康の入口です。」 紹介 健康寿命にふかくかかわるお口ケアの教科書 「歯の調子が悪ければ、歯医者さんにいけばいい。自分でできるのは歯磨きくらい」 というあなた。その考え方、時代遅れです!! 歯のケアを怠るとなる病気は、むし歯と歯周病だけ? 大間違い! アメリカでは、Floss or Die?(フロスしますか、それとも死にますか)というスローガンもあるほど、 歯と全身の健康はふかく結びついているのです。 なんと、ウイルスによる感染症・心臓病・肺炎・がん・認知症の原因にも! しかもコロナ禍で、私たちは一年中マスクを装着。 口腔ケアのプロである歯科医は警告します、 「今が人類史上、最悪な状態」! 口の中がネバネバしていませんか? 口臭がすると家族に言われていませんか? 歯と歯の間にすき間ができたなあと感じていませんか? そういや歯が長くなったような……口を開けると舌がいつも白っぽい……… このなかのひとつでも当てはまったら、この本を読むべきです! 自分でできるホームケア法と、だれしも苦手な歯医者さんとの付き合い方を、ギュッと一冊に。 さらに、舌の位置を正し、だ液を増やす「お口の筋トレ」法を初公開。 今こそ健康寿命も人生も、好転させましょう。 (小学館HPより転載) 著者 堀 滋(ほり しげる) 歯科医師。サウラデンタルクリニック院長。 1959 年生まれ。日本大学松戸歯学部卒業。昭和大学歯学部付属歯科病院口腔外科にて臨床を学びながら同医局にて白血球の活性酸素産生に関する研究を行い日本炎症学会等で学会発表も行う。 退局後は 日本橋中央歯科診療所勤務を経て、1990年中野区にて堀歯科診療所を開設。 診療の傍ら、スウェーデンのイエテ ボリ大学で実践されている歯周病治療を学ぶ、歯周病臨床実践コース、同アドバンスコース、ペン シルバニア大学 アドバンスインプラントコース受講など、海外の最新治療を学び続け積極的に治療に 取り入れている。 2017年保険診療を終了し、自由診療専門のサウラデンタルクリニックに名称変更。 2021年、開業30周年を期に港区青山に移転し、院内換気システムや低濃度オゾンガスによる院内環境 殺菌システムなどコロナウィルス感染予防対策を徹底的に強化した新たなクリニックを開設。 院内には、顔まわりから全身の筋肉ケアのためのリラクゼーションサロンも併設。 (サウラデンタルクリニックHPより抜粋) ISBN 978-4-09-310686-3 C2077 A5判 128頁 発行 小学館 発売日 2021年8月5日
-

1年中楽しめる花の折り紙
¥1,400
SOLD OUT
【中古 状態きれい】 (参考:定価1,480円+税) ☆店長のひと言 「こういうのをササッと折れる人、ほんと尊敬します。」 紹介 季節をテーマに1年中飾って楽しめるかわいい花の折り紙作品集。 立体の花のほか、花のカードやプレゼントバッグなど実用的で役立つアイテムも豊富。初心者からベテランまで楽しめる内容です。 著者プロフィール 山口真(やまぐち まこと) 1944年、東京生まれ。日本折紙協会事務局員を経て折り紙作家として活躍中。1989年、折り紙専門のギャラリー「おりがみはうす」を開設。日本折紙学会事務局長。OrigamiUSA永久会員。British Origami Society会員。韓国折紙協会名誉会員。日本折紙学会機関誌『折紙探偵団マガジン』編集長 ISBN 978-4529057967 AB変形判 112頁 発行 日本ヴォーグ社 発行年月 2018年5月
-

1年中楽しめるはじめての切り紙
¥680
【中古 状態きれい】 (参考:定価900円+税) ☆店長のひと言 「図案を見ているだけでも楽しいですよ。」 内容紹介 かんたん4ステップで楽しめる切り紙本の決定版。 小さな子供からおじいちゃんおばあちゃんまで年齢問わず3世代で楽しめ、切ったものは壁に飾ったり、カードにはっても使えます。桜、クリスマスといった春夏秋冬のモチーフから干支、星座、動物、和のモチーフまでみんなで楽しめる図案を掲載。ハサミを持って手先を使い、季節を愛でながら心が豊かになる切り紙はおすすめのクラフトです。 ISBN:9784529052061 B5変 72ページ 出版社:日本ヴォーグ社 発行年月日:2013年06月
-

心とあたまを刺激する音読 語り継ぎたい30の教え
¥300
【中古 カバーに少し汚れあり】 (参考:定価1,300円+税) ☆店長のひと言 「有名な歴史上の人物やエピソードが書かれています。私は眠くなりました。」 紹介 ――1日1音読、始めてみませんか? 小学生のとき、国語の教科書を声に出して読んだ経験は誰しもが持つのではないでしょうか。 本書で紹介する作品は、明治~昭和初期に国語の教科書に実際に掲載されていたものです。作品には、日本人なら一度は聞いたことがあるような偉人が登場します。音読をしながら、その中に登場する偉人・時代背景について学べます。 ★紹介する題材は全部で30作品。1日1回、1か月で読み切れる! ★大き目の活字、全ふりがな付きで声に出して読みやすい! ★巻末の「音読ノート」で、音読の記録がつけられる! 著者プロフィール 山口 謡司 (ヤマグチ ヨウジ) (著/文) 1963(昭和38)年、長崎県佐世保市に生まれる。現在、大東文化大学文学部中国学科准教授。中国山東大学客員教授。博士(中国学)。中国山東大学国際漢学研究センター「全世界漢籍総合目録プロジェクト」日本代表。専門は、文献学、書誌学、日本語史など。テレビやラジオの出演も多く、NHK文化センター、朝日カルチャーセンターなどでも定期的に講演や講座を開いている。 著書に、『語彙力がないまま社会人になってしまった人へ』(ワニブックス)、『心とカラダを整える おとなのための1分音読』(自由国民社)、『文豪の凄い語彙力』(さくら舎)などがある。また、イラストレーター、書家としても活動。 ISBN 978-4-7593-1672-8 A5判 144頁 発行 海竜社 発売日 2019年8月9日
-

Disney Best Friendポストカード(大人のためのヒーリングスクラッチアート)
¥1,050
【中古 状態きれい】 (参考:定価1,150円+税) ☆店長のひと言 「線を削るとネオンサインみたいになります。癒やしにも予防にもどうぞ。」 紹介 削るだけで癒される「スクラッチアート」の、ディズニー人気キャラクター第二弾は、ミッキー&ミニー、ぷー&ピグレット、チップ&デール、トランプ&レディなど、仲良しコンビのアート。ポストカードサイズで手軽に楽しめ、プレゼントにもピッタリです! 著者プロフィール アイソトープ (アイソトープ) (イラスト) デザイン・企画制作会社。雑誌、実用書など、幅広いジャンルで活動中。学研大人のためのヒーリングスクラッチアートシリーズ、Disney Princess、SNOOPY、浮世六景ポストカードなど多数制作。 ISBN 978-4-05-750723-1 7頁 発行 学研プラス 発売日 2019年12月5日