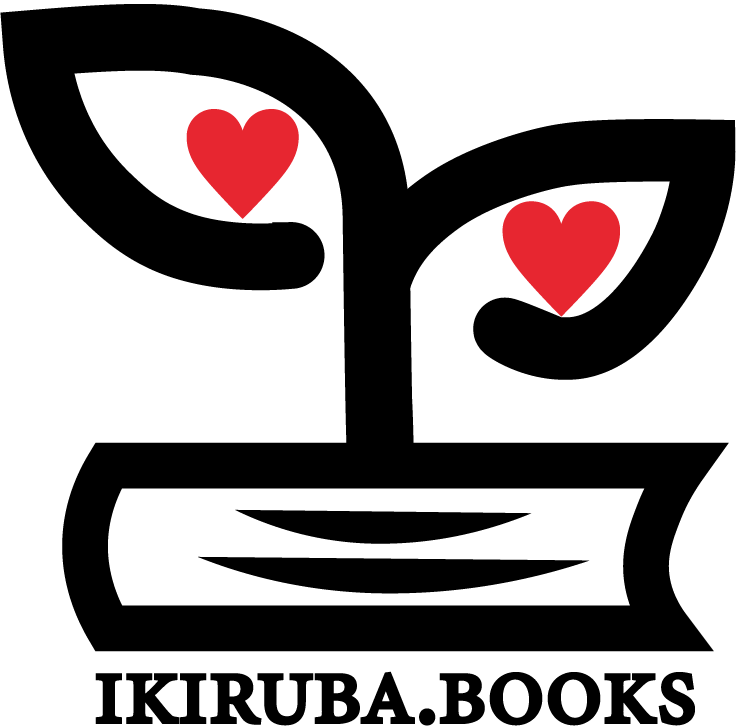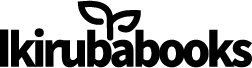-

医師が本当に伝えたい 12歳までの育児の真実 親子の身体と心を守るエビデンス
¥1,980
☆店長のひと言 「親でも子でもなく、“親子”の身体と心を守るというのがポイント。過去の私と母にエビデンスあげたい。」 紹介 ★睡眠トレーニング(ネントレ)は赤ちゃんの脳に有害? ★子どものワクチンについて知っておくべきことは? ★母親が仕事をすることが子どもに与える影響は? ★親の性格が子どもに与える影響とは? 子育てに関する根拠のない神話には、はっきりNOを。 答えのない問いには、考え方や行動のヒントを。母親についての疫学研究を行い、子どもの医療や社会問題に関するSNSでの発信が子育て層に圧倒的支持を集める小児科医・新生児科医の今西洋介氏(ふらいと先生)が、12歳までのお子さんの育児に役立つ「エビデンスにもとづく子育ての最新知識」を、1冊の本にまとめました。 赤ちゃんの睡眠トレーニングから子どもの食事指導、ワクチン、保育園vs幼稚園問題、そして子どもへの性被害を防ぐ方法まで。注目のメールマガジン「ふらいと先生のニュースレター」で紹介されたトピックの中から、特に反響の大きかったテーマを厳選し、新たな書下ろしも加えて再構成。 海外の研究論文や専門情報に裏付けられた最先端の子どもの医学情報を温かなメッセージとともにわかりやすく届ける本書は、日々子育てに奮闘するお父さん、お母さんにとって大きな力となるはずです。 目次 第1章 0歳~5歳までに知っておきたい真実 ― 未就学児のエビデンス ● 母親の仕事が子どもに与える影響―3歳児神話を科学的に検証する ● なぜ子どもの睡眠に気を配るべきか―子どもの睡眠① ● 「子どもが寝ない」に親ができる対策―子どもの睡眠② など 第2章 6歳~12歳までに知っておきたい真実 ― 学童期のエビデンス ●わが子を「いじめっ子」にしないために親にできること ● 「男の子は父親から学び、女の子は母親から学ぶ」説は本当か ● 親は子どもにどこまで厳しくするべきか など 第3章 妊娠期~ 出産までに知っておきたい真実 ― プレママ・プレパパのためのエビデンス ● 「母性愛神話」を科学的に検証する ● 無痛分娩って本当のところどうなの?―研究からわかること ● 胎教は行うべき? その効果は? など 著者プロフィール 今西洋介 (イマニシヨウスケ) (著) 小児科医・新生児科医。日本小児科学会専門医/日本周産期・新生児医学会新生児専門医。医学博士(公衆衛生学)。一般社団法人チャイルドリテラシー協会代表理事。小児公衆衛生学者。富山大学医学部卒業後、都市部や地方のNICU(新生児集中治療室)で新生児医療に従事。主な著書に『新生児科医・小児科医ふらいと先生の子育て「これってほんと?」答えます』(西東社、監修)、『小児科医「ふらいと先生」が教える みんなで守る子ども性被害』(集英社インターナショナル)ほか多数。 ISBN:978-4-296-00243-6 Cコード:0077 四六判272ページ 発行: 日経BP 発売日: 2025年4月25日

-

幻肢痛日記
¥2,090
☆店長のひと言 「大切なものほど失ってから気付くのと似ていると言えないでしょうか。」 内容紹介 切断した筈なのに、足のあった場所が痛む。「ない」のに「痛い」とはどういうことだろう? 右足を失った「僕」が経験した不思議な現象、幻肢痛から考えた、わからないものについての記録。 (河出書房新社ホームページより引用) https://bookandbeer.com/event/bb241118a/ 著者プロフィール 青木 彬 (アオキ アキラ) (著/文) 1989年生。キュレーター。首都大学東京インダストリアルアートコース卒。アートを「よりよく生きるための術」と捉えアーティストや企業等と協同しアートプロジェクトを企画。著書に『素が出るワークショップ』。 ISBN:978-4-309-23162-4 Cコード:0036 四六判200ページ 発行: 河出書房新社 初版年月日: 2024年10月25日
-

夜明けを待つ
¥1,980
紹介 生と死を見つめ続けてきたノンフィクション作家の原点がここに! 私たちは10年という長い年月を、とことん「死」に向き合って生きてきた。 しかし、その果てにつかみとったのは、「死」の実相ではない。 そこに見えたのは、ただ「生きていくこと」の意味だ。 親は死してまで、子に大切なことを教えてくれる。 (第1章「『死』が教えてくれること」より) 家族、病、看取り、移民、宗教……。 小さき声に寄り添うことで、大きなものが見えてくる。 『エンジェルフライト』『紙つなげ!』『エンド・オブ・ライフ』『ボーダー』……。 読む者の心を揺さぶる数々のノンフィクションの原点は、 佐々涼子の人生そのものにあった。 ここ10年に書き溜めてきたエッセイとルポルタージュから厳選! 著者初の作品集。 (目次より抜粋) 第1章 エッセイ 「死」が教えてくれること 夜明けのタクシー 体はぜんぶ知っている 今宵は空の旅を 命は形を変えて この世の通路 幸福への意思 もう待たなくていい ダイエット ハノイの女たち 未来は未定 夜明けを待つ 痛みの戒め 柿の色 ひろちゃん 和製フォレスト・ガンプ 誰にもわからない トンネルの中 スーツケース 梅酒 ばあばの手作り餃子 縁は異なもの 第2章 ルポルタージュ ダブルリミテッド1 サバイバル・ジャパニーズ ダブルリミテッド2 看取りのことば ダブルリミテッド3 移動する子どもたち ダブルリミテッド4 言葉は単なる道具ではない 会えない旅 禅はひとつ先の未来を予言するか 悟らない オウム以外の人々 遅効性のくすり 佐々涼子(ささ りょうこ) ノンフィクション作家。1968年生まれ。神奈川県出身。早稲田大学法学部卒。日本語教師を経てフリーライターに。2012年、『エンジェルフライト 国際霊柩送還士』(集英社)で第10回開高健ノンフィクション賞を受賞。2014年に上梓した『紙つなげ! 彼らが本の紙を造っている 再生・日本製紙石巻工場』(早川書房)は、紀伊國屋書店キノベス!第1位、ダ・ヴィンチBOOK OF THE YEAR第1位、新風賞特別賞などに、2020年の『エンド・オブ・ライフ』(集英社インターナショナル)は、Yahoo!ニュース|本屋大賞2020年 ノンフィクション本大賞に輝いた。他の著書に『ボーダー 移民と難民』(集英社インターナショナル)など。 2024年9月、悪性脳腫瘍のため横浜市戸塚区の自宅で死去。56歳没 ISBN:978-4-7976-7438-5 Cコード:0095 四六判 272ページ 発行: 集英社インターナショナル 発売日: 2023年11月24日

-

武士の介護休暇
¥1,078
☆店長のひと言 「大ヒット作『武士の家計簿』をパクったようなタイトルに惹かれてページを開いたら最後です。」 紹介 はじめに 第一章 江戸時代の介護事情──介護休暇を取った武士── 日記に残された「武士の介護」/武士が利用した「看病断」という介護休業制度/武士の「近距離介護」/「看病断」の申請手順/当時の要介護状態となる原因とは──『孝義録』から読み解く──/なぜ幕府は「孝行」を重視したのか?/江戸期の日本人に多かった眼病・盲目の人/中風で半身麻痺に/江戸時代の認知症/庶民層の介護の実態/オランダ人医師ポンペが見た貧困の中の介護/非血縁者による介護 第二章 江戸時代の「老い」の捉え方 時代によって変わる高齢者区分/江戸時代の高齢者人口は?/江戸時代では何歳から「高齢者」?/生前相続としての隠居/高齢でも働かされた武士/庶民の隠居事情/早期リタイアを夢見た人々/『養生訓』『鶉衣』にみる老い 第三章 江戸時代以前の「老い」──古代~中世期の高齢者観── 古代~中世期では何歳から高齢者?/高齢世代まで生きられた人はどのくらいいた?/尊敬の対象・強者としての高齢者/高齢者は神に近い存在/『万葉集』における老いの見方/『枕草子』『方丈記』『徒然草』における高齢者観/変化する理想の老後/若く見られたがる愚かさについて/江戸時代とは異なる古代~中世期における高齢者観 第四章 江戸時代以前の介護事情──古代~中世期の介護── 当時の要介護状態となる原因とは/老いた親が鬼になる/中世期の脳卒中/白内障で失明/身内が介護しないと批判の対象に/見捨てられた老人を介護した女性の正体/身内がいない貧しい要介護者の末路/古代にも存在した驚きの介護制度/律令制度の要介護区分/ケアをすれば功徳を積める/名も知らぬ老僧を介護して家を得る/身寄りのない高齢者の介護・看取りの実情 第五章 古代~中世期の「姥捨て」 親を捨てた人々の物語/「運搬用具型」の姥捨て物語/「老親の知恵型」の姥捨て物語/「老親福運型」の姥捨て物語/「枝折り型」の姥捨て物語/救われる老親と棄老の実情/当時の人々が介護をした理由とは ①愛情や感謝──「情」の論理──/②中国からの影響──「儒」の論理──/③仏教からの影響──「仏」の論理──/④ギブアンドテイク──「互酬」の論理──/四つの論理の弱点と介護放棄 第六章 江戸時代の「介護に向かわせる」価値観 江戸時代に身寄りのない高齢者はどう介護された?/「地域社会で高齢の要介護者を支えるべし」/幕藩 著者プロフィール 﨑井 将之 (サキイ マサユキ) (著/文) 1976年生まれ。首都大学東京大学院社会科学研究科後期博士課程単位取得退学。哲学、国際市民社会論で修士号を取得。大手老人ホーム検索サイトで高齢者福祉関連ニュース記事を執筆。著書に『哲学のおさらい』。 ISBN:978-4-309-63179-0 Cコード:0221 新書判264ページ 発行: 河出書房新社 初版年月日: 2024年10月22日
-

体はゆく できるを科学する〈テクノロジー×身体〉
¥1,400
【中古 状態きれい】 (参考:定価1,600円+税) ☆店長のひと言 「器用な人って頭で体を縛っていないということなのかも。」 紹介 「できなかったことができる」って何だろう? 技能習得のメカニズムからリハビリへの応用まで―― ・「あ、こういうことか」意識の外で演奏ができてしまう領域とは ・なぜ桑田真澄選手は投球フォームが違っても結果は同じなのか ・環境に介入して体を「だます」“農業的”テクノロジーの面白さ ・脳波でしっぽを動かす――未知の学習に必要な体性感覚 ・「セルフとアザーのグレーゾーン」で生まれるもの ……etc. 古屋晋一(ソニーコンピュータサイエンス研究所)、柏野牧夫(NTTコミュニケーション科学基礎研究所)、小池英樹(東京工業大学)、牛場潤一(慶應義塾大学)、暦本純一(東京大学大学院)ら、5人の科学者/エンジニアの先端研究を通して、「できる」をめぐる体の“奔放な”可能性を追う。 日々、未知へとジャンプする“体の冒険”がここに 著者プロフィール 伊藤 亜紗 (イトウ アサ) (著/文) 東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授、東京工業大学科学技術創成研究院未来の人類研究センター長。東京大学大学院人文社会系研究科美学芸術学専門分野博士課程修了(文学博士)。専門は美学、現代アート。著書に『ヴァレリーの芸術哲学、あるいは身体の解剖』(水声社)、『目の見えない人は世界をどう見ているのか』(光文社新書)、『目の見えないアスリートの身体論』(潮新書)、『どもる体』(医学書院)、『記憶する体』(春秋社)、『手の倫理』(講談社メチエ)、『体はゆく できるを科学する〈テクノロジー×身体〉』(文藝春秋)など多数。 ISBN:978-4-16-391631-6 Cコード:0095 四六判248ページ 発行: 文藝春秋 発売日: 2022年11月28日

-

あらゆることは今起こる (シリーズケアをひらく)
¥2,200
☆店長のひと言 「事実は小説よりも木なり。」 紹介 眠い、疲れる、固まる、話が飛ぶ、カビを培養する。それは脳が励ましの歌を歌ってくれないから?――ADHDと診断された小説家は、薬を飲むと「36年ぶりに目が覚めた」。私は私の身体しか体験できない。にしても自分の内側でいったい何が起こっているのか。「ある場所の過去と今。誰かの記憶と経験。出来事をめぐる複数からの視点。それは私の小説そのもの」と語る著者の日常生活やいかに。SFじゃない並行世界報告! 著者プロフィール 柴崎友香(しばさき・ともか) 1973年、大阪府生まれ、東京都在住。大阪府立大学卒業。1999年「レッド、イエロー、オレンジ、オレンジ、ブルー」が文藝別冊に掲載されデビュー。2007年『その街の今は』で芸術選奨文部科学大臣新人賞、織田作之助賞、咲くやこの花賞を受賞。2010年『寝ても覚めても』で野間文芸新人賞、2014年『春の庭』で芥川賞を受賞。その他に『パノララ』『千の扉』『百年と一日』ほか、エッセイに『よう知らんけど日記』など、著書多数。 ISBN:978-4-260-05694-6 Cコード:3347 A5判304ページ 発行:医学書院 書店発売日: 2024年5月13日

-

治りませんように : べてるの家のいま
¥800
SOLD OUT
【中古 状態きれい】 (参考:定価2,400円+税) ☆店長のひと言 「売れますように」 紹介 精神障害やアルコール依存などを抱える人びとが、北海道浦河の地に共同住居と作業所"べてるの家"を営んで30年。 べてるの家のベースにあるのは「苦労を取りもどす」こと-保護され代弁される存在としてしか生きることを許されなかった患者としての生を抜けだして、一人ひとりの悩みを、自らの抱える生きづらさを、苦労を語ることばを取りもどしていくこと。 べてるの家を世に知らしめるきっかけとなった『悩む力』から8年、浦河の仲間のなかに身をおき、数かぎりなく重ねられてきた問いかけと答えの中から生まれたドキュメント。 目次 記憶 死神さん べてるの家 浦河弁 なつひさお 救急通い 遭難者 あきらめる 立ち往生 新しい薬 幻聴とダンス 生きる糧 青年の死 ぺてるの葬儀 その人を語る 爆発系 ピア・サポート 撤退 当事者研究 アイメッセージ 収穫の秋 病気への依存 人間アレルギー 治さない 日だまり 苦労の哲学 しあわせにならない 著者プロフィール 斉藤道雄 (サイトウミチオ) (著/文) 1947年生まれ。ジャーナリスト。TBSテレビ報道局の記者、ディレクター、プロデューサー、解説者として報道番組の取材、ドキュメンタリー番組の制作に従事。先端医療、生命倫理、マイノリティ、精神障害、ろう教育などをテーマとしてきた。2008年から5年間、明晴学園の校長、その後4年間、理事長を務めた。著書に『原爆神話の五〇年』(中公新書、1995)『もうひとつの手話』(晶文社、1999)『悩む力――べてるの家の人びと』(みすず書房、2002)『希望のがん治療』(集英社新書、2004)『治りませんように――べてるの家のいま』(みすず書房、2010)『手話を生きる――少数言語が多数派日本語と出会うところで』(みすず書房、2016)『治したくない――ひがし町診療所の日々』(みすず書房、2020)がある。 ISBN:978-4-622-07526-4 四六判 251ページ 発行: みすず書房 初版年月日: 2010年2月17日
-

わたしが誰かわからない : ヤングケアラーを探す旅
¥2,200
☆店長のひと言 「ヤングケアラー…、突然そう呼ばれた人の戸惑いを想像できないあなたへ。」 紹介 「ヤングケアラー」について取材をはじめた著者は、度重なる困難の果てに中断を余儀なくされた。一体ヤングケアラーとは誰なのか。世界をどのように感受していて、具体的に何に困っていているのか。取材はいつの間にか、自らの記憶をたぐり寄せる旅に変わっていた。ケアを成就できる主体とは、あらかじめ固まることを禁じられ、自他の境界を横断してしまう人ではないか――。著者はふたたび祈るように書きはじめた。 目次 はじめに 1 薄氷のような連帯 2 いちばん憎くて、いちばん愛している人 3 わたしが誰かわからない 4 わたしはなぜ書けないか 5 抱えきれない言葉の花束 6 固まることを禁じられた身体──ケア的主体とは何か 7 自己消滅と自己保存──水滴のように 8 犠牲と献身と生まれ変わり──自由へ おわりに 【著者略歴】 中村佑子(なかむら・ゆうこ) 1977年東京都生まれ。映像作家。慶應義塾大学文学部哲学科卒業。哲学書房にて編集者を経たのち、2005年よりテレビマンユニオンに参加。映画作品に『はじまりの記憶 杉本博司』(2012年)、『あえかなる部屋 内藤礼と、光たち』(2015年)がある。主なテレビ演出作に、「幻の東京計画 ~首都にありえた3つの夢~」(NHK BSプレミアム、2014年)、「地球タクシー レイキャビク編」(NHK BS1、2018年)など。本書が初の著書となる。 ISBN:978-4-260-05441-6 Cコード:3347 A5判232ページ 発行:医学書院 発売日: 2023年11月20日
-

ヤングでは終わらないヤングケアラー
¥1,910
【中古 状態きれい】 (参考:定価2,000円+税) ☆店長のひと言 「ある日大人たちがやってきて、あなたは“ヤングケアラー”ですよと言って帰って行きました、、、にさせないために。」 内容紹介 閉じられそうな未来を拓く ヤングケアラー経験者で作業療法士、看護師になった立場から作業療法や環境調整、メンタルヘルスの視点、看護や精神分析、家族支援の視点を踏まえつつ、ヤングケアラーの現状とこれからについて分析・支援方策を提言。 CONTENTS Part1 ヤングケアラーの多様性を理解してほしい 幼少期・思春期・成人期から障がいがある当事者のきょうだい 他 Part2 ライフステージから考えるヤングケアラー 1)きょうだいケアラーの物理的、精神的苦労 2)きょうだいの人格の礎となる心理社会的成長と発達 3)きょうだいの進学・就労の選択肢 4)きょうだいの主体的な選択が認められ、新しい家庭を営む 5)きょうだいの人生の振り返りと親亡き後 Part3 ヤングケアラーへの調査動向と支援の取り組み 1)厚生労働省などの調査・研究・通知 2)ヤングケアラーに関する先進的な地方自治体の取り組み Part4 きょうだいヤングケアラー支援をすすめるために 1)ピアサポート(きょうだい会)の存在 2)親との関係性を再構築すること 3)きょうだい自身が自分を大切にするために 4)きょうだいが頼れる⁉ 既存の公的機関・相談機関 Part5 〈提言〉きょうだいヤングケアラーへの支援のために 1)地域に応じたヤングケアラーへの調査と啓発・支援体制の構築を 2)ピアサポート体制のあり方について 3)支援者がキーパーソンを限定せず、当事者の自立支援という視点をもつこと 4)福祉制度をよりわかりやすく使いやすく 5)きょうだいヤングケアラーの近くにいる大人への提言 (クリエイツかもがわホームページより引用) 著者プロフィール 木村諭志 看護師 参考)https://www.spu.ac.jp/academics/db/tabid334.html?pdid=333kimu 仲田海人 作業療法士 参考)https://kodomoshien.cfa.go.jp/young-carer/interview/ ISBN 978-4-86342-315-2 C0036 A5判・215ページ 発行 クリエイツかもがわ 発売年月 2021年10月
-

障害者の傷、介助者の痛み
¥1,150
【中古 状態きれい】 (参考:定価2,200円+税) ☆店長のひと言 「地域っていうか、みんな好きなところで生きていきたいよね。」 紹介 相模原障害者殺傷事件以前/以後をつなぐ、現場から組み上げたケア論の到達点。 介助するとはそもそもどういった経験か。「介助で食べていく」とはどういうことか。介助する人/される人が培ってきた〈つながり〉の技法とはいかなるものか。介助者として長年暮らしてきた著者が誘う、障害者と健常者がともに地域で暮らし続けるための必読書。 著者プロフィール 渡邉 琢 (ワタナベ タク) 1975年名古屋生まれ。京都大学大学院文学研究科修士課程修了(西洋哲学史専修)。2000年、日本自立生活センター(JCIL・京都)に介助者登録。2004年、JCILに就職。京都市における24時間介護保障の実現に尽力。2006年、仲間とともに「かりん燈~万人の所得保障を目指す介助者の会」を結成。現在、自立生活運動の事務局員、介助派遣部門のコーディネーター、ピープルファースト京都の支援者として活動中。著書に『介助者たちは、どう生きていくのか』(生活書院、2011年)。 ISBN:978-4-7917-7122-6 Cコード:0030 四六判350ページ 発行:青土社 発売日: 2018年12月11日
-

障害があり女性であること : 生活史からみる生きづらさ
¥2,750
☆店長のひと言 「“弱者”のステレオタイプ化や専門と言う名の縦割りから脱するには。」 紹介 障害のある女性48名の生活史から、「障害があり女性である人たち」を生きづらくさせている社会構造や差別について、深く考察した一冊。障害者について論じられるときには、性差別のせいで女性の声がかき消され、女性について論じられるときには障害者差別のせいで障害女性の声はかき消されるという状況がある。しかし、障害のある女性が受ける差別の実態を明らかにする試みはいまだ途上にあり、複雑に絡み合う問題を把握するためのデータは圧倒的に不足している。本書は、この不足を埋めることを試みるものである。 目次 第Ⅰ部 障害とジェンダーをめぐる困難 第Ⅱ部 ライフコースと性役割 第Ⅲ部 これまでとこれから 課題・論点 著者プロフィール 土屋 葉 (ツチヤヨウ) (著/文 | 編集) 1973年生まれ。専攻は家族社会学。お茶の水女子大学大学院人間文化研究科修了。博士(社会科学)。現在、愛知大学文学部教授。著書『障害者家族を生きる』(勁草書房)、共著『被災経験の聴きとりから考える――東日本大震災後の日常生活と公的支援』(生活書院)。障害学研究会中部部会の一員として編んだものに、『愛知の障害者運動――実践者たちが語る』(現代書館)がある。 ISBN:978-4-7684-3598-4 Cコード:0036 四六判320ページ 発行:現代書館 書店発売日: 2023年10月4日

-

自閉症は津軽弁を話さない リターンズ 「ひとの気持ちがわかる」のメカニズム
¥1,100
☆店長のひと言 「話さないではなく話せないと思ってしまっていました。」 紹介 「自閉症の子って津軽弁話さないよね」妻の一言から調査は始まった。10年間の研究のすえ妻の正しさは証明され、この変わった研究は全国紙にも載る結果に。それから数年後、方言を話すようになった自閉症児が現れた――。多数者である私たちはどう方言を話すか、相手の意図をどう読み取っているか。そもそも「普通」の発達とは何かを問うことで、ことばの不思議から自閉スペクトラム症を捉えなおそうと試みる画期的ノンフィクション。 第I部 自閉スペクトラム症の振る舞いと認知の謎 第1章 音声の絶対音感者 第2章 自閉症は熊本弁がわからない 第3章 人はどうやってことば遣いを選ぶのか――社会的関係性と心理的関係性 第4章 なぜ、ごっこ遊びでは共通語を使うのか 第5章 印象としての方言 第6章 意図とミラーニューロン――行為を見ることの意味 第7章 意図とコミュニケーション――目標とプランの読み取り 第8章 意図と協同作業――なぜ、意図を読むことが大切なのか 第9章 ルール間の葛藤――社会的ルールとオリジナルルール 第10章 社会的手がかりへの選好のパラドクス ――わからないから注意を向けないのか、注意を向けていないからわからないのか 第11章 伝わる情報、広がる情報――ミームの概念 第12章 共同注意と情報の共有 第13章 もしも自閉スペクトラム症の子が25人、定型発達の子が5人のクラスがあったら 第14章 おさらい 第II部 新たなる謎 第15章 方言を話すようになった自閉スペクトラム症 第16章 再び調査開始 第17章 ケースの実態 第18章 なぜ、自閉スペクトラム症も方言を話すようになるのか ――社会的スキルの獲得と関係性の変化 第19章 自閉症は日本語を話さない 目次 第I部 自閉スペクトラム症の振る舞いと認知の謎 第1章 音声の絶対音感者 第2章 自閉症は熊本弁がわからない 第3章 人はどうやってことば遣いを選ぶのか――社会的関係性と心理的関係性 第4章 なぜ、ごっこ遊びでは共通語を使うのか 第5章 印象としての方言 第6章 意図とミラーニューロン――行為を見ることの意味 第7章 意図とコミュニケーション――目標とプランの読み取り 第8章 意図と協同作業――なぜ、意図を読むことが大切なのか 第9章 ルール間の葛藤――社会的ルールとオリジナルルール 第10章 社会的手がかりへの選好のパラドクス ――わからないから注意を向けないのか、注意を向けていないからわからないのか 第11章 伝わる情報、広がる情報――ミームの概念 第12章 共同注意と情報の共有 第13章 もしも自閉スペクトラム症の子が25人、定型発達の子が5人のクラスがあったら 第14章 おさらい 第II部 新たなる謎 第15章 方言を話すようになった自閉スペクトラム症 第16章 再び調査開始 第17章 ケースの実態 第18章 なぜ、自閉スペクトラム症も方言を話すようになるのか ――社会的スキルの獲得と関係性の変化 第19章 自閉症は日本語を話さない 著者プロフィール 松本 敏治 (マツモトトシハル) (著/文) 1957年生まれ。博士(教育学)。公認心理師、特別支援教育士スーパーバイザー、臨床発達心理士。1987年、北海道大学大学院教育学研究科博士後期課程単位取得退学。1987~89年、稚内北星学園短期大学講師。89~91年、同助教授。91~2000年、室蘭工業大学助教授。00~03年、弘前大学助教授。03~16年9月、弘前大学教授。11~14年、弘前大学教育学部附属特別支援学校長。14~16年9月、弘前大学教育学部附属特別支援教育センター長。16年10月より、教育心理支援教室・研究所『ガジュマルつがる』代表。 ISBN:978-4-04-400781-2 Cコード:0147 文庫判272ページ 発行:KADOKAWA 初版年月日: 2023年8月25日
-

病と障害と、傍らにあった本。
¥2,200
☆店長のひと言 「本のいいところは、自分のペースで向き合えるところ。」 紹介 病名や障害の名前ではひとくくりにできない、その実情。それゆえにその只中にいる人は、心身のつらさのみならず、誰とも分かち合えない想いに孤独に陥りがちになる。そんな時、外の世界と自分の内とを繋ぐ「窓」となる本は、あったのか。12人12様の病や障害の体験と本との関わりについて綴る本書は、固有な体験としての病や障害の実情と、生きることの「意志」の現れでもある「読む」ことの力を伝える一冊です。 目次 【本を知る】 齋藤陽道 母の絵日記 頭木弘樹 本嫌いが病気をして本好きになるまで 岩崎航 病をふくめた姿で 【本が導く】 三角みづ紀 物語に導かれて 田代一倫 写真と生活 和島香太郎 てんかんと、ありきたりな日常 【本が読めない】 坂口恭平 ごめん、ベケット 鈴木大介 本が読めない。 【本と病と暮らしと】 與那覇潤 リワークと私―ブックトークがあった日々 森まゆみ 体の中で内戦が起こった。―原田病と足るを知る暮らし― 【本と、傍らに】 丸山正樹 常にそこにあるもの 川口有美子 それは、ただ生きて在ること 前書きなど 病名や障害の名でひと括りにできない 固有の症状や想い。 誰かと分かち合うこともできなくて、ひとり。 そんなとき、傍らには どんな本があったのか。 版元から一言 病や障害といった、重いテーマを扱いながら、本書に収録したエッセイにはどれも不思議と、一筋の光が指しているように思える。それは「読む」という行為に生きるという意志が含まれているからなのか。読後感は希望を見出す一冊です。 著者プロフィール 齋藤 陽道 (サイトウ ハルミチ) (著/文) 一九八三年東京都生まれ。写真家。生まれつき聞こえに障害がある感音性難聴と診断を受ける。中学生まで「聴文化」で育ったのち、都立石神井ろう学校入学を機に「日本手話」と出会う。またその頃から写真を始める。二〇一〇年に写真新世紀優秀賞受賞。二〇一一年、写真集『感動』、二〇一九年『感動、』(いずれも赤々舎)刊行。二〇一三年、ワタリウム美術館にて個展「宝物」開催。私生活では同じく感音性難聴である写真家、盛山麻奈美と結婚。二人の間に生まれた子供は二人とも聴者だった。二〇二〇年、息子へ歌う子守唄をきっかけに「うた」を探る日々を追ったドキュメンタリー映画『うたのはじまり』(河合宏樹監督)が公開。エッセイ集に二〇一八年刊行『声めぐり』(晶文社)、『異なり記念日』(医学書院)他多数。 頭木 弘樹 (カシラギ ヒロキ) (著/文) 文学紹介者。大学三年の二十歳のときに潰瘍性大腸炎を患い、十三年間の闘病生活を送る。そのときにカフカの言葉が救いとなった経験から二〇一一年、『絶望名人カフカの人生論』(飛鳥新社、のちに新潮文庫)、二〇一六年『絶望読書―苦悩の時期、私を救った本』(飛鳥新社、のちに河出文庫)、二〇一九年などの著書を刊行。また、ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』をミステリーとして再構成した『ミステリー・カット版 カラマーゾフの兄弟』(春秋社)、落語にも造詣が深く、『落語を聴いてみたけど面白くなかった人へ』(ちくま文庫)他著書多数。同年、潰瘍性大腸炎の闘病の日々を詳細に綴った『食べること出すこと』(医学書院)を刊行。NHK「ラジオ深夜便」の『絶望名言』コーナーに出演中。 岩崎 航 (イワサキ ワタル) (著/文) 一九七六年宮城県生まれ。詩人。本名は、岩崎稔。三歳の頃に筋ジストロフィーを発症。十七歳の頃、未来に絶望し死を考えたが、「病をふくめたありのままの姿」で自分の人生を生きようと思いを定める。現在は胃ろうからの経管栄養と人工呼吸器を使い、在宅医療や介護のサポートを得て自宅で暮らす。二十五歳から詩作、二〇〇四年から五行歌を詠む。二〇一三年、詩集『点滴ポール 生き抜くという旗印』(写真・齋藤陽道、ナナロク社)が大きな話題を呼ぶ。二〇一五年、エッセイ集『日付の大きいカレンダー』、二〇一八年、兄の岩崎健一が絵を、航が詩を綴った共著の画詩集『いのちの花、希望のうた』(以上、いずれもナナロク社)刊行。二〇二〇年、第二詩集『震えたのは』刊行予定。 三角 みづ紀 (ミスミ ミヅキ) (著/文) 一九八一年鹿児島県生まれ。東京造形大学に進学。一年生の冬に膠原病の全身性エリテマトーデスとの診断を受ける。その頃から詩の投稿をはじめ、二〇〇四年、第四十二回現代詩手帖賞受賞。同年、第一詩集『オウバアキル』にて第十回中原中也賞受賞。第二詩集『カナシヤル』で南日本文学賞と歴程新鋭賞を受賞。二〇一四年、第五詩集『隣人のいない部屋』で第二十二回萩原朔太郎賞を史上最年少で受賞。書評やエッセイの執筆も多く、二〇一七年、エッセイ集『とりとめなく庭が』(ナナロク社)刊行。ワークショップや詩のコピーライティングなど活動は多岐に渡り、中でも朗読活動を精力的に行う。スロヴェニア、リトアニア、イタリア、ベルギーなど多くの国際詩祭に招聘される。二〇二〇年、詩集『どこにでもあるケーキ』(ナナロク社)刊行。 田代 一倫 (タシロ カズトモ) (著/文) 一九八〇年福岡県生まれ。写真家。二〇〇〇年、大学在学中にうつ病と診断を受ける。九州産業大学大学院在学中の二〇〇六年、福岡市でアジア フォトグラファーズ ギャラリーの設立、運営に参加。同年、三木淳賞奨励賞受賞。韓国、九州で肖像写真を中心に撮影、発表。二〇一〇年に東京、新宿の photographers ‘galleryに拠点を移す。二〇一三年、東日本大震災の被災地の人々を撮影した『はまゆりの頃に 三陸、福島 2011~2013年』(里山社)刊行。同年さがみはら写真新人奨励賞を受賞。二〇一四年より東京の人々の撮影を開始、東京都写真美術館他で発表。二〇一七年に韓国・鬱陵島の人々を撮影した『ウルルンド』(KULA)刊行。二〇一七年秋より双極性障害を発症。二〇二〇年九月に新潟、砂丘館にて個展開催。 和島 香太郎 (ワジマ コウタロウ) (著/文) 一九八三年山形県生まれ。中学三年生の時に、てんかんと診断される。映像の世界を志して進学した京都造形芸術大学で、ドキュメンタリー映画監督、佐藤真に師事。二〇〇八年、文化庁若手映画作家育成プロジェクトに選出され、『第三の肌』を監督。二〇一二年、監督作品『小さなユリと 第一章・夕方の三十分』が、SKIPシティ国際Dシネマ映画祭短編部門にて奨励賞受賞。二〇一七年より、これまで知られることの少なかったてんかん患者の日々を素朴に語り合うポッドキャストラジオ「ぽつラジオ」を開始。二〇一九年、坪田義史監督のドキュメンタリー映画『だってしょうがないじゃない』で編集を担当。 坂口 恭平 (サカグチ キョウヘイ) (著/文) 一九七八年熊本県生まれ。二〇〇四年、路上生活者の住居を撮影した写真集『0円ハウス』(リトルモア)刊行。以降、ルポルタージュ、小説、思想書、画集、料理書など多岐にわたるジャンルの書籍、音楽、絵などを発表している。二〇一一年五月、福島第一原発事故後の政府の対応に疑問を抱き、自ら新政府初代内閣総理大臣を名乗り、新政府を樹立。希死念慮に苦しむ人々との対話を「いのっちの電話」として、自らの携帯電話(〇九〇-八一〇六-四六六六)の番号を公開。近年は投薬なしの生活を送るようになり、二〇二〇年、その経験と「いのっちの電話」をもとに行ったワークショップを誌上で再現した『自分の薬をつくる』(晶文社)、また「いのっちの電話」を十年続けてわかったことを記した『苦しい時は電話して』(講談社新書)を刊行。また、自らの「薬」として描いた風景画集『Pastel』(左右社)刊行。 鈴木 大介 (スズキ ダイスケ) (著/文) 一九七三年千葉県生まれ。文筆業。貧困からセックスワークに就く女性や子ども、詐欺集団など、社会の斥力の外にある人々をおもな取材対象とするルポライターとして執筆活動を行い、主な著書に『最貧困女子』(幻冬舎新書)など。しかし二〇一五年、四十一歳の時に突然、脳梗塞を発症。身体の麻痺は軽度だったが、その後遺症として記憶障害、認知障害などの高次機能障害が残る。その体験を綴ることを自らのリハビリとし、二〇一六年『脳が壊れた』、二〇一八年『脳は回復する 高次脳機能障害からの脱出』(いずれも新潮新書)を刊行。また、二〇一八年、高次機能障害と発達障害などの類次点を探った『されど愛しきお妻様 -「大人の発達障害」の妻と「脳が壊れた」僕の18年間』(講談社)、二〇二〇年『「脳コワさん」支援ガイド』(医学書院)、『不自由な脳』(金剛出版)など。小説に『里奈の物語』(文藝春秋)がある。 與那覇 潤 (ヨナハ ジュン) (著/文) 一九七九年神奈川県生まれ。歴史学者。地方公立大学に勤務していた二〇一四年に双極性障害を発症し、休職を経て離職。二〇一八年、自身の体験を踏まえた『知性は死なない』(文藝春秋)、二〇二〇年、『心を病んだらいけないの?』(斎藤環と共著、新潮選書)などの著作で、精神病理を切り口に現代社会の諸問題を考察している。本書では挙げきれなかったリハビリ中に影響された書物についても、後者のブックガイドで紹介した。その他、二〇〇九年、博士論文をまとめた『翻訳の政治学』(岩波書店)、二〇一一年、大学在職時の講義録をまとめた『中国化する日本』(文藝春秋、後に文庫化)、二〇一三年、『日本人はなぜ存在するか』(集英社、後に文庫化)などを刊行、著書その他多数。 森 まゆみ (モリ マユミ) (著/文) 一九五四年東京都生まれ。作家。一九八四年、季刊の地域雑誌「谷中・根津・千駄木」を創刊し、地元の人々の聞き書きをベースにした雑誌づくりで地域コミュニティの活性化に貢献。一九九二年、サントリー地域文化賞受賞。一九九八年『鷗外の坂』(新潮社)で芸術選奨文部大臣新人賞、二〇一四年『『青踏』の冒険:女が集まって雑誌をつくるということ』(平凡社)で紫式部文学賞受賞。他著書多数。二〇〇七年、自己免疫疾患である原田病に罹患。二〇一〇年、病後の日々を綴った『明るい原田病日記―私の体の中で内戦が起こった』(亜紀書房)を刊行。みずからの病の体験と東日本大震災を経て、「足る事を知る」ことの重要性を今一度再確認すべく、二〇一七年、縮小社会研究会の松久寛氏との共著『楽しい縮小社会』(筑摩書房)を刊行。近著に『本とあるく旅』(産業編集センター)など。 丸山 正樹 (マルヤマ マサキ) (著/文) 一九六一年東京都生まれ。シナリオライターとして活動。頸椎損傷という重い障害を持つ妻と生活をともにするうち、さまざまな障害を持つ人たちと交流するようになる。次第に、何らかの障害を持った人の物語を書くことを模索するようになり、二〇一一年、ろう者の両親のもと育った聴者の主人公が手話通訳士となって事件解決に一役買うミステリー小説『デフ・ヴォイス』(文藝春秋)でデビュー。同作が『デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳士』として文庫化(文春文庫)されたのに続き、『龍の耳を君に』(創元推理文庫)、『慟哭は聴こえない』(東京創元社)として人気シリーズとなり、二〇二〇年、スピンオフとして『刑事何森 孤高の相貌』(東京創元社)も刊行。他、居所不明児童をテーマにした『漂う子』(文春文庫)など。 川口 有美子 (カワグチ ユミコ) (著/文) 一九六二年東京都生まれ。都立西高卒(三三期生)。夫の海外赴任のためロンドンで暮らしていた最中の一九九五年、母がALSに罹患。その介護体験を記した『逝かない身体――ALS的日常を生きる』(医学書院)で二〇一〇年、第四十一回大宅壮一ノンフィクション賞受賞。他に『末期を越えて』(青土社)、共編著に『在宅人工呼吸器ケア実践ガイド―ALS生活支援のための技術・制度・倫理』(医歯薬出版)など。副理事長を務めるNPO法人さくら会ではヘルパー養成研修会を毎月開催。当面の目標は日本の難病呼吸器ユーザーの豊かな生を世界に知らしめること。都内マンションで猫3匹と理学療法士を目指す息子と同居中。
-

アルツハイマー病になった母がみた世界
¥2,100
【中古 状態きれい】 (参考:定価2,200円+税) ☆店長のひと言 「自分のためだけの日記やメモがSNSよりも助けになることがあると思う。」 紹介 認知症と診断された高齢者は、徐々に起こる認知機能の低下とそれにより生じる生活の困難を、どのように感じ、それにどう対応するのか。死の2年前まで綴っていた日記から、母が外界をどのように眺め感じていたかを専門医である息子が探る。精神医学の常識を覆そうと始めた試み。果たして、その先にみえたものとは? 目次 まえがき 母の生涯 母の両親 母の出生、五歳にして生母を亡くす 一二歳、父を失う 二二歳、次兄のシベリア抑留死 二四歳、結婚、二八歳、長女の夭逝 三人の子の母として、妻として 六四歳、夫との死別、モンゴル墓参、それからの生活 母の日記と生活 第一期 六七~七五歳――遅れてきた母の青春、忍び寄る老いの足音 六七歳(一九九一年) 「バックを落とさないように、じっと抱えていた」 六八~七五歳(一九九二~九九年) 人生の集大成とエンディングノート 六八歳(一九九二年) 「一時二八分男児誕生、五二・五cm三、六九四g」 六九歳(一九九三年) 「かすかにも藤の花ぶさそよがする」 七〇歳(一九九四年) モンゴル墓参 七一歳(一九九五年) 「老人とはこういうものか」 七二歳(一九九六年) 「どら焼きショックか?」 七三歳(一九九七年) エルサレムへ 七四歳(一九九八年) 「私の葬儀に関するノート、例の紙挟みに入れる」 七五歳(一九九九年) イタリア旅行、「今年も無事に暮れていく」 第二期 七六~七九歳――ほころび始める生活、認知機能低下に抗う 七六歳(二〇〇〇年) 結城屋騒動、「決してボケないように心身を大切にしよう」 七七歳(二〇〇一年) 「面倒なので雑炊にした」 七八歳(二〇〇二年) 「東京の老人ホームに入りたい」 七九歳(二〇〇三年) 「情けない、恥ずかしい、早く消えたい」 第三期八〇~八四歳――老いに翻弄される日々、崩れていく自我の恐怖 八〇歳(二〇〇四年) 「このまま呆けてしまうと思うと……」 八一歳(二〇〇五年) 「いよいよ来たかな?」 八二歳(二〇〇六年) このまま呆けてしまうのだろうか、「張れ!レイコ!」 八三歳(二〇〇七年) 「呆けてしまったみたい……呆けてしまった!!」 八四歳(二〇〇八年) 「一日一日呆けが進んでゆくようで恐ろしくて仕方がない」 第四期 八五~八七歳――それからの母のこと 八五歳(二〇〇九年) 「TELかけすぎて叱られる」 八六~八七歳(二〇一〇~一一年) 「長い間、ありがとうございました」 八六歳(二〇一〇年) 「苦しいって言ってるじゃないの!!」 八六歳(二〇一一年一~四月) 「早くなんとかしてちょうだい」 八六~八七歳(二〇一一年五月) 「ごきげんよう」 認知症とは何か アルツハイマー型認知症とは何か アルツハイマー型認知症急増という現象の意味 アルツハイマー病根治薬の開発は可能か 母の診断を考える 母の旅路 あとがき 著者プロフィール 齋藤正彦(さいとう まさひこ) 1952年生まれ.東京大学医学部卒業.都立松沢病院精神科医員,東京大学医学部精神医学教室講師,慶成会青梅慶友病院副院長,慶成会よみうりランド慶友病院副院長,翠会和光病院院長などを経て,2012年都立松沢病院院長,21年から同病院名誉院長.医学博士,精神保健指定医.主な研究テーマは老年期認知症の医療・介護,高齢者の意思能力,行為能力に関する司法判断. 著書に『都立松沢病院の挑戦』(岩波書店),『親の「ぼけ」に気づいたら』(文春新書),監修に『家族の認知症に気づいて支える本』(小学館),編著書に「講座精神疾患の臨床」『第7巻地域精神医療リエゾン精神医療精神科救急医療』(中山書店),『松沢病院発! 精神科病院のCOVID-19感染症対策』(新興医学出版社),『認知症医療・ケアのフロンティア』(日本評論社),『私たちの医療倫理が試されるとき』(ワールドプランニング)などがある. (岩波書店ホームページより引用) ISBN:978-4-00-061565-5 Cコード:0036 四六判254ページ 発行:岩波書店 発売日: 2022年11月10日
-

言葉を失ったあとで
¥1,800
SOLD OUT
【中古 帯の破損※以外は状態きれい(画像参照)】 (参考:定価1,800円+税) ☆店長のひと言 「被害者を減らすためにも加害者への理解と支援は必要なんだけれど、それを声高に主張すると世間様に叩かれるという…。」 紹介 アディクション・DVの第一人者と、沖縄で若い女性の調査を続ける教育学者。現場に居続ける二人が真剣に、柔らかく、具体的に語る、「聞く」ことの現実。 「聞くの実際」。アディクション・DVの第一人者と、沖縄で社会調査を続ける教育学者。それぞれの来歴から被害/加害をめぐる理解の仕方まで、とことん具体的に語りあった対談集。 【目次】 まえがき 信田さよ子 第一章 言葉を失ったあとで 二〇二〇年一一月二七日 中立の立場とはなにか/加害者の話をどう聞くか/加害を書けるか/加害者が被害を知る/性被害の特殊性/仏壇継承者/暴力の構造を知る/スタイルの違い/学校が話を聞けない場所に/援助が料金に見合うか/質疑応答へ/加害者の普通さ/厳罰化は何も解決しない/言葉をいっしょに探す/ゼロ・トレランスの弊害/まずはいい時間をつくる/三つの責任 読書案内① 第二章 カウンセリングという仕事、社会調査という仕事 二〇二一年二月六日 精神科医にできないこと/教室の実践記録のおもしろさ/原点は児童臨床のグループ/沖縄から離れて/「性の自己決定」の実際/社会調査が示すこと/医者になるか、女性のアルコールやるか/女性の依存症の特異さ/八〇年代の精神病院の経験が一生を決めた/生身の人間の話がおもしろい/ネクタイを褒める/沈黙に強くなる 読書案内② 第三章 話を聞いて書く 二〇二〇年二月二三日 精神疾患の鋳型/解離は手ごわい/医療との関係/加害はパターン化している/精神科の役割/値踏みされている/お金をもらうか払うか/許諾のとりかた/書く責任/モスバーガーの文脈/身体は触らない/身体は自分のもの/聞きとりのあと/トランスクリプトの確認の仕方 読書案内③ 第四章 加害と被害の関係 二〇二一年三月一二日 被害者元年/起源は七〇年代/仲間は当事者/学校現場の変化/公認心理師の国家資格/被害者の両義性/暴力をなくす練習/加害者プログラムの順番/加害者の書きづらさ/映画で描かれる暴力/打越正行さんの調査 読書案内④ 第五章 言葉を禁じて残るもの 二〇二一年三月二七日 性被害をどのように語りはじめるのか/臓器がぶらさがっている感覚/フラッシュバックの意味/被害経験の読み替え/選択肢のすくなさ/家族の性虐待/語りのフォーマット/言葉を禁じる/性加害者の能動性/ユタを買う/一二月の教室/オープンダイアローグの実践 読書案内⑤ 第六章 ケアと言葉 二〇二一年五月一一日 カウンセリングに来るひとたち/男性の語りのパターン/加害者の語り/加害者プログラムの肝/DV被害者支援と警察/家族はもうだめなのか?/使えるものはぜんぶ使う/親との関係を聞く/被害者共感の効果/権力と言葉/「加害者」という言葉の危うさ/ブルーオーシャンへ/被害者は日々生まれている/当事者の納得する言葉 読書案内⑥ あとがき――「聞く」の現場の言葉を聞く 上間陽子 著者プロフィール 信田 さよ子 (ノブタ サヨコ) (著/文) 1946年、岐阜県生まれ。公認心理師・臨床心理士。原宿カウンセリングセンター顧問、NPO法人RRP研究会の代表理事。著作に『家族と国家は共謀する』(角川新書)、『増補新版 ザ・ママの研究』(新曜社)、『カウンセラーは何を見ているか』(医学書院)など多数。 上間 陽子 (ウエマ ヨウコ) (著/文) 1972年、沖縄県生まれ。琉球大学教育学研究科教授。生活指導の観点から主に非行少年少女の問題を研究。著作に『海をあげる』(筑摩書房)、『裸足で逃げる』(太田出版)、共著に『地元を生きる』(ナカニシヤ出版)など。 ISBN:978-4-480-84322-7 Cコード:0095 四六判352ページ 発行:筑摩書房 発売日: 2021年12月2日
-

死を生きた人びと 訪問診療医と355人の患者
¥880
SOLD OUT
【中古 状態きれい】 (参考:定価2,400円+税) ☆店長のひと言 「どう死にたいかハッキリしている人は、生きたい人だと思う。」 紹介 355人の看取りに関わった往診医が語るさまざまな死の記録。延命のみに長けた現代社会で、患者たちが望み、模索し続けた最期とは。 現代日本では、患者の望む最期を実現することは非常に難しい。多くの患者が、ひたすら延命しようとする医者や、目前の死期を認識しない親族と患者自身、病院外の死を「例外」とみなす社会によって、望まない最期に導かれていくためだ。しかし著者の患者たちは、著者と語り合ううちにそれぞれの望む死を見いだしていく。その結果、7割の患者が自宅での死を選んでいる。鮮烈なエピソードを通じ読者に「どう死にたいか」を問う一冊。 目次 はじめに 第1章 在宅医療の世界へ 第2章 在宅死のリアリティ――死者三五五名からのメッセージ 1 在宅医療と在宅死 2 在宅医療・在宅死の経済的側面 3 患者と家族にとっての在宅死 4 医師は在宅医療を知らない 5 介護関係者・行政・社会にとっての在宅死 6 常に慰める 第3章 在宅死のアポリア ――情報社会が提供するさまざまなニュースから 1 「老い」は戦うべき相手か 2 希望なき生――「先生、死ねる薬はないのですか」 3 看取るのは医師だけか 4 医者にかからないで死ぬということ 5 在宅死なき在宅医療――ビジネス化の行き着くところ 6 在宅死は理想的な死か 7 最期を選べない患者たち 8 未来におけるアポリア 1 医師は足りるか / 2 訪問看護師は足りるか 3 介護職員は足りるか / 4 介護施設は足りるか 5 病床数は足りるか / 6 二〇二五年問題への対応策 第4章 見果てぬ夢 1 世界の悲惨/日本の悲惨 2 オーダーメイド医療/オートメーション医療 3 ある老医師の手紙 あとがき 著者プロフィール 小堀鷗一郎 (コボリオウイチロウ) (著/文) 1938年、東京生まれ。東京大学医学部医学科卒業。医学博士。東京大学医学部付属病院第一外科、国立国際医療研究センターに外科医として約40年間勤務。定年退職後、埼玉県新座市の堀ノ内病院に赴任、在宅診療に携わり、355人の看取りにかかわる。うち271人が在宅看取り。現在 訪問診療医。母は小堀杏奴。祖父は森鴎外。 ISBN:978-4-622-08690-1 Cコード:0036 四六判216ページ 発行:みすず書房 発売日: 2018年5月2日
-

根っからの悪人っているの?
¥1,760
☆店長のひと言 「被害者であり続けた人が加害者になった瞬間に悪のレッテルを貼られる…、改めて考えると恐ろしい話です。」 紹介 シリーズ「あいだで考える」創刊!不確かな時代を共に生きていくために必要な「自ら考える力」「他者と対話する力」「遠い世界を想像する力」を養う多様な視点を提供する、10代以上すべての人のための人文書のシリーズ。 『根っからの悪人っているの?――被害と加害のあいだ』著者の映画作品『プリズン・サークル』は、日本で1か所だけ、刑務所の中で行われている「TC(回復共同体)」という対話による更生プログラムを、20 代の受刑者4 人を中心に2 年間記録したドキュメンタリー。本書は、この映画を手がかりに、著者と10 代の若者たちが「サークル(円座になって自らを語りあう対話)」を行った記録である。映画に登場する元受刑者の2 人や、犯罪被害の当事者をゲストに迎え、「被害と加害のあいだ」をテーマに語りあう。(装画:丹野杏香) 目次 はじめに 第1回 初めての対話 『プリズン・サークル』を観て 「わかりたい」と思うには 「違い」に出会う 第2回 真人さんとの対話 刑務所のリアル 犯した罪をめぐって 大切なものとサンクチュアリ コラム おすすめの音楽 サンクチュアリが壊れたあと 第3回 翔さんとの対話 感情に気づき、感情を動かす サンクチュアリをつくる 自らの罪を語る コラム 感情をめぐるワーク 聴く・語る・変わる 第4回 山口さんとの対話 事件に遭遇して??山口さんの被害体験 コラム 事件後の子どもとの関係性の変化 少年の居場所 少年と会う 被害者と加害者が直接会うこと??「修復的司法」 コラム 修復的司法の個人的な取り組み 揺れていい 第5回 最後の対話 4回の対話の感想 根っからの悪人っているの? おわりに 被害と加害のあいだをもっと考えるための 作品案内 著者プロフィール 坂上香(さかがみ・かおり) 1965年大阪府生まれ。ドキュメンタリー映画作家。NPO法人out of frame代表。一橋大学大学院社会学研究科客員准教授。映画作品に『Lifers ライファーズ 終身刑を超えて』『トークバック 沈黙を破る女たち』『プリズン・サークル』(文化庁映画賞・文化記録映画大賞受賞)、著書に『プリズン・サークル』(岩波書店)などがある。 (創元社ホームページより引用)) ISBN:978-4-422-36015-7 Cコード:0336 四六判変型 192ページ 発行:創元社 発売日: 2023年10月17日

-

算数文章題が解けない子どもたち
¥2,420
☆店長のひと言 「小学生の頃から算数文章題が苦手で苦手で、、、結局今も解けない愛のパズルを抱いています。」 紹介 つまずきの原因を「読解力が足りない」で済ませては支援につながらない。著者らは学習の認知メカニズムにもとづいて、学力の基盤となることばの知識、数・形の概念理解、推論能力を測るテストを開発。その理念と内容、実施結果を紹介し、それで測る力が算数・国語の学力とどのような関係にあるのかを質的・量的に検討する。 目次 はじめに 第1章 「ことばのたつじん」「かんがえるたつじん」の基本理念――学びの前提を測るテスト 1-1 開発の意図と目的 1-2 学力とは何か 1-3 「生きた知識」とは何か 1-4 「生きた知識」を使うために必要な認知能力 1-5 テストデザインの基本理念 1-6 テストの使い方 第2章 誤答から見える算数学力 2-1 算数文章題テスト 2-2 3, 4 年生用問題の誤答タイプ 2-3 5 年生用問題の誤答タイプ 2-4 誤答分析のまとめ 2-5 個人差 2-6 階層ごとの誤答タイプの分布 第3章 「 ことばのたつじん」による言語力のアセスメント 3-1 テストの概要 3-2 「ことばのたつじん①」――語彙の深さと広さ 3-3 「ことばのたつじん②」――空間・時間のことば 3-4 「ことばのたつじん③」――動作のことば 3-5 言語力の個人差 3-6 「ことばのたつじん」と学力の関係 第4章 「 かんがえるたつじん」による思考力のアセスメント 4-1 テストの概要 4-2 「かんがえるたつじん①」――整数・分数・小数の概念 4-3 「かんがえるたつじん②」――図形イメージの心的操作 4-4 「かんがえるたつじん③」――推論の力 4-5 「かんがえるたつじん」と学力の関係 第5章 「 ことばのたつじん」「かんがえるたつじん」と学力の関係――統計分析 5-1 算数文章題テストを学力の指標とした重回帰分析 5-2 標準学力テストを学力の指標とした重回帰分析 5-3 重回帰分析からの考察 第6章 学習のつまずきの原因 6-1 知識の問題 6-2 推論と認知処理能力の問題 6-3 相対的視点と認知的柔軟性の問題 6-4 読解力と推論力の問題 6-5 複数要素の統合への手立てが重要 付録1 ほんものの学力を育む家庭環境――保護者アンケート調査から A-1 保護者アンケート調査 A-2 家庭環境が学力に及ぼす影響 A-3 ほんものの学力を生む家庭環境 付録2 「ことばのたつじん」「かんがえるたつじん」の開発の過程 付録3 「ことばのたつじん」「かんがえるたつじん」の頒布の対象と入手方法 終わりのことば 注 ISBN:978-4-00-005415-7 Cコード:0037 A5判 224ページ 発行:岩波書店 発売日: 2022年06月16日
-

患者の話は医師にどう聞こえるのか ~診察室のすれちがいを科学する~
¥3,180
【中古 帯にやや傷みあり】 (参考:定価3,200円+税) ☆店長のひと言 「検査データで診断、治療方針は患者に決めてもらう医師が増えたような気がします。」 紹介 現代医学はMRI、PETスキャンなどのハイテク機器に夢中だが、最大にして最良の診断ツールは医師と患者の会話だ。有史以来、会話がもっとも病気を発見してきたのだ。 だが、患者が「しゃべった」ことと医師が「聞いた」ことは、どんなときも、いともたやすく別のストーリーになる可能性を秘めている。 症状を伝えたい一心の患者は、一刻も早く医師に言い分を主張したい。一方、つねに数多くのタスクを抱えながら、効率を上げろという圧力にさらされている医師は、一刻も早く診察を結論に導こうとする。さらには医師と患者双方の固定観念や無意識の偏見、共有していない問題なども加わり、コミュニケーションのミスはすぐに医療ミスへとつながっていくこともありうるのだ。 患者は、きちんと自分の症状を伝える努力をしているだろうか? 医師は、患者がほんとうに伝えたいことを受けとる努力をしているだろうか? アメリカの内科医が心を揺さぶるヒューマンストーリーを通して、避けては通れぬ医師と患者のコミュニケーションの問題を徹底分析する。 目次 第1章 コミュニケーションはとれていたか 第2章 それぞれの言い分 第3章 相手がいてこそ 第4章 聞いてほしい 第5章 よかれと思って 第6章 なにが効くのか 第7章 チーフ・リスニング・オフィサー 第8章 きちんと伝わらない 第9章 単なる事実と言うなかれ 第10章 害をなすなかれ――それでもミスをしたときは 第11章 本当に言いたいこと 第12章 専門用語を使うということ 第13章 その判断、本当に妥当ですか? 第14章 きちんと学ぶ 第15章 ふたりの物語が終わる 第16章 「ほんとうの」会話を 謝辞 訳者あとがき 出典と註 索引 著者プロフィール ダニエル・オーフリ (ダニエルオーフリ) (著/文) 1965-。ニューヨーク在住の内科医。アメリカ最古の公立病院・ベルビュー病院勤務。ニューヨーク大学医学部准教授。著書にMedicine in Translation: Journeys with My Patients (2010)、Intensive Care: A Doctor's Journey (2013)、 When Doctors Feel: How Emotions Affect the Practice of Medicine (2013 ; 『医師の感情』医学書院 2016)、What Patients Say, What Doctors Hear (2017 ; 『患者の話は医師にどう聞こえるのか』みすず書房 2020)、When We Do Harm: A Doctor Confronts Medical Error (2020) がある。New York Times紙やSlate Magazine誌で医療や医師と患者の関係について執筆を行うほか、医療機関初の文芸誌Bellevue Literary Reviewの編集長も務める。 原井宏明 (ハライヒロアキ) (翻訳) 原井クリニック院長、株式会社原井コンサルティング&トレーニング代表取締役。精神保健指定医。日本認知・行動療法学会専門行動療法士。MINTメンバー。日本動機づけ面接協会代表理事。1984年岐阜大学医学部卒業、ミシガン大学文学部に留学。国立肥前療養所精神科、国立菊池病院精神科、医療法人和楽会なごやメンタルクリニックを経て現職。著書『対人援助職のための認知・行動療法』(金剛出版 2010)『方法としての動機づけ面接』(岩崎学術出版社 2012)『図解 やさしくわかる強迫性障害』(共著 ナツメ社 2012)『「不安症」に気づいて治すノート』(すばる舎 2016)ほか多数。訳書 ガワンデ『医師は最善を尽くしているか』『死すべき定め』(いずれもみすず書房 2013、2016)オーフリ『患者の話は医師にどう聞こえるのか』(共訳、みすず書房 2020)ほか多数。 勝田さよ (カツダサヨ) (翻訳) 翻訳者。長年、医学・医療機器分野の実務翻訳に携わり、滞米時にはコミュニティカレッジで医学の基礎を学ぶ。翻訳者ネットワーク「アメリア」メディカルクラウン会員。訳書 オーフリ『患者の話は医師にどう聞こえるのか』(共訳、みすず書房 2020)。 ISBN:978-4-622-08951-3 Cコード:0036 四六判 304ページ 発行:みすず書房 書店発売日: 2020年11月12日
-

福祉は性とどう向き合うか
¥1,540
【中古 状態きれい】 (参考:定価2,200円+税) ☆店長のひと言 「障害者や高齢者と“フツー”の人では別もののように思われがちですよね。」 内容紹介 「私、知的障害者だから恋愛できないね」は、日本社会の現実なのか。老いらくの性は、年甲斐もないことなのか。障害者・高齢者の性・恋愛・結婚は、自己責任なのか。本書は、当事者とその家族・支援者(福祉職員・街コン関係者等)へのインタビュー等を基に、「機会平等」の観点から支援の是非・あり方について考えたものである。「自己決定の尊重」と「社会規範」の狭間にある、誰もが持つ「性的ニーズ」への支援について真正面から捉えた一冊。 [ここがポイント] ◎ 誰もが持つ「性的ニーズ」への支援を真正面から捉えた一冊。 ◎ 支援者、当事者、当事者の家族の三者への聞き取り調査を通し、福祉現場で生じているジレンマを明示。 ◎ 「自己決定の尊重」と「社会規範」の狭間にあるニーズに対する福祉のあり方を考察。 目次 まえがき 序 章 福祉専門職の悩み——現場からの報告(結城康博) 1 タブー視される「性」の問題 2 レイプ未遂?——判断の困難な認知症高齢者のケース 3 福祉専門職へのセクシュアルハラスメント 4 現場が抱える問題①——高齢者福祉施設の場合 5 現場が抱える問題②——障害者福祉施設の場合 6 超高齢化社会の到来 第Ⅰ部 高齢者・障害者の性 第1章 高齢者の性・恋愛・結婚(後藤宰人) 1 性生活を続ける高齢者夫婦たち 2 恋をする高齢者たち 3 恐怖を覚える女性——求める夫と避ける妻 第2章 高齢者と性風俗(後藤宰人) 1 性風俗に通う男性高齢者たち 2 「上客」として扱われる男性高齢者 3 人は死ぬまで性欲を持ち続ける 4 男性高齢者が性風俗に求めるもの 5 性風俗を利用する女性高齢者 第3章 障害者の性・恋愛・結婚①——肢体不自由者の場合(武子愛) 1 切実な欲求としての「性」 2 肢体不自由者の周囲を取り巻く問題 3 本人を取り巻く問題 4 障害者の権利に関する条約 5 「性的ニーズ」を要求できるかどうかは運次第——支援者の姿勢が鍵 第4章 障害者の性・恋愛・結婚②——知的障害者の場合(武子愛) 1 知的障害者であるがゆえに生じる困難 2 施設を利用する知的障害者の問題——「性的ニーズ」を満たすことができない人々 3 性風俗産業に利用される女性 4 「搾取」による「寂しさ」の解消——軽度の知的障害者が抱えるジレンマ 第5章 障害者と性風俗(後藤宰人) 1 健常者も障害者も同じ 2 障害者対応性風俗と障害者専用性風俗 3 障害者が「専門店」に求めるもの 4 性風俗から見える社会のひずみ 第Ⅱ部 利用者の「性的ニーズ」と福祉専門職 第6章 「性的ニーズ」と向き合うことになった福祉専門職(武子愛) 1 介護とセクシュアルハラスメントは分けられない? 2 「性的ニーズ」の対象となることはどのように捉えられてきたのか——先行研究の知見から 3 施設(組織)で対応したケース 4 一職員のみでの対応を求められたケース 5 自分に向けられた「性的ニーズ」の表明をどう捉えるか——虐待防止法をめぐって 第7章 「性的ニーズ」をどのように捉えるのか(武子愛) 1 「性」に立ち入りたくない福祉現場 2 支援する側はどう思ったのか——支援者たちの証言から 3 「性的ニーズ」への支援の障害——社会規範・利用者の判断能力・支援の根拠 4 福祉の理念および人権に関する宣言から 5 「性的ニーズ」への支援は可能か 第Ⅲ部 公共政策・社会環境から見た「性的ニーズ」 第8章 「性的ニーズ」への支援と公共政策(結城康博) 1 社会保障費の増加の中で 2 介護保険外サービスを利用した支援 3 現行の法令に規定されている余暇活動への支援 4 公共財と私的財 5 ボランティアによる支援 6 厳しい社会保障費問題の壁 7 「性的ニーズ」に関するケア・支援に悩む従事者 第9章 「性的ニーズ」を取り巻く社会環境——社会福祉の視点から(米村美奈) 1 社会福祉における性の捉え方 2 利用者の「性的ニーズ」を取り巻く障壁 3 障壁を作り出したのは誰か 終 章 自己決定を尊重した支援は可能か(米村美奈) 1 嘘をついた男性利用者——行きたかったのはレストランではなく性風俗 2 自己決定とは 3 自己決定への支援 4 支援者の自己開示——「性的ニーズ」への対応に求められるもの 5 利用者の「真」のニーズの追求 6 対話による潜在的ニーズの把握 7 支援者が自己決定に「No」ということ——婦人保護施設のケースを踏まえて 8 利用者のニーズだけがすべてではない——婦人保護施設に保護された女性たち 9 専門職の責務 あとがき 索 引 (ミネルヴァ書房HPより転載) 結城 康博(著/文), 米村 美奈(著/文), 武子 愛(著/文), 後藤 宰人(著/文) ISBN 978-4-623-08169-1 四六判 244頁 発行 ミネルヴァ書房 書店発売日 2018年2月25日
-

敏感すぎるあなたへ 緊張、不安、パニックは自分で断ち切れる
¥1,540
【中古 状態きれい】 (参考:定価1,600円+税) ☆店長のひと言 「性格や病気ではなく、一時的な脳の誤作動と考えるだけで、少しラクになれる気がします。」 紹介 あがり症、不安などはあなたのせいではなく、脳の誤動作かも。仕事などで極度の緊張、息苦しさ、腹痛が続き、何かおかしいと思っている人、また、心療内科に行っても「単なるストレス」と言われるだけの人など、病的とは言えないまでも、緊張や不安で日常生活に支障が出ている人向けの、自分でできる行動療法。 食生活、運動、思考法などを変えるだけで、心がすっとラクになる。ドイツで大ベストセラー! ベルリン有名クリニック臨床心理士が脳科学に基づく画期的な方法を伝授。 食事、運動、「テンセンテンス法」、「5つのチャンネルテクニック」……etc 脳に「良い手本」を見せて、すばやく、持続的に不安を断ち切る。 もう不安にはならない! 著者プロフィール クラウス・ベルンハルト (クラウスベルンハルト) (著/文) 臨床心理士。科学・医療ジャーナリストとして活躍後、心理学、精神医学を学ぶ。 現在、不安症やパニック発作の専門家として、ベルリンでカウンセリングルームを開設。 最新の脳科学に基づいた画期的療法「ベルンハルト・メソッド」はドイツで注目を集めている。 脳神経科学教育マネジメント協会(AFNB)会員。 ISBN:9784484181035 出版社:CCCメディアハウス 判型:4-6 ページ数:208ページ 定価:1600円(本体) 発行年月:2018年03月
-

ウイルスも認知症も生きづらいのも、すべて歯のせい?
¥1,210
☆店長のひと言 「お口は健康の入口です。」 紹介 健康寿命にふかくかかわるお口ケアの教科書 「歯の調子が悪ければ、歯医者さんにいけばいい。自分でできるのは歯磨きくらい」 というあなた。その考え方、時代遅れです!! 歯のケアを怠るとなる病気は、むし歯と歯周病だけ? 大間違い! アメリカでは、Floss or Die?(フロスしますか、それとも死にますか)というスローガンもあるほど、 歯と全身の健康はふかく結びついているのです。 なんと、ウイルスによる感染症・心臓病・肺炎・がん・認知症の原因にも! しかもコロナ禍で、私たちは一年中マスクを装着。 口腔ケアのプロである歯科医は警告します、 「今が人類史上、最悪な状態」! 口の中がネバネバしていませんか? 口臭がすると家族に言われていませんか? 歯と歯の間にすき間ができたなあと感じていませんか? そういや歯が長くなったような……口を開けると舌がいつも白っぽい……… このなかのひとつでも当てはまったら、この本を読むべきです! 自分でできるホームケア法と、だれしも苦手な歯医者さんとの付き合い方を、ギュッと一冊に。 さらに、舌の位置を正し、だ液を増やす「お口の筋トレ」法を初公開。 今こそ健康寿命も人生も、好転させましょう。 (小学館HPより転載) 著者 堀 滋(ほり しげる) 歯科医師。サウラデンタルクリニック院長。 1959 年生まれ。日本大学松戸歯学部卒業。昭和大学歯学部付属歯科病院口腔外科にて臨床を学びながら同医局にて白血球の活性酸素産生に関する研究を行い日本炎症学会等で学会発表も行う。 退局後は 日本橋中央歯科診療所勤務を経て、1990年中野区にて堀歯科診療所を開設。 診療の傍ら、スウェーデンのイエテ ボリ大学で実践されている歯周病治療を学ぶ、歯周病臨床実践コース、同アドバンスコース、ペン シルバニア大学 アドバンスインプラントコース受講など、海外の最新治療を学び続け積極的に治療に 取り入れている。 2017年保険診療を終了し、自由診療専門のサウラデンタルクリニックに名称変更。 2021年、開業30周年を期に港区青山に移転し、院内換気システムや低濃度オゾンガスによる院内環境 殺菌システムなどコロナウィルス感染予防対策を徹底的に強化した新たなクリニックを開設。 院内には、顔まわりから全身の筋肉ケアのためのリラクゼーションサロンも併設。 (サウラデンタルクリニックHPより抜粋) ISBN 978-4-09-310686-3 C2077 A5判 128頁 発行 小学館 発売日 2021年8月5日
-

なぜ人と人は支え合うのか
¥600
【中古 裏カバーにシール痕あり※画像参照】 (参考:定価880円+税) ☆店長のひと言 「根本的な問いほど真剣に考えなくては、ですね。」 紹介 『こんな夜更けにバナナかよ』から15年、渡辺一史最新刊 ほんとうに障害者はいなくなった方がいいですか? 今日、インターネット上に渦巻く次のような「問い」にあなたならどう答えますか? 「障害者って、生きてる価値はあるんでしょうか?」 「なんで税金を重くしてまで、障害者や老人を助けなくてはいけないのですか?」 「自然界は弱肉強食なのに、なぜ人間社会では弱者を救おうとするのですか?」 気鋭のノンフィクションライターが、豊富な取材経験をもとにキレイゴトではない「答え」を真摯に探究! あらためて障害や福祉の意味を問い直す 障害者について考えることは、健常者について考えることであり、同時に、自分自身について考えることでもある。2016年に相模原市で起きた障害者殺傷事件などを通して、人と社会、人と人のあり方を根底から見つめ直す。 著者プロフィール 渡辺 一史 (ワタナベカズフミ) (著/文) ノンフィクションライター。1968年、名古屋市生まれ。中学・高校、浪人時代を大阪府豊中市で過ごす。北海道大学文学部を中退後、北海道を拠点に活動するフリーライターとなる。2003年、札幌で自立生活を送る重度身体障害者とボランティアの交流を描いた『こんな夜更けにバナナかよ』(北海道新聞社、後に文春文庫)を刊行し、大宅壮一ノンフィクション賞、講談社ノンフィクション賞を受賞。2011年、2冊目の著書『北の無人駅から』(北海道新聞社)を刊行し、サントリー学芸賞、石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞、地方出版文化功労賞などを受賞。札幌市在住。 ISBN 978-4-480-68343-4 新書判 256頁 発行 筑摩書房 書店発売日 2018年12月5日
-

聞く技術 聞いてもらう技術
¥946
☆店長のひと言 「野菜作りは土作り。」 紹介 「聞かれることで、ひとは変わる」 カウンセラーが教える、コミュニケーションの基本にして奥義。読んですぐに実践できる、革新的な一冊。 第19回大佛次郎論壇賞、紀伊國屋じんぶん大賞2020 W受賞 『居るのはつらいよ』の東畑開人、待望の新書第一作! 聞かれることで、ひとは変わる――。 カウンセラーが教える、コミュニケーションの基本にして奥義。 「聞く」は声が耳に入ってくることで、「聴く」は声に耳を傾けること――。「聴く」のほうがむずかしそうに見えて、実は「聞く」ほうがむずかしい。「聞く」の不全が社会を覆ういまこそ「聞く」を再起動しなければならない。そのためには、それを支える「聞いてもらう」との循環が必要だ。小手先の技術から本質まで、読んだそばからコミュニケーションが変わる、革新的な一冊。 「「聞いてもらう技術」? ふしぎな言葉に聞こえるかもしれません。その感覚をぜひ覚えておいてください。このふしぎさこそが、「聞く」のふしぎさであり、そして「聞く」に宿る深い力であって、この本でこれから解き明かしていく謎であるからです。」(本文より) 世の中にはたくさんの素晴らしい「聞く技術」本があるわけですが、心理士としてひとつだけ不満がありました。「聞く技術」を必要としているときほど、実は技術なんか使っている余裕がないことです。 たとえば、パートナーや家族、同僚などの身近な人間関係で揉めているとき、あるいは政治や社会課題をめぐって敵と味方が二分されるとき、本当は対話が必要なときこそ、僕らの「聞く」は不全に陥ります。相手の話を聞いていられなくなる。 そういうとき、必要なのは、「聞く技術」ではなく「聞いてもらう技術」です。僕らが話を聞けなくなるのは、僕ら自身の話を聞いてもらえていないときだと思うからです。 「聞く」はふしぎです。聞くための小手先の技術から、聞いてもらうことに備わる深いちからまで、20年近い臨床経験から学んだことを、すべて書いてみました。 ――東畑開人 目次 【目次】 まえがき この本の問い/対話が難しい時代に/「聞く」を回復する/聞いてもらう技術?/いざ、「聞く」の世界へ 聞く技術 小手先編 1 時間と場所を決めてもらおう/2 眉毛にしゃべらせよう/3 正直でいよう/4 沈黙に強くなろう/5 返事は遅く/6 7色の相槌/7 奥義オウム返し/8 気持ちと事実をセットに/9 「わからない」を使う/10 傷つけない言葉を考えよう/11 なにも思い浮かばないときは質問しよう/12 また会おう/小手先の向こうへ 第1章 なぜ聞けなくなるのか 届かなかった言葉/社会に欠けているもの/聞くは神秘ではない/「対象としての母親」と「環境としての母親」/ほどよい母親/「対象としての聞く」と「環境としての聞く」/失敗とは何か/痛みを聞く/聞くのが難しい/首相に友達を/聞くはグルグル回る 第2章 孤立から孤独へ 連鎖する孤独/孤独と孤立のちがい/孤立とはどういう状態か/手厚い守り/個室のちから/メンタルヘルスの本質/他者の声が心に満ちる/安心とはなにか/孤立したひとの矛盾/一瞬で解決しない/心は複数ある/第三者は有利/個人と個室の関係/象牙とビニール/「聞いてもらう技術」へ 聞いてもらう技術 小手先編 日常編/1 隣の席に座ろう/2 トイレは一緒に/3 一緒に帰ろう/4 ZOOMで最後まで残ろう/5 たき火を囲もう/6 単純作業を一緒にしよう/7 悪口を言ってみよう/体にしゃべらせる ― 日常編まとめ/緊急事態編/8 早めにまわりに言っておこう/9 ワケありげな顔をしよう/10 トイレに頻繁に行こう/11 薬を飲み、健康診断の話をしよう/12 黒いマスクをしてみよう/13 遅刻をして、締切を破ろう/未完のテクニック――緊急事態編まとめ 第3章 聞くことのちから、心配のちから 心に毛を生やそう/素人と専門家のちがい/初めてのカウンセリング/2種類の「わかる」/年をとってわかること/それ、つらいよね/世間知の没落/シェアのつながり/世間のちから/世間知と専門知の関係/心配できるようになること/カウンセラーの仕事は通訳/診断名のちから/バカになる/世間知の正体/理解がエイリアンを人間に変える/時間のちから 第4章 誰が聞くのか 対話を担う第三者/食卓を分断する話題/「話せばわかる」が通用しないとき/幽霊の話/聞いてもらおう/第三者には3種類ある/聞かれることで、人は変わる/当事者であり、第三者でもある/聞く技術と聞いてもらう技術 あとがき――聞く技術 聞いてもらう技術 本質編 著者プロフィール 東畑 開人 (トウハタ カイト) (著/文) 1983年東京生まれ。京都大学大学院教育学研究科博士後期課程修了。博士(教育学)・臨床心理士。専門は、臨床心理学・精神分析・医療人類学。白金高輪カウンセリングルーム主宰。著書に『野の医者は笑う―心の治療とは何か?』(誠信書房)『居るのはつらいよ―ケアとセラピーについての覚書』(医学書院)『心はどこへ消えた?』(文藝春秋 2021)『なんでも見つかる夜に、こころだけが見つからない』(新潮社)など。『居るのはつらいよ』で第19回(2019年)大佛次郎論壇賞受賞、紀伊國屋じんぶん大賞2020受賞。 ISBN 978-4-480-07509-3 新書判 256頁 発行 筑摩書房 書店発売日 2022年10月11日