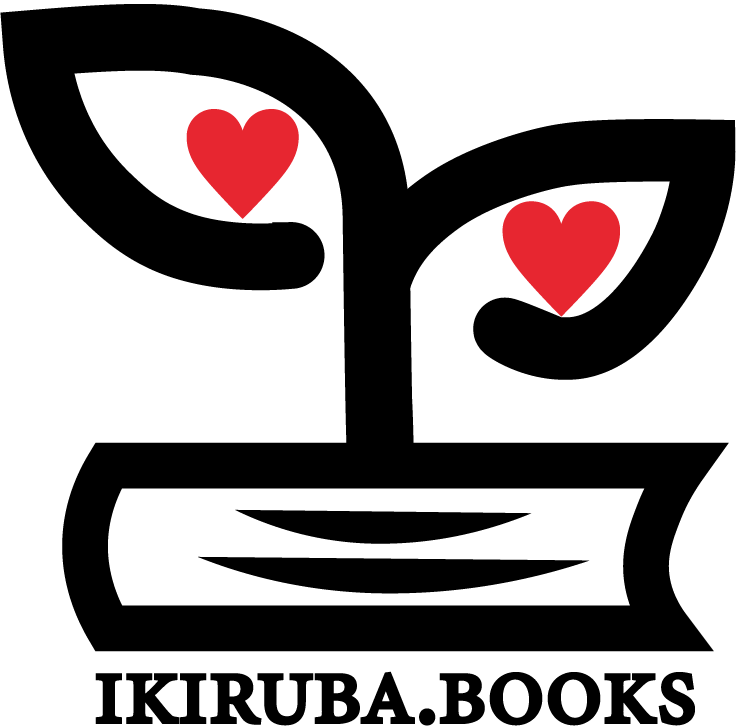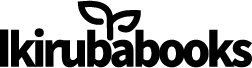-

ビッグイシュー519号
¥500
☆店長のひと言 「AI時代に必要なもの、それは健康です。」 【内容紹介】 特集 直観する脳 AIと人間 チャットGPTやGeminiなど、生成AIは急速に人々の生活に根づき始めました。悩み相談の相手もすれば、数時間・数日・数年かかった計算や検索作業がものの数分で完結する場合もあります。その利便性は第4次産業革命とも呼ばれる一方、ニュースに関する6割近くの回答は正確性に問題があるなど、数々の弊害も生まれています。 そんなAI の時代だからこそ「私たち一人ひとりの人間がどのように脳を使っていくか、という問いかけが必要だ」と脳神経外科医・研究者の岩立康男さん(東千葉メディカルセンター・センター長)は語ります。そもそもAIに何を聞くか?何をさせるか?は、私たち人間の判断力やひらめきにかかっているからです。 岩立さんは、AIを使いこなすためにもひらめきや判断力をもたらす「直観」が何より大事だと言います。そして、人間が持つ最大の強みは「忘れること」だとも。 岩立さんに、私たち人間の「直観する脳」「忘れる脳力」について聞きました。 TOP INTERVIEW スペシャルインタビュー ハリス・ディキンソン 現在29歳、いま最も注目を集める若手俳優の一人、英国出身のハリス・ディキンソン。2028年に公開予定の伝記映画『THE BEATLES ‒ A Four-Film Cinematic Event(仮題)』ではジョン・レノンを演じることでも話題を呼んでいます。 そんなディキンソンがこの数年にわたって取り組んできたホームレス支援の活動、初の監督作品について語りました。 リレーインタビュー・私の分岐点留学プランナー、元タレント 石井あみさん 子育てフレンドリーなフィリピンに移住 細かいことにもイライラしない生活 国際記事 英国。探検家ドウェイン・フィールズ、チーフスカウトに 自然ドキュメンタリー番組で人気の探検家、ドウェイン・フィールズ。過酷な自然環境を旅して回る彼が、2024年9月、英国スカウト協会からチーフスカウトに任命されました。野外活動にかかわりながら青少年の健全なエンパワメントに尽力する、彼の活躍を追いました。 (地球市民)セピデ・ファルシさん。ガザに住む24歳女性ファトマとのビデオ通話を映画に 10代の時にフランスに出国した、イラン出身のセピデ・ファルシ監督。イスラエルの攻撃が続くガザで暮らす24歳のフォトジャーナリスト、ファトマ・ハッスーナとのビデオ通話を記録し、ドキュメンタリー映画『手に魂を込め、歩いてみれば』を制作しました。ファトマが遺したもの、そして映画に込めた思いとは。 WORLD STREET NEWS 世界短信 連載記事 浜矩子の新ストリート・エコノミクス 川柳が暴く、今日的「互恵」 コミック マムアンちゃん ウィスット・ポンニミット ホームレス人生相談 母の電話に心穏やかでいられません 宇宙・地球・人間 池内了の市民科学メガネ 詐欺の手口いろいろ 読者のページ My Opinion 販売者に会いにゆく 『ファクトゥム』ヤスミン・カールソン 色とりどり 希望をつむぐ本屋さん 100の本棚のある店内 棚移動や本の補充で、つねに変わる景色 (エッセイ)カヨが与えてくれたもの 内澤旬子さん 東京から小豆島へ移住してすぐにヤギを迎えることになった内澤旬子さん(文筆家・イラストレーター)によるイラストとエッセイ。ヤギのカヨとの出合いや創意工夫をしながらヤギたちの世話をする日々を描きます。さらに、ヤギを飼ったことで思わぬ大きな恩恵があったと語ります。 表現する人/葛本康彰さん 偶然の自然現象を反映してつくる FROM EDITORIAL 編集後記 (ビッグイシュー日本HPより抜粋)

-

ビッグイシュー514号
¥500
☆店長のひと言 「スペシャルインタビューは、昭和じゃないほうのAdoさんです。念のため。」 【内容紹介】 特集 あたりまえを壊す人類学へ 「あたりまえがいろいろな局面で崩壊している現代の世界。人類学は多くの人が信じてきた、あたりまえが行き詰まっている時に、そうした行き詰まりを乗り越えるための、また別の可能性を提示することのできる学問」だと里見龍樹さん(早稲田大学人間科学学術院教授)は言います。 2008年3月、里見さんはメラネシアに位置するソロモン諸島のマライタ島の北東岸にあるフォウバイタ村(仮名)を訪れ、以来通算21ヵ月、滞在してフィールドワークを行いました。ここには東西1〜4km、南北30km以上にわたって広大なサンゴ礁が広がる海があり、アシと呼ばれる人たちがサンゴのかけらを積み上げて築いた人工の島が合計90個以上も点在しています。里見さんは、島の人々とともに暮らすフィールドワークの中で、これまで謎に包まれていた島の歴史などを解いていきます。 そんな里見さんが語る「人類学の問い直しの歴史と、マライタ島でのフィールドワークや研究で見えてきたこと、これからの人類学」とは? TOP INTERVIEW スペシャルインタビュー Ado 小学一年生の時、従妹に「悪ノ娘」「悪ノ召使」(作詞・作曲:mothy)の二次創作動画を勧められたのを機に、父親のパソコンでボーカロイド楽曲を聴き始めたという“歌い手”のAdoさん。 小学校高学年になると、「ニコニコ動画」やニンテンドー3DSに配信されていたソフト「うごくメモ帳」から、姿を見せずに活動する歌い手の文化に興味をもつようになりました。17歳最後の日に「うっせぇわ」で衝撃のメジャーデビューを飾り、早5年。以降も次々に話題作を世に送り出してきました。そんなAdoさんが、新曲『MAGIC』や大盛況を博した世界ツアー、また11月に控えた東京・大阪のドームツアーについて語ります。 リレーインタビュー・私の分岐点俳優 金城大和さん 東京でしかできない、エキストラに応募 芝居のおもしろさにすっかり取り憑かれた 国際記事 英国。「音楽は人間にとって共通の普遍的な言語」 現代のクラシック音楽界で頭角を現す、カネー=メイソン一家の若き演奏家たち。その7人の子どもたちを育てたエッセイストの母カディアトゥは今年、自身と家族の体験を綴った回顧録を上梓し、英国で話題を呼びました。アフリカの血を引く移民として一家が直面してきた人種差別や“英国人らしさ”の問題について、彼女の思いを聞きました。 WORLD STREET NEWS 世界短信 連載記事 原発ウォッチ! 防衛省の報告書、「原子力潜水艦保有」を記載 浜矩子の新ストリート・エコノミクス タコ市vsタヌ木の合戦? 雨宮処凛の活動日誌 日本、酷暑で奪われた命とドイツのセーフティネット ホームレス人生相談 母とどう話していいかわかりません 「新型コロナワクチン」論争 映画『ヒポクラテスの盲点』、大西隼さんに聞く 国民の83%が、のべ4億3千万回以上摂取した新型コロナワクチン。救われた命は36万人以上ともいわれる一方で、副反応や重篤例、死亡例も多数報告されている。後遺症患者や研究者への取材を続け、ドキュメンタリー映画『ヒポクラテスの盲点』を制作した監督の大西隼さんに話を聞いた。 読者のページ My Opinion 販売者に会いにゆく 日本『ビッグイシュー日本版』黒木幸一さん 『はだしのゲンはまだ怒っている』込山正徳 監督 漫画家・中沢啓治さん(1939-2012年)が自身の被爆体験をもとに描いた漫画『はだしのゲン』。翻訳され世界へ広がり、各地で読み継がれてきたその作品を題材にしたドキュメンタリー『はだしのゲンはまだ怒っている』が11月14日から全国で順次公開される。込山正徳監督に本作に込める思いを聞いた。 香山リカ むかわ町穂別診療所の四季・秋 栗の木まで歩ける道を作った、とみさん 都内の古民家で開く「夜パンカフェ」 みんなが隣人の空間でゆったり過ごす FROM EDITORIAL 編集後記 (ビッグイシュー日本HPより抜粋)
-

検証 ナチスは「良いこと」もしたのか?
¥902
☆店長のひと言 「読んだあとに自分の見識がどう変わるか(変われる)どうか。」 内容紹介 「ナチスは良いこともした」という言説は、国内外で定期的に議論の的になり続けている。アウトバーンを建設した、失業率を低下させた、福祉政策を行った――功績とされがちな事象をとりあげ、ナチズム研究の蓄積をもとに事実性や文脈を検証。歴史修正主義が影響力を持つなか、多角的な視点で歴史を考察することの大切さを訴える。 目次 はじめに 第一章 ナチズムとは? 第二章 ヒトラーはいかにして権力を握ったのか? 第三章 ドイツ人は熱狂的にナチ体制を支持していたのか? 第四章 経済回復はナチスのおかげ? 第五章 ナチスは労働者の味方だったのか? 第六章 手厚い家族支援? 第七章 先進的な環境保護政策? 第八章 健康帝国ナチス? おわりに ブックガイド 著者プロフィール 小野寺拓也(オノデラ タクヤ) 1975年生まれ.東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了. 博士(文学).昭和女子大学人間文化学部専任講師を経て,現在,東京外国語大学大学院総合国際学研究院准教授.専門はドイツ現代史. 著書に『野戦郵便から読み解く「ふつうのドイツ兵」――第二次世界大戦末期におけるイデオロギーと「主体性」』(山川出版社),訳書にウルリヒ・ヘルベルト『第三帝国――ある独裁の歴史』(KADOKAWA)などがある. 田野大輔(タノ ダイスケ) 1970年生まれ.京都大学大学院文学研究科博士後期課程研究指導認定退学.博士(文学).大阪経済大学人間科学部准教授等を経て,現在,甲南大学文学部教授.専門は歴史社会学,ドイツ現代史. 著書に『ファシズムの教室――なぜ集団は暴走するのか』(大月書店),『愛と欲望のナチズム』(講談社),『魅惑する帝国――政治の美学化とナチズム』(名古屋大学出版会)などがある. (岩波書店ホームページより引用) ISBN:978-4-00-271080-8 Cコード:0336 A5判120ページ 発行:岩波書店 発売日: 2023年07月07日

-

冤罪と人類 道徳感情はなぜ人を誤らせるのか
¥1,100
【中古 状態きれい】 (参考:定価1,240円+税) ☆店長のひと言 「道徳と偏見って紙一重ですよね!って言われたらあなたならどう思います?」 内容紹介 拷問、捏造、自白の強要……検事総長賞を受けた名刑事・紅林麻雄はなぜ冤罪を続発させたのか? 圧倒的筆力で人間の業を抉る怪著 著者プロフィール 管賀江留郎(かんが・えるろう) 少年犯罪データベース主宰。書庫に籠もって、ただひたすらに古い文献を読み続ける日々を送っている。著書に『戦前の少年犯罪』。 (Hayakawa Books & Magazinesより転載) ISBN 978-4-15-050574-5 文庫判 688頁 発行 早川書房 発売日 2021年4月28日
-

もの食う人びと
¥300
【中古 状態きれい】 (参考:定価720円+税) ☆店長のひと言 「新聞に連載していたとき読んでいました。過酷な状況と食事の描写の対比が衝撃でした。 紹介 バングラデシュで、旧ユーゴで、ソマリアで、チェルノブイリで…人びとはいま、なにを食べ、考えているか。熟達の記者・芥川賞作家の著者が、世界の飢餓線上を彷徨い、ともに食らい、語らい、鮮やかに紡いだ、驚愕と感動のドラマ。現代報道の壁を突破し抜いた、世紀末の食の黙示録。文庫化に際し、新たに書き下ろし独白とカラー写真を収録。 目次 旅立つ前に 残飯を食らう 食いものの恨み ピナトゥボの失われた味 塀の中の食事 食とネオナチ 黒を食う モガディシオ炎熱日誌 麗しのコーヒー・ロード バナナ畑に星が降る 兵士はなぜ死んだのか 禁断の森 チェロ弾きの少女 儒者に食事作法を学ぶ 背番号27の孤独な戦い ある日あの記憶を殺しに〔ほか〕 著者プロフィール 辺見 庸 (ヘンミ ヨウ) (著) 小説家、ジャーナリスト、詩人。元共同通信記者。宮城県石巻市出身。宮城県石巻高等学校を卒業後、早稲田大学第二文学部社会専修へ進学。同学を卒業後、共同通信社に入社し、北京、ハノイなどで特派員を務めた。北京特派員として派遣されていた1979年には『近代化を進める中国に関する報道』で新聞協会賞を受賞。1991年、外信部次長を務めながら書き上げた『自動起床装置』を発表し第105回芥川賞を受賞。 ISBN:978-4-04-341701-8 Cコード:0195 文庫判 368ページ 発行:KADOKAWA 発売日: 1997年06月20日
-

天路の旅人
¥1,450
【中古 カバーに少し傷みあり(画像参照)】 (参考:定価: 2,400円+税) ☆店長のひと言 「本の厚みが旅の厚み」 紹介 「この稀有な旅人のことを、どうしても書きたい」。「旅」の真髄に迫る、九年ぶりの大型ノンフィクション。第二次大戦末期、敵国の中国大陸の奥深くまで「密偵」として潜入した若者・西川一三。敗戦後もラマ僧に扮したまま、幾度も死線をさまよいながらも、未知なる世界への歩みを止められなかった。その果てしない旅と人生を、彼の著作と一年間の徹底的なインタビューをもとに描き出す。著者史上最長にして、新たな「旅文学」の金字塔。 著者プロフィール 沢木 耕太郎 (サワキ コウタロウ) (著/文) さわきこうたろう 作家。 1947年、東京都生まれ。横浜国立大学卒業。79年『テロルの決算』で大宅壮一ノンフィクション賞、82年『一瞬の夏』で新田次郎文学賞、85年『バーボン・ストリート』で講談社エッセイ賞、93年『深夜特急第三便』でJTB紀行文学大賞、2003年それまでの作家活動に対して菊池寛賞、06年 『凍』で講談社ノンフィクション賞を受賞。近著に、短編小説集『あなたがいる場所』、エッセイ集『ポーカー・フェース』、児童書『月の少年』、絵本『わるいことがしたい!』などがある。 ISBN:978-4-10-327523-7 Cコード:0095 四六変型判576ページ 発行: 新潮社 初版年月日: 2022年10月25日
-

別れを告げない
¥2,750
☆店長のひと言 「最近思うんですよ、苦労は本当に人を成長させるのだろうか、と…。」 紹介 作家のキョンハは、虐殺に関する小説を執筆中に、何かを暗示するような悪夢を見るようになる。ドキュメンタリー映画作家だった友人のインソンに相談し、短編映画の制作を約束した。 済州島出身のインソンは10代の頃、毎晩悪夢にうなされる母の姿に憎しみを募らせたが、済州島4・3事件を生き延びた事実を母から聞き、憎しみは消えていった。後にインソンは島を出て働くが、認知症が進む母の介護のため島に戻り、看病の末に看取った。キョンハと映画制作の約束をしたのは葬儀の時だ。それから4年が過ぎても制作は進まず、私生活では家族や職を失い、遺書も書いていたキョンハのもとへ、インソンから「すぐ来て」とメールが届く。病院で激痛に耐えて治療を受けていたインソンはキョンハに、済州島の家に行って鳥を助けてと頼む。大雪の中、辿りついた家に幻のように現れたインソン。キョンハは彼女が4年間ここで何をしていたかを知る。インソンの母が命ある限り追い求めた真実への情熱も…… いま生きる力を取り戻そうとする女性同士が、歴史に埋もれた人々の激烈な記憶と痛みを受け止め、未来へつなぐ再生の物語。フランスのメディシス賞、エミール・ギメ アジア文学賞受賞作。 著者プロフィール ハン・ガン (ハン ガン) (著/文) Han Kang 한강 1970年、韓国・光州生まれ。延世大学国文学科卒業。2005年、三つの中篇小説をまとめた『菜食主義者』で韓国最高峰の文学賞である李箱文学賞を受賞、同作で16年にアジア人初の国際ブッカー賞を受賞。17年、『少年が来る』でイタリアのマラパルテ賞を受賞、23年、『別れを告げない』(本書)でフランスのメディシス賞(外国小説部門)を韓国人として初めて受賞し、24年にフランスのエミール・ギメ・アジア文学賞を受賞した。本書は世界22か国で翻訳刊行が決定している。他の邦訳作品に、『ギリシャ語の時間』『すべての、白いものたちの』『回復する人間』『そっと 静かに』『引き出しに夕方をしまっておいた』がある。 斎藤 真理子 (サイトウ マリコ) (翻訳) 翻訳家。パク・ミンギュ『カステラ』(共訳)で第一回日本翻訳大賞、チョ・ナムジュ他『ヒョンナムオッパへ』で〈韓国文学翻訳院〉翻訳大賞受賞。訳書は他に、ハン・ガン『回復する人間』『すべての白いものたちの』『ギリシャ語の時間』『引き出しに夕方をしまっておいた』(共訳)、パク・ソルメ『もう死んでいる十二人の女たちと』『未来散歩練習』、ペ・スア『遠きにありて、ウルは遅れるだろう』、パク・ミンギュ『ピンポン』、チョ・セヒ『こびとが打ち上げた小さなボール』、ファン・ジョンウン『誰でもない』『年年歳歳』『ディディの傘』、チョン・イヒョン『優しい暴力の時代』、チョン・ミョングァン『鯨』、チョン・セラン『フィフティ・ピープル』『保健室のアン・ウニョン先生』『声をあげます』『シソンから、』、チョ・ナムジュ『82年生まれ、キム・ジヨン』『サハマンション』、李箱『翼 李箱作品集』など。著書『韓国文学の中心にあるもの』、『本の栞にぶら下がる』、『曇る眼鏡を拭きながら』(共著) ISBN:978-4-560-09091-6 Cコード:0097 四六判304ページ 発行: 白水社 書店発売日: 2024年4月2日

-

肉食の哲学
¥1,500
【中古 状態きれい】 (参考:定価2,200円+税) ☆店長のひと言 「人間が本当に欲しているのは肉じゃなくて血なのではないだろうか。」 紹介 肉食は私たちの〈原罪〉なのか? 過激化するベジタリアン(ビーガン)の論理の危うさを暴き、カニバリズムや人工肉の哲学的意味の議論を通じ、「肉食は我々の義務である」と語る刺激的な哲学エッセイ。動物行動学から哲学へと横断する注目の著者ドミニク・レステルの初邦訳。 著者は語る。 「菜食主義とは、我が身を神になぞらえる人間の思い上がりである。そこには動物への愛など存在しない──。」 肉食は残酷だ、タンパク質は動物から摂らなくても十分だ……。 食肉加工場の襲撃など、テロリズムにまで過激化するビーガンの主張に、 どことなくいかがわしいものを感じるのはなぜだろうか。 人工肉や臓器移植、植物の知性、遺伝子組み換え、動物解放論など、 菜食主義をめぐるさまざまなトピックスに触れながら、 この世界で私たち人間とはいかなる存在なのか、自在に論じる注目の1冊。 目次 アペリティフに代えて アミューズ 倫理的ベジタリアンをどのように捉えるか オードブル ベジタリアン実践小史 一皿目のメインディッシュ 二皿目のメインディッシュ 肉食者の倫理 デザートに代えて 日本語版へのあとがき 訳者あとがき 著者プロフィール ドミニク・レステル (ドミニク レステル) (著/文) 1961年生まれ。哲学者、動物行動学者。動物行動学を起点に人間と動物や機械の関係について論じている。主な著書に『動物性 ヒトという身分に関する試論』(L’Animalité: Essai sur le statut de l’humain, 1996)、『文化の動物的起源』(Les Origines animales de la culture, 2001)、『ヒトは何の役に立つのか』(À quoi sert l’homme?, 2015)などがある。 ISBN:978-4-86528-279-5 Cコード:0010 四六判172ページ 発行: 左右社 初版年月日: 2020年6月30日
-

武士の介護休暇
¥1,078
☆店長のひと言 「大ヒット作『武士の家計簿』をパクったようなタイトルに惹かれてページを開いたら最後です。」 紹介 はじめに 第一章 江戸時代の介護事情──介護休暇を取った武士── 日記に残された「武士の介護」/武士が利用した「看病断」という介護休業制度/武士の「近距離介護」/「看病断」の申請手順/当時の要介護状態となる原因とは──『孝義録』から読み解く──/なぜ幕府は「孝行」を重視したのか?/江戸期の日本人に多かった眼病・盲目の人/中風で半身麻痺に/江戸時代の認知症/庶民層の介護の実態/オランダ人医師ポンペが見た貧困の中の介護/非血縁者による介護 第二章 江戸時代の「老い」の捉え方 時代によって変わる高齢者区分/江戸時代の高齢者人口は?/江戸時代では何歳から「高齢者」?/生前相続としての隠居/高齢でも働かされた武士/庶民の隠居事情/早期リタイアを夢見た人々/『養生訓』『鶉衣』にみる老い 第三章 江戸時代以前の「老い」──古代~中世期の高齢者観── 古代~中世期では何歳から高齢者?/高齢世代まで生きられた人はどのくらいいた?/尊敬の対象・強者としての高齢者/高齢者は神に近い存在/『万葉集』における老いの見方/『枕草子』『方丈記』『徒然草』における高齢者観/変化する理想の老後/若く見られたがる愚かさについて/江戸時代とは異なる古代~中世期における高齢者観 第四章 江戸時代以前の介護事情──古代~中世期の介護── 当時の要介護状態となる原因とは/老いた親が鬼になる/中世期の脳卒中/白内障で失明/身内が介護しないと批判の対象に/見捨てられた老人を介護した女性の正体/身内がいない貧しい要介護者の末路/古代にも存在した驚きの介護制度/律令制度の要介護区分/ケアをすれば功徳を積める/名も知らぬ老僧を介護して家を得る/身寄りのない高齢者の介護・看取りの実情 第五章 古代~中世期の「姥捨て」 親を捨てた人々の物語/「運搬用具型」の姥捨て物語/「老親の知恵型」の姥捨て物語/「老親福運型」の姥捨て物語/「枝折り型」の姥捨て物語/救われる老親と棄老の実情/当時の人々が介護をした理由とは ①愛情や感謝──「情」の論理──/②中国からの影響──「儒」の論理──/③仏教からの影響──「仏」の論理──/④ギブアンドテイク──「互酬」の論理──/四つの論理の弱点と介護放棄 第六章 江戸時代の「介護に向かわせる」価値観 江戸時代に身寄りのない高齢者はどう介護された?/「地域社会で高齢の要介護者を支えるべし」/幕藩 著者プロフィール 﨑井 将之 (サキイ マサユキ) (著/文) 1976年生まれ。首都大学東京大学院社会科学研究科後期博士課程単位取得退学。哲学、国際市民社会論で修士号を取得。大手老人ホーム検索サイトで高齢者福祉関連ニュース記事を執筆。著書に『哲学のおさらい』。 ISBN:978-4-309-63179-0 Cコード:0221 新書判264ページ 発行: 河出書房新社 初版年月日: 2024年10月22日
-

辺境のラッパーたち ~立ち上がる「声の民族誌」~
¥3,520
☆店長のひとラップ HEY YO, 魂抜かれたヒップホップ HEN-KYO de rap survive 他人(ひと)のせいにすんなリスナー 声なき声ひろえ Listen Now! 紹介 ラッパーのことばに耳をすませば、世界のリアルが見えてくる。 戦火が絶えないガザやウクライナで、弾圧が続くチベットやイランで、格差にあえぐモンゴルやインドで、海の端の日本で――。アメリカで生まれたヒップホップ文化、なかでもラップミュージックは世界に広がり、「辺境」に生きる者たちは声なき声をリリックに託す。現代社会の歪みを鮮やかに映し出す、世界各地のラッパーたちの声を幅広い執筆陣が紹介する。ラッパー、ダースレイダー、ハンガー(GAGLE)のインタビューも収録。 http://www.seidosha.co.jp/book/index.php?id=3935 著者 [編者]島村一平(しまむら・いっぺい) 国立民族学博物館人類文明誌研究部教授。文化人類学・モンゴル研究専攻。博士(文学)。早稲田大学法学部卒業後、テレビ番組制作会社に就職。取材で訪れたモンゴルに魅せられ制作会社を退社、モンゴルへ留学する。モンゴル国立大学大学院修士課程修了(民族学専攻)。日本に帰国後、総合研究大学院大学博士後期課程に入学。同大学院を単位取得退学後、国立民族学博物館講師(研究機関研究員)、滋賀県立大学人間文化学部准教授等を経て現職。著書に『憑依と抵抗——現代モンゴルにおける宗教とナショナリズム』(晶文社)、『ヒップホップ・モンゴリア——韻がつむぐ人類学』(青土社)、『増殖するシャーマン——モンゴル・ブリヤートのシャーマニズムとエスニシティ』(春風社)など多数。 (青土社ホームページより) ISBN:978-4-7917-7654-2 Cコード:0039 四六判544ページ 発行: 青土社 発売日: 2024年6月26日

-

なぜ少年は聖剣を手にし、死神は歌い踊るのか
¥2,090
☆店長のひと言 「私、こんな本ばかり読んで遊んで暮らしたいんです、ホントは。」 内容紹介 映画、マンガ、アニメ、音楽、ゲーム、ラノベを学問する方法! ありとあらゆる場面で私たちは漫画を読み、ゲームをし、アニメや映画を鑑賞しています。この本は、それらを「学問」としてより深く知りたい、考えたいとあなたが思ったときに――ポップカルチャーと神話をめぐる学びの旅に出たいとあなたが思ったそのときに――携えるアイテム、手に取る一冊として作りました。 扱うのは、米津玄師「死神」、『BLEACH』、東方Project、『サマータイムレンダ』、『呪術廻戦』、『鬼滅の刃』、怪奇漫画、『美少女戦士セーラームーン』、蜷川幸雄の舞台演出、『葬送のフリーレン』、『坂道のアポロン』、『君の名は。』、『ゴジラ』、神話と宗教リテラシー、「美しい国」のポップカルチャー、『進撃の巨人』、『ジャガーノート』他多数。 各章の冒頭には、「アプローチ方法」と「作品概要」を記し、どのような学問的な立場から、どのような分析視点から、それぞれの論者が作品にアプローチするかを示し、読解していく方法を丁寧に記しました。 物語は、読まれると同時に私たちの見る世界を形作り、息づきはじめたイメージは、あらたな枠組みを作りはじめる――。そんな物語とそこに現れる神話は、現代を生きる私たちにとって何なのでしょうか。 ポップカルチャーや神話について関心がある人はもちろん、レポートや卒論のような少し「真面目」な目的でポップカルチャーや神話、あるいはその両方の関係を考えたいという人に。 執筆は、植朗子、清川祥恵、南郷晃子、川村悠人、渡勇輝、木下資一、斎藤英喜、横道誠、木村武史、勝又泰洋、三村尚央、上月翔太、鈴村裕輔、庄子大亮、平藤喜久子、藤巻和宏、河野真太郎。 装画:いそにん(@isonin7777) 目次 はじめに [米津玄師「死神」×死神] 米津玄師「死神」考(南郷晃子) 一 はじめに/二 落語「死神」と米津玄師「死神」/三 落語「死神」のルーツ/四 日本における死神/五 死神の喜悦/六 終わりに [BLEACH×言葉] 死神たちは言葉を振るう――『BLEACH』と古代インドにおける言葉と詠唱 (川村悠人) 一 はじめに/二 『BLEACH』と古代インドにおける言葉/三 言葉の詠唱/四 おわりに― 古代と現代を繋ぐ「言葉」 [東方 Project×幻想] トポスとしての別世界――「東方 Project」の世界観と想像力(渡勇輝) 一 はじめに/二 データベースとしての東方/三 底流にある「神道」的世界/四 トポスとしての別世界/五 おわりに [コラム] 『サマータイムレンダ』の蛭子神――異形神の孤独と悲しみ(木下資一) [コラム] 「魔術師」として生きること(斎藤英喜) [鬼滅の刃×聖剣] 『鬼滅の刃』炭治郎に継承される「聖剣」――日輪刀と刀鍛冶の物語(植朗子) 一 はじめに/二 日輪刀と鬼殺隊の超自然的な力/三 竈門家と「日の呼吸」をつなぐ縁/四 継承される「聖剣」縁壱の日輪刀/五 「聖剣」と「英雄」のモティーフ/六 「聖剣」継承の助力者となる刀鍛冶たち/七 おわりに [怪奇マンガ×終末] 神話の原初的断片としての怪奇マンガ――ジャンル論的考察(横道誠) 一 聖俗×生理的な嫌悪感×狂気=戦慄+拙劣/二 日本怪奇マンガ小史/三 五つの作品に焦点を当てて/四 おわりに [美少女戦士セーラームーン×ブリコラージュ] 美少女戦士セーラームーン――ブリコラージュと神話・宗教・スピリチュアリティ・科学技術(木村武史) 一 はじめに/二 伝統的な神話素とモチーフの採用と転換/三 セーラー戦士の身体表象/四 コズミックな戦い/五 科学 /技術と神話・宗教の融合/六 結び [コラム] ローマ神話の「母と息子」――『コリオレイナス』にみる蜷川幸雄の階段の利用法(勝又泰洋) [葬送のフリーレン×記憶] 「英雄神話」の語り直しとしての『葬送のフリーレン』(三村尚央) 一 序/二 過去の模倣としての現在/三 「内なる心」を描く物語形式―叙事詩から小説へ/四 過去を思い出すことの重要性と危険性/五 「魔法」と「言葉」―自身の「外」と「内」の繋がりと断絶/六 結語 [坂道のアポロン×音楽] ジャズする神々、あるいは友人たち――『坂道のアポロン』における神話的イメージの重なり合い(上月翔太) 一 「坂道のアポロン」とは誰か/二 もうひとりの「アポロン」/三 呪いと憧れの神話的イメージの重なり/四 光の交流/五 アポロン的音楽とディオニュソス的音楽のマンガ表現/六 ジャズのマンガ表現/七 ケンカとしてのジャズ [君の名は。×彗星] 映画『君の名は。』に見出す「現代の神話」の可能性(鈴村裕輔) 一 はじめに/二 入れ替わる身体の神話性/三 水と彗星/四 彗星と大火/五 忘却と記憶/六 スペクタクルとしての災厄/七 おわりに [ゴジラ×怪獣] 「怪獣」の神話性――『ゴジラ』たちは何を表象するのか(庄子大亮) 一 はじめに/二 ゴジラ映画の展開/三 ゴジラが意味するもの―ゴジラと竜/四 「他者」としての怪獣/五 怪獣の多様な相貌/六 おわりに [コラム] ポップカルチャーから何を論じるのか(平藤喜久子) [コラム] 保守×愛国×神話――「美しい国」のポップカルチャー(藤巻和宏) [進撃の巨人×天地創造] 国造りと(反)成長の物語――『進撃の巨人』とポスト冷戦の私たち(河野真太郎) 一 はじめに/二 巨人の神話/三 戦後日本と『進撃の巨人』/四 グローバリゼーションと民族紛争、部族主義へ/五 反成長と不思議の国の巨人たち [ジャガーノート×ポスト・コロニアリズム] 暴走する運命――英米近代における「ジャガーノート」表象(清川祥恵) 一 序/二 「ジャガーノート」のエティモロジー/三 「狂気」の自覚/四 運命の糸/五 結論―暴走する世界の行方 あとがき(植 朗子) 執筆者プロフィール 著者プロフィール 神戸神話・神話学研究会 (コウベシンワシンワガクケンキュウカイ) (編) 神戸神話・神話学研究会(通称:神神神 Shin Shin Shin)は2018年に神戸大学の研究プロジェクトから派生して発足した研究会です。おもに近現代を研究対象として活動しています。 https://shin3ken.wordpress.com/ 植 朗子 (ウエ アキコ) (編) 神戸大学国際文化学研究推進インスティテュート学術研究員。伝承文学(とくに怪異を語る「伝説」)。『鬼滅夜話 キャラクター論で読み解く『鬼滅の刃』』(扶桑社、二〇二一年)、『キャラクターたちの運命論―『岸辺露伴は動かない』から『鬼滅の刃』まで』(平凡社新書、二〇二三年)など。 清川 祥恵 (キヨカワ サチエ) (編) 佛教大学文学部講師、神戸大学国際文化学研究推進インスティテュート連携フェロー。英文学・ユートピアニズム。「夜を生きるパンサーの子ら―映画『ブラックパンサー』における「神話」と「黒人の生(ブラック・ライヴズ)」」清川祥恵・南郷晃子・植朗子編『人はなぜ神話〈ミュトス〉を語るのか―拡大する世界と〈地〉の物語』(文学通信、二〇二二年)、「英雄からスーパーヒーローへ―十九世紀以降の英米における「神話」利用」植朗子・南郷晃子・清川祥恵編『「神話」を近現代に問う』(勉誠出版、二〇一八年)など。 南郷 晃子 (ナンゴウ コウコ) (編) 桃山学院大学国際教養学部准教授、神戸大学国際文化学研究推進インスティテュート連携フェロー。近世説話。「児島高徳の蓑姿―「近代」津山における歴史/物語の葛藤」清川祥恵・南郷晃子・植朗子編『人はなぜ神話〈ミュトス〉を語るのか―拡大する世界と〈地〉の物語』(文学通信、二〇二二年)、「花の名を持つ女―むごく殺されるお菊、お花をめぐって」木村武史編『性愛と暴力の神話学』(晶文社、二〇二二年)、「奇談と武家家伝―雷になった松江藩家老について」東アジア恠異学会編『怪異学講義―王権・信仰・いとなみ』(勉誠出版、二〇二一年)など。 川村 悠人 (カワムラ ユウト) (著) ①広島大学大学院人間社会科学研究科准教授 ②古代中世インドの言語論、文学、神話 ③『ことばと呪力―ヴェーダ神話を解く』(晶文社、二〇二二年)、『神の名の語源学』(溪水社、二〇二一年) 渡 勇輝 (ワタリ ユウキ) (著) ①摂南大学非常勤講師 ②日本思想史 ③「「古」を幻視する―平田国学と柳田民俗学」(『現代思想 総特集:平田篤胤』二〇二三年一二月臨時増刊号)、「柳田国男と「平田派」の系譜―大国隆正と宮地厳夫に注目して」(山下久夫・斎藤英喜編『平田篤胤 狂信から共振へ』法藏館、二〇二三年)、「近代神道史のなかの「神道私見論争」―国民的「神道」論の出現」(『日本思想史学』五二号、二〇二〇年)など。 木下 資一 (キノシタ モトイチ) (著) ①神戸大学名誉教授 ②日本伝承文化論・日本説話文学 ③神戸説話研究会編『論集 中世・近世説話と説話集』(共著、和泉書院、二〇一四年)、神戸説話研究会編『続古事談注解』(共著、和泉書院、一九九四年)、新日本古典文学大系『宝物集 閑居友 比良山古人霊託』(共著、岩波書店、一九九三年) 斎藤 英喜 (サイトウ ヒデキ) (著) ①佛教大学歴史学部教授 ②神話思想史 ③『陰陽師たちの日本史』(角川新書、二〇二三年)、『読み替えられた日本書紀』(角川選書、二〇二〇年)、『折口信夫 神性を拡張する復活の喜び』(ミネルヴァ書房、二〇一九年)ほか。 横道 誠 (ヨコミチ マコト) (著) ①京都府立大学准教授 ②文学・当事者研究 ③『グリム兄弟とその学問的後継者たち―神話に魂を奪われて』(ミネルヴァ書房、二〇二三年)、『村上春樹研究―サンプリング、翻訳、アダプテーション、批評、研究の世界文学』(文学通信、二〇二三年)、『みんな水の中―「発達障害」自助グループの文学研究者はどんな世界に棲んでいるか』(医学書院、二〇二一年) 木村 武史 (キムラ タケシ) (著) ①筑波大学人文社会系教授 ②宗教学、アメリカ研究 ③『北米先住民族の宗教と神話の世界』(筑波大学出版会、二〇二二年)、『性愛と暴力の神話学』(編著、晶文社、二〇二二年)、『死の神話学』(編著、晶文社、二〇二四年)、その他多数。 勝又 泰洋 (カツマタ ヤスヒロ) (著) ①京都大学非常勤講師 ②西洋古典学 ③「ピロストラトス『テュアナのアポッローニオス』におけるサスペンスの技法」(『西洋古典論集』二六号、二〇二二年)、「アエネーアースのトゥルヌス殺害を振り返る―アーシュラ・K・ル=グウィン『ラーウィーニア』で描かれる『アエネーイス』の結末場面」(『待兼山論叢』五三号、二〇一九年)、「語り手の自己呈示と読み手の形成―読者を引き込む語りの仕掛け」(小池登・佐藤昇・木原志乃編『『英雄伝』の挑戦―新たなプルタルコス像に迫る』京都大学学術出版会、二〇一九年) 三村 尚央 (ミムラ タカヒロ) (著) ①千葉工業大学工学部教育センター教授 ②イギリス文学、記憶研究(memory studies) ③『「記憶」で読む『鬼滅の刃』』(小鳥遊書房、二〇二四年)、『カズオ・イシグロを読む』(水声社、二〇二二年)、『記憶と人文学』(小鳥遊書房、二〇二一年) 上月 翔太 (コウヅキ ショウタ) (著) ①愛媛大学教育・学生支援機構教育企画室講師 ②西洋古典文学、高等教育論 ③『カリキュラムの編成』(玉川大学出版部、二〇二二年、分担執筆)、『西洋古代の地震』(京都大学学術出版会、二〇二一年、共訳)など。 鈴村 裕輔 (スズムラ ユウスケ) (著) ①名城大学外国語学部准教授 ②比較思想・政治史・比較文化 ③『政治家石橋湛山』(中央公論新社、二〇二三年)、『清沢満之における宗教哲学と社会』(法政大学出版局、二〇二二年)、“JoJo’s Bizarre Adventure and the Myth of the ‘Gentleman’: Cues from the Series’ ‘Phantom Blood’ and‘Battle Tendency’”(『名城大学外国語学部紀要』第七号、二〇二四年) 庄子 大亮 (ショウジ ダイスケ) (著) ①関西大学等非常勤講師 ②西洋文化史(神話の意味・継承・影響) ③『アトランティス=ムーの系譜学︱〈失われた大陸〉が映す近代日本』(講談社、二〇二二年)、『世界の見方が変わるギリシア・ローマ神話』(河出書房新社、二〇二二年)、『大洪水が神話になるとき︱人類と洪水 五〇〇〇年の精神史』(河出書房新社、二〇一七年) 平藤 喜久子 (ヒラフジ キクコ) (著) ①國學院大學神道文化学部教授 ②神話学 ③平藤喜久子・港千尋共編著『〈聖なるもの〉を撮る』(山川出版社、二〇二三年)、平藤喜久子『神話の歩き方』(集英社、二〇二二年)、平藤喜久子・櫻井義秀共編著『現代社会を宗教文化で読み解く 比較と歴史からの接近』(ミネルヴァ書房、二〇二二年) 藤巻 和宏 (フジマキ カズヒロ) (著) ①近畿大学文芸学部教授 ②日本古典文学 ③『聖なる珠の物語―空海・聖地・如意宝珠―』(平凡社、二〇一七年)、『近代学問の起源と編成』(井田太郎との共編著、勉誠出版、二〇一四年) 河野 真太郎 (コウノ シンタロウ) (著) ①専修大学国際コミュニケーション学部教授 ②イギリス文学・文化、ジェンダーとカルチュラル・スタディーズ ③『正義はどこへ行くのか─映画・アニメで読み解く「ヒーロー」』(集英社新書、二〇二三年)、『はたらく物語─マンガ・アニメ・映画から「仕事」を考える8章』(笠間書院、二〇二三年)、『増補 戦う姫、働く少女』(ちくま文庫、二〇二三年)など。 ISBN:978-4-86766-066-9 Cコード:0070 A5判288ページ 発行: 文学通信 初版年月日: 2024年9月30日
-

「能力」の生きづらさをほぐす
¥1,980
【中古 カバー、帯にスレあり(画像参照)】 (参考:定価2,000円+税) ☆店長のひと言 「女子力、人間力、免疫力、長州力…、いろいろ言われても疲れちゃうよね。」 紹介 【発売たちまち重版!】 生きる力、リーダーシップ力、コミュ力… ◯◯力が、私たちを苦しめる。 組織の専門家が命をかけて探究した、他者と生きる知恵。 前職では「使えない」私が、現職では「優秀」に。 それって、本当に私の「能力」なの? 移ろいがちな他人の評価が、生きづらさを生み出す能力社会。 ガン闘病中の著者が、そのカラクリを教育社会学と組織開発の視点でときほぐし、 他者とより良く生きるあり方を模索する。 目次 はじめに プロローグ 母さん、僕は仕事のできない、能力のないやつですか? 第1話 能力の乱高下 第2話 能力の化けの皮剝がし―教育社会学ことはじめ 第3話 不穏な「求める能力」―尖るのを止めた大学 第4話 能力の泥沼―誰も知らない本当の私 第5話 求ム、能力屋さん―人材開発業界の価値 第6話 爆売れ・リーダーシップ―「能力」が売れるカラクリ① 第7話 止まらぬ進化と深化―「能力」が売れるカラクリ② 第8話 問題はあなたのメンタル―能力開発の行き着く先 第9話 葛藤をなくさない―母から子へ エピローグ 母さん、ふつうでない私は幸せになれますか? 伴走者からの言葉 磯野真穂 おわりに 著者プロフィール 勅使川原 真衣 (テシガワラ マイ) (著) てしがわら・まい:1982年横浜生まれ。東京大学大学院教育学研究科修士課程修了。BCG、ヘイ グループなど外資コンサルティングファーム勤務を経て独立。2017年に組織開発を専門とする、おのみず株式会社を設立し、企業はもちろん、病院、学校などの組織開発を支援する。二児の母。2020年から乳ガン闘病中。 磯野 真穂 (イソノ マホ) (執筆伴走) いその・まほ:人類学者。専門は文化人類学、医療人類学。2010年早稲田大学文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。早稲田大学文化構想学部助教、国際医療福祉大学大学院准教授を経て2020年より独立。 著書に『なぜふつうに食べられないのか-―拒食と過食の文化人類学』(春秋社)、『医療者が語る答えなき世界――「いのちの守り人」の人類学』(ちくま新書)、『ダイエット幻想――やせること、愛されること』(ちくまプリマ―新書)、『他者と生きる』(集英社新書)、共著に『急に具合が悪くなる』(晶文社)がある。本作では、著者の執筆に伴走し、言葉を寄せる。 訂正のお知らせ: 初版第1刷p105の5行目に訂正がございました。以下を修正いたします。 ×社会教育学者 → ○教育社会学者 ISBN:978-4-910534-02-2 Cコード:0095 四六判264ページ 発行: どく社 初版年月日: 2022年12月25日
-

目の見えない人は世界をどう見ているのか
¥550
【中古 状態きれい】 (参考:定価760円+税) ☆店長のひと言 「私がもし視覚を失ったら…、今のところ不安しかないのですが。さて。」 紹介 私たちは日々、五感―視覚・聴覚・嗅覚・触覚・味覚―からたくさんの情報を得て生きている。なかでも視覚は特権的な位置を占め、人間が外界から得る情報の八〜九割は視覚に由来すると言われている。では、私たちが最も頼っている視覚という感覚を取り除いてみると、身体は、そして世界の捉え方はどうなるのか??? 美学と現代アートを専門とする著者が、視覚障害者の空間認識、感覚の使い方、体の使い方、コミュニケーションの仕方、生きるための戦略としてのユーモアなどを分析。目の見えない人の「見方」に迫りながら、「見る」ことそのものを問い直す。 目次 【序 章】見えない世界を見る方法 【第1章】空 間 ― 見える人は二次元、見えない人は三次元? 【第2章】感 覚 ― 読む手、眺める耳 【第3章】運 動 ― 見えない人の体の使い方 【第4章】言 葉 ― 他人の目で見る 【第5章】ユーモア ― 生き抜くための武器 著者紹介 伊藤亜紗(いとうあさ) 1979年東京都生まれ。東京工業大学リベラルアーツセンター准教授。専門は美学、現代アート。もともと生物学者を目指していたが、大学三年次より文系に転向。2010年に東京大学大学院人文社会系研究科基礎文化研究専攻美学芸術学専門分野博士課程を単位取得のうえ退学。同年、博士号を取得(文学)。日本学術振興会特別研究員などを経て2013年より現職。研究のかたわら、アート作品の制作にもたずさわる。主な著作に『ヴァレリーの芸術哲学、あるいは身体の解剖』(水声社)、参加作品に小林耕平《タ?イ?ム?マ?シ?ン》(国立近代美術館)などがある。 ISBN 978-4-334-03854-0 新書判 発行 光文社 書店発売日 2015年4月16日

-

性愛論
¥550
【バーゲンブック※】 (参考:定価900円+税) ☆店長のひと言 「性愛?シャイなのでよくわかりません。」 内容紹介 ひとはなぜ、愛するのか。身体はなぜ、もうひとつの身体を求めるのか。猥褻論、性別論、性関係論からキリスト教圏の性愛倫理とその日本的展開まで。永遠の問いを原理的に考察。 (河出書房新社ホームページより引用) 著者プロフィール 橋爪 大三郎 (ハシヅメ ダイサブロウ) (著/文) 1948年、神奈川県生まれ。社会学者。『はじめての構造主義』、『世界がわかる宗教社会学入門』、『世界は宗教で動いてる』、『ふしぎなキリスト教』(共著)、『ゆかいな仏教』(共著)など著書多数。 ISBN:978-4-309-41565-9 Cコード:0136 文庫判264ページ 発行:河出書房新社 初版年月日: 2017年9月6日 ※バーゲンブック(自由価格本)とは、出版社の意思で定価販売ではなく、割引販売できる未使用の本・雑誌のことです。通常本と区別するため裏表紙にシールが貼ってあります。

-

近衛秀麿 亡命オーケストラの真実
¥1,900
SOLD OUT
【バーゲンブック※】 (参考:定価: 3,800円+税) ☆店長のひと言 「生き方はプログレですな。」 紹介 「ベルリンフィルをはじめて指揮した日本人」として近年再評価が高まる日本人指揮者であり、2018年に生誕120年を迎える近衛秀麿。第二次世界大戦の戦火の中で、これまで「空白の期間」として知られることのなかった決死の人道活動の軌跡を追ったドキュメンタリーであり、その知られざる活動の謎を、丹念な調査で明らかにした1冊。 目次 プロローグ 第1章 欧州での活躍 第2章 活動の軌跡を追って 第3章 ナチス占領下のポーランド公演 第4章 謎のオーケストラ「コンセール・コノエ」 第5章 亡命オーケストラとユダヤ人音楽家の国外脱出 第6章 「コンセール・コノエ」解散から終戦まで エピローグ 出生から終戦までの活動年表 欧州演奏批評 著者プロフィール 菅野 冬樹 (スガノ フユキ) (著/文) 1955年、東京都生まれ。日本大学芸術学部卒業。映像、音楽等の企画・制作を手がけるプロデューサー。1993年、全米映画製作者連盟のライセンスを日本人として初めて取得。マルチメディア事業の展開、コンテンツ制作など、数々の分野で活躍。1970年代後半に、作曲家・水谷川忠俊氏(近衛秀麿の三男)と知り合った後、30年以上の間、近衛秀麿についての調査・研究を海外も含め行っている。 ISBN:978-4-490-20976-1 Cコード:0073 A5判384ページ 発行:東京堂出版 書店発売日: 2017年12月8日 ※バーゲンブック(自由価格本)とは、出版社の意思で定価販売ではなく、割引販売できる未使用の本・雑誌のことです。通常本と区別するため裏表紙にシールが貼ってあります。

-

夜更かしの社会史
¥4,180
☆店長のひと言 「少々お高い本なのでよく眠れますよ!」 紹介 夜間も積極的に生産・消費をするようになり、不眠化した都市の活動。人びとはいかに夜を明かし、眠りについてどんな認識や習慣を生み出してきたか。夜の活用に対する志向や動き、安眠グッズ・睡眠学習器・眠気覚ましなどの商品の変遷を取り上げ、眠る/眠らないことの両方を同時に要請する産業社会の特性を追究。私たちの生活と睡眠の関係史に迫る。 目次 序章 安眠/不眠を欲望する社会…右田裕規 Ⅰ部 眠らない工場の出現―生産領域の不眠化 第一章 規範化する睡眠とロマン化する不眠―二〇世紀初頭における睡眠言説のマッピング―…近森高明 はじめに―「この俺の不眠」と「みんなの睡眠」 一 睡眠言説のマッピング―睡眠はいかに語られたか 二 規範化される睡眠―睡眠言説の構造分析 三 ロマン化される不眠―例外者の括り出し おわりに―現代に続く「よき睡眠」と「よき人生」のループ 第二章 「夜なべ」の近代史…右田裕規 はじめに 一 近世の夜業 二 村から都市への移行 三 照明技術の変化 四 夜業に対する社会的忌避の変化 おわりに 第三章 夜業と興奮剤の二〇世紀…―ヒロポンからコーヒーへ―…右田裕規 はじめに 一 近代興奮剤の略史 二 ヒロポンと「機械」 三 機械燃料のイメージ 四 ドリンク剤・コーヒーの「稀釈」 おわりに Ⅱ部 眠らない街の出現―消費領域の不眠化 第一章 夜の消費文化と商業照明…右田裕規 はじめに 一 一九世紀末の夜の東京 二 夜の消費文化の成長 三 商業照明のシンボル作用 四 戦時経済下の夜の東京 おわりに 第二章 盛り場と安眠妨害―夜間レジャー施設の営業音の問題化過程―…右田裕規 はじめに 一 カフェー征伐 二 都市住人の夜間騒音被害の実態 三 戦後の営業音規則 おわりに Ⅲ部 安眠を支えるモノたち―睡眠の商品化 第一章 寝床を電化する―「電気あんか」の技術社会史―…近森高明 はじめに―一枚の広告ポスターを読み解く 一 電気あんかの出現―大正・昭和初期 二 電気あんかの増殖―高度経済成長期 三 電気あんかの衰退―ポスト高度経済成長期 おわりに 第二章 時間の再魔術化と呪術的なモノの蘇り―「寝かしつけ」をめぐって―…竹内里欧 はじめに―「睡眠中学習」から「睡眠後学習」へ 一 「睡眠力」の時代 二 「寝かしつけ」にまつわる新聞記事の言説 三 「寝かしつけ」に役立つとうたうモノの氾濫 四 時間にかんするアンビバレントな願望と願望に応えるモノたち おわりに―時間をめぐる「力」の奪還 Ⅳ部 眠りの人工的制御という夢―睡眠の資源化 第一章 覚醒と睡眠のあいだを生きる―坂口安吾の覚醒剤と睡眠薬―…西村大志 はじめに 一 規律・勤勉・集中 二 覚醒剤と過覚醒 三 睡眠薬と人工睡眠 四 意志 おわりに 第二章 夢の勉強法としての睡眠学習…井上義和 はじめに―一九八二年の「明け方のつぶやき」 一 睡眠学習への欲望 二 第一号機〈SLミラクル〉の誕生 三 睡眠学習器の仕組みとモデルチェンジ 四 空想科学小説と録音再生技術 五 「悪夢の洗脳法」か「夢の勉強法」か おわりに 終章 眠りのコントロールからマネジメントへ―二〇〇〇年代以降の睡眠言説―…近森高明 一 睡眠をめぐる「問題―解決」の転換 二 「質」へのフォーカス―「最高の睡眠」へ 三 可視化・数値化―スリープテックの世界 四 ライフハック化―「超一流」の誘惑 五 脱規範化と超管理化のゆくえ あとがき 著者プロフィール 右田 裕規 (ミギタ ヒロキ) (編集) 1973年、島根県に生まれる。1998年、京都大学文学部卒業。2004年、京都大学大学院文学研究科博士後期課程研究指導認定退学。現在、山口大学時間学研究所准教授、博士(文学) ※2020年12月現在 【主要編著書】『天皇制と進化論』(青弓社、2009年)、「ラーメン史を「夜」から読む」(西村大志編『夜食の文化誌』青弓社、2010年)、「近代都市民衆の天皇実写映画の鑑賞体験」(『新しい歴史学のために』294、2019年) ISBN:978-4-642-03931-4 Cコード:3036 A5判266ページ 発行:吉川弘文館 初版年月日: 2024年2月10日
-

土偶を読む ー130年間解かれなかった縄文神話の謎ー
¥1,550
【中古 状態きれい 】 (参考:定価1,700円+税) ☆店長のひと言 「ど、土偶欲しい…!」 内容紹介 日本考古学史上最大の謎の一つがいま、解き明かされる。 土偶とは――「日本最古の神話」が刻み込まれた植物像であった! 「考古学×イコノロジー研究」から気鋭の研究者が 秘められた謎を読み解く、スリリングな最新研究書。 ・縄文時代に大量に作られた素焼きのフィギュア=「土偶」。 日本列島においては1万年以上前に出現し、2千年前に忽然とその姿を消した。 現代までに全国各地で2万点近くの土偶が発見されている。 ・一般的な土偶の正体として 「妊娠女性をかたどったもの」 「病気の身代わり」 「狩猟の成功を祈願する対象」 「宇宙人」…… などの説がこれまでに展開された。が、実はいずれも確証が得られていない。 ・本書では〈考古学の実証研究〉(データ)と 〈美術史学のイコノロジー研究〉(図像解釈学)によって ハート形土偶から縄文のビーナス、そして遮光器土偶まで 名だたる国内の「土偶の真実」を明らかにする。 そこには現代につながる縄文人たちの精神史が描かれていた。 日本、5000年の歴史。 現代人の心的ルーツを明らかにする人文書の新しい展開へ。 目次 はじめに 序章:人類学の冒険 第1章:土偶プロファイリング1 ハート形土偶 第2章:土偶プロファイリング2 合掌土偶 第3章:土偶プロファイリング3 椎塚土偶 第4章:土偶プロファイリング4 みみずく土偶 第5章:土偶プロファイリング5 星形土偶 第6章:土偶プロファイリング6 縄文のビーナス 第7章:土偶プロファイリング7 結髪土偶 第8章:土偶プロファイリング8 刺突文土偶 第9章:土偶プロファイリング9 遮光器土偶 第10章:土偶の解読を終えて おわりに 著者プロフィール 竹倉史人 (タケクラフミト) (著/文) 1976年東京生まれ。武蔵野美術大学映像学科中退を経て、東京大学教養学部文科III類に入学。 東京大学文学部宗教学・宗教史学科卒業後、フリーター、自営業、会社役員などを経験。 2019年東京工業大学大学院社会理工学研究科価値システム専攻博士課程満期退学。 専門は宗教人類学。著書に『輪廻転生―<私>をつなぐ生まれ変わりの物語』(講談社現代新書、2015) ISBN 978-4-7949-7261-3 四六判 338頁 発行 晶文社 発売日 2021年4月27日
-

土偶を読むを読む
¥2,200
☆店長のひと言 「土偶を読むを読むを読むを読むを読むを読むを読む、くらいまで行く頃には謎が解明されているでしょうか。」 紹介 「土偶の正体」は果たして本当に解き明かされたのか? 竹倉史人『土偶を読む』(晶文社)を大検証! 考古学の実証研究とイコノロジー研究を用いて、土偶は「植物」の姿をかたどった植物像という説を打ち出した本書は、NHKの朝の番組で大きく取り上げられ、養老孟司ほか、各界の著名人たちから絶賛の声が次々にあがり、ついに学術書を対象にした第43回サントリー学芸賞をも受賞。 「『専門家』という鎧をまとった人々のいうことは時にあてにならず、『これは〇〇学ではない』と批判する“研究者”ほど、その『○○学』さえ怪しいのが相場である。『専門知』への挑戦も、本書の問題提起の中核をなしている」(佐伯順子)と評された。 しかし、このような世間一般の評価と対照的に、『土偶を読む』は考古学界ではほとんど評価されていない。それは何故なのか。その理由と、『土偶を読む』で主張される「土偶の正体」、それに至る論証をていねいに検証する。 考古学の研究者たちは、今、何を研究し、何がわかって、何がわからないのか。専門家の役割とは一体なんなのか、専門知とはどこにあるのか。『土偶を読む』を検証・批判することで、さまざまな問題が見えてくる。本書は、縄文研究の現在位置を俯瞰し、土偶を読み、縄文時代を読む書でもある。 執筆は、望月昭秀、金子昭彦、小久保拓也、佐々木由香、菅豊、白鳥兄弟、松井実、山科哲、山田康弘、吉田泰幸(順不同)。 【『土偶を読む』の検証は、たとえれば雪かきに近い作業だ。本書を読み終える頃には少しだけその道が歩きやすくなっていることを願う。雪かきは重労働だ。しかし誰かがやらねばならない。(望月昭秀)…はじめにより】 目次 はじめに はたして本当に土偶の正体は解明されたのか? 検証 土偶を読む(望月昭秀) 1 カックウ(中空土偶)、合掌土偶――クリ 1‒1 カックウ(中空土偶) 全然そっくりじゃないカックウとクリ 恣意的な資料の選択の豊作 1‒2 合掌土偶 屈折像土偶あれこれ クリというメジャーフード 「イコノロジー×考古学」は正しいふれこみか? 2 ハート形土偶――オニグルミ 土偶の前後左右 クリやオニグルミの利用範囲と重なっていない土偶の方が圧倒的に少ない 3 山形土偶、ミミズク土偶、余山貝塚土偶――貝 3‒1 山形土偶 書を捨てよ、考古館へ行こう ハマグリと山形土偶の分布範囲 ハマグリとは関係のないところで山形土偶は出来上がる 3‒2 ミミズク土偶 山形土偶とミミズク土偶の中間は存在するが、ハマグリとイタボガキの中間は存在しない 髪型か貝殻か 食用利用されていないイタボガキ 貝の加工工場、中里貝塚 「世紀の発見」に成功した人類学者 3‒3 余山貝塚土偶 4 縄文のビーナス――トチノキ カモメラインという新たな分類 顔の造形について 顔よりも尻派 ほとんど重ならないトチノミ利用 5 結髪土偶、刺突文土偶――イネ、ヒエ 5‒1 結髪土偶 引用元に話を聞いてみる 結髪土偶はどうやって成立したか 5‒2 刺突文土偶 ヒエを栽培していた証拠もない 6 遮光器土偶――サトイモ 遮光器土偶の中心地点ではサトイモは 徐々に大きくなる遮光器土偶の目 縄文ルネサンス 自家中毒的な認知バイアス 7 土偶を読む図鑑 7‒1 縄文の女神 7‒2 仮面の女神 7‒3 始祖女神像(バンザイ土偶) 7‒4 三内丸山遺跡の大型板状土偶 7‒5 縄文くらら 検証まとめ 参考文献 「土偶とは何か?」の研究史(白鳥兄弟) 1 本稿の目的と内容 1‒1 土偶研究の「通説」 1‒2 本稿の内容 2‒1 第1期 明治期 ◎1868~1912年 2‒2 第2期 大正~昭和戦中期 ◎1912~1945年 2‒3 第3期 昭和戦後期 ◎1946~1988年 2‒4 第4期 平成期以降 ◎1989~2020年 3 まとめ 3‒1 各説の内容 3‒2 おわりに 参考文献 〈インタビュー〉今、縄文研究は?(山田康弘) 発想の面白さはある 批判で自由な議論はできなくなる? 民族誌と考古学との接続の問題 理化学で前進している考古学研究 人骨と土器でわかること 男性の世界観と女性の世界観 似ているということ つくりあげられた考古学者のイメージ 考古学の担い手たち 専門家の役割とは? 疲れてしまう取材 土偶研究の次のステップは 参考文献 物語の語り手を絶対に信用するな。だが私たちは信用してしまう(松井実) 参考文献 土偶は変化する。――合掌・「中空」土偶→遮光器土偶→結髪/刺突文土偶の型式編年(金子昭彦) はじめに 1 東北地方北部・縄文時代後期後半~晩期初めの土偶の変遷 2 遮光器土偶および関連土偶(東北北部・晩期前半土偶)の変遷 3 屈折像 B 類と結髪土偶の変遷 4 刺突文土偶の変遷 参考文献 植物と土偶を巡る考古対談(佐々木由香・小久保拓也・山科哲) 考古学会は閉鎖的で強権的? 日本考古学会は男性社会で、土偶は男性のおもちゃ? 土偶については誰も答えられない、何もわかっていない、そして土偶の専門家はいない? 専門知について 土偶を読むをどう読む? データの恣意性― クルミ、トチノキ、クリ、サトイモの痕跡をデータから考える イコノロジーという手法 型式学というものさし 考古学は学際的な研究から孤立しているのか 土偶って一体何? 土偶研究があり得るとすれば、その今後は? なぜ評価されたのか、その土壌を考える 参考文献 考古学・人類学の関係史と『土偶を読む』(吉田泰幸) 加速させる人類学、減速させる考古学 人類学者の説を吸収する考古学者たち 社会へも取り込まれる人類学者の縄文理解 二〇二〇年代の考古学の「叩かれ方」 たとえ「穴だらけ」でも 参考文献 実験:「ハート形土偶サトイモ説」(望月昭秀) ついに土偶の謎を解きました! ハート形土偶サトイモ説 雨乞いの儀式と土偶 『となりのトトロ』の雨乞いのシーン 実験(解読)を終えて 参考文献 知の「鑑定人」――専門知批判は専門知否定であってはならない(菅豊) はじめに 考古学者たちの冷たいあしらい 『土偶を読む』の評価にあらわれる専門知への疑念 専門家が言うことはあてにならない パブリック・アーケオロジーの知見 考古学者が『土偶を読む』に向き合わなかったいくつかの理由 知の「品質管理」 まとめ― 「ポスト真実時代」の専門知の役割 引用・参考文献 おわりに 感謝に次ぐ感謝 執筆者紹介 著者プロフィール 望月 昭秀 (モチヅキ アキヒデ) (編著) 『縄文ZINE』編集長。1972年、静岡県静岡市生まれ。ニルソンデザイン事務所代表。書籍の装丁や雑誌のデザインを主たる業務としながら、出来心で都会の縄文人のためのマガジン『縄文ZINE』を二〇一五年から発行し編集長をつとめる。著書に『縄文人に相談だ』(国書刊行会/文庫版は角川文庫)、『蓑虫放浪』(国書刊行会)、『縄文ZINE(土)』、『土から土器ができるまで/小さな土製品をつくる』(ニルソンデザイン事務所)など。現代の縄文ファン。 小久保拓也 (コクボ タクヤ) (著) 八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館学芸員。1976年、埼玉県生まれ。同館での展示・史跡整備・世界遺産を担当。主な論文として「縄文時代の漆」『JOMON』7特定非営利活動法人 国際縄文学協会(2018)、「青森県における縄文時代墓の諸様相」『列島における縄文時代墓制の諸様相』縄文時代文化研究会(2019)、「土偶(青森県風張1遺跡出土)」『國華』1496國華編輯委員会(2018)、「是川石器時代遺跡での保存・活用、地域との協働」『文化遺産の世界』40 NPO法人文化遺産の世界(2022)がある。 山田 康弘 (ヤマダ ヤスヒロ) (著) 1967年、東京都生まれ。国立歴史民俗博物館教授を経て、東京都立大学人文社会学部教授。専門は先史学。縄文時代の墓制を中心に当時の社会構造・精神文化について研究を行う一方で、考古学と人類学を融合した研究分野の開拓を進めている。著書に『縄文人も恋をする! ?』(ビジネス社、2022)、『縄文時代の歴史』(講談社、2019)、『縄文時代の不思議と謎』(実業之日本社、2019)がある。 佐々木 由香 (ササキ ユカ) (著) 金沢大学古代文明・文化資源学研究所考古科学部門特任准教授。明治大学黒耀石研究センター客員研究員。主な著者に「縄文人の植物利用―新しい研究法からみえてきたこと―」工藤雄一郎・国立歴史民俗博物館編『ここまでわかった!縄文人の植物利用』新泉社(2014)、「植物資源利用からみた縄文文化の多様性」『縄文文化と学際研究のいま』雄山閣(2020)がある。 山科 哲 (ヤマシナ アキラ) (著) 1973年、北海道生まれ。茅野市尖石縄文考古館勤務。同館の企画展『ちっちゃい土器の奥深い世界』(2017年)、『あさばち 縄文人のうつわの作り分け』(2018年)、『背中から見る土偶』(2021年)などを通じて、これまであまり取り上げられなかった角度から資料を紹介、来館された方々にちょっとした新たな発見をしてもらいたいと思っている。主な論文「霧ヶ峰黒曜石原産地における黒曜石採掘と流通」(『移動と流通の縄文社会史』、雄山閣)がある。 白鳥兄弟 (ハクチョウキョウダイ) (著) 1971年、フィリピン生まれ。横浜ユーラシア文化館主任学芸員、東京都公認ヘブンアーティスト。専門は骨角器、特に銛頭など狩猟漁撈具。博物館で考古学の学芸員として勤務するかたわら、土偶マイムのパフォーマンスを行っている。主な著書に、横浜市歴史博物館監修『おにぎりの文化史』(河出書房新社、2019)がある。 松井 実 (マツイ ミノル) (著/文) 1988年、岐阜県岐阜市生まれ。東京都立産業技術大学院大学助教。専門は工業設計と文化進化としているが難しいことはわからない。千葉大学特任研究員、富士通デザイン、フリーランスウェブデベロッパーを経て現職。博士(工学)。https://xerroxcopy.github.io 金子 昭彦 (カネコ アキヒコ) (著) 1964年、静岡県生まれ。(公財)岩手県文化振興事業団岩手県立博物館学芸第三課長。専門は縄文時代・土偶。主な著書に「遮光器土偶」『縄文時代の考古学11心と信仰』(同成社、二2007)、『遮光器土偶と縄文社会』(同成社、2001)、編著に『月刊考古学ジャーナル』No.745「特集今日の土偶研究」(ニューサイエンス社、2020)がある。 吉田 泰幸 (ヨシダ ヤスユキ) (著) 1975年、愛知県生まれ。盛岡大学文学部社会文化学科准教授。専門は縄文考古学、縄文と現代、考古学の民族誌。主な論文に“Archaeological Practice and Social Movements: Ethnography of Jomon Archaeology and the Public”(共著 Journal of the International Center for、Cultural Resource Studies, Kanazawa University, Vol.2, 2016)、“Approaches to Experimental Pit House Reconstructions in the Japanese Central Highlands: Architectural History, Community Archaeology and Ethnology”(共著 EXARC Journal, 2021/4, 2021)がある。 菅 豊 (スガ ユタカ) (著) 1963年、長崎県生まれ。東京大学東洋文化研究所教授。専門は民俗学。主な著書に『「新しい野の学問」の時代へ―知識生産と社会実践をつなぐために―』(岩波書店、2013)、『鷹将軍と鶴の味噌汁―江戸の鳥の美食学』(講談社、2021)、編著に『パブリック・ヒストリー入門―開かれた歴史学への挑戦―』(勉誠出版、2019、北條勝貴との共編著)がある。 関連リンク 『土偶を読むを読む』という書籍を出します。 - 縄文ZINE_note https://note.com/22jomon/n/na416aa91ba48 ISBN:978-4-86766-006-5 Cコード:0021 四六判432ページ 発行:文学通信 発売日: 2023年4月28日
-

闇の自己啓発
¥820
SOLD OUT
【中古 状態きれい】 (参考:定価1,900円+税) ☆店長のひと言 「闇と言われる世界のことをテレビや新聞で知る頃には、もうすっかり遅いんだろう。」 紹介 ダークウェブと中国、両極端な二つの社会が人間の作動原理を映し出し、AIや宇宙開発などの先端技術が〈外部〉への扉を開く。反出生主義を経由し、私たちはアンチソーシャルな「自己啓発」の地平に至る。話題騒然のnote連載読書会「闇の自己啓発会」を書籍化 著者プロフィール 江永泉 https://note.com/imuziagane/ 木澤 佐登志 (キザワ サトシ) (著/文) 1988年生まれ。文筆家。思想、ポップカルチャー、アングラカルチャーの諸相を領域横断的に分析、執筆する。 著書に『ダークウェブ・アンダーグラウンド――社会秩序を逸脱するネット暗部の住人たち』(イースト・プレス)、『ニック・ランドと新反動主義――現代世界を覆う〈ダーク〉な思想』(星海社新書)、共著に『闇の自己啓発』(早川書房)、『異常論文』(ハヤカワ文庫)がある。『SFマガジン』にて「さようなら、世界――〈外部〉への遁走論」を連載する。 ひでシス https://twitter.com/hidesys 役所暁 https://note.com/yakusho_akatsuki/
-

政治と宗教 統一教会問題と危機に直面する公共空間
¥800
【中古 状態きれい】 (参考:定価840円+税) ☆店長のひと言 「宗教も権力もいつのまにか距離感がバグってくる。」 紹介 元首相銃殺事件と「国葬」が呼び起こした「政治と宗教」の問題をめぐっての緊急出版。統一教会と政治家の協力関係の歴史、右派的主張をもつ宗教勢力の影響力増大、創価学会の変遷と自公連立政権の誕生、フランスのライシテとカルト規制、アメリカの政治と宗教右派など、公共空間が直面している現在の危機を多角的に考察する。 目次 序章 公共空間における宗教の位置………島薗 進 第1章 統一教会による被害とそれを産んだ要因………島薗 進 第2章 統一教会と政府・自民党の癒着………中野昌宏 第3章 自公連立政権と創価学会………中野 毅 第4章 フランスのライシテとセクト規制………伊達聖伸 第5章 アメリカ――政教分離国家と宗教的市民………佐藤清子 終章 統一教会問題と公共空間の危機………島薗 進 あとがき 著者プロフィール 島薗進 (シマゾノススム) 東京大学大学院人文科学研究科博士課程・単位取得退学。東京大学大学院人文社会系研究科・教授、上智大学グリーフケア研究所所長を経て、現在 大正大学客員教授、上智大学グリーフケア研究所客員所員。専門は宗教学、死生学、生命倫理。著書『国家神道と日本人』(岩波新書、2010年)『教養としての神道』(東京経済新報社、2022年)『宗教学の名著30』(ちくま新書、2008年)『明治大帝の誕生』(春秋社、2019年)『死生観を問う』(朝日新聞出版、2023年)など。 ISBN:978-4-00-431957-3 Cコード:0236 新書判242ページ 発行:岩波書店 初版年月日: 2023年1月20日
-

小田嶋隆の学歴論
¥1,300
【中古 状態きれい】 (参考:定価1,500円+税) ☆店長のひと言 「病歴なら負けないぞ。」 紹介 日本を支配する階級制度、学歴の謎を解く! 一流大学の学生にオンナがむらがるというのは本当か? 一代限りの身分であるはずの学歴がなぜ世襲されるのか? 学閥とは何か?(早稲田フリーメーソン・稲門会の暗躍と跳梁) 「東大なんかくだらない」と言えるのは東大生だけなのだろうか 2022年6月に他界した著者が、自ら代表作と明言していた小田嶋隆クラシックス3部作、第1弾 <解説> 内田樹 「脱力する知性-私の小田嶋隆論」 「小田嶋さんの思い出」 本橋信宏「早稲田を横に出て物書きになる」 目次 第1章 クラスは階級の卵である 第2章 一流大学の学生にオンナがむらがるというのは本当か? 第3章 最終学歴の違う者同士は、どうして打ち解けることができないのか? 第4章 「学歴にこだわらない」と言いながら受験に狂奔している人々の本音 コラム❶ シブマクのトゥーリオ 第5章 一代限りの身分であるはずの学歴がなぜ世襲されるのか? 第6章 学歴コンプレックスはいかにして相続されるのか 第7章 学閥とは何か?(早稲田フリーメーソン・稲門会の暗躍と跳梁) コラム❷ 寄付金350万円のトリック 第8章 学歴婚制度は隠微なアパルトヘイトなのか? 第9章 学歴無用論をあざ笑うカップリングパーティの条件 第10章 「東大なんかくだらない」と言えるのは東大生だけなのだろうか 第11章 中卒という見えない人々 第12章 田中角栄=低学歴なるがゆえに能力をひけらかさねばならなかった男の生涯 第13章 郷ひろみ=お受験用仮面夫婦を演じ通した元夫妻の幼稚舎物語 第14章 森喜朗=学力の欠如がむしろ﹁実力﹂の証明になる裏口入学の政治的背景 第15章 広末涼子と吉永小百合はどうしてこんなにも扱いが違うのだろうか コラム❸ ヒロスエの「大学生活」 第16章 菊川怜=学歴コンプレックスの解毒剤としての利用法 第17章 野村沙知代=サッチーを許せなかった本当の理由 第18章 わが学歴=ペーパーテスト巧者の社会的不適応傾向について 解説 内田樹「脱力する知性-私の小田嶋隆論」「小田嶋さんの思い出」 解説 本橋信宏「早稲田を横に出て物書きになる」 著者プロフィール 小田嶋隆 (オダジマタカシ) (著/文) 1956年東京赤羽生まれ。早稲田大学卒業。一年足らずの食品メーカー営業マンを経て、テクニカルライターの草分けとなる。国内では稀有となったコラムニストの一人。著書に『我が心はICにあらず』 (BNN、光文社文庫)、『仏の顔もサンドバッグ』 (宝島社)、『人はなぜ学歴にこだわるのか。』(メディアワークス、光文社文庫。解説・内田樹)、『地雷を踏む勇気』(技術評論社)、『小田嶋隆のコラム道』『上を向いてアルコール』 『小田嶋隆のコラムの切り口』(以上、ミシマ社)、『ポエムに万歳!』 (新潮社)、『友だちリクエストの返事が来ない午後』(太田出版)、『ア・ピース・オブ・警句』(日経BP)、『日本語を、取り戻す。』(亜紀書房)、10年分のTwitterを武田砂鉄が編纂、解説した『災間の唄』(サイゾー)、小説『東京四次元紀行』(イースト・プレス)など多数。2022年、65歳で逝去。 ISBN:978-4-7816-2146-3 Cコード:0095 四六判256ページ 発行:イースト・プレス 発売日: 2022年11月26日
-

小田嶋隆の友達論
¥1,300
【中古 状態きれい】 (参考:定価1,500円+税) ☆店長のひと言 「友を論じるな、感じろ!」 紹介 友だちがいるって本当はウソなんじゃないのか。 友だちの友だちは他人。 人と人とがいともたやすくつながってしまう、そんな世の中で、はたして友だちとは何だろう? 稀代のコラムニストが友だちについて考えに考えた! 真の友をもてないのはまったく惨めな孤独である。友人が無ければ世界は荒野に過ぎない。by フランシス・ベーコン 自分の住んでいる荒野をお花畑だと思い込むことができる人間だけが真の友を持つとができる。by 小田嶋隆 2022年6月に他界した著者が、自ら代表作と明言していた小田嶋隆クラシックス3部作、第2弾 <解説> 平川克美「小田嶋隆の常識」 武田砂鉄「チョロいヤツにはなるな」 【目次】 第1章 友だちリクエストの不可思議 第2章 幼年期の王国とギャング・エイジ 第3章 夢の中の自分としての友だち 第4章 ヤンキーとの遭遇と別離 第5章 女の友情のうらやましさ 第6章 ヤクザという生き方 第7章 友情と愚行 第8章 グラスの底に友情はあるのか 第9章 コストとベネフィットとセックスレスと退廃 第10章 異邦人であることの有利さについて 第11章 コミュ力という魔法の杖 第12章 真の仲間を持たない仲間たちの論争 第13章 出発できないジモティーのためのロードサイド 第14章 友だちが死ぬことについて 第15章 友情製造装置としての新入社員研修 第16章 友だちのいない子どもが勉強家になるメカニズムについて 第17章 人気者という専制君主 第18章 恋愛至上主義から友情原理主義への転換と装飾から草食への変化について 第19章 ミソまみれの日常 第20章 チームスピリットという監獄 第21章 一人ひとりが一人である素晴らしい家族の話 第22章 空気を読むな本を読め、ヨメの顔色読んだら負けぞ 第23章 敵を発明する能力 第24章 友だちはナマモノだよ 解説 平川克美「小田嶋隆の常識」 解説 武田砂鉄「チョロいヤツにはなるな」 目次 【目次】 第1章 友だちリクエストの不可思議 第2章 幼年期の王国とギャング・エイジ 第3章 夢の中の自分としての友だち 第4章 ヤンキーとの遭遇と別離 第5章 女の友情のうらやましさ 第6章 ヤクザという生き方 第7章 友情と愚行 第8章 グラスの底に友情はあるのか 第9章 コストとベネフィットとセックスレスと退廃 第10章 異邦人であることの有利さについて 第11章 コミュ力という魔法の杖 第12章 真の仲間を持たない仲間たちの論争 第13章 出発できないジモティーのためのロードサイド 第14章 友だちが死ぬことについて 第15章 友情製造装置としての新入社員研修 第16章 友だちのいない子どもが勉強家になるメカニズムについて 第17章 人気者という専制君主 第18章 恋愛至上主義から友情原理主義への転換と装飾から草食への変化について 第19章 ミソまみれの日常 第20章 チームスピリットという監獄 第21章 一人ひとりが一人である素晴らしい家族の話 第22章 空気を読むな本を読め、ヨメの顔色読んだら負けぞ 第23章 敵を発明する能力 第24章 友だちはナマモノだよ 解説 平川克美「小田嶋隆の常識」 解説 武田砂鉄「チョロいヤツにはなるな」 著者プロフィール 小田嶋隆 (オダジマタカシ) (著/文) 1956年東京赤羽生まれ。早稲田大学卒業。一年足らずの食品メーカー営業マンを経て、テクニカルライターの草分けとなる。国内では稀有となったコラムニストの一人。著書に『我が心はICにあらず』 (BNN、光文社文庫)、『仏の顔もサンドバッグ』 (宝島社)、『人はなぜ学歴にこだわるのか。』(メディアワークス、光文社文庫。解説・内田樹)、『地雷を踏む勇気』(技術評論社)、『小田嶋隆のコラム道』『上を向いてアルコール』 『小田嶋隆のコラムの切り口』(以上、ミシマ社)、『ポエムに万歳!』 (新潮社)、『友だちリクエストの返事が来ない午後』(太田出版)、『ア・ピース・オブ・警句』(日経BP)、『日本語を、取り戻す。』(亜紀書房)、10年分のTwitterを武田砂鉄が編纂、解説した『災間の唄』(サイゾー)、小説『東京四次元紀行』(イースト・プレス)など多数。2022年、65歳で逝去。 ISBN:978-4-7816-2147-0 Cコード:0095 四六判256ページ 発行:イースト・プレス 発売日: 2022年11月26日
-

死を生きた人びと 訪問診療医と355人の患者
¥880
SOLD OUT
【中古 状態きれい】 (参考:定価2,400円+税) ☆店長のひと言 「どう死にたいかハッキリしている人は、生きたい人だと思う。」 紹介 355人の看取りに関わった往診医が語るさまざまな死の記録。延命のみに長けた現代社会で、患者たちが望み、模索し続けた最期とは。 現代日本では、患者の望む最期を実現することは非常に難しい。多くの患者が、ひたすら延命しようとする医者や、目前の死期を認識しない親族と患者自身、病院外の死を「例外」とみなす社会によって、望まない最期に導かれていくためだ。しかし著者の患者たちは、著者と語り合ううちにそれぞれの望む死を見いだしていく。その結果、7割の患者が自宅での死を選んでいる。鮮烈なエピソードを通じ読者に「どう死にたいか」を問う一冊。 目次 はじめに 第1章 在宅医療の世界へ 第2章 在宅死のリアリティ――死者三五五名からのメッセージ 1 在宅医療と在宅死 2 在宅医療・在宅死の経済的側面 3 患者と家族にとっての在宅死 4 医師は在宅医療を知らない 5 介護関係者・行政・社会にとっての在宅死 6 常に慰める 第3章 在宅死のアポリア ――情報社会が提供するさまざまなニュースから 1 「老い」は戦うべき相手か 2 希望なき生――「先生、死ねる薬はないのですか」 3 看取るのは医師だけか 4 医者にかからないで死ぬということ 5 在宅死なき在宅医療――ビジネス化の行き着くところ 6 在宅死は理想的な死か 7 最期を選べない患者たち 8 未来におけるアポリア 1 医師は足りるか / 2 訪問看護師は足りるか 3 介護職員は足りるか / 4 介護施設は足りるか 5 病床数は足りるか / 6 二〇二五年問題への対応策 第4章 見果てぬ夢 1 世界の悲惨/日本の悲惨 2 オーダーメイド医療/オートメーション医療 3 ある老医師の手紙 あとがき 著者プロフィール 小堀鷗一郎 (コボリオウイチロウ) (著/文) 1938年、東京生まれ。東京大学医学部医学科卒業。医学博士。東京大学医学部付属病院第一外科、国立国際医療研究センターに外科医として約40年間勤務。定年退職後、埼玉県新座市の堀ノ内病院に赴任、在宅診療に携わり、355人の看取りにかかわる。うち271人が在宅看取り。現在 訪問診療医。母は小堀杏奴。祖父は森鴎外。 ISBN:978-4-622-08690-1 Cコード:0036 四六判216ページ 発行:みすず書房 発売日: 2018年5月2日
-

インド独立の志士「朝子」
¥1,710
【中古 状態きれい】 (参考:定価2,300円+税) ☆店長のひと言 「ガンジーしか知らなくてすみません。」 紹介 日本で生まれ育ったインド人女性の数奇な運命 アシャ(日本名「朝子」)という女性のことを知る者はそう多くないだろう。アシャは1928年、神戸を拠点にインド独立運動を展開していた父サハーイと母サティの間に長女として生まれた。サハーイは、日本におけるインド独立運動のなかでは「中村屋のボース」ことR・B・ボースに次ぐ存在で、「自由インド仮政府」の閣僚を務めた人物でもある。 神戸の小学校を卒業後、昭和高女(昭和女子大学の前身)在学中に来日したチャンドラ・ボースに感化されてインド独立運動に身を捧げることを誓ったアシャは、インド国民軍(INA)に入隊することを決意。1945年5月、バンコクにあったINA婦人部隊に配属されるも、日本の敗戦により活動は終了してしまう。その翌年、シンガポールで父と合流したのち、アシャは生まれて初めて祖国インドの地を踏んだ――。 本書は、本人と関係者へのインタビューのほか、未公開の日記や回顧録など貴重な資料を駆使し、一独立運動家の目で見た戦前・戦後の日印関係を再構成。日本で生まれ育ち、若くしてインド独立運動に身を投じたアシャとその家族の数奇な運命を通して、気鋭の研究者が日印関係史に新たな視角をもたらした傑作である。 目次 プロローグ――出征 第一章 父と母の物語――インド独立運動家の両親のもとに生まれて 第二章 上京――昭和高女への進学 第三章 転機――チャンドラ・ボース登場 第四章 南へ――女学生「朝子」から兵士「アシャ」へ 第五章 入隊――インド国民軍婦人部隊とアシャ 第六章 絶望と混乱――インド国民軍の終焉 第七章 祖国の地――インド独立とビハール州での新生活 エピローグ――「アシャ」と「朝子」のあいだで あとがき/注/参考文献/人名索引/事項索引 著者プロフィール 笠井 亮平 (カサイ リョウヘイ) (著/文) 1976年、愛知県生まれ。青山学院大学大学院国際政治経済学研究科にて修士号取得後、在中国、在インド、在パキスタンの日本大使館で外務省専門調査員を歴任。現在は岐阜女子大学南アジア研究センター特別研究員として南アジア・中国情勢に関する研究を行っているほか、早稲田大学大学院(2015年~)および日本経済大学(2014年~)で非常勤講師を務めている。共著に『軍事大国化するインド』(亜紀書房)、『インド民主主義の発展と現実』(勁草書房)、『台頭するインド・中国』(千倉書房)など。翻訳者としても活動しており、訳書に『ネオ・チャイナ』(白水社)がある。 ISBN:978-4-560-08495-3 Cコード:0022 四六判270ページ 発行:白水社 発売日: 2016年3月26日