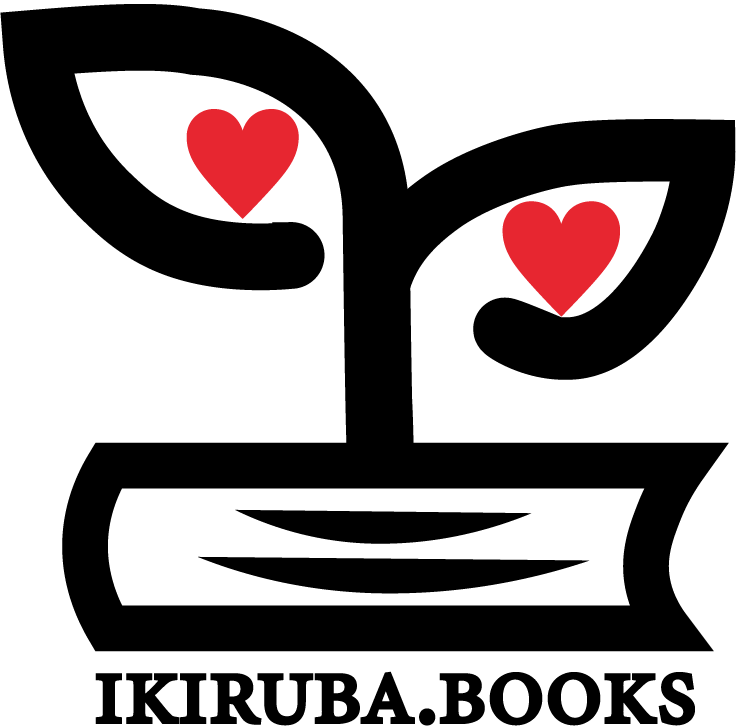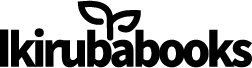-

ビッグイシュー519号
¥500
☆店長のひと言 「AI時代に必要なもの、それは健康です。」 【内容紹介】 特集 直観する脳 AIと人間 チャットGPTやGeminiなど、生成AIは急速に人々の生活に根づき始めました。悩み相談の相手もすれば、数時間・数日・数年かかった計算や検索作業がものの数分で完結する場合もあります。その利便性は第4次産業革命とも呼ばれる一方、ニュースに関する6割近くの回答は正確性に問題があるなど、数々の弊害も生まれています。 そんなAI の時代だからこそ「私たち一人ひとりの人間がどのように脳を使っていくか、という問いかけが必要だ」と脳神経外科医・研究者の岩立康男さん(東千葉メディカルセンター・センター長)は語ります。そもそもAIに何を聞くか?何をさせるか?は、私たち人間の判断力やひらめきにかかっているからです。 岩立さんは、AIを使いこなすためにもひらめきや判断力をもたらす「直観」が何より大事だと言います。そして、人間が持つ最大の強みは「忘れること」だとも。 岩立さんに、私たち人間の「直観する脳」「忘れる脳力」について聞きました。 TOP INTERVIEW スペシャルインタビュー ハリス・ディキンソン 現在29歳、いま最も注目を集める若手俳優の一人、英国出身のハリス・ディキンソン。2028年に公開予定の伝記映画『THE BEATLES ‒ A Four-Film Cinematic Event(仮題)』ではジョン・レノンを演じることでも話題を呼んでいます。 そんなディキンソンがこの数年にわたって取り組んできたホームレス支援の活動、初の監督作品について語りました。 リレーインタビュー・私の分岐点留学プランナー、元タレント 石井あみさん 子育てフレンドリーなフィリピンに移住 細かいことにもイライラしない生活 国際記事 英国。探検家ドウェイン・フィールズ、チーフスカウトに 自然ドキュメンタリー番組で人気の探検家、ドウェイン・フィールズ。過酷な自然環境を旅して回る彼が、2024年9月、英国スカウト協会からチーフスカウトに任命されました。野外活動にかかわりながら青少年の健全なエンパワメントに尽力する、彼の活躍を追いました。 (地球市民)セピデ・ファルシさん。ガザに住む24歳女性ファトマとのビデオ通話を映画に 10代の時にフランスに出国した、イラン出身のセピデ・ファルシ監督。イスラエルの攻撃が続くガザで暮らす24歳のフォトジャーナリスト、ファトマ・ハッスーナとのビデオ通話を記録し、ドキュメンタリー映画『手に魂を込め、歩いてみれば』を制作しました。ファトマが遺したもの、そして映画に込めた思いとは。 WORLD STREET NEWS 世界短信 連載記事 浜矩子の新ストリート・エコノミクス 川柳が暴く、今日的「互恵」 コミック マムアンちゃん ウィスット・ポンニミット ホームレス人生相談 母の電話に心穏やかでいられません 宇宙・地球・人間 池内了の市民科学メガネ 詐欺の手口いろいろ 読者のページ My Opinion 販売者に会いにゆく 『ファクトゥム』ヤスミン・カールソン 色とりどり 希望をつむぐ本屋さん 100の本棚のある店内 棚移動や本の補充で、つねに変わる景色 (エッセイ)カヨが与えてくれたもの 内澤旬子さん 東京から小豆島へ移住してすぐにヤギを迎えることになった内澤旬子さん(文筆家・イラストレーター)によるイラストとエッセイ。ヤギのカヨとの出合いや創意工夫をしながらヤギたちの世話をする日々を描きます。さらに、ヤギを飼ったことで思わぬ大きな恩恵があったと語ります。 表現する人/葛本康彰さん 偶然の自然現象を反映してつくる FROM EDITORIAL 編集後記 (ビッグイシュー日本HPより抜粋)

-

ビッグイシュー518号
¥500
☆店長のひと言 「鳥には鳥以外の声は何に聞こえてるんですかね?雑音?」 【内容紹介】 特集 シジュウカラは言葉を話す 鈴木俊貴さん(動物言語学者/東京大学准教授)は街の中を歩いていて、鳥の声が聞こえてくると言葉として理解できるといいます。まるでドリトル先生のようではないですか。そんな稀有な能力を、大学3年生の冬から長野県の軽井沢にある「野鳥の森」で研究を始め、これまで20年にもおよぶ研究生活によって手に入れました。 特に、シジュウカラを対象に、森の中に巣箱をかけて鳥たちの繁殖や子育ての様子を観察し、多様な実験を繰り返した結果、仲間を集める鳴き声、ヘビやハシブトガラス、猛禽類などに対し、警戒を促す鳴き声を特定。ヒナたちも親鳥の鳴き声を聞き分けるなど、シジュウカラにも言葉があることを証明しました。さらに、2つの言葉を組み合わせて文をつくること、文法があることなど、感動的な事実を明らかにしてきました。 今や国際的に認められ、国内外で大きな反響を呼ぶ鈴木さんの研究と、新たに創設した学問「動物言語学」について聞きました。 TOP INTERVIEW スペシャルインタビュー 森洋子 緻密な鉛筆画で、子どもたちが想像と現実を行き来する世界を描いた絵本『かえりみち』『おるすばん』などで知られる森洋子さん。そんな森さんの新作『ある星の汽車』は、ある星の生き物の未来を問いかける、美しく胸を打つ絵本。昨年10月に発売、すでに4刷を重ねるほど注目を集めています。 森さんに作家としての道のりと、『ある星の汽車』の誕生などについて聞きました リレーインタビュー・私の分岐点「ALOHA7」代表。元アナウンサー 大木優紀さん 唯一の趣味だった「旅行」を仕事に。家族でハワイに移住した今が分岐点 国際記事 イタリア。シチリアの「アンドロメダ劇場」 イタリア西南部の地中海に浮かぶシチリア島。ロレンツォ・レイナは牧羊を本業としながら独学で建築を学び、約40年かけて野外の劇場やオブジェを創り上げました。天文学にインスピレーションを得たその独特な創造性は、どこから生まれ、どのように実現したのでしょうか?そんな彼が、できあがるまでの軌跡や想いを語ります。 WORLD STREET NEWS 世界短信 連載記事 原発ウォッチ! 「原発停止で国富流出」は“印象論” 浜矩子の新ストリート・エコノミクス 岩と硬い平面の挟間で 雨宮処凛の活動日誌 「この国で未来を描く」ことが「違法」とされる子どもたち ホームレス人生相談 体力維持のために心がけていることは? ジェンダー平等を目指す地方議会議員候補者を支援 ――わたしたちのバトン基金 女性議員比率が先進国でいまだ最低水準の日本。地方議会議員に立候補を考える人たちの壁になっているのが、選挙に出るための「金銭面での不安」です。そうした経済的なリスクをサポートする「わたしたちのバトン基金」が設立されました。代表の能條桃子さんに話を聞きました。 読者のページ My Opinion 販売者に会いにゆく カナダ『リティネレール』ラボワ 夜パン模様 「捨てない」を目指す思いをともに 監督インタビュー 『愛がきこえる』沙漠 監督 FROM EDITORIAL 編集後記 (ビッグイシュー日本HPより抜粋)
-

ビッグイシュー517号
¥500
☆店長のひと言 「目的地までの予定は立てるけど、途中で忘れるタイプです。」 【内容紹介】 特集 道草、寄り道、回り道 あなたは目的地に決まったルートで向かわれますか?それとも、時々は道順を変えたり、時には途中で道草したり、寄り道することに、心惹かれるほうですか?さらには回り道をして、結局は目的地にたどり着けなかったりすることも? また、一つの目的を叶えるための行動でも、道草や寄り道、回り道をしてしまったりすることがあるでしょうか?その結果、困ったことになったとしても、一方で思わぬ出来事に遭遇したり、予期しなかった出会いがあったり、見知らぬ世界を訪れることになったり。これまで、まっすぐに進まなかったことで失ったこと、得たことなどの悲喜こもごもについて、下記10人のみなさんからエッセイが届きました。 木下龍也さん(歌人)、岡崎武志さん(書評家)、小池伸介さん(ツキノワグマ研究者)、大塚敦子さん(ジャーナリスト)、川崎哲さん(社会活動家)、若菜晃子さん(編集者)、香山リカさん(精神科医)、伊藤比呂美さん(詩人)、津村記久子さん(作家)、星野智幸さん(作家) TOP INTERVIEW スペシャルインタビュー バーニー・サンダース 「国民皆保険」や「大学授業料の無償化」政策を掲げ、先日ニューヨーク市長に当選したゾーラン・マムダニ氏にも大きな影響を与えるなど、若い世代を含めて圧倒的な人気を誇る米国の政治家バーニー・サンダース。 圧倒的な格差社会で“民主社会主義者”を名乗り続ける、彼の哲学とは? リレーインタビュー・私の分岐点フローリスト 前田有紀さん 庭仕事の後、鏡に映った「私らしさ」 ”自分軸”で生きようと心に決めた 国際記事 米国ワシントンDC.野宿地追われるホームレス 今年8月11日、ドナルド・トランプ米大統領は“治安改善”を盾に、ワシントンDCの首都警察(MPD)を一時的に連邦政府の指揮下に置き、同市内への州兵派遣を決定。この動きは、同市の自治を揺るがしただけでなく、最も弱い立場にあるホームレス生活者やその支援者らに大きな衝撃を与えました。ワシントンDCを拠点とする『ストリート・センス』誌の記者が総出で現場を取材し、その実態をレポートします。 WORLD STREET NEWS 世界短信 連載記事 浜矩子の新ストリート・エコノミクス EBPM主義への強い疑念 コミック マムアンちゃん ウィスット・ポンニミット ホームレス人生相談 聴覚障害があり、声かけに悩んでいます 自立応援の家「まちごろりん」東京里山開拓団 本誌310号での取材から7年。NPO法人東京里山開拓団は、東京・八王子にある荒れた山林を児童養護施設の子どもたちと一緒に伐り拓く活動だけでなく、その取り組みをさらに広げています。街なかの空き家を改修して児童養護施設の退所者に無償で貸し出す事業「まちごろりん」の4軒目の改修現場を訪れ、話を聞きました。 宇宙・地球・人間 池内了の市民科学メガネ 「顔面偏差値」って何? AI診断の新商売 読者のページ My Opinion 販売者に会いにゆく 『アプロポ』ゲオルゲ・クラチウン 色とりどり 希望をつむぐ本屋さん 交流生む「ブックフェア」 映画エッセイ/2025年、ミニシアターと映画 毎年恒例、その年の映画とミニシアターを振り返る、シアターキノ代表・中島洋さんのエッセイ。中島さんが最も新作を期待しているという監督たちの作品や、誠実な眼差しが共感の輪を広げ異例の大ヒットとなった『どうすればよかったか?』をはじめとしたドキュメンタリー作品、新しい時代になりつつあるという女性監督が大活躍する国内外の作品について語ります。 ふくしまから もし、米国の原発安全規則「B.5.b」の対策を行っていれば 福島第一原発の事故を防げた可能性 FROM EDITORIAL 編集後記 (ビッグイシュー日本HPより抜粋)
-

ビッグイシュー504号
¥500
☆店長のひと言 「食べ物で人を元気にできる人は、ほぼ神様。」 【内容紹介】 特集 喜びと誇り、枝元なほみを偲ぶ 今年2月27日にご逝去された、料理研究家の枝元なほみさん。 ビッグイシューの誌面ではもちろん、認定 NPO 法人ビッグイシュー基金の共同代表、また、日本の食や農業を考えリードする人として社会的にも活躍されました。 雑誌では創刊1年後、12号特集(2004.9.1)での初インタビューをきっかけに、17号(2004.11.15)から120回連載の「枝元なほみのスローシンプルフード」が始まり、販売者とのコラボ連載「世界一あたたかい人生レシピ」も250回を超え(単行本2冊発行)、さらにコロナの禍中には「大人食堂」「夜のパン屋さん」を立ち上げ、全力を注ぎました。 そんな枝元さんの軌跡の一端として、連載「スローシンプルフード」から9編のエッセイほかを再掲。枝元さんとともに活動された仲間「チームむかご」「日本の種子(たね)を守る会」「夜のパン屋さん」のみなさんへのインタビュー、そして枝元さんの親友である詩人の伊藤比呂美さんにご寄稿いただきました。 TOP INTERVIEW スペシャルインタビュー デミ・ムーア 90年代、『ゴースト/ニューヨークの幻』などで、ヒット作を牽引する存在となった、俳優のデミ・ムーア。キャリアの中盤は不振に見舞われ、アイダホ州で静かな生活を送った後、2019年に赤裸々な回顧録『インサイド・アウト』でカムバックしました。62歳となった今、身体的な恐怖体験を描き、新時代の映画として話題を集めるボディ・ホラー『サブスタンス』に出演。ルッキズムや男性支配社会などをテーマにした本作への思いを語ります。 リレーインタビュー・私の分岐点書評家、ライター 杉江松恋さん 会社員の傍ら、ミステリー書評を書いた 誰も気づいていない分野を開拓したい 国際記事 英国 木工技術ワークショップで困窮者の仕事作り 産業革命発祥の地であり、かつて毛織物や鉄鋼業で栄えたイングランド北部の街。 しかし時代の移り変わりとともに産業は衰退し、失業率が高止まりして生活困窮者が増える一方、家賃高騰で荒廃した空き家が目立ちます。そこで自立支援団体「ハンドクラフテッド」は、社会的に孤立した人々を対象に、木工技術習得のためのワークショップを開いています。 連載記事 原発ウォッチ 4 月28 日、イベリア半島で停電 浜矩子の新ストリート・エコノミクス コンクラーベの授けもの 雨宮処凛の活動日誌 必見!! 映画『選挙と鬱』水道橋博士の立候補から辞任まで 読者のページ My Opinion 販売者に会いにゆく カナダ『メガフォン』リチャード・ヤング 監督インタビュー 『デリカド』カール・マルクーナス監督 販売者主宰「歩こう会」150 回記念 ゴトゴト走る路面電車に乗って FROM EDITORIAL 編集後記 (ビッグイシュー日本HPより抜粋)
-

医師が本当に伝えたい 12歳までの育児の真実 親子の身体と心を守るエビデンス
¥1,980
☆店長のひと言 「親でも子でもなく、“親子”の身体と心を守るというのがポイント。過去の私と母にエビデンスあげたい。」 紹介 ★睡眠トレーニング(ネントレ)は赤ちゃんの脳に有害? ★子どものワクチンについて知っておくべきことは? ★母親が仕事をすることが子どもに与える影響は? ★親の性格が子どもに与える影響とは? 子育てに関する根拠のない神話には、はっきりNOを。 答えのない問いには、考え方や行動のヒントを。母親についての疫学研究を行い、子どもの医療や社会問題に関するSNSでの発信が子育て層に圧倒的支持を集める小児科医・新生児科医の今西洋介氏(ふらいと先生)が、12歳までのお子さんの育児に役立つ「エビデンスにもとづく子育ての最新知識」を、1冊の本にまとめました。 赤ちゃんの睡眠トレーニングから子どもの食事指導、ワクチン、保育園vs幼稚園問題、そして子どもへの性被害を防ぐ方法まで。注目のメールマガジン「ふらいと先生のニュースレター」で紹介されたトピックの中から、特に反響の大きかったテーマを厳選し、新たな書下ろしも加えて再構成。 海外の研究論文や専門情報に裏付けられた最先端の子どもの医学情報を温かなメッセージとともにわかりやすく届ける本書は、日々子育てに奮闘するお父さん、お母さんにとって大きな力となるはずです。 目次 第1章 0歳~5歳までに知っておきたい真実 ― 未就学児のエビデンス ● 母親の仕事が子どもに与える影響―3歳児神話を科学的に検証する ● なぜ子どもの睡眠に気を配るべきか―子どもの睡眠① ● 「子どもが寝ない」に親ができる対策―子どもの睡眠② など 第2章 6歳~12歳までに知っておきたい真実 ― 学童期のエビデンス ●わが子を「いじめっ子」にしないために親にできること ● 「男の子は父親から学び、女の子は母親から学ぶ」説は本当か ● 親は子どもにどこまで厳しくするべきか など 第3章 妊娠期~ 出産までに知っておきたい真実 ― プレママ・プレパパのためのエビデンス ● 「母性愛神話」を科学的に検証する ● 無痛分娩って本当のところどうなの?―研究からわかること ● 胎教は行うべき? その効果は? など 著者プロフィール 今西洋介 (イマニシヨウスケ) (著) 小児科医・新生児科医。日本小児科学会専門医/日本周産期・新生児医学会新生児専門医。医学博士(公衆衛生学)。一般社団法人チャイルドリテラシー協会代表理事。小児公衆衛生学者。富山大学医学部卒業後、都市部や地方のNICU(新生児集中治療室)で新生児医療に従事。主な著書に『新生児科医・小児科医ふらいと先生の子育て「これってほんと?」答えます』(西東社、監修)、『小児科医「ふらいと先生」が教える みんなで守る子ども性被害』(集英社インターナショナル)ほか多数。 ISBN:978-4-296-00243-6 Cコード:0077 四六判272ページ 発行: 日経BP 発売日: 2025年4月25日

-

別れを告げない
¥2,750
☆店長のひと言 「最近思うんですよ、苦労は本当に人を成長させるのだろうか、と…。」 紹介 作家のキョンハは、虐殺に関する小説を執筆中に、何かを暗示するような悪夢を見るようになる。ドキュメンタリー映画作家だった友人のインソンに相談し、短編映画の制作を約束した。 済州島出身のインソンは10代の頃、毎晩悪夢にうなされる母の姿に憎しみを募らせたが、済州島4・3事件を生き延びた事実を母から聞き、憎しみは消えていった。後にインソンは島を出て働くが、認知症が進む母の介護のため島に戻り、看病の末に看取った。キョンハと映画制作の約束をしたのは葬儀の時だ。それから4年が過ぎても制作は進まず、私生活では家族や職を失い、遺書も書いていたキョンハのもとへ、インソンから「すぐ来て」とメールが届く。病院で激痛に耐えて治療を受けていたインソンはキョンハに、済州島の家に行って鳥を助けてと頼む。大雪の中、辿りついた家に幻のように現れたインソン。キョンハは彼女が4年間ここで何をしていたかを知る。インソンの母が命ある限り追い求めた真実への情熱も…… いま生きる力を取り戻そうとする女性同士が、歴史に埋もれた人々の激烈な記憶と痛みを受け止め、未来へつなぐ再生の物語。フランスのメディシス賞、エミール・ギメ アジア文学賞受賞作。 著者プロフィール ハン・ガン (ハン ガン) (著/文) Han Kang 한강 1970年、韓国・光州生まれ。延世大学国文学科卒業。2005年、三つの中篇小説をまとめた『菜食主義者』で韓国最高峰の文学賞である李箱文学賞を受賞、同作で16年にアジア人初の国際ブッカー賞を受賞。17年、『少年が来る』でイタリアのマラパルテ賞を受賞、23年、『別れを告げない』(本書)でフランスのメディシス賞(外国小説部門)を韓国人として初めて受賞し、24年にフランスのエミール・ギメ・アジア文学賞を受賞した。本書は世界22か国で翻訳刊行が決定している。他の邦訳作品に、『ギリシャ語の時間』『すべての、白いものたちの』『回復する人間』『そっと 静かに』『引き出しに夕方をしまっておいた』がある。 斎藤 真理子 (サイトウ マリコ) (翻訳) 翻訳家。パク・ミンギュ『カステラ』(共訳)で第一回日本翻訳大賞、チョ・ナムジュ他『ヒョンナムオッパへ』で〈韓国文学翻訳院〉翻訳大賞受賞。訳書は他に、ハン・ガン『回復する人間』『すべての白いものたちの』『ギリシャ語の時間』『引き出しに夕方をしまっておいた』(共訳)、パク・ソルメ『もう死んでいる十二人の女たちと』『未来散歩練習』、ペ・スア『遠きにありて、ウルは遅れるだろう』、パク・ミンギュ『ピンポン』、チョ・セヒ『こびとが打ち上げた小さなボール』、ファン・ジョンウン『誰でもない』『年年歳歳』『ディディの傘』、チョン・イヒョン『優しい暴力の時代』、チョン・ミョングァン『鯨』、チョン・セラン『フィフティ・ピープル』『保健室のアン・ウニョン先生』『声をあげます』『シソンから、』、チョ・ナムジュ『82年生まれ、キム・ジヨン』『サハマンション』、李箱『翼 李箱作品集』など。著書『韓国文学の中心にあるもの』、『本の栞にぶら下がる』、『曇る眼鏡を拭きながら』(共著) ISBN:978-4-560-09091-6 Cコード:0097 四六判304ページ 発行: 白水社 書店発売日: 2024年4月2日

-

ブッチャー・ボーイ
¥1,410
【中古 状態きれい】 (参考:定価2,800円+税) ☆店長のひと言 「親を選べないという当然の事実が最も残酷でもあり。」 紹介 フランシー少年の語りに翻弄されながら、 この悲喜劇を原書で読み終えたときの衝撃は忘れられない。 しかしいま、あらためて翻訳で読み、その恐ろしいほどの現実感に体が震えた。 アイルランドから世界に打ち込まれたこの楔はさらに鋭く深く胸に刺さる。 ーー金原瑞人(翻訳家・法政大学教授) 今まで読んだ本で泣いたのは、新美南吉『ごんぎつね』、 筒井康隆『農協月へ行く』、菅原孝標女『更級日記』、そしてこの『ブッチャー・ボーイ』。 『ごん…』は清さに、『農協…』は哀れさに、『更級日記』は切なさに。 『ブッチャー・ボーイ』この少年の物語は、痛さに泣く。殴られるように泣いた。 1ページ目からラストまで、一字一句すべて読む者を離さない迫力のドライブ感。 ーー姫野カオルコ(小説家) 〈いまから二十年か三十年か四十年くらいまえ、ぼくがまだほんの子供だったときのこと、小さな田舎町に住んでいたぼくはミセス・ニュージェントにやったことが原因で町のやつらに追われていた〉ーーアイルランドの田舎町、飲んだくれの父と精神不安定な母のもとで、フランシー・ブレイディーは親友のジョーと共に愉快な日々を送っていた。そう、ミセス・ニュージェントから「あんたらはブタよ!」という言葉を浴びるまでは……あらゆる不幸に見舞われた少年が、狂気と妄想と絶望の果てに見い出したものとは何か? アイルランド版〈ライ麦畑でつかまえて〉+〈時計じかけのオレンジ〉とも称された、鬼才パトリック・マッケイブが鮮烈で瑞々しい筆致で描く問題作にして感動作、映画化もされた傑作長篇(1992年作)がついに邦訳。 解説=栩木伸明 著者プロフィール 矢口誠 (ヤグチマコト) (翻訳) 1962年生まれ。慶應義塾大学国文科卒。翻訳家。主な訳書にファウアー『数学的にありえない』(文藝春秋)、バリンジャー『煙で描いた肖像画』(創元推理文庫)、ウェストレイク『アルカード城の殺人』(扶桑社ミステリー)、『レイ・ハリーハウゼン大全』(河出書房新社)、バーンスタイン『メイキング・オブ・マッドマックス 怒りのデス・ロード』(玄光社)、デイヴィス『虚構の男』(国書刊行会)などがある。 ISBN:978-4-336-07296-2 Cコード:0097 四六変型判352ページ 発行: 国書刊行会 初版年月日: 2022年1月17日
-

ビッグイシュー497号
¥500
☆店長のひと言 「対話で回復するならば、言葉で病むこともあるわけで。」 【内容紹介】 特集 対話から回復へ オープンダイアローグの10年 統合失調症や双極症、うつ病、ひきこもり、認知症、発達障害……。こうした生きづらさに苦しむ人たちが、薬物も入院も最低限に、もしくは必要とすらせず、ただ“対話”だけで回復する「オープンダイアローグ(OD)」が少しずつ広がりをみせています。 ODは元々、1980年代からフィンランドで実践が続けられてきた精神科医療の新しいアプローチです。対話を繰り返すことで症状が回復するケースが明らかになり、世界的な注目を集めています。 しかし、なぜ対話だけで回復が起こるのか?日本での普及に取り組んできたOD第一人者の斎藤環さん(精神科医)は、ODの根底には「人間の尊厳、自由や権利を尊重していくことで結果的に回復が起こる」という思想があると語ります。 日本での普及が本格化して今年で10年。茨城県で「つくばダイアローグハウス」を開業したばかりの斎藤さんを訪ね、「ODとは何か。10年にわたる取り組みとこれから」についてお聞きしました。 TOP INTERVIEW スペシャルインタビュー モニカ・バルバロ ボブ・ディランの若き日を描いた伝記映画『名もなき者/ A COMPLETE UNKNOWN』で、公民権運動や反戦活動家としても知られるシンガーソングライターのジョーン・バエズを 演じたモニカ・バルバロ。俳優としてのキャリアを振り返るとともに、女性に対する蔑視・差別の問題を語ります。 リレーインタビュー・私の分岐点アーティスト 新城大地郎さん 離れてみて感じた “ 宮古島 ” の魅力。書と自分が一体化した時、生まれる1枚 国際記事 カナダ、世代間で連鎖する“同化政策のトラウマ” 憲法で先住民族の権利を保障し、過去の同化政策についても公式に謝罪したカナダ。しかし現実には、先住民族が置かれた状況は依然として厳しく、改善に向かっているとは言い難いです。社会問題から子どもを守ろうと取り組む児童福祉サービスの陰で引き裂かれる親子の実態について、当事者と里親の証言を伝えます。 WORLD STREET NEWS 世界短信 滝田明日香のケニア便り 1.5トンの雄キリン、6人がかりで地面に倒して治療 連載記事 浜矩子の新ストリート・エコノミクス ジジ抜きとジジ入り コミック マムアンちゃん ウィスット・ポンニミット ホームレス人生相談 × 枝元なほみの悩みに効く料理 古い服を捨てられません ☆ 好き勝手チョコ ☆ 連載250回記念、枝元さんインタビュー 食べたいという気持ちは生きる根っこ 宇宙・地球・人間 池内了の市民科学メガネ カルシウムを吸収し定着させる「骨活」のすすめ 読者のページ My Opinion 販売者に会いにゆく 『アプロポ』イフェアニ・マドゥアコ トミヤマユキコの「マンガを通して社会問題を考える」3 自分向けでない世界で、どっこい生きてる人 トミヤマユキコさんの「マンガを通して社会問題を考える」エッセイ第3弾。トミヤマさんは、「この世界が『ふつうの人』を基準にデザインされていて、そうじゃない人たちがありのままでいられるようにはできていない」と語ります。 そんな自分向けにデザインされていない世界の中にあっても、どっこい生きている人がたくさん出てきて、さまざまなヒントを与えてくれる、トミヤマさんが最近注目する、マンガ5作品を紹介します。 監督インタビュー 『犬と戦争 ウクライナで私が見たこと』山田あかね監督 FROM EDITORIAL 編集後記 (ビッグイシュー日本HPより抜粋)
-

ビッグイシュー491号
¥450
☆店長のひと言 「大人になるって、アンパンマンや恐竜を突然卒業することなのでしょうか。」 【内容紹介】 特集 恐竜関心大国 日本と恐竜 世界中の子どもたちに人気がある恐竜。加えて日本は大人も恐竜好きが多い恐竜関心大国です。いま、鳥類は恐竜の子孫であるなど、大人たちが知っていた恐竜についての常識は大きく変わりました。 かつて、アジアとつながる大陸の縁の海岸線の一部だった日本。その大地を闊歩していた恐竜たち。恐竜研究のパイオニアである真鍋真さん(古生物学者・国立科学博物館副館長)は「1980年代以降、日本各地から恐竜の化石が出始め、日本での恐竜についての研究は加速度的に進んでいる」と言います。そして、日本の地層の重要性と、それを世界に向けて発信することをいつも意識してきました。 現在、学名が認められている恐竜は1 1 0 0 種程度。三畳紀から白亜紀の1億6000万年ぐらいの期間に恐竜が繫栄していたことを考えると、おそらく何十万種といたはず。今知られている恐竜は氷山の一角と語る真鍋さんに、「恐竜関心大国・日本、日本の恐竜、恐竜研究の歴史と最前線、恐竜から学ぶこと」などについて聞きました。 TOP INTERVIEW スペシャルインタビュー ニック・ケイヴ オーストラリア出身、世界中のファンから絶大な支持を得る、シンガーソングライターのニック・ケイヴ。新作アルバム『WILD GOD』を発表し、愛する家族を喪った悲しみと、AI、リアルな音楽への思いを語ります。 リレーインタビュー・私の分岐点モデル Amoさん いじめで不登校に。ブログで仲間と出会う かわいいのアイコンであり続けたい 国際記事 EU・チュニジアの国策に翻弄される移民・難民 2023年、サハラ以南のアフリカ諸国からチュニジアを経由して地中海を越え、ヨーロッパをめざす移民・難民が急増しました。EUは人々の流入を食い止めるため、チュニジアへ10億ユーロ(約1560億円)を援助。その結果、同国内で今なお何万人もの移民・難民が襲撃や強制送還の危険にさらされています。写真家のヨハン・パーションが、各国からチュニジアに逃れてきた人々の惨状を伝えます。 WORLD STREET NEWS 世界短信 国内記事 大阪・梅田、都会の中に生きる木々に出合う 三浦豊さん 森の案内人・三浦豊さんとの森歩きも7回目(前回は472号)。今回はこれまでと少し趣を変え、ビルが立ち並ぶ大阪・梅田エリアを一緒に歩きました。自然の芽吹きと人の手による植栽、そのどちらの魅力にも触れられるまち歩きのハイライトを紹介します。 連載記事 浜矩子の新ストリート・エコノミクス Back in the USSR? コミック マムアンちゃん ウィスット・ポンニミット ホームレス人生相談 × 枝元なほみの悩みに効く料理 毎日のニュースに疲れてしまいます ☆ 鮭ときのこの炊き込みご飯 ☆ 長さ80m「52 間の縁側」に、誰でもどうぞ! 石井英寿さん宇宙・地球・人間 池内了の市民科学メガネ 芭蕉は越後で天の川を見たのか? 読者のページ My Opinion 販売者に会いにゆく セルビア『リツェウリツェ』ラジッチ 地球温暖化と海面上昇、太平洋の島々から 清水靖子さん FROM EDITORIAL 編集後記 (ビッグイシュー日本HPより抜粋)
-

52ヘルツのクジラたち
¥680
【中古 カバーに傷みあり(画像参照)】 (参考:定価: 740円+税) ☆店長のひと言 「かわいそうで終わると、あとは何も聞こえませんよ。」 紹介 2021年本屋大賞第1位。待望の文庫化。 52ヘルツのクジラとは、他のクジラが聞き取れない高い周波数で鳴く世界で一匹だけのクジラ。何も届かない、何も届けられない。そのためこの世で一番孤独だと言われている。 自分の人生を家族に搾取されてきた女性・貴瑚と、母に虐待され「ムシ」と呼ばれる少年。孤独ゆえ愛を欲し、裏切られてきた彼らが出会い、新たな魂の物語が生まれる――。 〈解説〉内田剛 著者プロフィール 町田そのこ (マチダソノコ) (著/文) 一九八〇年生まれ。福岡県在住。 「カメルーンの青い魚」で、第15回「女による女のためのR-18文学賞」大賞を受賞。二〇一七年に同作を含む『夜空に泳ぐチョコレートグラミー』でデビュー。他の著作に「コンビニ兄弟―テンダネス門司港こがね村店―」シリーズ(新潮社)、『うつくしが丘の不幸の家』(東京創元社)などがある。本作で二〇二一年本屋大賞を受賞。 近著に『星を掬う』(中央公論新社)、『宙ごはん』 (小学館)、『あなたはここにいなくとも』(新潮社)。 ISBN:978-4-12-207370-8 Cコード:1193 文庫判312ページ 発行:中央公論新社 書店発売日: 2023年5月25日
-

子どもたちの階級闘争
¥1,980
【中古 状態きれい】 (参考:定価: 2,400円+税) ☆店長のひと言 「無償化で解決する問題なんてむしろ問題ではないわけでして。」 紹介 「わたしの政治への関心は、ぜんぶ託児所からはじまった。」英国の地べたを肌感覚で知り、貧困問題や欧州の政治情勢へのユニークな鑑識眼をもつ書き手として注目を集めた著者が、保育の現場から格差と分断の情景をミクロスコピックに描き出す。 2008年に著者が保育士として飛び込んだのは、英国で「平均収入、失業率、疾病率が全国最悪の水準」と言われる地区にある無料の託児所。「底辺託児所」とあだ名されたそこは、貧しいけれど混沌としたエネルギーに溢れ、社会のアナキーな底力を体現していた。この託児所に集まる子どもたちや大人たちの生が輝く瞬間、そして彼らの生活が陰鬱に軋む瞬間を、著者の目は鋭敏に捉える。ときにそれをカラリとしたユーモアで包み、ときに深く問いかける筆に心を揺さぶられる。 著者が二度目に同じ託児所に勤めた2015-2016年のスケッチは、経済主義一色の政策が子どもの暮らしを侵蝕している光景であり、グローバルに進む「上と下」「自己と他者」の分断の様相の顕微描写である。移民問題をはじめ、英国とEU圏が抱える重層的な課題が背景に浮かぶ。 地べたのポリティクスとは生きることであり、暮らすことだ──在英20年余の保育士ライターが放つ、渾身の一冊。 目次 はじめに──保育士とポリティクス I 緊縮託児所時代 2015-2016 リッチとプアの分離保育 パラレルワールド・ブルース コラム 子どもたちを取り巻く世界 1 貧困ポルノ オリバー・ツイストと市松人形 緊縮に唾をかけろ 貧者分断のエレジー コラム 子どもたちを取り巻く世界 2 RISE──出世・アンガー・蜂起 リトル・モンスターと地上の星々 ふぞろいのカボチャたち クールでドープな社会変革 ギャングスタラップ児とムスリム・プリンセス 天使を憐れむ歌 コスプレと戦争と平和 託児所から見たブレグジット コラム 子どもたちを取り巻く世界 3 フットボールとソリダリティ ターキッシュ・ホリデイ(トルコの休日) フードバンクの勃興とわれわれの衰退 ザ・フィナーレ 笑い勝つその日のために 中書き II 底辺託児所時代 2008-2010 あのブランコを押すのはあなた フューリーより赤く その先にあるもの。 ゴム手袋のヨハネ 小説家と底辺託児所 神の御使い 母獣。そして消えて行く子供たち 故国への提言──UK里親制度って、結構ボロックスだよ。 白髪のアリス 炊事場のスーザン・ボイル ロザリオ たどり着いたらいつもどしゃ降り 愛のモチーフ マイ・リトル・レイシスト ブライトン・ロック──ミテキシーとベッキーと、時々、ミッキー もう一人のデビー 人種と平等のもやもや──インクルージョン ある追悼 おわりに──地べたとポリティクス 初出一覧 著者プロフィール ブレイディみかこ (ブレイディミカコ) (著/文) 保育士・ライター・コラムニスト。著書に、『花の命はノー・フューチャー』(2005年、碧天舎。ちくま文庫より2017年改題復刊予定)、『アナキズム・イン・ザ・UK──壊れた英国とパンク保育士奮闘記』(2013年)、『ザ・レフト──UK左翼セレブ列伝』(2014年)(以上、Pヴァイン)、『ヨーロッパ・コーリング──地べたからのポリティカル・レポート』(2016年、岩波書店)、『THIS IS JAPAN──英国保育士が見た日本』(2016年、太田出版)、『いまモリッシーを聴くということ』(2017年4月刊予定、Pヴァイン)、『子どもたちの階級闘争――ブロークン・ブリテンの無料託児所から』(2017年4月、みすず書房)。雑誌『図書』に「女たちのテロル」を連載中。1996年から英国・ブライトン在住。 ISBN:978-4-622-08603-1 Cコード:0036 四六判296ページ 発行:みすず書房 書店発売日: 2017年4月19日

-

かがみの孤城
¥900
【中古 状態きれい】 (参考:定価1,800円+税) ☆店長のひと言 「感動ではイジメはなくならない。でも優しい人は増えるかもしれない。」 紹介 あなたを、助けたい。 学校での居場所をなくし、閉じこもっていたこころの目の前で、ある日突然部屋の鏡が光り始めた。輝く鏡をくぐり抜けた先にあったのは、城のような不思議な建物。そこにはちょうどこころと似た境遇の7人が集められていた―― なぜこの7人が、なぜこの場所に。すべてが明らかになるとき、驚きとともに大きな感動に包まれる。 生きづらさを感じているすべての人に贈る物語。一気読み必至の著者最高傑作。 著者プロフィール 辻村 深月 (ツジムラ ミヅキ) (著/文) 1980年2月29日生まれ。山梨県出身。千葉大学教育学部卒業。2004年に『冷たい校舎の時は止まる』で第31回メフィスト賞を受賞しデビュー。他の著作に『子どもたちは夜と遊ぶ』『凍りのくじら』『ぼくのメジャースプーン』『スロウハイツの神様』『名前探しの放課後』『ゼロ、ハチ、ゼロ、ナナ。』『島はぼくらと』『家族シアター』(以上、講談社)、『クローバーナイト』(光文社)、『青空と逃げる』(中央公論新社)など。最新刊は『小説 映画ドラえもん のび太の月面探査記』(小学館)、『傲慢と善良』(朝日新聞出版)。『ツナグ』(新潮社)で第32回吉川英治文学新人賞、『鍵のない夢を見る』(文藝春秋)で第147回直木三十五賞を受賞、『かがみの孤城』(ポプラ社)で第15回本屋大賞第1位となる。新作の度に期待を大きく上回る作品を刊行し続け、幅広い読者からの熱い支持を得ている。 ISBN:978-4-591-15332-1 Cコード:0093 四六判558ページ 発行:ポプラ社 発売日: 2017年5月9日
-

障害があり女性であること : 生活史からみる生きづらさ
¥2,750
☆店長のひと言 「“弱者”のステレオタイプ化や専門と言う名の縦割りから脱するには。」 紹介 障害のある女性48名の生活史から、「障害があり女性である人たち」を生きづらくさせている社会構造や差別について、深く考察した一冊。障害者について論じられるときには、性差別のせいで女性の声がかき消され、女性について論じられるときには障害者差別のせいで障害女性の声はかき消されるという状況がある。しかし、障害のある女性が受ける差別の実態を明らかにする試みはいまだ途上にあり、複雑に絡み合う問題を把握するためのデータは圧倒的に不足している。本書は、この不足を埋めることを試みるものである。 目次 第Ⅰ部 障害とジェンダーをめぐる困難 第Ⅱ部 ライフコースと性役割 第Ⅲ部 これまでとこれから 課題・論点 著者プロフィール 土屋 葉 (ツチヤヨウ) (著/文 | 編集) 1973年生まれ。専攻は家族社会学。お茶の水女子大学大学院人間文化研究科修了。博士(社会科学)。現在、愛知大学文学部教授。著書『障害者家族を生きる』(勁草書房)、共著『被災経験の聴きとりから考える――東日本大震災後の日常生活と公的支援』(生活書院)。障害学研究会中部部会の一員として編んだものに、『愛知の障害者運動――実践者たちが語る』(現代書館)がある。 ISBN:978-4-7684-3598-4 Cコード:0036 四六判320ページ 発行:現代書館 書店発売日: 2023年10月4日

-

もうやってらんない
¥480
【中古 状態きれい】 (参考:定価2,500円+税) ☆店長のひと言 「“あのとき、実は傷ついたのよね。”とあとで言われたときの気持ちを思い出しました。」 紹介 ある日、アフリカ系アメリカ人のベビーシッター、エミラは、誘拐犯に間違えられてしまう。黒人差別だと怒る白人の雇い主アリックスは、抗議するようエミラを焚きつけるが、そのいっぽうで名誉黒人気取りの恋人がアリックスの元カレだと知ったエミラは――。 著者プロフィール カイリー・リード(Kiley Reid) 1987年、ロサンゼルス生まれ。アリゾナ大学とメアリーマウント・マンハッタン・カレッジで学ぶ。トルーマン・カポーティ財団のフェローシップを受けながら、数多くのピュリッツァー賞受賞者を輩出してきたアイオワ・ライターズ・ワークショップを修了した。2019年刊行の本書『もうやってらんない』は、デビュー作にしてブッカー賞にノミネートされ、全米での書籍の売れ行きに最も影響力があるとされる女優リース・ウィザースプーンのブッククラブの選定図書になった。現在ペンシルヴェニア州フィラデルフィア在住。 (Hayakawa Books & Magazinesより引用) ISBN:978-4-15-210098-6 Cコード:0097 四六判448ページ 発行:早川書房 発売日: 2022年4月5日
-

病と障害と、傍らにあった本。
¥2,200
☆店長のひと言 「本のいいところは、自分のペースで向き合えるところ。」 紹介 病名や障害の名前ではひとくくりにできない、その実情。それゆえにその只中にいる人は、心身のつらさのみならず、誰とも分かち合えない想いに孤独に陥りがちになる。そんな時、外の世界と自分の内とを繋ぐ「窓」となる本は、あったのか。12人12様の病や障害の体験と本との関わりについて綴る本書は、固有な体験としての病や障害の実情と、生きることの「意志」の現れでもある「読む」ことの力を伝える一冊です。 目次 【本を知る】 齋藤陽道 母の絵日記 頭木弘樹 本嫌いが病気をして本好きになるまで 岩崎航 病をふくめた姿で 【本が導く】 三角みづ紀 物語に導かれて 田代一倫 写真と生活 和島香太郎 てんかんと、ありきたりな日常 【本が読めない】 坂口恭平 ごめん、ベケット 鈴木大介 本が読めない。 【本と病と暮らしと】 與那覇潤 リワークと私―ブックトークがあった日々 森まゆみ 体の中で内戦が起こった。―原田病と足るを知る暮らし― 【本と、傍らに】 丸山正樹 常にそこにあるもの 川口有美子 それは、ただ生きて在ること 前書きなど 病名や障害の名でひと括りにできない 固有の症状や想い。 誰かと分かち合うこともできなくて、ひとり。 そんなとき、傍らには どんな本があったのか。 版元から一言 病や障害といった、重いテーマを扱いながら、本書に収録したエッセイにはどれも不思議と、一筋の光が指しているように思える。それは「読む」という行為に生きるという意志が含まれているからなのか。読後感は希望を見出す一冊です。 著者プロフィール 齋藤 陽道 (サイトウ ハルミチ) (著/文) 一九八三年東京都生まれ。写真家。生まれつき聞こえに障害がある感音性難聴と診断を受ける。中学生まで「聴文化」で育ったのち、都立石神井ろう学校入学を機に「日本手話」と出会う。またその頃から写真を始める。二〇一〇年に写真新世紀優秀賞受賞。二〇一一年、写真集『感動』、二〇一九年『感動、』(いずれも赤々舎)刊行。二〇一三年、ワタリウム美術館にて個展「宝物」開催。私生活では同じく感音性難聴である写真家、盛山麻奈美と結婚。二人の間に生まれた子供は二人とも聴者だった。二〇二〇年、息子へ歌う子守唄をきっかけに「うた」を探る日々を追ったドキュメンタリー映画『うたのはじまり』(河合宏樹監督)が公開。エッセイ集に二〇一八年刊行『声めぐり』(晶文社)、『異なり記念日』(医学書院)他多数。 頭木 弘樹 (カシラギ ヒロキ) (著/文) 文学紹介者。大学三年の二十歳のときに潰瘍性大腸炎を患い、十三年間の闘病生活を送る。そのときにカフカの言葉が救いとなった経験から二〇一一年、『絶望名人カフカの人生論』(飛鳥新社、のちに新潮文庫)、二〇一六年『絶望読書―苦悩の時期、私を救った本』(飛鳥新社、のちに河出文庫)、二〇一九年などの著書を刊行。また、ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』をミステリーとして再構成した『ミステリー・カット版 カラマーゾフの兄弟』(春秋社)、落語にも造詣が深く、『落語を聴いてみたけど面白くなかった人へ』(ちくま文庫)他著書多数。同年、潰瘍性大腸炎の闘病の日々を詳細に綴った『食べること出すこと』(医学書院)を刊行。NHK「ラジオ深夜便」の『絶望名言』コーナーに出演中。 岩崎 航 (イワサキ ワタル) (著/文) 一九七六年宮城県生まれ。詩人。本名は、岩崎稔。三歳の頃に筋ジストロフィーを発症。十七歳の頃、未来に絶望し死を考えたが、「病をふくめたありのままの姿」で自分の人生を生きようと思いを定める。現在は胃ろうからの経管栄養と人工呼吸器を使い、在宅医療や介護のサポートを得て自宅で暮らす。二十五歳から詩作、二〇〇四年から五行歌を詠む。二〇一三年、詩集『点滴ポール 生き抜くという旗印』(写真・齋藤陽道、ナナロク社)が大きな話題を呼ぶ。二〇一五年、エッセイ集『日付の大きいカレンダー』、二〇一八年、兄の岩崎健一が絵を、航が詩を綴った共著の画詩集『いのちの花、希望のうた』(以上、いずれもナナロク社)刊行。二〇二〇年、第二詩集『震えたのは』刊行予定。 三角 みづ紀 (ミスミ ミヅキ) (著/文) 一九八一年鹿児島県生まれ。東京造形大学に進学。一年生の冬に膠原病の全身性エリテマトーデスとの診断を受ける。その頃から詩の投稿をはじめ、二〇〇四年、第四十二回現代詩手帖賞受賞。同年、第一詩集『オウバアキル』にて第十回中原中也賞受賞。第二詩集『カナシヤル』で南日本文学賞と歴程新鋭賞を受賞。二〇一四年、第五詩集『隣人のいない部屋』で第二十二回萩原朔太郎賞を史上最年少で受賞。書評やエッセイの執筆も多く、二〇一七年、エッセイ集『とりとめなく庭が』(ナナロク社)刊行。ワークショップや詩のコピーライティングなど活動は多岐に渡り、中でも朗読活動を精力的に行う。スロヴェニア、リトアニア、イタリア、ベルギーなど多くの国際詩祭に招聘される。二〇二〇年、詩集『どこにでもあるケーキ』(ナナロク社)刊行。 田代 一倫 (タシロ カズトモ) (著/文) 一九八〇年福岡県生まれ。写真家。二〇〇〇年、大学在学中にうつ病と診断を受ける。九州産業大学大学院在学中の二〇〇六年、福岡市でアジア フォトグラファーズ ギャラリーの設立、運営に参加。同年、三木淳賞奨励賞受賞。韓国、九州で肖像写真を中心に撮影、発表。二〇一〇年に東京、新宿の photographers ‘galleryに拠点を移す。二〇一三年、東日本大震災の被災地の人々を撮影した『はまゆりの頃に 三陸、福島 2011~2013年』(里山社)刊行。同年さがみはら写真新人奨励賞を受賞。二〇一四年より東京の人々の撮影を開始、東京都写真美術館他で発表。二〇一七年に韓国・鬱陵島の人々を撮影した『ウルルンド』(KULA)刊行。二〇一七年秋より双極性障害を発症。二〇二〇年九月に新潟、砂丘館にて個展開催。 和島 香太郎 (ワジマ コウタロウ) (著/文) 一九八三年山形県生まれ。中学三年生の時に、てんかんと診断される。映像の世界を志して進学した京都造形芸術大学で、ドキュメンタリー映画監督、佐藤真に師事。二〇〇八年、文化庁若手映画作家育成プロジェクトに選出され、『第三の肌』を監督。二〇一二年、監督作品『小さなユリと 第一章・夕方の三十分』が、SKIPシティ国際Dシネマ映画祭短編部門にて奨励賞受賞。二〇一七年より、これまで知られることの少なかったてんかん患者の日々を素朴に語り合うポッドキャストラジオ「ぽつラジオ」を開始。二〇一九年、坪田義史監督のドキュメンタリー映画『だってしょうがないじゃない』で編集を担当。 坂口 恭平 (サカグチ キョウヘイ) (著/文) 一九七八年熊本県生まれ。二〇〇四年、路上生活者の住居を撮影した写真集『0円ハウス』(リトルモア)刊行。以降、ルポルタージュ、小説、思想書、画集、料理書など多岐にわたるジャンルの書籍、音楽、絵などを発表している。二〇一一年五月、福島第一原発事故後の政府の対応に疑問を抱き、自ら新政府初代内閣総理大臣を名乗り、新政府を樹立。希死念慮に苦しむ人々との対話を「いのっちの電話」として、自らの携帯電話(〇九〇-八一〇六-四六六六)の番号を公開。近年は投薬なしの生活を送るようになり、二〇二〇年、その経験と「いのっちの電話」をもとに行ったワークショップを誌上で再現した『自分の薬をつくる』(晶文社)、また「いのっちの電話」を十年続けてわかったことを記した『苦しい時は電話して』(講談社新書)を刊行。また、自らの「薬」として描いた風景画集『Pastel』(左右社)刊行。 鈴木 大介 (スズキ ダイスケ) (著/文) 一九七三年千葉県生まれ。文筆業。貧困からセックスワークに就く女性や子ども、詐欺集団など、社会の斥力の外にある人々をおもな取材対象とするルポライターとして執筆活動を行い、主な著書に『最貧困女子』(幻冬舎新書)など。しかし二〇一五年、四十一歳の時に突然、脳梗塞を発症。身体の麻痺は軽度だったが、その後遺症として記憶障害、認知障害などの高次機能障害が残る。その体験を綴ることを自らのリハビリとし、二〇一六年『脳が壊れた』、二〇一八年『脳は回復する 高次脳機能障害からの脱出』(いずれも新潮新書)を刊行。また、二〇一八年、高次機能障害と発達障害などの類次点を探った『されど愛しきお妻様 -「大人の発達障害」の妻と「脳が壊れた」僕の18年間』(講談社)、二〇二〇年『「脳コワさん」支援ガイド』(医学書院)、『不自由な脳』(金剛出版)など。小説に『里奈の物語』(文藝春秋)がある。 與那覇 潤 (ヨナハ ジュン) (著/文) 一九七九年神奈川県生まれ。歴史学者。地方公立大学に勤務していた二〇一四年に双極性障害を発症し、休職を経て離職。二〇一八年、自身の体験を踏まえた『知性は死なない』(文藝春秋)、二〇二〇年、『心を病んだらいけないの?』(斎藤環と共著、新潮選書)などの著作で、精神病理を切り口に現代社会の諸問題を考察している。本書では挙げきれなかったリハビリ中に影響された書物についても、後者のブックガイドで紹介した。その他、二〇〇九年、博士論文をまとめた『翻訳の政治学』(岩波書店)、二〇一一年、大学在職時の講義録をまとめた『中国化する日本』(文藝春秋、後に文庫化)、二〇一三年、『日本人はなぜ存在するか』(集英社、後に文庫化)などを刊行、著書その他多数。 森 まゆみ (モリ マユミ) (著/文) 一九五四年東京都生まれ。作家。一九八四年、季刊の地域雑誌「谷中・根津・千駄木」を創刊し、地元の人々の聞き書きをベースにした雑誌づくりで地域コミュニティの活性化に貢献。一九九二年、サントリー地域文化賞受賞。一九九八年『鷗外の坂』(新潮社)で芸術選奨文部大臣新人賞、二〇一四年『『青踏』の冒険:女が集まって雑誌をつくるということ』(平凡社)で紫式部文学賞受賞。他著書多数。二〇〇七年、自己免疫疾患である原田病に罹患。二〇一〇年、病後の日々を綴った『明るい原田病日記―私の体の中で内戦が起こった』(亜紀書房)を刊行。みずからの病の体験と東日本大震災を経て、「足る事を知る」ことの重要性を今一度再確認すべく、二〇一七年、縮小社会研究会の松久寛氏との共著『楽しい縮小社会』(筑摩書房)を刊行。近著に『本とあるく旅』(産業編集センター)など。 丸山 正樹 (マルヤマ マサキ) (著/文) 一九六一年東京都生まれ。シナリオライターとして活動。頸椎損傷という重い障害を持つ妻と生活をともにするうち、さまざまな障害を持つ人たちと交流するようになる。次第に、何らかの障害を持った人の物語を書くことを模索するようになり、二〇一一年、ろう者の両親のもと育った聴者の主人公が手話通訳士となって事件解決に一役買うミステリー小説『デフ・ヴォイス』(文藝春秋)でデビュー。同作が『デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳士』として文庫化(文春文庫)されたのに続き、『龍の耳を君に』(創元推理文庫)、『慟哭は聴こえない』(東京創元社)として人気シリーズとなり、二〇二〇年、スピンオフとして『刑事何森 孤高の相貌』(東京創元社)も刊行。他、居所不明児童をテーマにした『漂う子』(文春文庫)など。 川口 有美子 (カワグチ ユミコ) (著/文) 一九六二年東京都生まれ。都立西高卒(三三期生)。夫の海外赴任のためロンドンで暮らしていた最中の一九九五年、母がALSに罹患。その介護体験を記した『逝かない身体――ALS的日常を生きる』(医学書院)で二〇一〇年、第四十一回大宅壮一ノンフィクション賞受賞。他に『末期を越えて』(青土社)、共編著に『在宅人工呼吸器ケア実践ガイド―ALS生活支援のための技術・制度・倫理』(医歯薬出版)など。副理事長を務めるNPO法人さくら会ではヘルパー養成研修会を毎月開催。当面の目標は日本の難病呼吸器ユーザーの豊かな生を世界に知らしめること。都内マンションで猫3匹と理学療法士を目指す息子と同居中。
-

支える,支えられる,支え合う
¥1,100
【中古 状態きれい】 (参考:定価1,450円+税) ☆店長のひと言 「支える人もまた誰かに支えられているわけで。若者よ、遠慮はいらぬぞ。」 紹介 あなたの周りに誰かの助けを必要としている人はいますか? あなたは困ったことがあったら周りにSOSを出すことはできますか? サヘル・ローズさんが自らの体験をたどりながら、他者を思いやり、寄り添うことの大切さを伝えます。森山誉恵さん、慎泰俊さん、三好祐也さん、ブローハン聡さんなど、10代の居場所づくり、病気の子どもの教育など様々な支援に携わる方々の活動も紹介します。 目次 この本の内容 サヘル・ローズ 自分を大切にして、そしてまわりの人に目を向けて はじめに イランから日本へ 「違うこと」を否定しないで ランドセルの思い出 SOSを出せない これから出会うべき人がたくさんいる 気がついたら声をかけてあげて 自分の「色」を大切に 人と比べる必要はない いまの経験は、いつかだれかを助ける力になる 森山誉恵子 こどもたちの安心・安全な育ちを保障する 安心して過ごせる場所はどこ? 親の経済状況で環境が変わる? 学習ボランティアで感じたことは 支援の仕組みからこぼれ落ちる子どもたち 10代のための相談サイトMex(ミークス) 自分の好きなことをして過ごせる居場所「3(さん)」 一人で抱え込まないでいいんだよ 【コラム1】 あなたに居場所はありますか? 慎泰俊 だれにでも平等にチャンスのある世の中にしたい お金のサービスの支援活動 200万人以上の子どもたちにサービスを届ける なぜこういう活動をはじめたの? だれもが同じようにチャレンジできる社会 小さなことから変えられる 日々の積み重ね 【コラム2】 開発途上国の子どもたち 三好祐也 病気を抱えていても自分らしくいられるように 何で自分だけ? 入院している子どもたちが勉強できるように みんなと一緒に勉強したい 退院してからも支援が必要 友達が車いすを押してくれた 友達とのつながりが大切 「伝える努力」と「休む勇気」 【コラム3】 病気を抱える子ども達はどうやって勉強している? ブローハン聡 自分で生き方を選べることの大切さ 継父の暴力におびえる日々 小学校時代 はじめて安心して眠ることができた 母が誇れるような生き方をしよう 親友に打ち明けた時の反応 〈自分という「資格」〉を取ろう 当事者としての活動 閉じた世界から抜け出して広い世界を知った 【コラム4】 虐待について 支え合うための本棚 著者プロフィール サヘル・ローズ (サヘル・ローズ) (著/文) 俳優・タレント 1985年イラン生まれ。幼少時代はイランの孤児院で生活し、7歳のときにフローラ・ジャスミンの養女として引き取られる。8歳で養母とともに来日。高校時代に受けたラジオ局J-WAVEのオーディションに合格して芸能活動を始める。レポーター、ナレーター、コメンテーターなど様々なタレント活動のほか、俳優として映画やテレビドラマに出演し舞台にも立つ。 また芸能活動以外で、国際人権NGOの「すべての子どもに家庭を」の活動では親善大使を務めていた。私的にも援助活動を続け、公私にわたる福祉活動が評価され、アメリカで人権活動家賞を受賞。著書には『戦場から女優へ』(文藝春秋)、フォトジャーナリストの安田菜津紀氏との共著で写真詩集『あなたと、わたし』(日本写真企画)がある。 ISBN:978-4-00-027242-1 Cコード:0336 B6判126ページ 発行:岩波書店 初版年月日: 2021年11月26日

-

パワハラ問題 アウトの基準から対策まで
¥410
【中古 状態きれい】 (参考:定価800円+税) ☆店長のひと言 「ハラスメントは法律だけ理解しても減らないところが難しいですが、もはや知らなかったでは済まされないのもまた事実。」 紹介 被害者になったら……加害者だと言われたら……。1000件以上のハラスメント相談を受けてきた弁護士が、パワハラ防止法を徹底解説したうえで、予防策や危機管理、過去の裁判例まで詳述。全組織人必読の書。 目次 まえがき 第1章 まず基礎知識から 第2章 ウィズコロナ時代のハラスメント 第3章 アウトとセーフの事例を理解する 第4章 パワハラ防止法の徹底解剖 第5章 国家公務員と地方公務員の職場はどうなるか 第6章 経営者と管理職は何をすればよいのか 第7章 パワハラ経営者、管理職にならないために 第8章 グレーゾーンをこわがらない方法 第9章 問題化した場合のリカバリー 第10章 管理職が被害者になるとき 第11章 問題集:あなたならどう動くか ケース1 【なぜオレがパワハラ上司に】/ケース2 【一生懸命指導しているのに】/ケース3 【グレーの場合】/ケース4 【無意識パワハラ】/ケース5 【内容証明が来た】/ケース6 【パワハラを見たとき】/ケース7 【カスタマー・パワハラ】/ケース8 【最悪の結果】 現場で役立つ最新パワハラ判決30選 1 パワハラを認めた判決例 2 パワハラを認めなかった判決例 あとがき 主要な参考文献 専門家による相談窓口 著者プロフィール 井口 博 (イグチ ヒロシ) 弁護士。元裁判官。ジョージタウン大学ロースクール大学院修了。 ISBN:978-4-10-610878-5 Cコード:0234 新書判256ページ 発行:新潮社 初版年月日: 2020年10月20日
-

言葉を失ったあとで
¥1,800
SOLD OUT
【中古 帯の破損※以外は状態きれい(画像参照)】 (参考:定価1,800円+税) ☆店長のひと言 「被害者を減らすためにも加害者への理解と支援は必要なんだけれど、それを声高に主張すると世間様に叩かれるという…。」 紹介 アディクション・DVの第一人者と、沖縄で若い女性の調査を続ける教育学者。現場に居続ける二人が真剣に、柔らかく、具体的に語る、「聞く」ことの現実。 「聞くの実際」。アディクション・DVの第一人者と、沖縄で社会調査を続ける教育学者。それぞれの来歴から被害/加害をめぐる理解の仕方まで、とことん具体的に語りあった対談集。 【目次】 まえがき 信田さよ子 第一章 言葉を失ったあとで 二〇二〇年一一月二七日 中立の立場とはなにか/加害者の話をどう聞くか/加害を書けるか/加害者が被害を知る/性被害の特殊性/仏壇継承者/暴力の構造を知る/スタイルの違い/学校が話を聞けない場所に/援助が料金に見合うか/質疑応答へ/加害者の普通さ/厳罰化は何も解決しない/言葉をいっしょに探す/ゼロ・トレランスの弊害/まずはいい時間をつくる/三つの責任 読書案内① 第二章 カウンセリングという仕事、社会調査という仕事 二〇二一年二月六日 精神科医にできないこと/教室の実践記録のおもしろさ/原点は児童臨床のグループ/沖縄から離れて/「性の自己決定」の実際/社会調査が示すこと/医者になるか、女性のアルコールやるか/女性の依存症の特異さ/八〇年代の精神病院の経験が一生を決めた/生身の人間の話がおもしろい/ネクタイを褒める/沈黙に強くなる 読書案内② 第三章 話を聞いて書く 二〇二〇年二月二三日 精神疾患の鋳型/解離は手ごわい/医療との関係/加害はパターン化している/精神科の役割/値踏みされている/お金をもらうか払うか/許諾のとりかた/書く責任/モスバーガーの文脈/身体は触らない/身体は自分のもの/聞きとりのあと/トランスクリプトの確認の仕方 読書案内③ 第四章 加害と被害の関係 二〇二一年三月一二日 被害者元年/起源は七〇年代/仲間は当事者/学校現場の変化/公認心理師の国家資格/被害者の両義性/暴力をなくす練習/加害者プログラムの順番/加害者の書きづらさ/映画で描かれる暴力/打越正行さんの調査 読書案内④ 第五章 言葉を禁じて残るもの 二〇二一年三月二七日 性被害をどのように語りはじめるのか/臓器がぶらさがっている感覚/フラッシュバックの意味/被害経験の読み替え/選択肢のすくなさ/家族の性虐待/語りのフォーマット/言葉を禁じる/性加害者の能動性/ユタを買う/一二月の教室/オープンダイアローグの実践 読書案内⑤ 第六章 ケアと言葉 二〇二一年五月一一日 カウンセリングに来るひとたち/男性の語りのパターン/加害者の語り/加害者プログラムの肝/DV被害者支援と警察/家族はもうだめなのか?/使えるものはぜんぶ使う/親との関係を聞く/被害者共感の効果/権力と言葉/「加害者」という言葉の危うさ/ブルーオーシャンへ/被害者は日々生まれている/当事者の納得する言葉 読書案内⑥ あとがき――「聞く」の現場の言葉を聞く 上間陽子 著者プロフィール 信田 さよ子 (ノブタ サヨコ) (著/文) 1946年、岐阜県生まれ。公認心理師・臨床心理士。原宿カウンセリングセンター顧問、NPO法人RRP研究会の代表理事。著作に『家族と国家は共謀する』(角川新書)、『増補新版 ザ・ママの研究』(新曜社)、『カウンセラーは何を見ているか』(医学書院)など多数。 上間 陽子 (ウエマ ヨウコ) (著/文) 1972年、沖縄県生まれ。琉球大学教育学研究科教授。生活指導の観点から主に非行少年少女の問題を研究。著作に『海をあげる』(筑摩書房)、『裸足で逃げる』(太田出版)、共著に『地元を生きる』(ナカニシヤ出版)など。 ISBN:978-4-480-84322-7 Cコード:0095 四六判352ページ 発行:筑摩書房 発売日: 2021年12月2日
-

星を掬う
¥650
【中古 状態きれい】 (参考:定価1,600円+税) ☆店長のひと言 「掬うは、“救う”か“巣食う”か。」 紹介 町田そのこ 2021年本屋大賞受賞後第1作目は、すれ違う母と娘の物語。 小学1年の時の夏休み、母と二人で旅をした。 その後、私は、母に捨てられた――。 ラジオ番組の賞金ほしさに、ある夏の思い出を投稿した千鶴。 それを聞いて連絡してきたのは、自分を捨てた母の「娘」だと名乗る恵真だった。 この後、母・聖子と再会し同居することになった千鶴だが、記憶と全く違う母の姿を見ることになって――。 著者プロフィール 町田 そのこ (マチダソノコ) (著/文) 1980年生まれ。福岡県在住。 「カメルーンの青い魚」で、第十五回「女による女のためのR-18文学賞」大賞を受賞。2017年に同作を含む『夜空に泳ぐチョコレートグラミー』でデビュー。他の著作に『ぎょらん』『コンビニ兄弟―テンダネス門司港こがね村店―』(新潮社)、『うつくしが丘の不幸の家』(東京創元社)がある。 ISBN:978-4-12-005473-0 Cコード:0093 四六判328ページ 発行:中央公論新社 発売日: 2021年10月18日
-

ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい
¥480
【中古 状態きれい】 (参考:定価680円+税) ☆店長のひと言 「ぬいぐるみは裏切らないから。」 内容紹介 僕もみんなみたいに恋愛を楽しめたらいいのに。大学二年生の七森は“男らしさ”“女らしさ”のノリが苦手。こわがらせず、侵害せず、誰かと繋がれるのかな? ポップで繊細な感性光る小説4篇。 恋愛を楽しめないの、僕だけ? "男らしさ""女らしさ"のノリが苦手な大学二年生の七森。こわがらせず、侵害せず、誰かと繋がりたいのに。 ジェンダー文学の新星! 鋭敏な感性光る小説4篇を収録。 (河出書房新社ホームページより引用) 著者プロフィール 大前 粟生 (オオマエ アオ) (著/文) 1992年兵庫県生まれ。著書に『回転草』『私と鰐と妹の部屋』『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』『おもろい以外いらんねん』『きみだからさびしい』『死んでいる私と、私みたいな人たちの声』等がある。 ISBN:978-4-309-41935-0 Cコード:0193 文庫判200ページ 発行:河出書房新社 発売日: 2023年1月10日
-

根っからの悪人っているの?
¥1,760
☆店長のひと言 「被害者であり続けた人が加害者になった瞬間に悪のレッテルを貼られる…、改めて考えると恐ろしい話です。」 紹介 シリーズ「あいだで考える」創刊!不確かな時代を共に生きていくために必要な「自ら考える力」「他者と対話する力」「遠い世界を想像する力」を養う多様な視点を提供する、10代以上すべての人のための人文書のシリーズ。 『根っからの悪人っているの?――被害と加害のあいだ』著者の映画作品『プリズン・サークル』は、日本で1か所だけ、刑務所の中で行われている「TC(回復共同体)」という対話による更生プログラムを、20 代の受刑者4 人を中心に2 年間記録したドキュメンタリー。本書は、この映画を手がかりに、著者と10 代の若者たちが「サークル(円座になって自らを語りあう対話)」を行った記録である。映画に登場する元受刑者の2 人や、犯罪被害の当事者をゲストに迎え、「被害と加害のあいだ」をテーマに語りあう。(装画:丹野杏香) 目次 はじめに 第1回 初めての対話 『プリズン・サークル』を観て 「わかりたい」と思うには 「違い」に出会う 第2回 真人さんとの対話 刑務所のリアル 犯した罪をめぐって 大切なものとサンクチュアリ コラム おすすめの音楽 サンクチュアリが壊れたあと 第3回 翔さんとの対話 感情に気づき、感情を動かす サンクチュアリをつくる 自らの罪を語る コラム 感情をめぐるワーク 聴く・語る・変わる 第4回 山口さんとの対話 事件に遭遇して??山口さんの被害体験 コラム 事件後の子どもとの関係性の変化 少年の居場所 少年と会う 被害者と加害者が直接会うこと??「修復的司法」 コラム 修復的司法の個人的な取り組み 揺れていい 第5回 最後の対話 4回の対話の感想 根っからの悪人っているの? おわりに 被害と加害のあいだをもっと考えるための 作品案内 著者プロフィール 坂上香(さかがみ・かおり) 1965年大阪府生まれ。ドキュメンタリー映画作家。NPO法人out of frame代表。一橋大学大学院社会学研究科客員准教授。映画作品に『Lifers ライファーズ 終身刑を超えて』『トークバック 沈黙を破る女たち』『プリズン・サークル』(文化庁映画賞・文化記録映画大賞受賞)、著書に『プリズン・サークル』(岩波書店)などがある。 (創元社ホームページより引用)) ISBN:978-4-422-36015-7 Cコード:0336 四六判変型 192ページ 発行:創元社 発売日: 2023年10月17日

-

福祉は性とどう向き合うか
¥1,540
【中古 状態きれい】 (参考:定価2,200円+税) ☆店長のひと言 「障害者や高齢者と“フツー”の人では別もののように思われがちですよね。」 内容紹介 「私、知的障害者だから恋愛できないね」は、日本社会の現実なのか。老いらくの性は、年甲斐もないことなのか。障害者・高齢者の性・恋愛・結婚は、自己責任なのか。本書は、当事者とその家族・支援者(福祉職員・街コン関係者等)へのインタビュー等を基に、「機会平等」の観点から支援の是非・あり方について考えたものである。「自己決定の尊重」と「社会規範」の狭間にある、誰もが持つ「性的ニーズ」への支援について真正面から捉えた一冊。 [ここがポイント] ◎ 誰もが持つ「性的ニーズ」への支援を真正面から捉えた一冊。 ◎ 支援者、当事者、当事者の家族の三者への聞き取り調査を通し、福祉現場で生じているジレンマを明示。 ◎ 「自己決定の尊重」と「社会規範」の狭間にあるニーズに対する福祉のあり方を考察。 目次 まえがき 序 章 福祉専門職の悩み——現場からの報告(結城康博) 1 タブー視される「性」の問題 2 レイプ未遂?——判断の困難な認知症高齢者のケース 3 福祉専門職へのセクシュアルハラスメント 4 現場が抱える問題①——高齢者福祉施設の場合 5 現場が抱える問題②——障害者福祉施設の場合 6 超高齢化社会の到来 第Ⅰ部 高齢者・障害者の性 第1章 高齢者の性・恋愛・結婚(後藤宰人) 1 性生活を続ける高齢者夫婦たち 2 恋をする高齢者たち 3 恐怖を覚える女性——求める夫と避ける妻 第2章 高齢者と性風俗(後藤宰人) 1 性風俗に通う男性高齢者たち 2 「上客」として扱われる男性高齢者 3 人は死ぬまで性欲を持ち続ける 4 男性高齢者が性風俗に求めるもの 5 性風俗を利用する女性高齢者 第3章 障害者の性・恋愛・結婚①——肢体不自由者の場合(武子愛) 1 切実な欲求としての「性」 2 肢体不自由者の周囲を取り巻く問題 3 本人を取り巻く問題 4 障害者の権利に関する条約 5 「性的ニーズ」を要求できるかどうかは運次第——支援者の姿勢が鍵 第4章 障害者の性・恋愛・結婚②——知的障害者の場合(武子愛) 1 知的障害者であるがゆえに生じる困難 2 施設を利用する知的障害者の問題——「性的ニーズ」を満たすことができない人々 3 性風俗産業に利用される女性 4 「搾取」による「寂しさ」の解消——軽度の知的障害者が抱えるジレンマ 第5章 障害者と性風俗(後藤宰人) 1 健常者も障害者も同じ 2 障害者対応性風俗と障害者専用性風俗 3 障害者が「専門店」に求めるもの 4 性風俗から見える社会のひずみ 第Ⅱ部 利用者の「性的ニーズ」と福祉専門職 第6章 「性的ニーズ」と向き合うことになった福祉専門職(武子愛) 1 介護とセクシュアルハラスメントは分けられない? 2 「性的ニーズ」の対象となることはどのように捉えられてきたのか——先行研究の知見から 3 施設(組織)で対応したケース 4 一職員のみでの対応を求められたケース 5 自分に向けられた「性的ニーズ」の表明をどう捉えるか——虐待防止法をめぐって 第7章 「性的ニーズ」をどのように捉えるのか(武子愛) 1 「性」に立ち入りたくない福祉現場 2 支援する側はどう思ったのか——支援者たちの証言から 3 「性的ニーズ」への支援の障害——社会規範・利用者の判断能力・支援の根拠 4 福祉の理念および人権に関する宣言から 5 「性的ニーズ」への支援は可能か 第Ⅲ部 公共政策・社会環境から見た「性的ニーズ」 第8章 「性的ニーズ」への支援と公共政策(結城康博) 1 社会保障費の増加の中で 2 介護保険外サービスを利用した支援 3 現行の法令に規定されている余暇活動への支援 4 公共財と私的財 5 ボランティアによる支援 6 厳しい社会保障費問題の壁 7 「性的ニーズ」に関するケア・支援に悩む従事者 第9章 「性的ニーズ」を取り巻く社会環境——社会福祉の視点から(米村美奈) 1 社会福祉における性の捉え方 2 利用者の「性的ニーズ」を取り巻く障壁 3 障壁を作り出したのは誰か 終 章 自己決定を尊重した支援は可能か(米村美奈) 1 嘘をついた男性利用者——行きたかったのはレストランではなく性風俗 2 自己決定とは 3 自己決定への支援 4 支援者の自己開示——「性的ニーズ」への対応に求められるもの 5 利用者の「真」のニーズの追求 6 対話による潜在的ニーズの把握 7 支援者が自己決定に「No」ということ——婦人保護施設のケースを踏まえて 8 利用者のニーズだけがすべてではない——婦人保護施設に保護された女性たち 9 専門職の責務 あとがき 索 引 (ミネルヴァ書房HPより転載) 結城 康博(著/文), 米村 美奈(著/文), 武子 愛(著/文), 後藤 宰人(著/文) ISBN 978-4-623-08169-1 四六判 244頁 発行 ミネルヴァ書房 書店発売日 2018年2月25日
-

ビッグイシュー462号
¥450
☆店長のひと言 「ビッグイシュー日本版 創刊20周年おめでとうございます!買いましょう!!」 【内容紹介】 古気候学と“気候危機” 今年の夏は“危険”な暑さが続いた。20世紀後半に指摘され始めた地球温暖化問題は、広く社会に受け入れられるまで半世紀以上かかった。また、歴史時代には大気中の二酸化炭素(CO₂)濃度が今より高い状態が存在しなかったので、気候変動の議論は19世紀後半以降の気候観測結果をもとに行われてきた。 しかし、地球史をさかのぼって数千~数千万年前の地質記録(氷床コア、海洋堆積物など)を研究する古気候学は、温暖化に伴う未知の気候も探っている。 長らく古気候学を研究してきた多田隆治さん(東京大学名誉教授)は「すでに温暖化はかなり進行し、人為的なCO₂放出を止めただけではすぐに元には戻らない」「自然界がCO₂を放出する速度の100倍で人類がCO₂を出し続ければ、現在の気候モードを維持するメカニズムが機能する限界(しきい値)を超え、急激な気候変動(モード・ジャンプ)が起こってしまう可能性がある」と言う。多田さんに、古気候学から見た“気候危機”について聞いた。 TOP INTERVIEW スペシャルインタビュー 羽生善治 今年6月に満を持して日本将棋連盟の会長に就任した羽生善治さん。本誌創刊20周年記念号に4度目の登場です。前人未踏の永世七冠や歴代トップのタイトル通算獲得数を誇る「将棋界のレジェンド」が、50代の変化、AIとの共生、そして将棋の未来を語ります。 リレーインタビュー・私の分岐点今成夢人さん 撮影の仕事に徹するはずだった記者会見 突然、レスラーとして引っ張り出された 国際記事 世界で復活する「現金給付」と「ベーシック・インカム」 WORLD STREET NEWS 世界短信 連載記事 原発ウォッチ 中電、山口県と上関町に中間貯蔵施設、調査提案 浜矩子の新ストリート・エコノミクス プーチンの背中の藁一本 雨宮処凛の活動日誌 「五公五民」の負担に悲鳴。「最賃上げろ」デモ ホームレス人生相談 × 枝元なほみの悩みに効く料理 アイドルグッズの整理に踏ん切りがつきません ☆ 味たまおむすび ☆ ビッグイシューアイ 2年かけて自作したタイニーハウス「もぐら号」 読者のページ My Opinion 販売者に会いにゆく 東京・渋谷駅宮益坂上交差点 S・K さん FROM EDITORIAL 編集後記 (ビッグイシュー日本HPより抜粋)
-

母は死ねない
¥1,650
☆店長のひと言 「“私”ではなく“母”。」 紹介 育てたい。愛したい。それだけの願いを叶えることが、こんなにも難しい――。一人として同じではない女性たちと著者自身の切なる声をたしかに聴き取る。 著者プロフィール 河合 香織 (カワイ カオリ) (著/文) 1974年生まれ。ノンフィクション作家。2004年、障害者の性と愛の問題を取り上げた『セックスボランティア』が話題を呼ぶ。09年、『ウスケボーイズ 日本ワインの革命児たち』で小学館ノンフィクション大賞、19年に『選べなかった命 出生前診断の誤診で生まれた子』で大宅壮一賞および新潮ドキュメント賞をW受賞。ほか著書に『分水嶺 ドキュメント コロナ対策専門家会議』『帰りたくない 少女沖縄連れ去り事件』(『誘拐逃避行――少女沖縄「連れ去り」事件』改題)、『絶望に効くブックカフェ』がある。 ISBN 978-4-480-81570-5 四六判 224頁 発行 筑摩書房 発売日 2023年3月13日