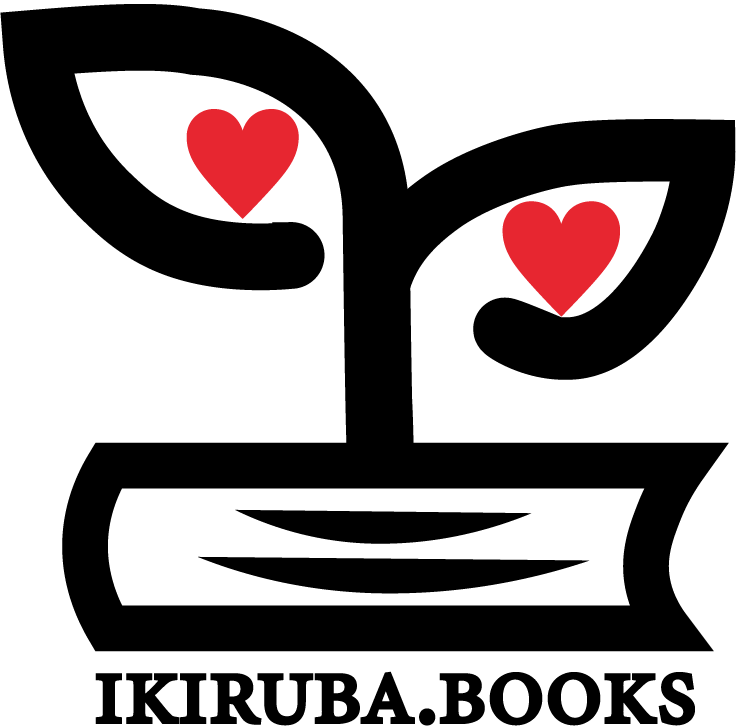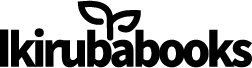-

子どもたちへ、今こそ伝える戦争
¥1,000
【中古 状態きれい】 (参考:定価1,800円+税) ☆店長のひと言 「子どもは戦争に対して受け身でいるしかないということを改めて思い知らされます。」 紹介 この本は、子どもから子どもへのメッセージです。 戦争を日常とした当時の子どもたちから、現代の子どもたちへ、その暮らしと思いが19人それぞれの視点で描かれています。 日々子どもに伝える仕事をしている作家たちによる自分自身の話は、戦争の話をはじめて読むお子さんにも伝わりやすいことでしょう。 小学生のお子さんたちは、ご家族に戦争体験者がいない人が多いと思います。 ぜひご家族でもお読みください。巻末には用語解説、地図、年表などを載せました。 ひとりずつのお話は短く、イラストも入り、読み進めやすくなっています。 戦争の体験は、子どもの本の作家19人のその後の人生に大きな影響を与え、強く生きていく動機になり、表現する仕事を選ばせたと感じます。 子どもの生きる力の素晴らしさ、そして、子どもの心に刻まれる戦争の痕跡の大きさをさまざな視点から伝える1冊です。 著者……長 新太、和歌山 静子、那須 正幹、長野 ヒデ子、おぼ まこと、 立原 えりか、田島 征三、山下 明生、いわむら かずお、三木 卓、 間所 ひさこ、今江 祥智、杉浦 範茂、那須田 稔、井上 洋介、 森山 京、かこ さとし、岡野 薫子、田畑 精一(敬称略) 解説……柳田邦男(ノンフィクション作家) *すべてかき下ろし(長 新太さんを除く) *すべての漢字にふりがなつき *小学3年生から ISBN:978-4-06-219626-0 Cコード:8036 A5判178ページ 発行: 講談社 発売日: 2015年7月17日
-

もの食う人びと
¥300
【中古 状態きれい】 (参考:定価720円+税) ☆店長のひと言 「新聞に連載していたとき読んでいました。過酷な状況と食事の描写の対比が衝撃でした。 紹介 バングラデシュで、旧ユーゴで、ソマリアで、チェルノブイリで…人びとはいま、なにを食べ、考えているか。熟達の記者・芥川賞作家の著者が、世界の飢餓線上を彷徨い、ともに食らい、語らい、鮮やかに紡いだ、驚愕と感動のドラマ。現代報道の壁を突破し抜いた、世紀末の食の黙示録。文庫化に際し、新たに書き下ろし独白とカラー写真を収録。 目次 旅立つ前に 残飯を食らう 食いものの恨み ピナトゥボの失われた味 塀の中の食事 食とネオナチ 黒を食う モガディシオ炎熱日誌 麗しのコーヒー・ロード バナナ畑に星が降る 兵士はなぜ死んだのか 禁断の森 チェロ弾きの少女 儒者に食事作法を学ぶ 背番号27の孤独な戦い ある日あの記憶を殺しに〔ほか〕 著者プロフィール 辺見 庸 (ヘンミ ヨウ) (著) 小説家、ジャーナリスト、詩人。元共同通信記者。宮城県石巻市出身。宮城県石巻高等学校を卒業後、早稲田大学第二文学部社会専修へ進学。同学を卒業後、共同通信社に入社し、北京、ハノイなどで特派員を務めた。北京特派員として派遣されていた1979年には『近代化を進める中国に関する報道』で新聞協会賞を受賞。1991年、外信部次長を務めながら書き上げた『自動起床装置』を発表し第105回芥川賞を受賞。 ISBN:978-4-04-341701-8 Cコード:0195 文庫判 368ページ 発行:KADOKAWA 発売日: 1997年06月20日
-

迷いのない人生なんて
¥1,144
☆店長のひと言 「若い頃の自分に言いたい。迷わない大人はけっこう危ない。」 紹介 共同通信の好評連載「迷い道」を書籍化。家族との葛藤、仕事の失敗、病気の苦悩、親しい人との別れ、挫折……。私たちの身近にいるごく普通の人々が様々な生きづらさと向き合い、回り道の人生を歩んできた姿を描く。迷いを抱えながら生きる人への共感とエールを込めた一冊。 目次 はじめに ◎ あさのあつこさんに聞く 回り道だらけの半生 1 向き合う、問い続ける 1 母さんに何も期待しない 尾﨑瑠南(作業療法士) 2 求め続けた女性の声 工藤理江(ボイストレーナー) 3 生きていてもいいかな 木田塔子(看護師) 4 飼育員であり続けたい 盛田勝寛(水族館飼育員) 5 捨てられそうになった子 福江悦子(彫刻家) 6 許されてここにいる 沼田和也(牧師) 7 熱くて意味ある空間を 柳田尚久(轍学舎塾長) 8 母でも私のままで 栗並えみ(働く母親) 9 あなたのことが怖かった 荻野善弘(カレー店店主) 10 母の病「神なんていない」 坂根真実(宗教2世) 11 沖縄に向き合う「右翼」 中村之菊(右翼活動家) 12 反発と執着、引き合う心 伊東優(建築士) 13 一緒に前を向けなかった 斎藤無冥(僧侶) 2 見つめる、伝える 14 絵に導かれ外の世界へ 三上真穂(大学院生) 15 「あれはドラマですから」 加藤浩美(写真家) 16 もう記者は続けられない 浮田圭一郎(高校教師) 17 あなたの分身じゃない 中嶋悠紀子(演劇家) 18 可能性なんてなかった 松田修(現代美術家) 19 私に何ができるのか 高橋美香(パレスチナ取材の写真家) 20 神の愛、伝え続ける 花田憲彦(牧師) 21 放水指示、指揮官の宿命 新井雄治(元東京消防庁消防総監) 22 すぐ逃げ帰ると思っていた 川村久恵(アイヌ記念館副館長) 23 心の奥、拾ってくれた 千葉広和(国賠償請求訴訟の原告) 24 これは僕の投げ方じゃない 水尾嘉孝(野球部コーチ) 25 贖罪の思い胸に反戦運動 山里節子(反戦運動家) 26 資本主義への挑戦敗れ 田中克治(元印刷会社社長) 27 母の葛藤、寄り添い祈る 菊池文子(語り部の被爆者) 3 踏み出す、歩む 28 やっと自由になれる 野島さえ(鍼灸師、トレーナー) 29 暗闇から、春の日だまり 吉田千寿子(東日本大震災被災者) 30 共に生きる未来が見えない 大内紀彦(特別支援学校教員) 31 わが子の思いに近づきたい 浅井道子(那須雪崩事故遺族) 32 おまえの努力が足りない 白木浩一郎(老舗旅館元経営者) 33 気丈な妻、記憶喪失に 山本秀勝(手品師) 34 確率という言葉が憎かった 大津一貴(元プロサッカー選手) 35 さいころ一から振り直し 奥川拓二(会社社長) 36 苦悩抱きしめ、共に歩む 八尾敬子(就労継続支援施設長) 37 避難の経験、そっと横に 高橋恵子(原発避難住民) 38 生きる意味、取り戻して 山下泰三(元会社員) 4 つながる、つなぐ 39 息苦しさ、乗り越えて 中野民夫(元博報堂社員) 40 つながりながら縛らない 内田加奈(作業療法士) 41 きっと加害者になっていた 中島坊童(不登校、引きこもり支援者) 42 いないよ、ここに 立花泰彦(ミュージシャン) 43 しゃべるのは苦手だけれど 伊神敬人(看護師) 44 この社会が正解なのか 森哲也(書店店主) 45 遺族に悼まれ死者になる 殿平善彦(僧侶) 46 深い孤独と性自認の揺れ 倉田めば(元薬物依存症患者) 47 虐待なんてあり得ない 菅家英昭(会社員) 著者プロフィール 共同通信社 (キョウドウツウシンシャ) (著/文) 一般社団法人共同通信社は、全国各地の新聞社や放送局、海外メディアなどに記事、写真、映像を配信している通信社。1945年に創立。東京に本社を置き、全国に支社局、海外主要都市に総支局がある。 ISBN:978-4-00-500985-5 Cコード:0236 新書判260ページ 発行:岩波書店 初版年月日: 2024年5月17日
-

「空気」を読んでも従わない
¥500
【中古 状態きれい】 (参考:定価820円+税) ☆店長のひと言 「そもそも空気を読めるだけですごい能力なわけで、それ以上求めるのは無茶な話なんですよ。」 内容紹介 「個性」が大事というけれど、集団の中であまり目立つと浮いてしまう、他人の視線を気にしながら、本当の自分は抑えつけていかないと……。この社会はどうしてこんなに息苦しいのだろう。もっと自分らしく、伸び伸びと生きていきたい! そんな悩みをかかえるアナタにとっておきのアドバイス。「空気」を読んでも従わない生き方のすすめ。 目次 はじめに 1 なぜ先輩に従わなければいけないの? 2 どうして,人の頼みを断れないのだろう? 3 「世間」と「社会」 4 「世間」の始まり 5 「世間」を壊そうとする人達 6 根強く残る「世間」 7 「世間」は中途半端に壊れている 8 外国には「世間」はない 9 人の頼みを断るのがつらいヒミツ 10 もし人から頼まれたら 11 敵を知るということ 12 「空気」ということ 13 「世間」のルール1 年上がえらい 14 「世間」のルール2 「同じ時間を生きる」ことが大切 15 「世間」のルール3 贈り物が大切 16「世間」のルール4 仲間外れを作る 17 「世間」のルール5 ミステリアス 18 「世間」はなかなか変わらない 19 5つのルールと戦い方 20 強力な「世間」との戦い方 21 同調圧力 22 自分を大切に思うこと 23 仲間外れを恐れない 24 たったひとつの「世間」ではなく 25 私を支えるもの 26 スマホの時代に おわりに 著者プロフィール 鴻上 尚史 (コウカミ ショウジ) (著/文) 鴻上尚史(こうかみ・しょうじ) 作家・演出家・映画監督。1958年愛媛県生まれ。早稲田大学法学部卒業。大学在学中の1981年、劇団「第三舞台」を旗揚げする。87年「朝日のような夕日をつれて87」で紀伊國屋演劇賞団体賞、95年「スナフキンの手紙」で岸田國士戯曲賞、2007年に旗揚げした「虚構の劇団」の旗揚げ三部作戯曲集『グローブ・ジャングル』で10年、読売文学賞戯曲・シナリオ賞を受賞。著書に『「空気」と「世間」』『不死身の特攻兵』(以上、講談社現代新書)、『ベター・ハーフ』(講談社)、『人間ってなんだ』『人生ってなんだ』『世間ってなんだ』(以上、講談社+α新書)、『鴻上尚史のほがらか人生相談』(朝日新聞出版)、『同調圧力のトリセツ』(中野信子との共著、小学館新書)など多数。 ISBN:978-4-00-500893-3 Cコード:0236 新書判 224ページ 発行:岩波書店 発売日: 2019年04月20日

-

辺境のラッパーたち ~立ち上がる「声の民族誌」~
¥3,520
☆店長のひとラップ HEY YO, 魂抜かれたヒップホップ HEN-KYO de rap survive 他人(ひと)のせいにすんなリスナー 声なき声ひろえ Listen Now! 紹介 ラッパーのことばに耳をすませば、世界のリアルが見えてくる。 戦火が絶えないガザやウクライナで、弾圧が続くチベットやイランで、格差にあえぐモンゴルやインドで、海の端の日本で――。アメリカで生まれたヒップホップ文化、なかでもラップミュージックは世界に広がり、「辺境」に生きる者たちは声なき声をリリックに託す。現代社会の歪みを鮮やかに映し出す、世界各地のラッパーたちの声を幅広い執筆陣が紹介する。ラッパー、ダースレイダー、ハンガー(GAGLE)のインタビューも収録。 http://www.seidosha.co.jp/book/index.php?id=3935 著者 [編者]島村一平(しまむら・いっぺい) 国立民族学博物館人類文明誌研究部教授。文化人類学・モンゴル研究専攻。博士(文学)。早稲田大学法学部卒業後、テレビ番組制作会社に就職。取材で訪れたモンゴルに魅せられ制作会社を退社、モンゴルへ留学する。モンゴル国立大学大学院修士課程修了(民族学専攻)。日本に帰国後、総合研究大学院大学博士後期課程に入学。同大学院を単位取得退学後、国立民族学博物館講師(研究機関研究員)、滋賀県立大学人間文化学部准教授等を経て現職。著書に『憑依と抵抗——現代モンゴルにおける宗教とナショナリズム』(晶文社)、『ヒップホップ・モンゴリア——韻がつむぐ人類学』(青土社)、『増殖するシャーマン——モンゴル・ブリヤートのシャーマニズムとエスニシティ』(春風社)など多数。 (青土社ホームページより) ISBN:978-4-7917-7654-2 Cコード:0039 四六判544ページ 発行: 青土社 発売日: 2024年6月26日

-

正岡子規スケッチ帖
¥924
☆店長のひと言 「病床にあって自己を保ち、且つ創造的でいられる人がこの世にどれだけいようか。」 紹介 「写生は多くモルヒネを飲みて後やる者と思へ」。子規の絵は味わいある描きぶりの奥に気魄が宿る。子規にとって絵を描くことは病床の慰めや楽しみ以上の、生きるよすがであった。最晩年の三か月に描き、『果物帖』『草花帖』『玩具帖』と題してまとめられた画帖をオールカラーで収録。漱石、鼠骨ら、子規の絵をめぐる文章を併載する。 目次 第一部 子規のスケッチ帖 『菓物帖』 『草花帖』 『玩具帖』 第二部 子規の絵画観 「明治二十九年の俳句界」より 画 『病牀六尺』より 明治三十五年八月六日条 八月九日条 八月二十三日条 八月二十四日条 第三部 子規の絵をめぐって 寒川鼠骨「子規居士の絵――「菓物帖と草花帖」」 寒川鼠骨「解説と回顧」 下村為山「子規氏の絵」 夏目漱石「子規の画」 解題 『玩具帖』について(平岡瑛二) 編者解説(復本一郎) 著者プロフィール 正岡 子規(マサオカ シキ) (著/文) 説明不要ですよね? 復本 一郎 (フクモト イチロウ) (著/文) 1943年、愛媛県宇和島市に生まれる。横浜市で育つ。早稲田大学第一文学部文学科国文学専修卒業。同大学大学院文学研究科日本文学専攻博士課程単位取得満期退学。福岡教育大学、静岡女子大学、静岡大学を経て、神奈川大学経営学部教授。現在、神奈川大学名誉教授。文学博士。『芭蕉における「さび」の構造』で窪田空穂賞受賞。また、俳句分野の功績に対して第9回横浜文学賞を受賞。『俳句と川柳』(講談社学術文庫)、『俳句とエロス』(講談社現代新書)『芭蕉歳時記』(講談社選書メチエ)、『芭蕉俳句16のキーワード』(NHKブックス)、『江戸俳句夜話』(NHKライブラリー)など著書多数。 ISBN:978-4-00-360047-4 Cコード:0171 204ページ 発行:岩波書店 初版年月日: 2024年5月15日
-

しにたい気持ちが消えるまで
¥1,570
【中古 状態きれい】 (参考:定価1,600円+税) ☆店長のひと言 「死にたいも生きたいも自然なこと。でもそれだけでは終わらない。」 紹介 16歳のとき、死のうと思った。すごく天気の良い日で、こんな日に死ねるなんて幸せだと思った。自宅のベランダから飛び降り、頸髄を損傷するが一命をとりとめる。 「死ななくて良かった」、「何もできなくても生きていていい」 現在を生きる筆者による、自死を止めたい、やさしくなりたい、お守りのような言葉。書き下ろし自伝エッセイ。 著者プロフィール 豆塚エリ (マメツカエリ) (著/文) 1993年、愛媛県生まれ。16歳のとき、飛び降り自殺を図り頸髄を損傷、現在は車椅子で生活する。大分県別府市で、こんぺき出版を拠点に、詩や短歌、短編小説などを発表。NHK Eテレ『ハートネットTV』に出演するなど、幅広く活動中。 ISBN:978-4-7796-4671-3 Cコード:0095 四六判304ページ 発行:三栄 発売日: 2022年9月16日
-

奔流 コロナ「専門家」はなぜ消されたのか
¥1,980
☆店長のひと言 「実際消されたかどうかは置いといてだけど、特に初めの頃にはさんざん世話になっておいてさ、みんなちゃんとお礼くらい言った??」 紹介 「嫌われたって、やるしかないんだ」 尾身茂、押谷仁、西浦博ー感染症専門家たちは、コロナ渦3年間、国家の命運を託された。彼らは何と闘い、なぜ放逐されたのか?政権と世論に翻弄されながら危機と戦った感染症専門家の悲劇! 小学館ノンフィクション賞大賞受賞の気鋭ライターの弩級ノンフィクション 著者プロフィール 広野 真嗣 (ヒロノ シンジ) (著/文) 1975年、東京都生まれ。慶応義塾大法学部卒。神戸新聞記者を経て、猪瀬直樹事務所のスタッフとなり、2015年10月よりフリーに。17年に『消された信仰』(小学館)で第24回小学館ノンフィクション大賞受賞。 ISBN:978-4-06-534465-1 Cコード:0036 四六判304ページ 発行:講談社 発売日: 2024年1月17日

-

わたしが誰かわからない : ヤングケアラーを探す旅
¥2,200
☆店長のひと言 「ヤングケアラー…、突然そう呼ばれた人の戸惑いを想像できないあなたへ。」 紹介 「ヤングケアラー」について取材をはじめた著者は、度重なる困難の果てに中断を余儀なくされた。一体ヤングケアラーとは誰なのか。世界をどのように感受していて、具体的に何に困っていているのか。取材はいつの間にか、自らの記憶をたぐり寄せる旅に変わっていた。ケアを成就できる主体とは、あらかじめ固まることを禁じられ、自他の境界を横断してしまう人ではないか――。著者はふたたび祈るように書きはじめた。 目次 はじめに 1 薄氷のような連帯 2 いちばん憎くて、いちばん愛している人 3 わたしが誰かわからない 4 わたしはなぜ書けないか 5 抱えきれない言葉の花束 6 固まることを禁じられた身体──ケア的主体とは何か 7 自己消滅と自己保存──水滴のように 8 犠牲と献身と生まれ変わり──自由へ おわりに 【著者略歴】 中村佑子(なかむら・ゆうこ) 1977年東京都生まれ。映像作家。慶應義塾大学文学部哲学科卒業。哲学書房にて編集者を経たのち、2005年よりテレビマンユニオンに参加。映画作品に『はじまりの記憶 杉本博司』(2012年)、『あえかなる部屋 内藤礼と、光たち』(2015年)がある。主なテレビ演出作に、「幻の東京計画 ~首都にありえた3つの夢~」(NHK BSプレミアム、2014年)、「地球タクシー レイキャビク編」(NHK BS1、2018年)など。本書が初の著書となる。 ISBN:978-4-260-05441-6 Cコード:3347 A5判232ページ 発行:医学書院 発売日: 2023年11月20日
-

支える,支えられる,支え合う
¥1,100
【中古 状態きれい】 (参考:定価1,450円+税) ☆店長のひと言 「支える人もまた誰かに支えられているわけで。若者よ、遠慮はいらぬぞ。」 紹介 あなたの周りに誰かの助けを必要としている人はいますか? あなたは困ったことがあったら周りにSOSを出すことはできますか? サヘル・ローズさんが自らの体験をたどりながら、他者を思いやり、寄り添うことの大切さを伝えます。森山誉恵さん、慎泰俊さん、三好祐也さん、ブローハン聡さんなど、10代の居場所づくり、病気の子どもの教育など様々な支援に携わる方々の活動も紹介します。 目次 この本の内容 サヘル・ローズ 自分を大切にして、そしてまわりの人に目を向けて はじめに イランから日本へ 「違うこと」を否定しないで ランドセルの思い出 SOSを出せない これから出会うべき人がたくさんいる 気がついたら声をかけてあげて 自分の「色」を大切に 人と比べる必要はない いまの経験は、いつかだれかを助ける力になる 森山誉恵子 こどもたちの安心・安全な育ちを保障する 安心して過ごせる場所はどこ? 親の経済状況で環境が変わる? 学習ボランティアで感じたことは 支援の仕組みからこぼれ落ちる子どもたち 10代のための相談サイトMex(ミークス) 自分の好きなことをして過ごせる居場所「3(さん)」 一人で抱え込まないでいいんだよ 【コラム1】 あなたに居場所はありますか? 慎泰俊 だれにでも平等にチャンスのある世の中にしたい お金のサービスの支援活動 200万人以上の子どもたちにサービスを届ける なぜこういう活動をはじめたの? だれもが同じようにチャレンジできる社会 小さなことから変えられる 日々の積み重ね 【コラム2】 開発途上国の子どもたち 三好祐也 病気を抱えていても自分らしくいられるように 何で自分だけ? 入院している子どもたちが勉強できるように みんなと一緒に勉強したい 退院してからも支援が必要 友達が車いすを押してくれた 友達とのつながりが大切 「伝える努力」と「休む勇気」 【コラム3】 病気を抱える子ども達はどうやって勉強している? ブローハン聡 自分で生き方を選べることの大切さ 継父の暴力におびえる日々 小学校時代 はじめて安心して眠ることができた 母が誇れるような生き方をしよう 親友に打ち明けた時の反応 〈自分という「資格」〉を取ろう 当事者としての活動 閉じた世界から抜け出して広い世界を知った 【コラム4】 虐待について 支え合うための本棚 著者プロフィール サヘル・ローズ (サヘル・ローズ) (著/文) 俳優・タレント 1985年イラン生まれ。幼少時代はイランの孤児院で生活し、7歳のときにフローラ・ジャスミンの養女として引き取られる。8歳で養母とともに来日。高校時代に受けたラジオ局J-WAVEのオーディションに合格して芸能活動を始める。レポーター、ナレーター、コメンテーターなど様々なタレント活動のほか、俳優として映画やテレビドラマに出演し舞台にも立つ。 また芸能活動以外で、国際人権NGOの「すべての子どもに家庭を」の活動では親善大使を務めていた。私的にも援助活動を続け、公私にわたる福祉活動が評価され、アメリカで人権活動家賞を受賞。著書には『戦場から女優へ』(文藝春秋)、フォトジャーナリストの安田菜津紀氏との共著で写真詩集『あなたと、わたし』(日本写真企画)がある。 ISBN:978-4-00-027242-1 Cコード:0336 B6判126ページ 発行:岩波書店 初版年月日: 2021年11月26日

-

絵はがきにされた少年 新版
¥730
【中古 状態きれい】 (参考:定価1,700円+税) ☆店長のひと言 「今じゃアフリカを次の金脈としか見ていない人の多さよ。」 紹介 内戦中のスーダンで撮影した「ハゲワシと少女」でピュリッツァー賞を受賞、 その直後に自殺したカメラマン。ルワンダ大虐殺を生き延びた老人の孤独。 アパルトヘイトの終わりを告げる暴動。紛争の資金源となるダイヤモンド取引の闇商人……。 新聞社の特派員として取材をつづける中で、著者は先入観をくずされ、 アフリカに生きる人々、賢者たちに魅せられていく。 アフリカ―遠い地平の人々が語る11の物語。 第三回開高健ノンフィクション賞受賞作品 目次 第一部 奇妙な国へようこそ 1 あるカメラマンの死 2 どうして僕たち歩いてるの 3 噓と謝罪と、たったひとりの物語 4 何かを所有するリスク 第二部 語られない言葉 1 絵はがきにされた少年 2 老鉱夫の勲章 3 混血とダイヤモンド 4 語らない人、語られない歴史 第三部 砂のよう、風のように 1 ゲバラが植えつけた種 2 「お前は自分のことしか考えていない」 3 ガブリエル老の孤独 文庫版(二〇一〇年)あとがき あとがきにかえて 引用文献 ISBN:978-4-434-28068-9 Cコード:0095 四六判276ページ 発行:柏艪舎 発売:株式会社星雲社 初版年月日: 2020年10月30日

-

オタクを武器に生きていく (14歳の世渡り術)
¥990
【中古 状態きれい】 (参考:定価1,420円+税) ☆店長のひと言 「オタクっていうのは専門家の卵なんすよ。(あとは殻を破れるかどうか)」 内容紹介 好きを活かして活躍できる人・できない人って具体的に何が違うの? 日本一のオタクアナウンサーである著者が、アニメ業界・動画配信等で活躍する方々と徹底討論し、その要件をまとめました。 〈目次〉 まえがき 「がんばれ」って書いてある攻略本ってムカつきませんか? 第1章 オタクの時代! ■オタクの時代、到来 ■クラスにはオタクとギャルしかいない説 ■ジャンルは何だっていい! ■ネガティブイメージからの変遷 ■オタクが必要とされる時代へ ■ワクワクする人生を送るために、オタクであれ ■好きを仕事にできる人は一握り問題 ■「オタクを武器に生きていく」の定義と4つの仮説 【定義】「オタクを武器に生きていく」とは? 【仮説1】「そんなことどうでもいいでしょ」……は無視したほうがいい? 【仮説2】「この道一筋!」……じゃないほうがいい? 【仮説3】「労働=つらいことのガマン代」……ではない? 【仮説4】「将来、何になりたい?」……は考えないほうがいい? ■ひとつだけ、ほぼ確実なのは「アテンプト」 第2章 オタク人生相談! 先輩たちに聞いてみた ■「感情を考えること」を武器にする ―夢を叶えたオタク・竹達彩奈さん(声優) ■「アマチュア感覚」を武器にする ―会社員でオタク・高橋祐馬さん(アニメプロデューサー) ■「掛け合わせ」を武器にする ―意外性のありすぎるオタク・けいたんさん(ダンサー・配信者・経営者) ■友だちがいなくても、好きが仕事にならなくても、オタクは最強 ―次世代オタク・尾原和啓さん(IT批評家) 第3章 オタクを武器に生きていくための攻略法 ■仮説検証タイム ■「オタクの魂」とは、あなたの才能である 【見つけ方①】「自分だけが気にしていること」が才能 【見つけ方②】「世の中を変えたい」と思ったら才能 【見つけ方③】「なりたい」「やりたい」と思ったら、それはもう才能 オタクの魂が武器になる瞬間 ■「大人の技術」を4つに分類する 【技術①】まず決断、そして行動 【技術②】柔軟さを保つ 【技術③】掛け算を待つ 【技術④】仲間を増やす ■それでも自信がない人へ あとがき (河出書房新社ホームページより引用) 著者プロフィール 吉田 尚記 (ヨシダ ヒサノリ) (著/文) ニッポン放送アナウンサー。2012年第四九回ギャラクシー賞DJパーソナリティ賞。「マンガ大賞」発起人。マンガ、アニメ、アイドル関係等に精通。著書に『なぜ、この人と話をすると楽になるのか』(太田出版)等 ISBN:978-4-309-61744-2 Cコード:0395 四六判208ページ 発行:河出書房新社
-

脱・筋トレ思考
¥1,980
☆店長のひと言 「おい俺の筋肉、これでいいのかい!?」 ★紹介記事 https://ikiruba.hateblo.jp/entry/2022/06/24/172815 紹介 ハイパフォーマンスを生む「しなやかさ」 筋トレ思考(=勝利至上主義、過度な競争主義…)は、 心身の感覚をバラバラにする― 元ラグビー日本代表の著者が、 自身の実感と科学的知見をもとに「学び・スポーツ」の未来を拓く、救いの書。 指導者必読! 教育関係者にオススメ! 現代スポーツには勝利至上主義や商業主義、過度な競争主義がはびこっている。勝利、カネ、ランキング上位といった、目に見えてわかりやすい目的を掲げ、それに向けてシンプルな方法で解決を図る考え方を、本書では「筋トレ主義」と呼ぶ。筋肉さえつければパフォーマンスは高まるという単純思考が、スポーツ界でまことしやかに広がりつつあることに、私は一抹の不安を感じている。(略)本書は、スポーツ界のみならずいつしか社会全体にまで広がり、知らず識らずのうちに内面化しつつある、この「筋トレ主義」を乗り越えるための思索である。??まえがきより 目次 第1章 脱・筋トレ宣言 第2章 筋トレを警戒する人たち 第3章 豊かな感覚世界をめざして 第4章 「引退後」を言葉にする 第5章 感覚世界の見取り図??始原身体知 第6章 感覚世界の見取り図??形態化身体知・洗練化身体知 終章 脱・筋トレ思考 著者プロフィール 平尾 剛 (ヒラオ ツヨシ) (著/文) 1975年大阪府出身。神戸親和女子大学発達教育学部ジュニアスポーツ教育学科教授。同志社大学、三菱自動車工業京都、神戸製鋼コベルコスティーラーズに所属し、1999年第4回ラグビーW杯日本代表に選出。2007年に現役を引退。度重なる怪我がきっかけとなって研究を始める。専門はスポーツ教育学、身体論。著書に『近くて遠いこの身体』(ミシマ社)、『ぼくらの身体修行論』(内田樹氏との共著、朝日文庫)、監修に『たのしいうんどう』(朝日新聞出版)がある。 ISBN 978-4-909394-25-5 四六判 200頁 発行 ミシマ社 書店発売日 2019年8月29日
-

就職と体育会系神話
¥2,640
☆店長のひと言 「就職が人生のゴールかどうか、それはまた別のお話。」 ★ブログ記事 https://iki-blo.blogspot.com/2022/04/blog-post_20.html 内容紹介 体育会系の学生は就職活動で本当に有利なのか――。歴史と統計、そして当事者の語りを読み解きながら、「体育会系神話」の実態とそれを成立させる構造のダイナミズムを描き出し、大学スポーツのゆくえと学生アスリートのキャリアの未来を構想する。 目次 プロローグ 第1章 問題化する「体育会系」のキャリア形成 1 対象としての「体育会系神話」 2 先行研究の検討と本書の研究課題 3 本書の構成 第2章 体育会系就職の現在 1 誰が勝ち、誰が負けているのか 2 体育会系のなかでの勝者は誰か 3 なぜそのような勝敗がみられるのか――諸説の検討 4 体育会系の分化とジェンダー格差 第3章 体育会系神話の起源 1 本章の目的――近代企業が求めた身体とは 2 研究の手続き・進め方――どうすれば有用な身体のイメージを描けるか 3 体育会系神話の起源 4 「体育会系」と「教養系」 5 スーパーエリートとしての体育会系 第4章 体育会系就職の最盛期――一九九〇年代の体育会系就職と企業スポーツ 1 本章の対象と目的 2 事例――インタビュー調査から 3 社会文脈に埋め込まれた企業スポーツと体育会系就職/採用 第5章 日本社会のしくみと体育会系神話 1 本章の目的 2 「体育会系神話」成立の社会学的前提 3 日本社会のしくみを反映する体育会系就職 第6章 体育会系神話のゆくえ 1 大学スポーツのオルタナティブ 2 国際比較から学ぶ 3 日本は体育会系の「自立/自律」をめざす!? エピローグ 参考文献 謝辞 版元から一言 大学新卒就職市場で、まことしやかに語られる「体育会系は就活で有利」という神話。それはいつから成立し、どう変容して現在にいたるのか。そもそも、大学新卒就職市場で体育会系が本当に有利なのか。 まず、現在の体育会系学生のなかで、神話どおりの恩恵に浴しているのは誰なのかを明らかにする。体育会系学生への就職支援を展開する企業の協力のもとに調査をおこない、所属大学やスポーツによる差異、ジェンダー格差について統計的に検証する。 そのうえで、戦前・戦間期に最も売れたビジネス雑誌「実業之日本」の記事をたどりながら、明治末期から昭和初期までの間に大学スポーツへの社会的な評価が高まり、就職に有利にはたらくようになった起源と変容を掘り起こす。 さらに、1990年代に情報系躍進企業に就職し、営業として活躍した元企業アスリートの語りをもとに、揺るがない新卒採用の日本の特殊的慣行と凋落する企業スポーツとの関係のなかで現象していた体育会系就活や採用のリアルを克明に描写する。 企業の雇用実態、企業スポーツの盛衰、大学数の増加とスポーツ推薦枠、社会的・経済的な動向――。「体育会系神話」の実態とそれを成立させる構造のダイナミズムを明らかにして、大学スポーツのゆくえを提示する。 著者プロフィール 束原 文郎 (ツカハラ フミオ) (著) 1977年、東京都生まれ。横浜国立大学教育学部卒業。東京大学大学院教育学研究科単位取得満期退学。博士(スポーツ科学、早稲田大学)。京都先端科学大学健康医療学部准教授。専攻はスポーツを対象にした人文社会科学(スポーツマネジメント、スポーツ産業論、スポーツ文化論、スポーツ社会学など)。共著に『スポーツまちづくりの教科書』(青弓社)、『近代日本を創った身体』(大修館書店)など。 ISBN 978-4-7872-3491-9 C0036 四六判 282頁 発行 青弓社 発売日 2021年7月27日
-

水を縫う
¥1,180
【中古 状態とてもきれい】 (参考:定価1,600円+税) ☆店長のひと言 「ゆく河の流れは絶えずしてしかも元の水にあらず。世間の“当たり前”も。」 内容紹介 松岡清澄、高校一年生。一歳の頃に父と母が離婚し、祖母と、市役所勤めの母と、結婚を控えた姉の水青との四人暮らし。 学校で手芸好きをからかわれ、周囲から浮いている清澄は、かわいいものや華やかな場が苦手な姉のため、ウェディングドレスを手作りすると宣言するが――「みなも」 いつまでも父親になれない夫と離婚し、必死に生きてきたけれど、息子の清澄は扱いづらくなるばかり。そんな時、母が教えてくれた、子育てに大切な「失敗する権利」とは――「愛の泉」ほか全六章。 世の中の〈普通〉を踏み越えていく、清々しい家族小説。 著者プロフィール 寺地はるな(てらち・はるな) 1977年佐賀県生まれ。大阪府在住。会社勤めと主婦業のかたわら小説を書き始め、2014年『ビオレタ』でポプラ社新人賞を受賞しデビュー。『大人は泣かないと思っていた』『正しい愛と理想の息子』『夜が暗いとはかぎらない』『わたしの良い子』『希望のゆくえ』など著書多数。 ISBN 978-4-08-771712-9 四六判 248頁 発行 集英社 書店発売日 2020年5月26日

-

さかなのなみだ
¥950
SOLD OUT
【中古 カバーに破れあり。中身はきれい。】 (参考:定価定価 1,200円+税) ☆店長のひと言 「ギョギョッ…(涙)。」 内容紹介 さかなの世界にもいじめがある。 小さな学校のなかにも。せまい社会のなかにも──。 朝日新聞連載「いじめられている君へ」で紹介され、大反響! 子どもから大人の心までひびく、さかなクンの感動メッセージが絵本になりました。お魚好きの変わり者の少年が、人気者の「さかなクン」になるまでの道のりも紹介。教育の現場で、親子で、みんなで読んで考えたい必読書です。 著者プロフィール さかなクン (サカナクン) (著/文) 東京都出身、千葉県館山市在住。国立大学法人 東京海洋大学名誉博士/客員教授 2010年には絶滅したと思われていたクニマスの生息確認に貢献。 さらに海洋に関する普及・啓発活動の功績が認められ、「海洋立国推進功労者」として内閣総理大臣賞を受賞。 2011年農水省「お魚大使」、2012年文科省「日本ユネスコ国内委員会広報大使」に任命 2014年からは環境省国連生物多様性の10年委員会(UNDB-J)「地球いきもの応援団」生物多様性リーダーを務めています。 映画の原作にもなった単行本「一魚一会」(講談社)、講談社の動く図鑑 MOVE さかな新訂版のコラムの執筆や、 『朝日小学生新聞』にて毎週(土)「おしえてさかなクン」イラストコラムを連載中。 ISBN 978-4-576-07071-1 四六判 32頁 発行 二見書房 書店発売日 2007年5月11日
-

ぼのぼの名言集(上) 今日は風となかよくしてみよう
¥230
【中古 状態きれい】 (参考:定価838円+税) ☆店長のひと言 「かわいい顔してときどきドキッとするをこと言うので困ります。」 紹介 「ぼのぼの」は発表当初より、4コマ漫画でありながら哲学的であると評価され、多くのファンを掴みました。「いぢめる?」「しゅりんくっ」「それはヒミツです」「楽しいことが終わるのは、悲しいことが終わるため」「生き物はこまらない生き方なんか絶対ないんだよ」「さァ~どんどんしまっちゃうからね」などの名言が誕生しました。上巻はタレント東野幸治さんが、作者のいがらしみきおに笑いの視点から特別インタビューをしました。生きることが楽になる珠玉の言葉が本書には、たくさん収録されています。あなたの心にも、ちゃんと届きますように。 目次 第1章 最初にニオイがする次に感じる 第2章 こういう天気だと悩みがない 第3章 あぁ夏なんだなぁ 第4章 欲しいものがあるのはいい 第5章 キミはなにかつまらないの? 特別インタビュー 漫画家いがらしみきお、笑いの世界(インタビュアー・東野幸治) SBN 978-4-8124-9302-1 新書判 256頁 発行 竹書房 初版発行年月 2012年12月
-

ぼのぼの名言集(下) 理由はないけどすごくさびしくなる時がある
¥260
【中古 状態きれい】 (参考:定価838円+税) ☆店長のひと言 「ほのぼのしているようでしていないからぼのぼの説」 紹介 「ぼのぼの」は発表当初より、4コマ漫画でありながら哲学的であると評価され、多くのファンを掴みました。「いぢめる?」「しゅりんくっ」「それはヒミツです」「楽しいことが終わるのは、悲しいことが終わるため」「生き物はこまらない生き方なんか絶対ないんだよ」「さァ~どんどんしまっちゃうからね」などの名言が誕生しました。下巻は哲学者の内山節さんが解説をしました。生きることが楽になる珠玉の言葉が本書にはたくさん収録されています。あなたの心にも、ちゃんと届きますように。 目次 第1章 ボクが気がつくのはもう少し先だ 第2章 なつかしくなる言葉があるんだ 第3章 水はいつもボクにさわっている 第4章 そういう気がするんだね 第5章 ボクはちょっと行くところがある 解説 ぼのぼのの森の哲学について(哲学者・内山節) 著者プロフィール いがらしみきお (イガラシミキオ) (著/文) 1955年生まれ。宮城県出身。漫画家。主な作品に『I』『羊の木』『ぼのぼの』など多数。 ISBN 978-4-8124-9303-8 新書判 256頁 発行 竹書房 初版発行年月 2012年12月
-

ぶっちゃけ、誰が国を動かしているのか教えてください
¥1,760
☆店長のひと言 「選挙で一票入れる前に、この1冊をカートに入れてください!!」 ★ブログ記事 https://ikiruba.hateblo.jp/entry/2022/06/22/124203 内容紹介 「よくわからないけどダメそう」な日本の政治について、気鋭の若き社会学者と考える。生まれたときから当たり前のようにあるけれど、正体はよくわからない「民主主義」や「自由」の価値と意味。 目次 はじめに 講義1 ところで、国は誰が動かしているんですか? 講義2 自由民主主義は誰が選んだんですか? 講義3 ちなみに、自由ってなんですか? 講義4 メディアと政治の本当のはなし 講義5 私たちは政治にどうコミットしていくのか 政治や自由、メディアについて学びたい人のためのブックガイド おわりに 著者プロフィール 西田亮介(にしだ りょうすけ) 東京工業大学リベラルアーツ研究教育院准教授。1983年京都生まれ。専門は社会学。博士(政策・メディア)。慶應義塾大学総合政策学部卒業。同大学院政策・メディア研究科修士課程修了。同後期博士課程単位取得退学。同助教(有期・研究奨励II)、独立行政法人中小企業基盤整備機構リサーチャー、立命館大学大学院特別招聘准教授などを経て現職。 著書に『コロナ危機の社会学 感染したのはウイルスか、不安か』(朝日新聞出版)、『不寛容の本質 なぜ若者を理解できないのか、なぜ年長者を許せないのか』(経済界)、『メディアと自民党』(角川新書、2016年度社会情報学会優秀文献賞)、『なぜ政治はわかりにくいのか:社会と民主主義をとらえなおす』(春秋社)などがある。 ISBN 978-4-534-05916-1 四六判 発行 日本実業出版社 発売日 2022年3月25日

-

「隔離」という病い : 近代日本の医療空間
¥680
【中古 カバーに少し傷みあり 帯無し】 (参考:定価1,456円+税) ☆店長のひと言 「私はこの文庫版を生涯の一冊として持っています。人が本当に恐れるのは病か、それとも。」 内容紹介 強制収容、恐怖の宣伝、終身隔離。なぜ、ハンセン病患者への過酷な差別は、現代まで続いたのか?なぜ、近代の医療空間は、これほど歪められたのか?O‐157、エイズを含め、日本社会の「病い」観を問いなおす。 目次 序章 終わりからはじめること 第1章 近代国家であるために 第2章 隔離という病いをめぐって 第3章 「奇妙な国」の論理 第4章 「牧人」の系譜学 第5章 生きがい論の陥穽 第6章 ユートピアの枠 終章 そして、都市へ 著者プロフィール 武田 徹 (タケダトオル) (著/文) 1958年生まれ。ジャーナリスト、評論家、専修大学文学部教授。国際基督教大学大学院比較文化研究科博士課程修了。著書に『流行人類学クロニクル』(サントリー学芸賞受賞)、『「隔離」という病い』『偽満州国論』『「核」論』『戦争報道』『原発報道とメディア』『暴力的風景論』『日本語とジャーナリズム』『なぜアマゾンは1円で本が売れるのか』『日本ノンフィクション史』など。 ISBN 978-4-06-258109-7 254頁 発行 講談社 初版発行年月 1997年7月

-

自分で始めた人たち
¥1,870
☆店長のひと言 「批判や批評に終わらない、一歩前に進むために。」 内容紹介 民主主義は私たち一人ひとりの暮らしの中にある。元・クローズアップ現代の国谷裕子を含め、9人との対話で政治学を学び直す本。 はじめに 1章 ボランティアから始めたひと 2章 データで社会を変える人たち 3章 自治体と一緒に始めた人たち 4章 温故知新で地元をアップデートする人たち 5章 目の前の一人を幸せにして社会を変える人 6章 女性の視点から社会を変えていく人たち 座談会 これからの民主主義を考える あとがき 著者紹介 東京大学卒業。東京大学大学院法学政治学研究科博士課程修了。 博士(法学)。千葉大学法経学部助教授、東京大学社会科学研究所助教授、同准教授を経て2011年4月より現職。その間に、フランス社会科学高等研究院、コーネル大学ロースクールで客員研究員を務める。 主な著作に『政治哲学へ 現代フランスとの対話』(渋沢・クローデル賞LV特別賞、東京大学出版会)、『トクヴィル 平等と不平等の理論家』(サントリー学芸賞、講談社学術文庫)、『<私>時代のデモクラシー』(岩波新書)、『民主主義のつくり方』(筑摩選書)、『西洋政治思想史』(有斐閣アルマ)、『保守主義とは何か』(中公新書)、『未来をはじめる「一緒にいること」の政治学』(東京大学出版会)、『民主主義とは何か』(講談社現代新書、近刊)などがある。 (アカデミーヒルズHPより抜粋) ISBN 978-4-479-39382-5 四六判 280頁 発行 大和書房 発売日 2022年2月17日
-

ほぐほぐマムアンちゃん
¥1,650
☆店長のひと言 「まじほぐれます」 紹介 こころが沈んでどうしようもないとき。悩みのループから抜け出せないとき。傷ついて立ち直れないとき。気持ちの落ち込みが激しいとき。 14の悩みに、タムくんが答えました。傷ついたあなたによりそい、自分にはなかった視点をもらえる、マムアンちゃんの姿に励まされる。 タイ語でマンゴーはマムアン。髪型がマンゴーの形だからマムアンちゃん。 落ち込んだら、ほぐほぐされよう。 著者プロフィール ウィスット=ポンニミット タムくんという愛称で知られるマンガ家・アーティスト。日本のマンガに熱中した少年時代を経て、神戸の日本語学校に留学。 星野源、くるり、細野晴臣ほか、ミュージシャンとコラボレーションするなど多方面で活躍中。ホームレスの人の社会的自立を応援する雑誌「ビッグイシュー日本版」に長年四コママンガを連載。マムアンちゃんのイラストにメッセージを添えた「ひとこと」が人気を博す。 インスタグラムのフォロワーは約17 万人。タイのバンコク在住。 (岩波書店HPより転載) ISBN 978-4-265-85177-5 B5変型判 64頁 発行 岩崎書店 発売日 2020年11月5日

-

娘に語るお父さんの戦記 小さな天国の話(新装版)
¥891
☆店長のひと言 「妖怪だけやあらしません。」 内容紹介 21歳で南方へ出征した著者は、片腕を失い、マラリアに苦しみながらも、自然と共に暮らすラバウルの先住民たちと出会い、過酷な戦場を生き延びる。子どもたちに向けたありのままの戦争の記録。 著者 水木 しげる (ミズキ シゲル) 1922年生まれ、鳥取県境港市出身。21歳で南方出征。『テレビくん』で講談社児童まんが賞受賞。代表作に『ゲゲゲの鬼太郎』『悪魔くん』など多数。紫綬褒章、旭日小受章受賞。文化功労者。2015年没。 (河出書房新社HPより抜粋) ISBN 978-4-309-41906-0 文庫判 280頁 発行 河出書房新社 発売日 2022年7月21日
-

新・失敗学 正解をつくり出す技術
¥1,870
☆店長のひと言 「これ買って失敗もいいのでは?」 ★ブログ記事 https://ikiruba.hateblo.jp/entry/2022/07/03/170532 紹介 「決められた正解を素早く出す」ことが優秀な人とされた時代から「自ら正解をつくる」ことができる人の時代へ。 「自ら正解をつくり出す時代」の思考の技術。 近年の日本の地盤沈下の背景には、すでに世界が「正解がない時代」になってるにもかかわらず、いまだに日本では「決められた正解を素早く出すことが優秀な人の条件」とされていることにある。これらは変わらない偏差値信仰、近年の官僚・みずほ銀行などのエリート組織の躓きを見ても明らか。 「正解がない時代」とは「正解がいくつもある時代」のこと。そのためには自分たちで正解をつくっていく必要がある。そして自分たちで正解をつくるとは、仮説ー実行ー検証を回していくことにほかならない。 この過程で必ず付いてくるのが失敗。いままで避けがちだった失敗とどのように向き合い、どのように糧としてしゃぶりつくすのか、そこがこれからの時代の成否を分ける。 そのためのポイントを丁寧に解説、これから私たちが身につけるべき思考法を明らかにする。 第1章 正解がない時代の人材とは 第2章 すべては仮説から始まる 第3章 失敗を捉えなおす 第4章 仮説の基礎をつくる 第5章 仮説をつくる三つのポイント 第6章 仮説を実行する 著者紹介 畑村 洋太郎(ハタムラ ヨウタロウ) 1941年生まれ。東京大学工学部機械工学科修士課程修了。東京大学名誉教授。工学博士。専門は失敗学、創造的設計論、知能化加工学、ナノ・マイクロ加工学。2001年より畑村創造工学研究所を主宰。02年にNPO法人「失敗学会」、07年に「危険学プロジェクト」を立ち上げる。日本航空安全アドバイザリーグループ委員、JR西日本安全有識者会議委員、国土交通省リコールの原因調査・分析検討委員会委員長、11年6月より東京電力福島第一原子力発電所における事故調査・検証委員会委員長などを務める。著者に『失敗学のすすめ』『創造学のすすめ』『みる わかる 伝える』『危険不可視社会』(以上講談社)、『直観でわかる数学』『技術の創造と設計』(以上岩波書店)、『数に強くなる』(岩波新書)、『畑村式「わかる」技術』『回復力』『未曾有と想定外』『技術大国幻想の終わり』(以上、講談社現代新書)など多数。 ISBN 978-4-06-528213-7 四六判 248頁 発行 講談社 発売日 2022年5月18日