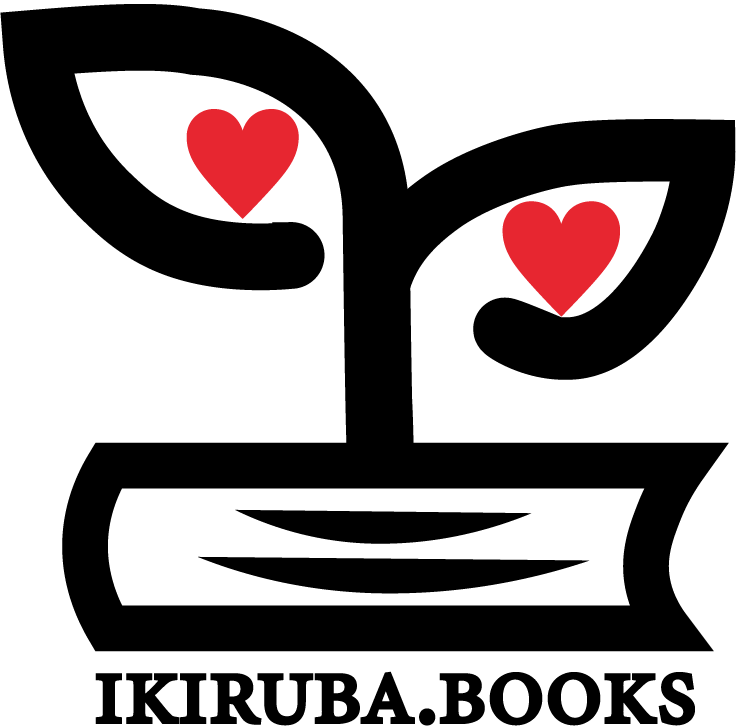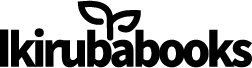-

ビッグイシュー504号
¥500
☆店長のひと言 「食べ物で人を元気にできる人は、ほぼ神様。」 【内容紹介】 特集 喜びと誇り、枝元なほみを偲ぶ 今年2月27日にご逝去された、料理研究家の枝元なほみさん。 ビッグイシューの誌面ではもちろん、認定 NPO 法人ビッグイシュー基金の共同代表、また、日本の食や農業を考えリードする人として社会的にも活躍されました。 雑誌では創刊1年後、12号特集(2004.9.1)での初インタビューをきっかけに、17号(2004.11.15)から120回連載の「枝元なほみのスローシンプルフード」が始まり、販売者とのコラボ連載「世界一あたたかい人生レシピ」も250回を超え(単行本2冊発行)、さらにコロナの禍中には「大人食堂」「夜のパン屋さん」を立ち上げ、全力を注ぎました。 そんな枝元さんの軌跡の一端として、連載「スローシンプルフード」から9編のエッセイほかを再掲。枝元さんとともに活動された仲間「チームむかご」「日本の種子(たね)を守る会」「夜のパン屋さん」のみなさんへのインタビュー、そして枝元さんの親友である詩人の伊藤比呂美さんにご寄稿いただきました。 TOP INTERVIEW スペシャルインタビュー デミ・ムーア 90年代、『ゴースト/ニューヨークの幻』などで、ヒット作を牽引する存在となった、俳優のデミ・ムーア。キャリアの中盤は不振に見舞われ、アイダホ州で静かな生活を送った後、2019年に赤裸々な回顧録『インサイド・アウト』でカムバックしました。62歳となった今、身体的な恐怖体験を描き、新時代の映画として話題を集めるボディ・ホラー『サブスタンス』に出演。ルッキズムや男性支配社会などをテーマにした本作への思いを語ります。 リレーインタビュー・私の分岐点書評家、ライター 杉江松恋さん 会社員の傍ら、ミステリー書評を書いた 誰も気づいていない分野を開拓したい 国際記事 英国 木工技術ワークショップで困窮者の仕事作り 産業革命発祥の地であり、かつて毛織物や鉄鋼業で栄えたイングランド北部の街。 しかし時代の移り変わりとともに産業は衰退し、失業率が高止まりして生活困窮者が増える一方、家賃高騰で荒廃した空き家が目立ちます。そこで自立支援団体「ハンドクラフテッド」は、社会的に孤立した人々を対象に、木工技術習得のためのワークショップを開いています。 連載記事 原発ウォッチ 4 月28 日、イベリア半島で停電 浜矩子の新ストリート・エコノミクス コンクラーベの授けもの 雨宮処凛の活動日誌 必見!! 映画『選挙と鬱』水道橋博士の立候補から辞任まで 読者のページ My Opinion 販売者に会いにゆく カナダ『メガフォン』リチャード・ヤング 監督インタビュー 『デリカド』カール・マルクーナス監督 販売者主宰「歩こう会」150 回記念 ゴトゴト走る路面電車に乗って FROM EDITORIAL 編集後記 (ビッグイシュー日本HPより抜粋)
-

ビッグイシュー482号
¥450
☆店長のひと言 「もう誰かに期待して投票するより、自ら議員になるほうが現実的な時代かも。」 【内容紹介】 特集 “選挙”の季節に 2024年は、世界各国でリーダーや議会の選挙が多数ある選挙イヤー。日本では、政治のジェンダーギャップが大きく(女性議員の数が少ない)、選挙に立候補できる年齢が高く(英国、フランス、韓国などは18歳以上)、低い投票率も問題になっています。その一方で、女性や若い世代が新しい選挙活動を始めています。 22年、若者の代弁者として20、30代の女性の地方議員を増やしたいと活動を始めた『FIFTYS PROJECT』は、23年に27人が当選。代表の能條桃子さん、長野県富士見町議会議員に当選した西明子さんに話を聞きました。 23年7月、10代、20代の若者たち6人が原告となった「立候補年齢引き下げ訴訟」は、現在係争中です。原告の能條さん、久保遼さん、中村涼香さんにインタビュー。 20年、弁護士で2児の母親の川久保皆実さんは、仕事や育児を犠牲にしないなどの「三ない原則」をかかげ、新しい選挙運動を行って、つくば市議会議員に当選。そんな川久保さんに取材しました。 TOP INTERVIEW スペシャルインタビュー ジュリアン・ムーア 若年性アルツハイマーを患う主人公を演じた『アリスのままで』(’14)により、アカデミー賞主演女優賞を受賞。その他、世界三大映画祭のすべてで女優賞を獲得するなど、現代を代表する俳優として知られるジュリアン・ムーア。今回、実在のスキャンダルをモチーフに制作された新作映画『メイ・ディセンバー ゆれる真実』で難役に挑んだ経験を語ります。 リレーインタビュー・私の分岐点元水泳日本代表 萩原智子さん 元水泳日本代表の萩原智子さん。2000年にシドニー五輪に出場し入賞。02 年日本選手権では、史上初の4冠を達成。04年に現役を引退するも、09年に現役復帰宣言。11年には婦人科疾患を患い手術し、復帰後、短水路日本記録をマーク。12年に再び引退し、最近では教育分野にも活躍の場を広げています。そんな萩原さんは小学6年生の時まで、当時170cmあった身長がコンプレックスだったと言います。コンプレックスが消えるきっかけとなった、スイミングスクールでのスピーチとは? 国際記事 WORLD STREET NEWS 世界短信 国内記事 探査(Tansa)レポート❹ 岡山県吉備中央町のPFOA検出、“ごまかし”説明 連載記事 原発ウォッチ 原発再稼働でも電気料金は安くならない 浜矩子の新ストリート・エコノミクス フランス、前代未聞のコアビタシオン突入か 雨宮処凛の活動日誌 ガザの悲劇に対して世界で上がる声 ホームレス人生相談 × 枝元なほみの悩みに効く料理 父との会話の糸口が見つかりません ☆ ナスの蒲焼丼 移動スーパーとくし丸、喜びや生きがい届けていきたい 2012年2月に徳島県で最初の1台が走り始めた「移動スーパー とくし丸」。食品や日用品、そして買い物をする喜びを“買い物困難者”へ届け続け、24年4月には47都道府県で約1200台が走るまでになりました。前回(本誌257号)の取材から9年。現在のとくし丸について、創業者で取締役の住友達也さんに聞きました。 読者のページ My Opinion 販売者に会いにゆく 『ビッグイシュー・オーストラリア版』ホリー 表現する人 瀬戸優さん。今にも動き出しそう、呼吸していそうな動物彫刻 FROM EDITORIAL 編集後記 (ビッグイシュー日本HPより抜粋)
-

ビッグイシュー481号
¥450
SOLD OUT
☆店長のひと言 「軒先にいすを置くだけでオープンな雰囲気になるから不思議。」 【内容紹介】 特集 まちに座る まち歩きで疲れたら、少し休んだり、風景や道行く人を眺めたり、どこかに座りたくなりませんか? すると、目線が低くなり、まちと世界の景色が一変します。そんな“まちに座る”ことを楽しむ人たちが増えつつあります。 ビールケースを使った「置きベン」で、立ち寄った人と対話する「対話之町京都ヲ目指ス上京」、高齢者がまちを歩く時の“歩き継ぎ”のため、自作のベンチを設置する「とまり木休憩所・おでかけベンチ協働プロジェクト」(京都)、人々の思い出のある椅子をワークショップで赤色に塗り、まちに配置する「赤い椅子プロジェクト」(東京・吉祥寺)、大阪の「赤いベンチプロジェクト」、モバイルこたつを片手に、まちのすき間でこたつを楽しむ「流しのこたつ」(大阪)。そして、元は室内用の椅子を野外に置いて活用する「野良イス」をウォッチする人Mr.tsubakingさん。 公共空間の楽しみ方を追求している笹尾和宏さんからは、“まちに座る”を楽しむエッセイが届きました。 TOP INTERVIEW スペシャルインタビュー スペシャル企画:エイミー・ワインハウスが遺したもの ソウルミュージック屈指の名盤として知られる『Back to Black』を2006年に発表、世界中で大反響を巻き起こしながら、11年に27歳の若さで急逝した英国のシンガーソングライター、エイミー・ワインハウス。彼女は生前、依存症であることを公表し、その闘いを歌詞にも綴ったことで知られています。 そんな彼女の思いを引き継ぎ、16年に設立された「エイミーズ・プレイス」は、薬物依存症と闘う若い女性たちに支援付き住宅を提供、エイミーの“特別な遺産”として存在しています。 リレーインタビュー・私の分岐点柔道家 山口香さん コロナ禍、立ち止まって考えた東京五輪 スポーツは"平和な日常”あってこそ 国際記事 WORLD STREET NEWS 世界短信 国内記事 探査(Tansa)レポート❸ 岡山吉備、水道水から28倍のPFOA検出 ふくしまから ALPS処理汚染水の海洋放出から9ヵ月 連載記事 浜矩子の新ストリート・エコノミクス 「委」と「移」では大違い コミック マムアンちゃん ウィスット・ポンニミット ホームレス人生相談 × 枝元なほみの悩みに効く料理 思い出が詰まった手紙を処分できません ☆ 豆のサラダ ☆ 宇宙・地球・人間 池内了の市民科学メガネ ほんわか ほっこり入浴剤 読者のページ My Opinion 販売者に会いにゆく セルビア『リツェウリツェ』ゴゴフ FROM EDITORIAL 編集後記 (ビッグイシュー日本HPより抜粋)
-

町を住みこなす 超高齢社会の居場所づくり
¥350
【中古 状態きれい】 (参考:定価800円+税) ☆店長のひと言 「超高齢化は会議室で起きてるんじゃない。我が家で起きているんだ!」 紹介 人口減少社会における居住は、個人にも、地域にも、社会にも今や大問題。人びとが住まいに求めるものは、プライバシーであったり、近所づきあいだったり、長い人生のステージに合わせて、さまざまに変遷していくことに注目。懐の深い、居場所づくりのユニークな事例を多数紹介し、これからの住まいのあり方を考える。 目次 第1章 時間-人生のスパンで住宅を考える 町が住みこなせない 町の生態学 町の機能の多様化 第2章 家族-十家族十色の暮らし方 住まい方は家族それぞれ 近居の力 町の多様性が近居を可能にする 第3章 引越し-「Gターン」がつくる生活の薬箱 住み替えとゆるい定住 同じ町の中で移り住むこと-Gターン 町が「地元」になること) 第4章 居場所-町のあちこちに主感のある場を 仮設住宅から学ぶ 遠くの親戚よりも近くの他人 「町の居場所」はどこに? 第5章 町を居場所にするために-居場所で住まいと町をつなぐ 超高齢社会に求められる町とは 時間-町をゆっくりと成長させる 家族-多様な住宅を混ぜる 引越し-町の住宅双六を 居場所-近隣に頼るきっかけの場づくり) 著者プロフィール 大月 敏雄 (オオツキ トシオ) 東京大学准教授。 1991年、東京大学工学部建築学科卒業。1996年、同大学大学院工学系研究科博士課程単位取得退学。横浜国立大学工学部建設学科助手。博士(工学)取得。2003年、東京理科大学工学部建築学科助教授を経て、現職に。主な著書に、『集合住宅の時間』(王国社)、『消えゆく同潤会アパートメント』(共編著、河出書房新社)、『2030年超高齢未来』(共著、東洋経済新報社)、『現代住宅研究の変遷と展望』(共著、丸善)など。 ISBN:978-4-00-431671-8 241ページ 発行:岩波書店 初版年月日: 2017年7月28日
-

ビッグイシュー468号
¥450
☆店長のひと言 「もはやブームになりつつある廃屋DIYなんですけど、、、大規模改修は地域の大工さんに依頼して欲しいです。」 【内容紹介】 特集 廃屋DIY いま、空き家は日本全国でおよそ846万戸以上。しかも、壁が崩れ、床が抜けたような「廃屋」が増えつつあり、これから日本は〝世界一の空き家大国〟になるとも言われている。 そんな中、廃屋をDIYで改修することで、魅力的な住まいや居場所に変える人々がいる。 西村周治さん(合同会社「廃屋」代表)は、神戸でボロボロの空き家を次々再生。梅元町では改修した空き家9軒からなる新しいコミュニティ「バイソン」を誕生させた。 フクイアサトさん(「いなか暮らしラボ古今集」代表)は、滋賀県高島市で崩れかけた古民家をDIYで何軒も改修。蓄積したノウハウを『空き家改修の教科書』として発表した。 空き家の使い道は、住宅に限らず、地域の共同スペースや店舗や作業場など無限大。住居費を下げるだけでなく、仲間たちとの出会い、新しいコミュニティも生まれる。 そんな空き家を近隣社会の資源に変えるDIYについて、西村さん、フクイさんに聞いた。 TOP INTERVIEW スペシャルインタビュー 趣里 2011年に俳優デビューしてから12年。NHK朝の連続テレビ小説「ブギウギ」の主演など、活躍著しい趣里さん。さらに11月からWOWOW で放送中のドラマ「東京貧困女子。―貧困なんて他人事だと思ってた―」では、女性たちの貧困に向き合う経済誌編集者を演じています。役作りを通じての思いを聞きました。 リレーインタビュー・私の分岐点Leolaさん 大自然の中で触れた音楽が私の原点。 熊本震災、地元の人たちに逆に励まされた 国際記事 英国。「写真ライブラリー」ホームレス状態の人々と愛犬 犬を飼っているホームレス状態にある人々への否定的なメッセージを取り払うために、英国の「センター・フォー・ホームレスネス・インパクト」と「ドッグ・トラスト」がパートナーシップを組み、彼らと愛犬のいきいきした姿を捉える写真ライブラリーを開設しました。時として“ライフライン”にもなりえる仲間である、ペットとの絆がもたらす効果とは? WORLD STREET NEWS 世界短信 国内記事 夜のパン屋さん3周年 いろいろな人が混ざってつながっていく場 表現する人:野田朗子さん ゆらぎや物語性、今を閉じ込めるガラス 連載記事 原発ウォッチ 福島第一原発、ALPS で5 人が被曝事故 浜矩子の新ストリート・エコノミクス 政治家に必要な御用聞き精神 雨宮処凛の活動日誌 「FREE FREE PALESTINE!」イスラエル大使館前に響く声 ホームレス人生相談 × 枝元なほみの悩みに効く料理 人生を消耗戦のように感じます ☆ ごぼうフライ ☆ ビッグイシューアイ 地球を救うサボテン。何重にも乾燥に耐えるしくみ 読者のページ My Opinion 販売者に会いにゆく ブラジル『トラソス』ミカエラ・ナザーリオ FROM EDITORIAL 編集後記 (ビッグイシュー日本HPより抜粋)
-

建築史的モンダイ
¥330
【中古 表紙に小さな角折れあり】 (参考:定価800円+税) ☆店長のひと言 「次に家を建てることがあったら、インテリア雑誌じゃなく歴史本から学んで建てようと思います。(ないけど)」 この本の内容 近代建築史研究一筋だった著者が中世ヨーロッパ建築、さらに初期キリスト教建築、新石器時代の建築へと歴史を遡るうちに気付いたのは、建築の発祥という大問題だった。何が始まりだろうか?住まいか?それとも神殿か?そもそも建築とは何をもって建築というのだろうか?長い長い年月を経て、石や穴だけとなった遺跡を訪ね、その遺跡のもらすつぶやきに耳をすませて見えてきたものとは?建築の起源、和洋の違い、日本独自の建築の歩み…「建築」にまつわる疑問を縦横無尽に解き明かす。 この本の目次 1 建築とは何だ??(建築と住まいの違いとは? 住まいの原型を考える ほか) 2 和洋の深い溝(和と洋、建築スタイルの根本的違い 教会は丸いのだ ほか) 3 ニッポンの建築(日本のモクゾウ 焼いて作る!?建築 ほか) 4 発明と工夫(ローマ人の偉大な発明 ガラスは「石」でありえるか? ほか) (筑摩書房HPより引用) 著者プロフィール 藤森 照信 (フジモリテルノブ) (著/文) 一九四六年長野県生まれ。東京大学大学院博士課程修了。近代建築、都市史研究の第一人者として活躍。東京大学名誉教授。八六年、赤瀬川原平氏、南伸坊氏らと路上観察学会を結成。自邸や赤瀬川氏邸のほか、神長官守矢史料館など独創的な建築も手がける。「ラ コリーナ近江八幡 草屋根」で日本芸術院賞受賞。著書に『藤森照信作品集』『茶室学講義』『藤森照信 現代住宅探訪記』など。 ISBN 978-4-480-06429-5 新書判 240頁 発行 筑摩書房 発売日 2008年9月1日
-

京都の「違和感」
¥1,050
【中古 状態きれい】 (参考:定価1,500円+税) ☆店長のひと言 「ま、観光客が一番違和感ありますけどねっ!」 内容紹介 〈京都ってなんかヘン!? 不動産鑑定士の視点から紐解く京都の不思議〉 〈観光客が感じた京都の「違和感」、たっぷりご紹介します!〉 東京在住の不動産鑑定士でもある著者が、京都を度々おとずれるなかで感じた素朴な疑問をあきらかにした謎解き読本。不動産鑑定士という独自の視点から、地図や図版・イラストを用いて京都の地理や街の特徴を分析し、祇園祭や花街などの文化を歴史から紐解いたり、日常的な京都の風景を地勢から読み解きます。京都に行ったことがない人から京都好きな人まで楽しく読める、観光客しか感じない京都の不思議な当たり前がわかる一書です。 著者プロフィール 杉本幸雄 (スギモトユキオ) (著/文) 不動産鑑定士 ISBN 978-4-473-04262-0 四六判 256頁 発行 淡交社 発売日 2018年8月31日
-

ジブリの立体建造物展 図録<復刻版>
¥2,970
☆店長のひと言 「まともな人にはこんなの描けないです。(偏見)」 紹介 2014~2018年にかけて開催された人気展覧会 「ジブリの立体建造物展」の図録が復刊! 『風の谷のナウシカ』から『思い出のマーニー』まで―― ジブリ作品に登場する、どこかに存在していそうな架空の建造物。その印象的な建物に注目し、展覧会の監修を務めた建築家・藤森照信氏による詳細解説、宮崎駿監督の文章と共に、設計の源に触れる一冊。 背景画、イメージボード、美術設定など約380点の図版を収録! ISBN 978-4-908406-92-8 A4変型判 192頁 発行 トゥーヴァージンズ 発売日 2021年11月18日
-

これからの建築
¥1,980
☆店長のひと言 「人口が減っていく時代に建築がどうあるべきか。」 紹介 街、ターミナル、学校、橋、ライブ空間、高層建築… 過去と未来をつなぐ、豊かな空間。 その手がかりを全力で探る! 「つくる」ことに意欲のあるすべての人へ 建築を語っているのではない。この本では建築が語っている。 ―いとうせいこう氏 「建築とは」と書かれると引いたり怯んだりしてしまうのだけれど、この本を読んで「建築」は社会や文化や誰かの人生や日々の生活や、その一つひとつの比喩でもあるんだということがよくわかりました。 ―後藤正文氏(ASIAN KUNG-FU GENERATION ) ミシマ社創業10周年記念企画 建築の希望を見つけるべく、さまざまなテーマで「これからの建築」について考えた文章をここに書いていく。同時に、スケッチを描くつもりだ。そうした文章やスケッチの断片が空間に宿った建築の意志を発見し、ひとりの建築家としてのマニフェストになるのではないか。そんな想いを胸に、筆を進めてみたい。―プロローグより 目次 プロローグ 建築家として働くこと 第一話 大工の言葉 第二話 街の見た目 第三話 蔵としての家 エッセイ① 音楽のある部屋 第四話 空間のなかの移動 第五話 芸術の文脈と身近さ 第六話 地域に開く学校 エッセイ② 風景と対話するスケッチ 第七話 人々が行き交う場所 第八話 高層建築の新しい挑戦 第九話 世界を結界する橋 エッセイ③ 軸線の先にある象徴的な建築 第十話 広い芝生とスポーツの巨大建築 第十一話 総合芸術としてのライブ空間 エピローグ 生命力のある建築 著者プロフィール 光嶋裕介 (コウシマ ユウスケ) (著) 建築家。一級建築士。1979 年、アメリカ、ニュージャージー州生まれ。8 歳までアメリカで育ち、中学卒業まで日本とカナダ、イギリスで過ごす。1995 年、単身帰国し、早稲田大学本庄高等学院に入学。2002 年、早稲田大学理工学部建築学科を卒業し、大学院は石山修武研究室へ。2004 年、大学院修了とともにドイツの建築設計事務所で働き、ベルリンで暮らす。2008 年に帰国し、光嶋裕介建築設計事務所を開設。2010 年、思想家の内田樹氏の自宅兼道場(合気道)の設計を依頼され、翌2011 年、建築家としての処女作、《凱風館(がいふうかん)》を神戸に完成。SDレビュー2011 に入選。主な作品に《レッドブル・ジャパン・本社オフィス(青山、2012)》、《如風庵(六甲、2014)》、《旅人庵(京都、2015)》など。著書に『みんなの家。〜建築家一年生の初仕事』(アルテスパブリッシング)、『建築武者修行〜放課後のベルリン』(イースト・プレス)など多数。2012 〜 15 年まで、首都大学東京にて助教をつとめ、現在は神戸大学にて、客員准教授。 ISBN 978-4-903908-82-3 四六判 248頁 発行 ミシマ社 発売日 2016年9月17日
-

時代劇聖地巡礼
¥1,980
☆店長のひと言 「この本片手に旅に出るのも良さそう。」 ★ブログ記事 https://iki-blo.blogspot.com/2022/04/blog-post_16.html 紹介 あの江戸の景色は京都にあり。 時代劇研究家が京都・滋賀のロケ地41カ所を実際に巡り、うなり、歓喜し、記した文と写真。 ・「彦根城」は、「江戸城」「赤穂城(忠臣蔵)」「岐阜城(信長のシェフ)」などに変身 ・『鬼平犯科帳』のオープニング・タイトルバックは「下鴨神社」 ・「妙心寺」は『八丁堀の七人』『壬生義士伝』大河ドラマ『新選組!』などで、武家屋敷や寺町に変化…etc. 本書は、少しでも時代劇をご覧になった方なら「あ、ここ、時代劇で見た場所だ!」と思えるような、京都とその周辺のロケ地の数々を皆さまにご紹介。お馴染みの観光地から、何気なく通り過ぎてきた場所まで、「時代劇のロケ地」という切り口を差し込むだけで、「江戸の景色」に変貌するのです。(序章より抜粋) 現代にいながら時代劇の世界へトリップ! 時代劇ファン垂涎の一冊。 目次 はじめに 序章 なぜ京都なのか? MAP1〜4 初日 下鴨神社→上賀茂神社→青蓮院→南禅寺→伏見稲荷大社→中ノ島橋(嵐山) 2日目 流れ橋→長岡天満宮(錦水亭)→光明寺→大映通り→仁和寺 3日目 等持院→大河内山荘庭園→二尊院→落合 4日目 大覚寺→広沢池→清凉寺→神護寺 5日目 妙心寺→今宮神社(参道のみ)→東福寺 6日目 梅宮大社 7日目 くろ谷 金戒光明寺→新日吉神宮→松本酒造(伏見)→宇治橘橋 8日目 隨心院→日吉大社→西教寺 9日目 彦根城→西の湖(舟下り)→八幡堀→西の湖(陸側) 10日目 今宮神社→谷山林道→沢ノ池 11日目 美山→摩気 12日目 広沢池→中之島の中州→西寿寺→化野念仏寺→東映太秦映画村→車折神社 特集コーナー 「京都、水の点描」「石段の見分け方」 「『鬼平犯科帳』エンディング映像はここで撮られた!」 あとがき 聖地巡礼リスト 著者プロフィール 春日太一 (カスガタイチ) (著/文) 映画史・時代劇研究家。1977年東京都生まれ。日本大学大学院博士後期課程修了。映画界を彩った俳優とスタッフたちのインタビューをライフワークにしている。著書に『天才 勝新太郎』(文春新書)、『ドラマ「鬼平犯科帳」ができるまで』(文春文庫)、『すべての道は役者に通ず』(小学館)、『時代劇は死なず! 完全版』(河出文庫)、『時代劇入門』(角川新書)、『大河ドラマの黄金時代』(NHK出版新書)など多数。 ISBN 978-4-909394-50-7 四六判 256頁 発行 ミシマ社 書店発売日 2021年4月20日
-

聖地巡礼ツーリズム
¥1,980
【中古 読むには問題なし(表紙に少し擦れあり)】 ☆店長のひと言 「Go To 聖地」 紹介 アニメの聖地から世界宗教の聖地、さらには負の聖地アウシュヴィッツまで。多様なタイプの国内外52の聖地/巡礼とツーリズムの動態を徹底分析。「動き」、「変化する」現代の聖地/巡礼を解読する新しい聖地巡礼案内。 目次 第1章 巡礼と聖地 第2章 伝統と聖地 第3章 世界遺産化と聖地 第4章 消費と聖地 第5章 メディアと聖地 第6章 悲劇と聖地 第7章 国家と聖地 第8章 戦争と聖地 山中 弘(編), 岡本 亮輔(編), 星野 英紀(編) ISBN 978-4-335-16071-4 263頁 発行 弘文堂 初版発行年月 2012年11月
-

バーナード・リーチ日本絵日記
¥1,265
☆店長のひと言 「アートではなく、生活の中の美を尋ねて。」 紹介 宮川香山(みやがわこうざん)・六代乾山(けんざん)に師事、東西の伝統を融合し、独自の美の世界を想像したイギリス人陶芸家リーチ。昭和28年、19年ぶりに訪れた第2の故郷日本で、濱田庄司・棟方志功・志賀直哉・鈴木大拙らと交遊を重ね、また、日本各地の名所や窯場を巡り、絵入りの日記を綴る。随所にひらめく鋭い洞察、真に美しいものを見つめる魂。リーチの日本観・美術観が迸(ほとばし)る興趣溢れる心の旅日記。 目次 第1章 序曲、東と西 第2章 日本―第一印象 第3章 深まる印象 第4章 山陰・山陽の旅 第5章 濱田の益子 第6章 山国の旅―松本 第7章 穫入れの秋の本州をめぐる 第8章 東京―京都 第9章 九州小鹿田にて 第10章 むすびそしてお別れ バーナード・リーチ年譜 (出版書誌データベースより転載) 著者 バ−ナ−ド・リ−チ(バーナード・リーチ) 1887-1979。イギリス人、香港で生まれる。幼児期は日本で過ごす。帰英後は、ロンドン美術学校などでエッチングを学ぶ。1909年日本への憧れを強くし再来日。上野桜木町に居を構えてエッチングを指導し、入門してきた柳宗悦ら白樺派の人々と親交を結ぶ。1911年六代目尾形乾山に富本憲吉とともに入門、その後千葉県我孫子の柳邸内に窯を築くなど日本国内で作陶を始める。1920年濱田を伴って帰英、コーンウォール州セント・アイヴスに日本風の登窯を築き、1922年にはリーチ工房を設立し生涯の拠点とした。 柳宗悦とはウィリアム・ブレイクや陶磁器への関心を通して、芸術に関する思想的な影響や刺激を与え合う生涯の友として親しく交わった。 日本民藝館が所蔵するリーチの陶磁作品は約120点。スリップウェアなどの西洋陶器と東洋陶磁の技術を融合させた独自の作風が特徴的である。来日の折に訪れた小鹿田や二川、布志名など地方の窯場で作られた作品も所蔵している。また、身近な人物や旅先の風景などを題材にしたエッチングや素描作品も約100点ある。 リーチ工房は、2008年より記念館兼製作工房として公開されている。 (日本民藝館HPより抜粋) 訳:柳 宗悦(ヤナギ ムネヨシ) 訳:水尾 比呂志(ミズオ ヒロシ) ISBN 978-4-06-159569-9 判型A6 360ページ 発行 講談社 発売日 2002年10月10日
-

建設業者 三七人の職人が語る肉体派・技能系仕事論
¥550
【中古 状態きれい】 (参考:定価1,400円+税) ☆店長のひと言 「あまりにも普通にしてしまうので素人には凄さが分からない世界。…すごい。」 紹介 ゼネコンの下請けとして働く職人から、宮大工・社寺板金のような伝統的建造物に携わる職人まで、建築にかかわる37人に聞いた、ものづくり・人材育成・仕事の流儀-。建築関係者のための月刊専門誌「建築知識」誌上で連載され、大反響を巻き起こした"職人ドキュメント"の完全版。 目次 鉄であれコンクリートであれ(鉄骨鳶・湯本春美「思いやりで仕事が回る」 クレーンオペレーター・千葉清和「勝負は一本目の柱で」 鉄骨工・池田章「中途半端な人間が必要なときもある」 ほか) 裏か、表か(給排水設備・小池猛「一本一本心臓から血管をつないでいくように」 電気設備・保坂和弘「"最後"の仕事」 石工・関田嗣雄「伝説の親方」 ほか) 木と伝統に魅せられて(素材生産・塩野二郎「大事なのは人間の中身だからね」 林業・田中惣次「誰が山を守ればいいのか?」 製材・沖倉喜彦「いま、木がものすごくよく見えてきている」 ほか) エクスナレッジ(著), 建築知識編集部(編著) ISBN 978-4-7678-1455-1 239頁 発行 エクスナレッジ 初版発行年月 2012年9月
-

土の絵師 伊豆長八の世界
¥1,210
【中古 読むには問題なし(表紙にややヤケあり)】 (参考:定価2,800円+税) ☆店長のひと言 「壁に宿る命。」 目次 1 長八の世界(伊豆長八の倉 土の絵 ほか) 2 美術館建設と町おこし(蘇る奔流 長八の鏝、いまの鏝 ほか) 3 長八の郷(伊豆半島周遊(抄) 松崎町長八作品散策 ほか) 4 長八とその門弟たち(伊豆長八の生涯-付・入江長八略年譜 思楽老コテばなし(抄) ほか) 5 長八の技、漆喰細工の裾野(江戸のアルチザン鏝絵師伊豆長八 長八の作風と技法 ほか) 村山 道宣(編), 伊豆 長八(著) ISBN 978-4-434-01845-9 253頁 発行 木蓮社 : 星雲社 初版発行年月 2002年11月