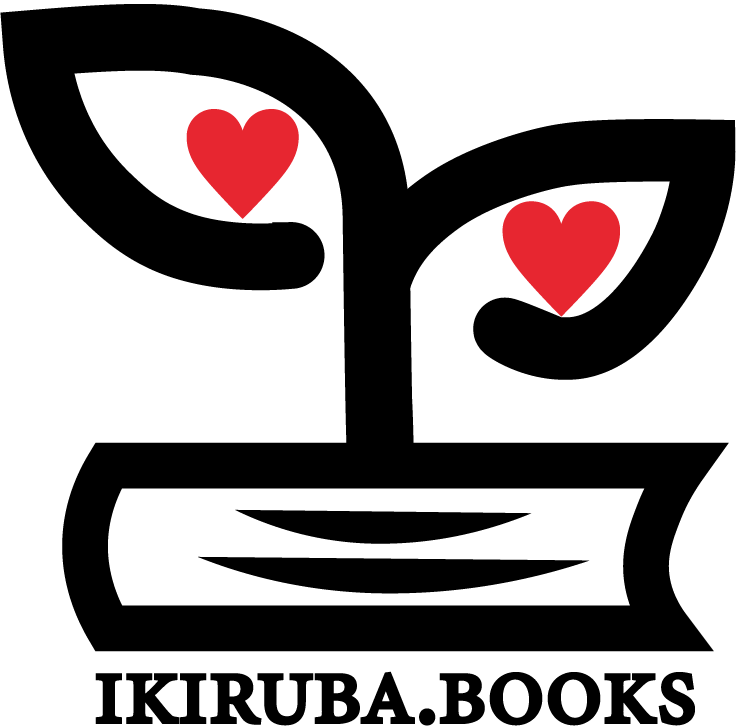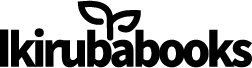-

ビッグイシュー512号
¥500
☆店長のひと言 「では先生、私は何に依存すればいいのでしょうか。」 【内容紹介】 特集 人間と薬物。そのつきあい方 人間は薬物とともに生きてきました。世界各地でさまざまな民族が病気の治療や宗教的な儀礼などに、また「酔い」や「ハイ」を体験するために薬物を使ってきました。こうした地域特有の薬物が、15世紀半ば頃に始まった大交易時代以降、帝国主義国家の植民地政策によって大量生産されて世界に広がり、人間の歴史をも変えてきました。 松本俊彦さん(精神科医、国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 薬物依存研究部部長)は言います。「私たちのごく身近にあるアルコール・タバコ・カフェインは大きな健康障害を生むので『ビッグスリー』、よくニュースになるアヘン・大麻・コカは『リトルスリー』と呼びます」。また、病院で患者に処方される「処方薬」、薬局で売られる「市販薬」などによる依存症者が今、増えているとも。 「薬物そのものによい薬も、悪い薬もなく、『よい使い方』と『悪い使い方』があるだけ」と語る松本さんに、薬物をめぐる人類史を踏まえつつ、身近な薬物とのつきあい方やその怖さについて話を聞きました。 TOP INTERVIEW スペシャルインタビュー オアシス 兄ノエル、弟リアムによって結成された英国のロックバンド「オアシス」。1994年のデビュー以来、数々の名曲によって圧倒的な人気を博しながらも、兄弟間の不和によって2009年に解散。再結成を待ち望むファンの期待も裏切られ続けました。 しかし、15年におよぶ月日が流れた昨年、奇跡の再結成を突然発表。現在、世界ツアーで熱狂を巻き起こし、今月末には待望の来日公演も予定しています。 そんなノエルとリアムの二人は、これまで英ビッグイシュー誌に幾度となく登場。過去のインタビューを振り返り、印象的なエピソードからオアシスの軌跡を振り返ります。 リレーインタビュー・私の分岐点タレント 戸島 花さん 趣味・特技の欄に書き続けた「囲碁」 グループ卒業後、夢の仕事ができるように 国際記事 『もしも君の町がガザだったら』高橋真樹さん 今なお続く、イスラエルによるガザ侵攻。世界各地で市民が「Free Palestine」の声を上げて連帯する一方、現地からの悲報はさらに深刻度を増しています。パレスチナ問題について懸念し、今年7月に『もしも君の町がガザだったら』を上梓したノンフィクションライターの高橋真樹さんに問題の本質を聞きました。 英国。“移民・難民申請者”のための「ローラーディスコ」 「表現する喜び、安心できる居場所、そして車ローラ輪ー を――」。英国外からポーツマス市内へ移住してきた若い人たちを対象に、ローラースケートとダンスを組み合わせたワークショップ「Skates4Mates」が始まった。主宰者である振付師・パフォーマー・エッセイストのジェニファー・アイアンズが、その体験をレポートする。 WORLD STREET NEWS 世界短信 連載記事 原発ウォッチ! 世界銀行とアジア開発銀行が原発融資解禁へ 浜矩子の新ストリート・エコノミクス 注目、日本の最低賃金制度 雨宮処凛の活動日誌 「不法滞在者ゼロプラン」で切り捨てられる子どもたち ホームレス人生相談 兄に彼女ができ、複雑な気持ちです 埋もれた名作を復刊・販売する学生たちー水野ゼミの本屋 知的財産法を学ぶ大学のゼミが運営するユニークな本屋が大阪市内にある。店名はゼミ名そのまま「水のゼミの本屋」。 本の権利関係の調査・確認から、出版・販売、読書会、グッズ開発、広報に至るまで、すべてを学生が手がける驚きの本屋を取材した。 読者のページ My Opinion 販売者に会いにゆく 米国『デンバー・ボイス』ハルヴィン・ジョーンズ 監督インタビュー『アフター・ザ・クエイク』井上剛監督 阪神・淡路大震災をモチーフにした村上春樹氏の連作短編集『神の子どもたちはみな踊る』を原作とする映画『アフター・ザ・クエイク』が10月3日より公開されます。独特の村上ワールドを映像化した井上剛監督に作品世界を聞きました。 創刊22周年記念 映画祭と写真展開催 “貧困”や“排除”そして社会を考えた FROM EDITORIAL 編集後記 (ビッグイシュー日本HPより抜粋)
-

別れを告げない
¥2,750
☆店長のひと言 「最近思うんですよ、苦労は本当に人を成長させるのだろうか、と…。」 紹介 作家のキョンハは、虐殺に関する小説を執筆中に、何かを暗示するような悪夢を見るようになる。ドキュメンタリー映画作家だった友人のインソンに相談し、短編映画の制作を約束した。 済州島出身のインソンは10代の頃、毎晩悪夢にうなされる母の姿に憎しみを募らせたが、済州島4・3事件を生き延びた事実を母から聞き、憎しみは消えていった。後にインソンは島を出て働くが、認知症が進む母の介護のため島に戻り、看病の末に看取った。キョンハと映画制作の約束をしたのは葬儀の時だ。それから4年が過ぎても制作は進まず、私生活では家族や職を失い、遺書も書いていたキョンハのもとへ、インソンから「すぐ来て」とメールが届く。病院で激痛に耐えて治療を受けていたインソンはキョンハに、済州島の家に行って鳥を助けてと頼む。大雪の中、辿りついた家に幻のように現れたインソン。キョンハは彼女が4年間ここで何をしていたかを知る。インソンの母が命ある限り追い求めた真実への情熱も…… いま生きる力を取り戻そうとする女性同士が、歴史に埋もれた人々の激烈な記憶と痛みを受け止め、未来へつなぐ再生の物語。フランスのメディシス賞、エミール・ギメ アジア文学賞受賞作。 著者プロフィール ハン・ガン (ハン ガン) (著/文) Han Kang 한강 1970年、韓国・光州生まれ。延世大学国文学科卒業。2005年、三つの中篇小説をまとめた『菜食主義者』で韓国最高峰の文学賞である李箱文学賞を受賞、同作で16年にアジア人初の国際ブッカー賞を受賞。17年、『少年が来る』でイタリアのマラパルテ賞を受賞、23年、『別れを告げない』(本書)でフランスのメディシス賞(外国小説部門)を韓国人として初めて受賞し、24年にフランスのエミール・ギメ・アジア文学賞を受賞した。本書は世界22か国で翻訳刊行が決定している。他の邦訳作品に、『ギリシャ語の時間』『すべての、白いものたちの』『回復する人間』『そっと 静かに』『引き出しに夕方をしまっておいた』がある。 斎藤 真理子 (サイトウ マリコ) (翻訳) 翻訳家。パク・ミンギュ『カステラ』(共訳)で第一回日本翻訳大賞、チョ・ナムジュ他『ヒョンナムオッパへ』で〈韓国文学翻訳院〉翻訳大賞受賞。訳書は他に、ハン・ガン『回復する人間』『すべての白いものたちの』『ギリシャ語の時間』『引き出しに夕方をしまっておいた』(共訳)、パク・ソルメ『もう死んでいる十二人の女たちと』『未来散歩練習』、ペ・スア『遠きにありて、ウルは遅れるだろう』、パク・ミンギュ『ピンポン』、チョ・セヒ『こびとが打ち上げた小さなボール』、ファン・ジョンウン『誰でもない』『年年歳歳』『ディディの傘』、チョン・イヒョン『優しい暴力の時代』、チョン・ミョングァン『鯨』、チョン・セラン『フィフティ・ピープル』『保健室のアン・ウニョン先生』『声をあげます』『シソンから、』、チョ・ナムジュ『82年生まれ、キム・ジヨン』『サハマンション』、李箱『翼 李箱作品集』など。著書『韓国文学の中心にあるもの』、『本の栞にぶら下がる』、『曇る眼鏡を拭きながら』(共著) ISBN:978-4-560-09091-6 Cコード:0097 四六判304ページ 発行: 白水社 書店発売日: 2024年4月2日

-

ビッグイシュー497号
¥500
☆店長のひと言 「対話で回復するならば、言葉で病むこともあるわけで。」 【内容紹介】 特集 対話から回復へ オープンダイアローグの10年 統合失調症や双極症、うつ病、ひきこもり、認知症、発達障害……。こうした生きづらさに苦しむ人たちが、薬物も入院も最低限に、もしくは必要とすらせず、ただ“対話”だけで回復する「オープンダイアローグ(OD)」が少しずつ広がりをみせています。 ODは元々、1980年代からフィンランドで実践が続けられてきた精神科医療の新しいアプローチです。対話を繰り返すことで症状が回復するケースが明らかになり、世界的な注目を集めています。 しかし、なぜ対話だけで回復が起こるのか?日本での普及に取り組んできたOD第一人者の斎藤環さん(精神科医)は、ODの根底には「人間の尊厳、自由や権利を尊重していくことで結果的に回復が起こる」という思想があると語ります。 日本での普及が本格化して今年で10年。茨城県で「つくばダイアローグハウス」を開業したばかりの斎藤さんを訪ね、「ODとは何か。10年にわたる取り組みとこれから」についてお聞きしました。 TOP INTERVIEW スペシャルインタビュー モニカ・バルバロ ボブ・ディランの若き日を描いた伝記映画『名もなき者/ A COMPLETE UNKNOWN』で、公民権運動や反戦活動家としても知られるシンガーソングライターのジョーン・バエズを 演じたモニカ・バルバロ。俳優としてのキャリアを振り返るとともに、女性に対する蔑視・差別の問題を語ります。 リレーインタビュー・私の分岐点アーティスト 新城大地郎さん 離れてみて感じた “ 宮古島 ” の魅力。書と自分が一体化した時、生まれる1枚 国際記事 カナダ、世代間で連鎖する“同化政策のトラウマ” 憲法で先住民族の権利を保障し、過去の同化政策についても公式に謝罪したカナダ。しかし現実には、先住民族が置かれた状況は依然として厳しく、改善に向かっているとは言い難いです。社会問題から子どもを守ろうと取り組む児童福祉サービスの陰で引き裂かれる親子の実態について、当事者と里親の証言を伝えます。 WORLD STREET NEWS 世界短信 滝田明日香のケニア便り 1.5トンの雄キリン、6人がかりで地面に倒して治療 連載記事 浜矩子の新ストリート・エコノミクス ジジ抜きとジジ入り コミック マムアンちゃん ウィスット・ポンニミット ホームレス人生相談 × 枝元なほみの悩みに効く料理 古い服を捨てられません ☆ 好き勝手チョコ ☆ 連載250回記念、枝元さんインタビュー 食べたいという気持ちは生きる根っこ 宇宙・地球・人間 池内了の市民科学メガネ カルシウムを吸収し定着させる「骨活」のすすめ 読者のページ My Opinion 販売者に会いにゆく 『アプロポ』イフェアニ・マドゥアコ トミヤマユキコの「マンガを通して社会問題を考える」3 自分向けでない世界で、どっこい生きてる人 トミヤマユキコさんの「マンガを通して社会問題を考える」エッセイ第3弾。トミヤマさんは、「この世界が『ふつうの人』を基準にデザインされていて、そうじゃない人たちがありのままでいられるようにはできていない」と語ります。 そんな自分向けにデザインされていない世界の中にあっても、どっこい生きている人がたくさん出てきて、さまざまなヒントを与えてくれる、トミヤマさんが最近注目する、マンガ5作品を紹介します。 監督インタビュー 『犬と戦争 ウクライナで私が見たこと』山田あかね監督 FROM EDITORIAL 編集後記 (ビッグイシュー日本HPより抜粋)
-

治りませんように : べてるの家のいま
¥800
SOLD OUT
【中古 状態きれい】 (参考:定価2,400円+税) ☆店長のひと言 「売れますように」 紹介 精神障害やアルコール依存などを抱える人びとが、北海道浦河の地に共同住居と作業所"べてるの家"を営んで30年。 べてるの家のベースにあるのは「苦労を取りもどす」こと-保護され代弁される存在としてしか生きることを許されなかった患者としての生を抜けだして、一人ひとりの悩みを、自らの抱える生きづらさを、苦労を語ることばを取りもどしていくこと。 べてるの家を世に知らしめるきっかけとなった『悩む力』から8年、浦河の仲間のなかに身をおき、数かぎりなく重ねられてきた問いかけと答えの中から生まれたドキュメント。 目次 記憶 死神さん べてるの家 浦河弁 なつひさお 救急通い 遭難者 あきらめる 立ち往生 新しい薬 幻聴とダンス 生きる糧 青年の死 ぺてるの葬儀 その人を語る 爆発系 ピア・サポート 撤退 当事者研究 アイメッセージ 収穫の秋 病気への依存 人間アレルギー 治さない 日だまり 苦労の哲学 しあわせにならない 著者プロフィール 斉藤道雄 (サイトウミチオ) (著/文) 1947年生まれ。ジャーナリスト。TBSテレビ報道局の記者、ディレクター、プロデューサー、解説者として報道番組の取材、ドキュメンタリー番組の制作に従事。先端医療、生命倫理、マイノリティ、精神障害、ろう教育などをテーマとしてきた。2008年から5年間、明晴学園の校長、その後4年間、理事長を務めた。著書に『原爆神話の五〇年』(中公新書、1995)『もうひとつの手話』(晶文社、1999)『悩む力――べてるの家の人びと』(みすず書房、2002)『希望のがん治療』(集英社新書、2004)『治りませんように――べてるの家のいま』(みすず書房、2010)『手話を生きる――少数言語が多数派日本語と出会うところで』(みすず書房、2016)『治したくない――ひがし町診療所の日々』(みすず書房、2020)がある。 ISBN:978-4-622-07526-4 四六判 251ページ 発行: みすず書房 初版年月日: 2010年2月17日
-

しにたい気持ちが消えるまで
¥1,570
【中古 状態きれい】 (参考:定価1,600円+税) ☆店長のひと言 「死にたいも生きたいも自然なこと。でもそれだけでは終わらない。」 紹介 16歳のとき、死のうと思った。すごく天気の良い日で、こんな日に死ねるなんて幸せだと思った。自宅のベランダから飛び降り、頸髄を損傷するが一命をとりとめる。 「死ななくて良かった」、「何もできなくても生きていていい」 現在を生きる筆者による、自死を止めたい、やさしくなりたい、お守りのような言葉。書き下ろし自伝エッセイ。 著者プロフィール 豆塚エリ (マメツカエリ) (著/文) 1993年、愛媛県生まれ。16歳のとき、飛び降り自殺を図り頸髄を損傷、現在は車椅子で生活する。大分県別府市で、こんぺき出版を拠点に、詩や短歌、短編小説などを発表。NHK Eテレ『ハートネットTV』に出演するなど、幅広く活動中。 ISBN:978-4-7796-4671-3 Cコード:0095 四六判304ページ 発行:三栄 発売日: 2022年9月16日
-

ビッグイシュー479号
¥450
☆店長のひと言 「認知症になって変わってしまうのは自分か、それとも周りか。」 【内容紹介】 特集 「認知症」を更新する 身近に「認知症」のある方はおられますか? 認知症の人に見える不思議な世界を知りたいと思いませんか? 当事者である丹野智文さんは、認知症当事者のための総合相談窓口「おれんじドア」を開き、多くの当事者から相談を受けてきた。丹野さんは「認知症と診断された時から当事者の暮らしは、それ以前とはまるっきり変わってしまう。それは認知症になったら“何もわからなくなる”などの間違った情報や、重度の症状だけが伝わっているからだ」と言う。 そこで、筧裕介さん(issue+design代表)は、100人以上の認知症のある人にインタビューをして、当事者の世界を具体的にイメージできる“14の世界”のストーリーを描く。筧さんは「認知症の方が抱えている問題の大半は、人との関係や周囲の環境との関係の中で起きています」と話す。 超高齢化が進む今、誰でも認知症になる可能性がある。丹野さん、筧さんに、当事者、家族、支援者、そして私たちと社会ができる工夫や備えについて聞いた。 TOP INTERVIEW スペシャルインタビュー 井浦新 今や日本の映画・ドラマ界では欠かせない存在となった井浦新さん。6月7日公開の映画『東京カウボーイ』で米国映画デビューを果たした彼が、自らの俳優人生と本作のテーマでもある人生の豊かさ、そして社会とのかかわりについて語ります。 リレーインタビュー・私の分岐点日本女子プロサッカーリーグ チェア 髙田春奈さん 社会貢献に携わる喜びと誇り 女子サッカーで一人ひとりが輝く社会に 国際記事 WORLD STREET NEWS 世界短信 国内記事 能登半島地震レポート④ 自宅、避難所、仮設住宅、移動のたびに大きな負担 表現する人 一瞬の世界、身近なものを作品に 鈴木康広さん 連載記事 浜矩子の新ストリート・エコノミクス どうしても知りたい日銀総裁の胸のうち コミック マムアンちゃん ウィスット・ポンニミット ホームレス人生相談 × 枝元なほみの悩みに効く料理 次世代へのバトンタッチに悩んでいます ☆ アスパラガスのちくわ巻き、肉巻き ☆ ネット世代に伝えたい。キノコ雲の下で起きた悲劇 『ターニング・ポイント:核兵器と冷戦』 宇宙・地球・人間 池内了の市民科学メガネ 私たちの「時間の濃縮度」 読者のページ My Opinion 販売者に会いにゆく 『ビッグイシュー台湾版』 カン・チューエン FROM EDITORIAL 編集後記 (ビッグイシュー日本HPより抜粋)
-

わたしが誰かわからない : ヤングケアラーを探す旅
¥2,200
☆店長のひと言 「ヤングケアラー…、突然そう呼ばれた人の戸惑いを想像できないあなたへ。」 紹介 「ヤングケアラー」について取材をはじめた著者は、度重なる困難の果てに中断を余儀なくされた。一体ヤングケアラーとは誰なのか。世界をどのように感受していて、具体的に何に困っていているのか。取材はいつの間にか、自らの記憶をたぐり寄せる旅に変わっていた。ケアを成就できる主体とは、あらかじめ固まることを禁じられ、自他の境界を横断してしまう人ではないか――。著者はふたたび祈るように書きはじめた。 目次 はじめに 1 薄氷のような連帯 2 いちばん憎くて、いちばん愛している人 3 わたしが誰かわからない 4 わたしはなぜ書けないか 5 抱えきれない言葉の花束 6 固まることを禁じられた身体──ケア的主体とは何か 7 自己消滅と自己保存──水滴のように 8 犠牲と献身と生まれ変わり──自由へ おわりに 【著者略歴】 中村佑子(なかむら・ゆうこ) 1977年東京都生まれ。映像作家。慶應義塾大学文学部哲学科卒業。哲学書房にて編集者を経たのち、2005年よりテレビマンユニオンに参加。映画作品に『はじまりの記憶 杉本博司』(2012年)、『あえかなる部屋 内藤礼と、光たち』(2015年)がある。主なテレビ演出作に、「幻の東京計画 ~首都にありえた3つの夢~」(NHK BSプレミアム、2014年)、「地球タクシー レイキャビク編」(NHK BS1、2018年)など。本書が初の著書となる。 ISBN:978-4-260-05441-6 Cコード:3347 A5判232ページ 発行:医学書院 発売日: 2023年11月20日
-

アルツハイマー病になった母がみた世界
¥2,100
【中古 状態きれい】 (参考:定価2,200円+税) ☆店長のひと言 「自分のためだけの日記やメモがSNSよりも助けになることがあると思う。」 紹介 認知症と診断された高齢者は、徐々に起こる認知機能の低下とそれにより生じる生活の困難を、どのように感じ、それにどう対応するのか。死の2年前まで綴っていた日記から、母が外界をどのように眺め感じていたかを専門医である息子が探る。精神医学の常識を覆そうと始めた試み。果たして、その先にみえたものとは? 目次 まえがき 母の生涯 母の両親 母の出生、五歳にして生母を亡くす 一二歳、父を失う 二二歳、次兄のシベリア抑留死 二四歳、結婚、二八歳、長女の夭逝 三人の子の母として、妻として 六四歳、夫との死別、モンゴル墓参、それからの生活 母の日記と生活 第一期 六七~七五歳――遅れてきた母の青春、忍び寄る老いの足音 六七歳(一九九一年) 「バックを落とさないように、じっと抱えていた」 六八~七五歳(一九九二~九九年) 人生の集大成とエンディングノート 六八歳(一九九二年) 「一時二八分男児誕生、五二・五cm三、六九四g」 六九歳(一九九三年) 「かすかにも藤の花ぶさそよがする」 七〇歳(一九九四年) モンゴル墓参 七一歳(一九九五年) 「老人とはこういうものか」 七二歳(一九九六年) 「どら焼きショックか?」 七三歳(一九九七年) エルサレムへ 七四歳(一九九八年) 「私の葬儀に関するノート、例の紙挟みに入れる」 七五歳(一九九九年) イタリア旅行、「今年も無事に暮れていく」 第二期 七六~七九歳――ほころび始める生活、認知機能低下に抗う 七六歳(二〇〇〇年) 結城屋騒動、「決してボケないように心身を大切にしよう」 七七歳(二〇〇一年) 「面倒なので雑炊にした」 七八歳(二〇〇二年) 「東京の老人ホームに入りたい」 七九歳(二〇〇三年) 「情けない、恥ずかしい、早く消えたい」 第三期八〇~八四歳――老いに翻弄される日々、崩れていく自我の恐怖 八〇歳(二〇〇四年) 「このまま呆けてしまうと思うと……」 八一歳(二〇〇五年) 「いよいよ来たかな?」 八二歳(二〇〇六年) このまま呆けてしまうのだろうか、「張れ!レイコ!」 八三歳(二〇〇七年) 「呆けてしまったみたい……呆けてしまった!!」 八四歳(二〇〇八年) 「一日一日呆けが進んでゆくようで恐ろしくて仕方がない」 第四期 八五~八七歳――それからの母のこと 八五歳(二〇〇九年) 「TELかけすぎて叱られる」 八六~八七歳(二〇一〇~一一年) 「長い間、ありがとうございました」 八六歳(二〇一〇年) 「苦しいって言ってるじゃないの!!」 八六歳(二〇一一年一~四月) 「早くなんとかしてちょうだい」 八六~八七歳(二〇一一年五月) 「ごきげんよう」 認知症とは何か アルツハイマー型認知症とは何か アルツハイマー型認知症急増という現象の意味 アルツハイマー病根治薬の開発は可能か 母の診断を考える 母の旅路 あとがき 著者プロフィール 齋藤正彦(さいとう まさひこ) 1952年生まれ.東京大学医学部卒業.都立松沢病院精神科医員,東京大学医学部精神医学教室講師,慶成会青梅慶友病院副院長,慶成会よみうりランド慶友病院副院長,翠会和光病院院長などを経て,2012年都立松沢病院院長,21年から同病院名誉院長.医学博士,精神保健指定医.主な研究テーマは老年期認知症の医療・介護,高齢者の意思能力,行為能力に関する司法判断. 著書に『都立松沢病院の挑戦』(岩波書店),『親の「ぼけ」に気づいたら』(文春新書),監修に『家族の認知症に気づいて支える本』(小学館),編著書に「講座精神疾患の臨床」『第7巻地域精神医療リエゾン精神医療精神科救急医療』(中山書店),『松沢病院発! 精神科病院のCOVID-19感染症対策』(新興医学出版社),『認知症医療・ケアのフロンティア』(日本評論社),『私たちの医療倫理が試されるとき』(ワールドプランニング)などがある. (岩波書店ホームページより引用) ISBN:978-4-00-061565-5 Cコード:0036 四六判254ページ 発行:岩波書店 発売日: 2022年11月10日
-

言葉を失ったあとで
¥1,800
SOLD OUT
【中古 帯の破損※以外は状態きれい(画像参照)】 (参考:定価1,800円+税) ☆店長のひと言 「被害者を減らすためにも加害者への理解と支援は必要なんだけれど、それを声高に主張すると世間様に叩かれるという…。」 紹介 アディクション・DVの第一人者と、沖縄で若い女性の調査を続ける教育学者。現場に居続ける二人が真剣に、柔らかく、具体的に語る、「聞く」ことの現実。 「聞くの実際」。アディクション・DVの第一人者と、沖縄で社会調査を続ける教育学者。それぞれの来歴から被害/加害をめぐる理解の仕方まで、とことん具体的に語りあった対談集。 【目次】 まえがき 信田さよ子 第一章 言葉を失ったあとで 二〇二〇年一一月二七日 中立の立場とはなにか/加害者の話をどう聞くか/加害を書けるか/加害者が被害を知る/性被害の特殊性/仏壇継承者/暴力の構造を知る/スタイルの違い/学校が話を聞けない場所に/援助が料金に見合うか/質疑応答へ/加害者の普通さ/厳罰化は何も解決しない/言葉をいっしょに探す/ゼロ・トレランスの弊害/まずはいい時間をつくる/三つの責任 読書案内① 第二章 カウンセリングという仕事、社会調査という仕事 二〇二一年二月六日 精神科医にできないこと/教室の実践記録のおもしろさ/原点は児童臨床のグループ/沖縄から離れて/「性の自己決定」の実際/社会調査が示すこと/医者になるか、女性のアルコールやるか/女性の依存症の特異さ/八〇年代の精神病院の経験が一生を決めた/生身の人間の話がおもしろい/ネクタイを褒める/沈黙に強くなる 読書案内② 第三章 話を聞いて書く 二〇二〇年二月二三日 精神疾患の鋳型/解離は手ごわい/医療との関係/加害はパターン化している/精神科の役割/値踏みされている/お金をもらうか払うか/許諾のとりかた/書く責任/モスバーガーの文脈/身体は触らない/身体は自分のもの/聞きとりのあと/トランスクリプトの確認の仕方 読書案内③ 第四章 加害と被害の関係 二〇二一年三月一二日 被害者元年/起源は七〇年代/仲間は当事者/学校現場の変化/公認心理師の国家資格/被害者の両義性/暴力をなくす練習/加害者プログラムの順番/加害者の書きづらさ/映画で描かれる暴力/打越正行さんの調査 読書案内④ 第五章 言葉を禁じて残るもの 二〇二一年三月二七日 性被害をどのように語りはじめるのか/臓器がぶらさがっている感覚/フラッシュバックの意味/被害経験の読み替え/選択肢のすくなさ/家族の性虐待/語りのフォーマット/言葉を禁じる/性加害者の能動性/ユタを買う/一二月の教室/オープンダイアローグの実践 読書案内⑤ 第六章 ケアと言葉 二〇二一年五月一一日 カウンセリングに来るひとたち/男性の語りのパターン/加害者の語り/加害者プログラムの肝/DV被害者支援と警察/家族はもうだめなのか?/使えるものはぜんぶ使う/親との関係を聞く/被害者共感の効果/権力と言葉/「加害者」という言葉の危うさ/ブルーオーシャンへ/被害者は日々生まれている/当事者の納得する言葉 読書案内⑥ あとがき――「聞く」の現場の言葉を聞く 上間陽子 著者プロフィール 信田 さよ子 (ノブタ サヨコ) (著/文) 1946年、岐阜県生まれ。公認心理師・臨床心理士。原宿カウンセリングセンター顧問、NPO法人RRP研究会の代表理事。著作に『家族と国家は共謀する』(角川新書)、『増補新版 ザ・ママの研究』(新曜社)、『カウンセラーは何を見ているか』(医学書院)など多数。 上間 陽子 (ウエマ ヨウコ) (著/文) 1972年、沖縄県生まれ。琉球大学教育学研究科教授。生活指導の観点から主に非行少年少女の問題を研究。著作に『海をあげる』(筑摩書房)、『裸足で逃げる』(太田出版)、共著に『地元を生きる』(ナカニシヤ出版)など。 ISBN:978-4-480-84322-7 Cコード:0095 四六判352ページ 発行:筑摩書房 発売日: 2021年12月2日
-

敏感すぎるあなたへ 緊張、不安、パニックは自分で断ち切れる
¥1,540
【中古 状態きれい】 (参考:定価1,600円+税) ☆店長のひと言 「性格や病気ではなく、一時的な脳の誤作動と考えるだけで、少しラクになれる気がします。」 紹介 あがり症、不安などはあなたのせいではなく、脳の誤動作かも。仕事などで極度の緊張、息苦しさ、腹痛が続き、何かおかしいと思っている人、また、心療内科に行っても「単なるストレス」と言われるだけの人など、病的とは言えないまでも、緊張や不安で日常生活に支障が出ている人向けの、自分でできる行動療法。 食生活、運動、思考法などを変えるだけで、心がすっとラクになる。ドイツで大ベストセラー! ベルリン有名クリニック臨床心理士が脳科学に基づく画期的な方法を伝授。 食事、運動、「テンセンテンス法」、「5つのチャンネルテクニック」……etc 脳に「良い手本」を見せて、すばやく、持続的に不安を断ち切る。 もう不安にはならない! 著者プロフィール クラウス・ベルンハルト (クラウスベルンハルト) (著/文) 臨床心理士。科学・医療ジャーナリストとして活躍後、心理学、精神医学を学ぶ。 現在、不安症やパニック発作の専門家として、ベルリンでカウンセリングルームを開設。 最新の脳科学に基づいた画期的療法「ベルンハルト・メソッド」はドイツで注目を集めている。 脳神経科学教育マネジメント協会(AFNB)会員。 ISBN:9784484181035 出版社:CCCメディアハウス 判型:4-6 ページ数:208ページ 定価:1600円(本体) 発行年月:2018年03月
-

ウイルスも認知症も生きづらいのも、すべて歯のせい?
¥1,210
☆店長のひと言 「お口は健康の入口です。」 紹介 健康寿命にふかくかかわるお口ケアの教科書 「歯の調子が悪ければ、歯医者さんにいけばいい。自分でできるのは歯磨きくらい」 というあなた。その考え方、時代遅れです!! 歯のケアを怠るとなる病気は、むし歯と歯周病だけ? 大間違い! アメリカでは、Floss or Die?(フロスしますか、それとも死にますか)というスローガンもあるほど、 歯と全身の健康はふかく結びついているのです。 なんと、ウイルスによる感染症・心臓病・肺炎・がん・認知症の原因にも! しかもコロナ禍で、私たちは一年中マスクを装着。 口腔ケアのプロである歯科医は警告します、 「今が人類史上、最悪な状態」! 口の中がネバネバしていませんか? 口臭がすると家族に言われていませんか? 歯と歯の間にすき間ができたなあと感じていませんか? そういや歯が長くなったような……口を開けると舌がいつも白っぽい……… このなかのひとつでも当てはまったら、この本を読むべきです! 自分でできるホームケア法と、だれしも苦手な歯医者さんとの付き合い方を、ギュッと一冊に。 さらに、舌の位置を正し、だ液を増やす「お口の筋トレ」法を初公開。 今こそ健康寿命も人生も、好転させましょう。 (小学館HPより転載) 著者 堀 滋(ほり しげる) 歯科医師。サウラデンタルクリニック院長。 1959 年生まれ。日本大学松戸歯学部卒業。昭和大学歯学部付属歯科病院口腔外科にて臨床を学びながら同医局にて白血球の活性酸素産生に関する研究を行い日本炎症学会等で学会発表も行う。 退局後は 日本橋中央歯科診療所勤務を経て、1990年中野区にて堀歯科診療所を開設。 診療の傍ら、スウェーデンのイエテ ボリ大学で実践されている歯周病治療を学ぶ、歯周病臨床実践コース、同アドバンスコース、ペン シルバニア大学 アドバンスインプラントコース受講など、海外の最新治療を学び続け積極的に治療に 取り入れている。 2017年保険診療を終了し、自由診療専門のサウラデンタルクリニックに名称変更。 2021年、開業30周年を期に港区青山に移転し、院内換気システムや低濃度オゾンガスによる院内環境 殺菌システムなどコロナウィルス感染予防対策を徹底的に強化した新たなクリニックを開設。 院内には、顔まわりから全身の筋肉ケアのためのリラクゼーションサロンも併設。 (サウラデンタルクリニックHPより抜粋) ISBN 978-4-09-310686-3 C2077 A5判 128頁 発行 小学館 発売日 2021年8月5日
-

こんなとき私はどうしてきたか
¥1,760
【中古 帯、カバーに少し汚れあり】 (参考:定価2,000円+税) ☆店長のひと言 「近頃世の中は、“寄り添う”なんて言葉を簡単に使うけれども。」 紹介 はじめて出会ったとき、暴力をふるわれそうになったとき、退院が近づいてきたとき、著者は患者さんにこんな言葉をかけてきた-本書は、二〇〇五年六月〜〇六年十月まで、兵庫県の有馬病院でおこなわれた「医師・看護師合同研修会」での講義内容をまとめたものである。 目次 1 こんなとき私はどう言うか(患者さんと出会ったとき 幻聴を四期に分けて考える 幻聴や妄想を実りあるものにするために 「匙を投げない」ことをどう伝えるか) 2 治療的「暴力」抑制論(患者さんを安全に抑える方法 "手負い"にしてはならない 患者さんにはどう見え、どう聞こえているか ふっと力が抜けるとき) 3 病棟運営についていくつかのヒント(どんな環境が人を苛立たせるのか 人的環境としての「部屋割り」 病棟スタッフの和をどう支えるか 改革時の病棟マネジメント-私の経験から) 4 「病気の山」を下りる(保護室の内と外 山を下りるということ 回復初期はからだに注目 下山のエネルギーを補給する) 5 回復とは、治療とは…(回復期は疲れる 疲れている患者さんに何を言うか 家族の方に知ってほしいこと 「依存」という切り口から 「回復に耐える」ということ) 著者 中井 久夫 1934年、奈良県生まれ。京都大学医学部卒業。現在は神戸大学名誉教授。著書として『精神科医がものを書くとき』『隣の病い』『世に棲む患者』『「つながり」の精神病理』『「思春期を考える」ことについて』(いずれも、ちくま学芸文庫)、『分裂病と人類』(東京大学出版会)、『精神科治療の覚書』『日本の医者』(いずれも日本評論社)、『西欧精神医学背景史』『災害がほんとうに襲った時』『復興の道なかばで』(いずれも、みすず書房)、『治療文化論』(岩波書店))など多数。 ISBN 978-4-260-00457-2 233頁 発行 医学書院 初版発行年月 2007年5月
-

自閉スペクトラム症の女の子が出会う世界
¥2,805
☆店長のひと言 「病気や障害からだけではない生きづらさが見えてくる」 内容紹介 幼児期、学校、就職、出産、老い……生まれてから老いるまでの間に、自閉スペクトラム症の女の子はどんな体験をするのか。自らも当事者の著者が、当事者や家族の証言をもとに描き出す。 目次 【目次】 本書に寄せて 序章 女の子たちも自分が何者なのか知る権利がある 第1章 女の人も自閉スペクトラム症になる ASDには性差がある/男女比はどれくらいか/神経学的特性は男女で異なる/特徴的な行動も違う/子どもの遊びの性差/その他の行動の性差を見る/人懐こくておしゃべり/女の子は自分を隠す 第2章 診断までの道のり 診断を受けるということ/診断基準DSM-5の改訂による影響/臨床医の知識と経験によって診断が大きく変わる/女性はASDと診断されづらい/他の病名がつく場合/女性のASD診断への道のり/女性に特化したASD診断の方法/ASDだと信じてもらえない/正確な診断を受けるために/最初に診断を受けた年齢/なぜ診断するのか?/子どもの診断/成人の診断/診断情報の開示 第3章 この子は何かが違う――乳幼児期 なかなか診断がつかない/女児の診断の遅れ/幼児期の指標/非言語コミュニケーションのなかで気づくこと/発話、言語コミュニケーション、言語理解で感じるずれ/予測できない状況が苦手/遊ぶ様子から見えること/強い関心を示す対象がある/ASDの女の子の典型的な関心対象/おもちゃの選択/広がる空想の世界/食べ物の好みから見えるもの/「女の子らしい」はあまり好まない/睡眠時の特徴/小児期における性自認 第4章 まわりになじめない――子ども時代の関係性 友達や他人とどのように接しているか/大人を好む/同世代との友人関係/観察し、模倣する/物事を共有できない 第5章 変わっていく身体と複雑な友人関係――思春期に出会う困難 何から始めればいいの?/同世代との関係性/難しくなる人間関係/「違い」の自覚/なじもうとする努力/ネットの友達/精神衛生上の問題/特徴が見えなくなる/コミュニケーションと社会的理解/この時期の関心事/変化への対処が難しい/自立スキルを養う/生理と身体の変化 第6章 家の外はカオスーー学校生活に必要な支援 学校でどう過ごすか/就学前(幼稚園・保育園)/物理的環境/教務スタッフ・支援員/決まりのない場所や遊びへのとまどい/小学校/休み時間の難しさ/学習スタイルの特徴/好きな科目・嫌いな科目/教師の対応/どんな環境で過ごしていたか/思春期以降の学校/カレッジ/大学/教育的支援が必要 第7章 大人になってからASDだとわかった女性たち――成人診断がもたらすもの 成人期の診断/診断がついたら何が変わる?/ASDでなければよかった?/もっと早く診断されていればよかった? 第8章 「ASDに見えない」――大人になってからの困難 成人期の特徴と「普通」に見えるということ/成人した女性に見られる特徴/非言語的な特徴/コミュニケーションにおける特徴/共有できない/自己刺激行動をとってしまう/変化や不確実なことへの対応が難しい/空想の世界と想像上の友達/服装の特徴/関心の対象/睡眠/自律スキルを身につけている 第9章 大人の人間関係――友人になるってどういうこと? 友人関係/友人づくりの難しさ/友達の少なさ/友人関係を維持するための努力/友達に求めるもの/惹かれる相手/同性が苦手/ネットの友達に助けられる/友人がいない/社会からの孤立/動物が友達/一人でいることを楽しむ 第10章 男か女かどちらでもないか?――セクシュアリティと性自認 いくつになっても「女らしさ」になじめない/特徴的な性自認/トランスジェンダー/ASDとトランスジェンダーの関係/性別を移行すべきか/性自認の違いに気づいたのはいつ?/カミングアウトするか/支援について/セクシュアリティはどのように決めるか/無性愛者 第11章 好きな人とつながりたい――恋愛・性行為・パートナーシップ 恋愛することの特別な難しさ/恋人候補への強い関心/シグナルを見逃す/パートナー選び/お世話係りとして/感覚的な好み/選択基準がない/独り身を貫く/最初の性的経験/性的暴行を受けるリスクが高い/レイプ/セックスと肉体的なつながり/良好な関係を築ける相手 第12章 子どもを産むとき――妊娠と育児のあれこれ 妊娠・出産・育児から得られる感情/子どもがほしいという気持ち/妊娠/出産/コミュニケーションの問題/感覚刺激を調整する必要性/母乳育児がうまくいく人、いかない人/ASDであり、母親であるということ/新生児期/母親としての劣等感/私の子育て/子どもに恥をかかせる/ASDであることの利点/ASDの子どもを持つ母親として/ASDの母親を持つ子どもたち 第13章 身体の不調とどう付き合うのか――健康で豊かな生活をおくるには 身体的な健康/アレルギー、不耐性、過敏症/アーレン症候群・スコトピック感受性症候群/月経/摂食障害/抑うつ/不安/自傷行為/自殺願望 第14章 こんな働き方をしています――就職するとき 就職するときの難しさ/仕事上の課題/期待される性役割/調整/理想の仕事/治療法と治療計画 第15章 ASDとともに老いてゆく――老後を考える 年齢を重ねることによる変化/高齢者の診断/医療・社会福祉の利用/心身への影響/人付き合いへの影響/加齢のプラス面/ASDのおばあちゃん 第16章 理想の生き方とはどんなもの?――死ぬ前におこなっておきたいこと 第17章 おわりに――あなたはどう生きていく? 訳者あとがき 原注 参考文献 索引 著者 サラ・ヘンドリックス (ヘンドリックス,サラ) 英国にて、自閉スペクトラム症者などを対象とした訓練や、コンサルティング、ビジネスをサポートする団体を運営する。自らも自閉スペクトラム症の診断を受けている。邦訳されている著書に『アスペルガー症候群の人の仕事観』がある。 堀越 英美 (ホリコシ ヒデミ) 1973年生まれ。文筆家。早稲田大学第一文学部卒。著書に『女の子は本当にピンクが好きなのか』『不道徳お母さん講座』『スゴ母列伝』『モヤモヤしている女の子のための読書案内』など、訳書に『世界と科学を変えた52人の女性たち』『ガール・コード』『ギタンジャリ・ラオ STEMで未来は変えられる』など。 (河出書房新社HPより転載) ISBN 978-4-309-25432-6 四六変型判 352頁 発行 河出書房新社 発売日 2021年10月26日
-

依存症のことがわかる本 防ぐ、回復を促すためにできること
¥1,540
☆店長のひと言 「依存しないようにではなく、よい依存にするために。」 【ひと目でわかるイラスト図解】 依存症とはなにか、どうすればやめられるのか 依存症は、違法薬物のみならず、アルコールや処方薬・市販薬などでも生じます。 ギャンブル、ゲームなどの行為に依存が生じることもあります。 なかでも、違法薬物に対する依存症は「犯罪」としての側面もあります。 違法薬物の所持・使用で逮捕された著名人などに対する激しいバッシングがくり返される一方で、大麻による検挙数は、若年層を中心に増加し続けています。 依存症そのものは、「ダメ、絶対」と言っているだけで防げるものではなく、回復を促すこともできません。 依存症は「安心して人に依存できない病」。 いやなこと、つらいことがあっても助けを求めず、お気に入りのものや行為だけでやり過ごそうとした結果、より困った状態に陥っていく、という面があります。 特定のもの、行為にはまっていく背景には、心の問題が隠されていることが多いのです。 人はだれしも、なにかに頼ることなく、生きていくのは難しい。 本書では、依存症の今を紹介しつつ、依存症とはなにか、なにが問題なのか、回復のために本人や周囲の人はどう対応していけばよいか、具体的に示していきます。 また、子どもへの予防教育はどう進めるべきなのかも紹介。 依存症予防と、依存症からの回復に役立つ一冊。 【主なポイント】 *「よい依存」が「悪い依存」に転じると依存症に近づいていく *依存が進むと脳の働き方が変化する *依存の対象は「もの」でも「行為」でも根っこは同じ *認められる、つながるうれしさがはまる入り口に *薬物依存症と犯罪の関係 *再発は想定内。回復のしかたには波がある *治療・回復プログラムの進め方 *突き放す前に家族ができること *予防教育の現状と、依存症を防ぐために教えたいこと 【本書の内容構成】 第1章 「依存症」とはなにか 第2章 依存対象の特徴を知る 第3章 回復に必要なこと 第4章 まわりの人ができること 第5章 「予防教育」を考える 著者紹介 監:松本 俊彦(マツモト トシヒコ) 松本俊彦(まつもと・としひこ) 国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部部長・同センター病院薬物依存症センターセンター長。1993年佐賀医科大学医学部卒業後、国立横浜病院精神科、神奈川県立精神医療センター、横浜市立大学医学部附属病院精神科、国立精神・神経センター精神保健研究所司法精神医学研究部、同研究所自殺予防総合対策センターなどを経て、2015年より現職。日本精神科救急学会理事、日本社会精神医学会理事、厚生労働省依存症対策全国センター共同センター長、日本学術会議アディクション分科会特任連携委員。『薬物依存症』(筑摩書房)、『よくわかるSMARPP』(金剛出版)、『アディクション・スタディーズ 薬物依存症を捉えなおす13章』(日本評論社)、『自分を傷つけずにはいられない 自傷から回復するためのヒント』(講談社)など、多数の著書・編著書がある。 (講談社BOOK倶楽部HPより転載) ISBN 978-4-06-523723-6 B5判 98p 発行 講談社 発売 2021年6月
-

世界一やさしい依存症入門
¥1,562
☆店長のひと言 「依存症がいかに身近なことかがわかります。」 内容紹介 「スマホもゲームもやめられない」「市販薬を飲む量が増えてきた」「本当はリスカをやめたい」…誰もがなりうる「依存症」について、最前線で治療にあたる精神科医がやさしくひも解く。 《もくじ》 はじめに 第1章 気づいたらハマってた──モノへの依存 ① 事例:きっかけは、試験前のエナジードリンク:エミさん(中学2年)の場合 カフェインがくれるのは「元気の前借り」 市販薬は謎の薬!? 「周囲が求める自分」になりたくて 疲れたときは、休もうよ 第2章 居場所がほしかっただけなのに──モノへの依存 ② 事例:大麻をくれたのは、憧れの人でした:ソウタくん(中学3年)の場合 やめるのは簡単でも、やめつづけるのは難しい クスリをやるのは、意志が弱いから? アルコールは立派な薬物 ゲートウェイ・ドラッグとしてのタバコ 薬物の先にあるもの 第3章 依存症のしくみと歴史 脳がハイジャックされる! 快感の正体、ドーパミン 依存症になりやすい人、なりにくい人 世界最古の薬物 アルコホリック・アノニマスの誕生 日本の薬物対策史 規制するだけでは解決しない 命を守る、ハーム・リダクション それでも薬物をやらないほうがいい理由 第4章 僕が僕であるために──行為への依存 ① 事例:気晴らしが止まらない:カイトくん(中学1年)の場合 手の中の小さな部屋、スマホ 今、このときを乗り切るために ゲームと心中するほどバカじゃない SNSにとらわれて インターネットが悪いのか? 誰にだって起こりうる 第5章 傷つけることで生きている──行為への依存 ② 事例:切った瞬間、すーっとしました:メイさん(中学3年)の場合 拒食と過食のスパイラル 心のストレスと食欲の関係 切っているのは、皮膚だけじゃない 死にたいくらいつらい今を、生き延びる トリガーはどこにある? 心の蓋の奥にひそむもの ただ、そこにいてくれるだけで 第6章 依存症の根っこにあるもの ある少年の物語 友が求めていたものは 依存症は、人に依存できない病 困った子は、困っている子 楽園ネズミと植民地ネズミ 自立って何だ? 第7章 社会と依存のいい関係 見せしめの逆効果 当たり前を疑う 依存症はなくならない 失敗しても、終わりじゃない ありのままの自分を許す [きみとあなたへのメッセージ] 依存症かもしれないきみへ 友達が依存症かもしれないきみへ 子どもが依存症かもしれない親御さんへ 生徒が依存症かもしれない先生へ [ヒコ先生の相談室] ・「あの子、依存症かも?」と思ったら ・信頼できる大人の見分け方 ・依存症の友達に、どう接したらいい? ・家族がゲームにハマったら ・友達の腕にリスカの痕を見つけたら ・逃げ場のつくり方 ・心の専門家になるには [困ったときの相談先リスト] おわりに 著者 松本 俊彦 (マツモト トシヒコ) 1967年生。精神科医。国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部長。佐賀医科大学卒。横浜市立大学医学部附属病院精神科等を経て現職。主著に『薬物依存症』『誰がために医師はいる』がある。 (河出書房新社HPより転載) ISBN 978-4-309-61734-3 C0347 四六判 234頁 発行 河出書房新社 発売日 2021年8月25日

-
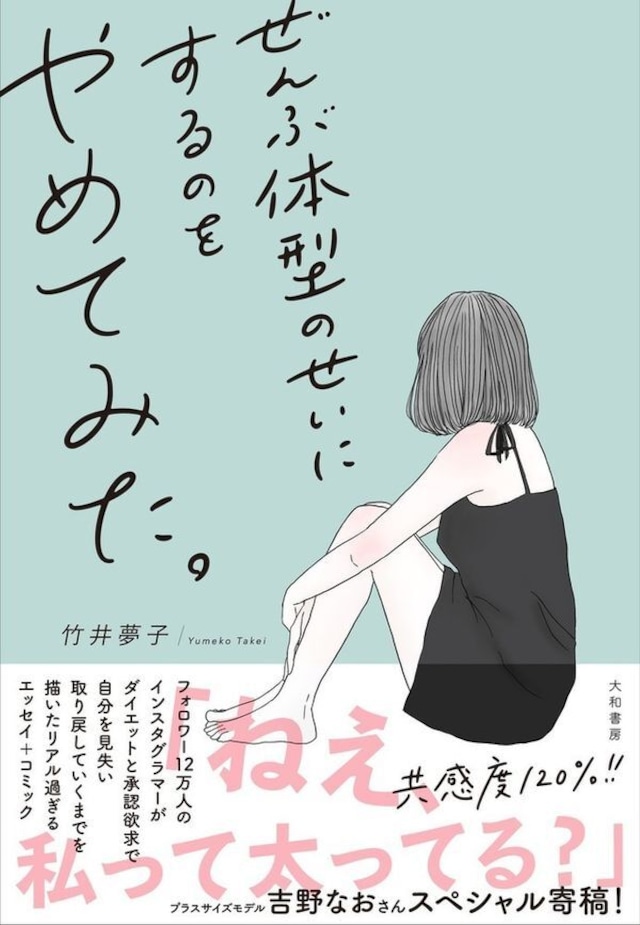
ぜんぶ体型のせいにするのをやめてみた。
¥1,540
☆店長のひと言 「心まで痩せさせてしまうダイエットとは。」 紹介 インスタでダイエットをテーマにフォロワー12万人までいった女子大生インフルエンサー。 大学時代に始めたひとり出版社「ブルーモーメント」の代表が、ダイエットや承認要求に追い詰められ、自分を見失いかけた女性を描くコミック+エッセイ 竹井 夢子(著/文) ISBN 978-4-479-77231-6 四六判 208頁 発行 大和書房 発売日 2021年6月26日
-

安心な認知症 マンガとQ&Aで、本人も家族も幸せになれる!
¥1,540
☆店長のひと言 「“絶対”はありませんが、事前に知っておくと安心や幸せのヒントになるかも知れません。」 ★ブログ記事 https://iki-blo.blogspot.com/2022/04/qa.html 内容紹介 NHKの人気テレビ番組司会者・立川志の輔さんも推薦! 「認知症の人が見ている世界/感じている世界」「認知症の介護をする家族が必要とする知恵」を、“認知症診療の第一人者”で日本認知症ケア学会理事長の繁田雅弘医師を代表とする、認知症にかかわる“プロフェッショナル”たちが、さまざまな視点から徹底解説。 取材ルポマンガ入りで楽しく読めて、超高齢社会ニッポンを待ち受ける「認知症世界の歩き方」が習得できる一冊です! <本書に掲載されている内容から抜粋 ※詳細は本書をご覧ください> Q:夫が「軽度認知障害」(MCI)と診断されました。いずれ認知症になるのでしょうか? A:軽度認知障害と診断された場合、その後、認知症へ進展するかどうかは、じつはわかりません。診断された人には以下のように説明することがあります。 「あいまいで中途医半端な状態なので戸惑うかもしれません。でもあまり気にせずに、まずはバランスのよい食事や適度な運動、持病の治療など、健康全般に気をつけることを心がけてください。何かを諦めたり、自信をなくしたりする必要はありません」 Q:父が認知症と診断されました。進行を防ぐために「脳トレ」をさせようと思います。いかがでしょうか? A:世界保健機関(WHO)が2019年に発表したガイドラインでは、脳トレなどの認知トレーニングの効果は否定されているわけではありませんが、エビデンス(医学的根拠)のレベルは非常に低いと示されています。脳トレが好きでやりがいを感じてやっているなら問題ありませんが、楽しめずにストレスを感じている場合は、やめたほうがよいでしょう。 Q:認知症になって数年もたてば、家族の顔もわからなくなると聞きました。本当ですか? A:認知症が進行していく経過やスピードは患者さんによってさまざまで、数年で症状が進む人もいれば、亡くなるまで症状が軽い人もいます。認知機能テストの点数は落ちても、仕事や日課を行うことをやめずにこれまでの生活を継続し、安定した状態が続いている人もいます。 Q:家族が認知症と診断されました。これから、どうしたらよいでしょう? A:早めに考えたいのは、家族の財産・経済状況を把握すること。年金や貯金、土地、金融商品、負債などは、できるだけ症状が進まないうち(本人が判断できる時期)に確認しておきましょう。今後、必要になってくる介護費用に備えるためにも大切です。 Q:乱暴な物言いや徘徊、物盗られ妄想など、認知症の「行動・心理症状」は、介護のやり方しだいで起こりにくくなるって本当ですか? A:本人が感じている不安や孤独感が軽くなり、気持ちが落ち着くと、起こりにくく、改善しやすいことがわかっています。 ……本書では、多くの人たちが感じてる不安を“安心に変えるアドバイス”が、具体的かつ実践的にたっぷりと紹介されています。 目次 ■序章)介護家族から学ぶ「認知症の真実」 ●症状が進んでも……/「認知症の本人」のホンネ/親戚や近所の人たちとの付き合い方/他 ■第1章)認知症への不安がなくなる「医療の最新常識」 ●認知症の可能性がある人/認知症を診てくれる医師の見つけ方/「誤診」問題/認知症と診断されたら……/「認知症の予防法」に対する誤解/薬について知っておくべきこと/他 ■第2章)本人も家族もラクになる!「介護環境」の整え方 ●診断されても慌てずに済む基礎知識/介護認定を受けるコツ/ケアマネジャーの選び方/「認知症カフェ」の賢い活用法/「介護費用」の支出額を抑える基本知識/「成年後見制度」「家族信託」のデメリット/他 ■第3章)知っておくと役立つ! 介護家族の知恵 ●できれば避けたい“認知症のNGケア”……何度も同じことを聞いてくる/家を出て帰ってこられなくなった/家電製品の操作ができなくなってきた/「あれ」「それ」で会話がうまくできなくなってきた/他 ■特別企画)“認知症のプロ”が、親の認知症に直面してわかったこと ■第4章)認知症とともに、幸せに暮らす ●第三者の存在が大事/「認知症病棟への一時入院」という選択/まだ大丈夫なうちから、施設入居の準備を/義務感にかられたムリな介護は避ける/納得の高い「看取り」のコツ/他 著者プロフィール 繁田 雅弘 (シゲタ マサヒロ) (監修) 東京慈恵会医科大学精神医学講座教授。日本認知症ケア学会理事長。認知症専門医。東京慈恵会医科大学を卒業後、精神医学講座に所属し、1992年よりスウェーデン・カロリンスカ研究所老年病学教室の客員研究員、2003年より東京都立保健科学大学教授、2005年より首都大学東京健康福祉学部学部長、2011年より首都大学東京副学長を務めた。2017年より東京慈恵会医科大学精神医学講座教授に就任、同時に首都大学東京(現 都立大学)の名誉教授の称号を得た。医療の枠にとらわれず、認知症の人をいかに支えるかを追求。神奈川県平塚市の実家にて認知症の啓発活動などを地域住民と共に行う「SHIGETAハウスプロジェクト」を主催。 森下 えみこ (モリシタ エミコ) (イラスト) 静岡県生まれ。コミックエッセイのほか、書籍や広告、雑誌などのイラスト、マンガを手がけている。おもな著書に『40歳になったことだし』(幻冬舎)、『マンガでわかる「すぐ不安になってしまう」が一瞬で消える方法』(すばる舎)、『老けない人はこれを食べているマンガ版』(新星出版社)、『今日も朝からたまご焼き』(KADOKAWA)などがある。 ISBN 978-4-391-15657-7 四六判 192頁 発行 主婦と生活社 発売日 2021年12月21日